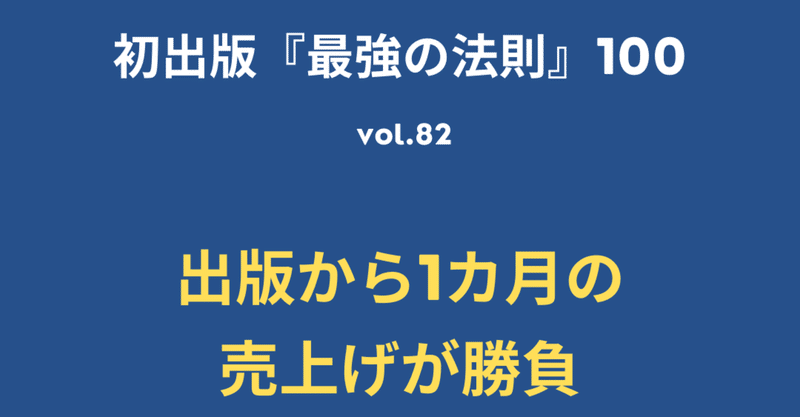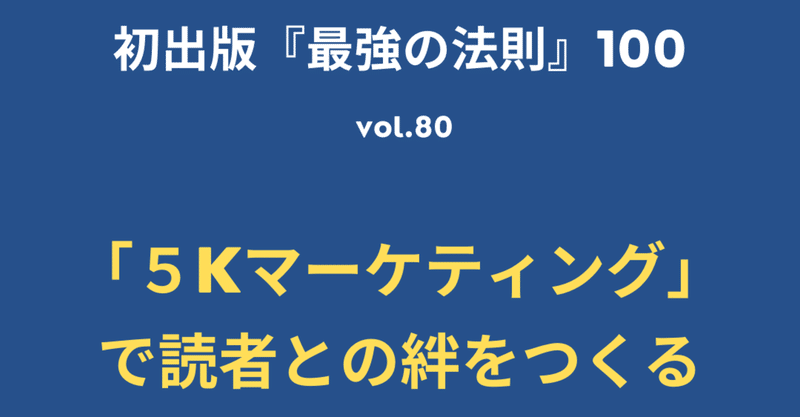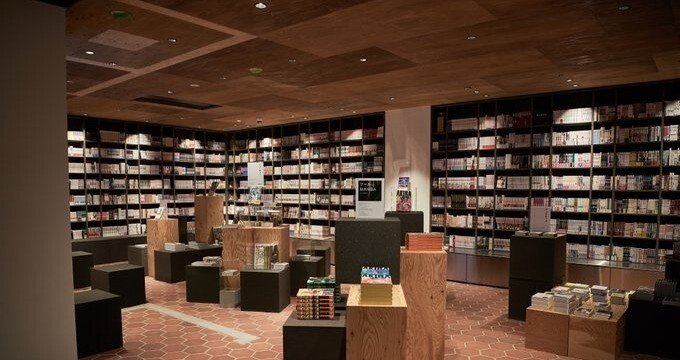
- 運営しているクリエイター
2022年2月の記事一覧
【初出版『最強の法則』100】 vol.83:売り伸ばしのために著者ができること
前回は、発売後1カ月の売上げが勝負というお話をさせていただきました。
今回は、発売1カ月以降の販売戦略を考えていきたいと思います。
発売1カ月の売上げ次第で、あなたの作品は出版社内でランク付けされます。
(本当はもっと前ですが、話をわかりやすくするために単純化しています)
①売上げが順調な場合→有料の宣伝広告を出すなど、施策を打ち出してさらに売り伸ばしていく。時期を見て重版をしていく。
②売上
【初出版『最強の法則』100】 vol.82:出版から1カ月の売上げが勝負
本の売上げは何で決まるのでしょうか。
SNSのフォロワーの数?宣伝?著者のあなた、出版社の知名度?
累計800万部の大ベストセラー作家・本田健さんが下記のようなことを話していました。
「最初の1か月は人望で売れる。それからは人気が出るかどうかだ」
最初の1カ月はあなたのご友人や“応援団(ファン)”がどんどん購入して、
SNSで紹介してくれたり、口コミで広めてくれるでしょう。
「○○さんのためな
【初出版『最強の法則』100】 vol.81:出版後に本を“育てていく”
「本を抱きしめて寝ています」
初出版直後の著者の方からよく聞く言葉です。
本当にやっているかどうかは別として、
そのぐらい自分の作品は愛おしいということでしょう。
編集者の私も、担当したかどうかは関係なく、枕元に置いている本はたくさんあります。
著者の方の気持ちは理解できる気がします。
出版はよく、出産に例えられます。
「産みの苦しみ」とよく言われますよね。
自分の作品は子ども、著者のあなたは
【初出版『最強の法則』100】 vol.80:「5Kマーケティング」で読者との絆をつくる
前回は、読者に自分の商品やサービスを提供する手法として、「FFMB」という考え方を紹介しました。
FFMBは「フリーエンド・フロントエンド・ミドルエンド・バックエンド」の略称。
簡単に言えば、読者の興味を引きそうな、読者だけの特典をまず無料で提供し、お手頃価格の商品・サービス、中程度の商品・サービス、本当に売りたい商品・サービスを購入してもらうように導いていく手法です。
そして、このFFMBの進
【初出版『最強の法則』100】 vol.79:読者リストを大切に育てていく
前回は、読者に自分の商品やサービスを提供する手法として、「FFMB」という考え方を紹介しました。
FFMBは「フリーエンド・フロントエンド・ミドルエンド・バックエンド」の略称。
簡単に言えば、読者の興味を引きそうな、読者だけの特典をまず無料で提供し、お手頃価格の商品・サービス、中程度、本当に売りたい商品・サービスを購入してもらうように導いていく手法です。
最近では、これをさらに進化させた「5Kマ
【初出版『最強の法則』100】 vol.78:無料で読者特典を提供するワケ
【初出版『最強の法則』100】
vol.78:無料で読者特典を提供するワケ
前回は、出版を自分のビジネスに繋げる=「集客する」ための具体的手順をお話しました。
集客ノウハウやマーケティングは専門家がたくさんいらっしゃいますし、
あなたも書籍以外のSNS等をうまく運用していると思いますので、
ここでは書籍での運用実態を見ていきます。
初歩段階の3つのポイントをおさらいしておきます。
①読者に何を
【初出版『最強の法則』100】 vol.77:読者に無料でコンテンツを提供する
読者には徹底的に「GIVE& GIVE&GIVE」する――。
前回は、出版を自分のビジネスに繋げるための基本的な姿勢をお伝えしました。
ビジネスに繋げるとはどういうことなのか。
おそらく、多くの方は、自分の商品・サービスを購入してもらうことを想像するでしょう。
あるいは、自分の運営するコミュニティに入会してもらうことかもしれません。
自分のファンや応援団になってくれればいい。そう考えている方もい
【初出版『最強の法則』100】 vol.76:読者には「GIVE& GIVE&GIVE」
今回は、いかに出版を自分のビジネスにつなげていくかを考えていきます。
この連載の3,4回目で「出版の目的」を決めることの大切さをお話しました。
「本が好きだから、1冊は出したい」
「自分のコンテンツをまとめたい」
「自分のノウハウや経験で世の中に貢献したい」
もちろん、様々な目的があっていいのです。
中でも、出版を自分のビジネスや仕事に結び付けたいという方は多いと思います。
「同じ業界の中で飛び
【初出版『最強の法則』100】 vol.75:「自分で売る」ことは、いい宣伝になる
前回までは、宣伝プロモーションの方法と実態を詳細に見てきました。
著者はもちろん、本の販売の専門家ではありません。
出版社には販売部・宣伝部という専門の部署があり、担当者がいるので、
基本的にお任せするのは当然です。
しかし、「自分で自分の本を売る」という意識は、強く持っていてほしいものです。
著者が売る意識をもっていないと、売れるものも売れません。
編集者も販売担当者も、著者が売ろうとしていた
【初出版『最強の法則』100】 vol.74:クラファンは宣伝ツールのひとつ
前回までは、宣伝プロモーション全体の流れを見てきました。
今回は、クラウドファンディング(クラファン)のことをお話します。
「クラファンが宣伝に関係あるの?」
と疑問に思う方がいるかもしれません。
「クラファンは出版にかかる資金を集めるものでしょう?」と。
確かに、クラファンは資金集めです。
もう一方で、いまや宣伝でもあり、マーケティングツールでもあるのです。
出版関係のクラファンの目的は、「
【初出版『最強の法則』100】 vol.73:SNS×応援団×宣伝=売れる
ここまで、宣伝プロモーションの大まかな流れを見てきました。
SNSでの発信、応援団的存在、宣伝…どれが欠けても書籍を売ることは難しい。
それはご理解いただけたかと思います。
ここで振り返っておきますが、基本となる方針は連載vol.61でお話した下記の4つです。
①自分の得意なSNSを強化する
②プロセスを見せる
③その過程で応援団をつくる
④編集者や出版社と緊密に連携する
では、実際の宣伝プロ
【初出版『最強の法則』100】 vol.72:効果的な広告は読者層を絞りきる
(最後に70回突破記念のプレゼントがあります)
前回に続き、有料の宣伝広告の運用実態2回目です。
「売れている作品だけを宣伝する」「コスパが見えにくい」
――前回は、厳しい実態をお話しました。
とはいえ、効果的な宣伝ができるケースがあることも事実です。
それは、書籍の企画と同様に、ターゲットを絞り切った宣伝をしているときです。
よくあるのは、地方紙やブロック紙に宣伝広告を掲載し、
その地方の
【初出版『最強の法則』100】 vol.71:売れているものしか宣伝しない
前回までは、ネタや記事としてメディアに取り上げられるケースを見てきました。
今回からは、有料の宣伝広告の運用のされ方を見ていきましょう。
書籍の宣伝広告も、あらゆる宣伝手段が可能です。
新聞広告、電車内広告、SNS広告、Amazon広告、テレビCM、街頭ビジョン…。
ただし、最近の傾向ははっきりしています。
「売れている作品だけを宣伝する」のです。
たとえば、書籍の宣伝でもっとも使われている新
【初出版『最強の法則』100】 vol.70:ネットメディアでバズらせる
(バレンタイン&70回記念!最後にSPプレゼントがあります)
前回からメディアがネタ、あるいは記事として、あなたの書籍やあなた自身を無料で取り上げるケースをお話してきました。
①テレビ、新聞、ラジオ、雑誌など既存の4大マスメディア
②①以外のネットメディアやSNS
前回は①をお話しましたが、
接する機会の多さ、拡散力、即購買につながるという点では、
今や②のネットメディアのほうに軍配があがる