
日本を支配する「お坊ちゃん文化」
昨日は、ホイチョイプロダクション・馬場康夫が「若大将シリーズ」を解説しているYouTube動画を見た。
「お、若大将か、懐かしいな」と思ったからだ。
【若大将シリーズ解説】昭和を彩った映画シリーズ「若大将」を徹底解説!(ホイチョイ的映画解説)
馬場の解説は面白く、懇切ていねいで有益だったが、私は別の感慨も持った。
「ここに日本の『お坊ちゃん文化』の精髄がある!」
と思ったのだ。
私は数日前、宮台真司をダシに、「文化人はみんな都会のお坊ちゃん」という記事を書いた。
岸田の改造内閣も、「お坊ちゃんお嬢さん」の世界に思える(そうでないのも入っているが)。
「お坊ちゃん文化」に敏感になっている。
都会の「ハイライフ」
加山雄三の「若大将」も、知らない世代がふえただろう。
加山雄三の東宝「若大将」シリーズは、1962年から1971年にかけて16本作られた。つまり、1年に1本以上、公開されていた人気シリーズである。
馬場も私も、それを子供時代、リアルタイムで見ている。1954年生まれの馬場は、私より少し年上だが、ほぼ同世代と言える。
馬場は小学校高学年のころ、私は小学校低学年のころに「若大将」に触れている。
「若大将」シリーズは、当時の都会の裕福な大学生たちの青春を描いている。つまり、ハイソサエティの「ハイライフ」の映画だ。
舞台は、慶応大学と思われる大学。リアルに慶応を卒業している加山雄三は、銀座の有名料理屋の跡取りの「若大将」、田中邦衛演じる親友の「青大将」は会社社長の息子、という設定。
いまでこそ大学進学率は60%を超えているが、1960年代は20%そこそこだったから、大学生というだけでエリートだ。
シリーズは毎回同じ、金持ちの子弟たちが、恋や部活に熱中し、のびのびと青春を謳歌するストーリーである。
「スキー」や「サーフィン」などの当時最先端のスポーツ、ファッションを紹介、またハワイなどの海外ロケをまじえて、いかにも高度成長期の流行と風俗を描いている。
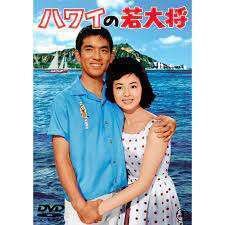
「大馬鹿野郎のお坊ちゃん」
それを、東京の映画館で見ていた馬場康夫も、会社の重役の息子で、小学校から大学まで「成蹊」の、まぎれもないお坊ちゃんだ。
だから、「若大将」シリーズは、まさに彼らの世界を描いた映画であり、彼のような「お坊ちゃん」たちの共感と熱狂を得たのであった。
馬場は、この「若大将」シリーズこそ自分の原点、「ソウルムービー」であると語り、全シリーズ作を何度も見て、1970年代の池袋でのリバイバル上映会で仲間と「応援鑑賞」したエピソードを語っている。
馬場は、自分たちを「甘やかされて育った大馬鹿野郎のお坊ちゃん」と呼ぶが、「若大将」のころは、その文化が許容されていた、という
「いまは、給付金サギをはたらいた経産省のキャリアとか、袋叩きにされている政治家の息子とかを生んで、世間から嫌われているけど、1960年代には、お坊ちゃんの中にも、加山雄三に代表される、ノブレス・オブリージュを叩き込まれた気持ちいい人がたくさんいて、そういうガツガツしたところがない人たちは、人に優しくていいね、と世間から好意をもって受け入れられていた」(動画11:30あたり)
たしかに、この映画では、「大馬鹿野郎のお坊ちゃん」の嫌味は田中邦衛に凝縮して表現され、対比的に加山雄三のさわやかさが強調される。世間の好意は、加山の属人的な魅力に負うところが大きかった。
しかし、日本中のだれもが馬場のような見方をしていたわけではないと思う。
田舎で見た「若大将」
私は、「若大将」シリーズは、1作だけ封切のときに見た。
マラソンの場面を覚えているから、たぶん「ゴー! ゴー! 若大将」(1967)だと思う。
近所の工務店に勤めていた「トシ兄ちゃん」という若い板金工に連れて行ってもらった。
小学校低学年の私が、自分から「若大将」を見たいと思うことはないだろうから、たぶんトシ兄ちゃんが見たいと思ったのだ。
トシ兄ちゃんは、なぜか子供の私をかわいがってくれて、仕事のヒマなときにキャッチボールの相手をしてくれたりした。
「若大将」を見に行った前年には、「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」(1966)に連れて行ってもらった。これは私が希望したのだろう。映画の内容もけっこう覚えている。
しかし、「若大将」のほうは、上述のマラソンの場面以来、ほとんど覚えていない。
いまとなっては、中卒か高卒で働いているトシ兄ちゃんが、「若大将」をどのように見たかが気になる。
私の田舎は高度成長から取り残され、まわりはさびれていた。大人の「文化」といえば、酒とたばことギャンブルだけだった。
同じように私をかわいがってくれていた、街工場に勤めていたタミ姉ちゃんは、「アカになった」と近所で噂されていた。
トシ兄ちゃんは「若大将」を、東京で見た馬場と同じように共感して見たわけではないだろう。しかし、映画にたいするトシ兄ちゃんの反応はなにひとつ覚えていない。
トシ兄ちゃんと映画を見たのはそれが最後だった。なんでも結婚して、工務店をやめたとのことだった。夫婦で歩く幸福そうなトシ兄ちゃんにその後一度だけ会ったが、それきりだ。もし生きていたら、死ぬまでにお礼を言いたい人の一人だ。
バブルとお坊ちゃん
話がそれたが。
田舎の貧しい人たちにとって、「若大将」の世界は、「奥様は魔女」や「サンセット77」などと同じ、バタ臭い絵空事だったと思う。見ているのは楽しいが、「自分たちの世界」だと思っては見ていない。子供の私にとってもそうだった。
その後、私は東京で就職した。
ときはまさにバブル期で、馬場が主宰するホイチョイプロダクションは、バブル文化のクリエーターだった。
ホイチョイが出版したベストセラー「見栄講座」(1983)を、私は面白く読んだ。
しかし、馬場が監督した映画「私をスキーに連れてって」(1987)や「彼女が水着にきがえたら」(1989)は、なにか反感を覚え、見に行っていない。
ご承知のとおり、原田知世主演の「私をスキーに連れてって」は大ヒットして、バブル期を代表するとされる映画である。

昨日のYouTube動画を見て、あれらの映画が、「若大将」シリーズへのオマージュであり、ほとんど模倣であることがわかった。
バブル期を描いた私の小説「平成の亡霊」では、「私をスキーに連れてって」「彼女が水着にきがえたら」は明示的には出てこない。だが、物語に「お坊ちゃん文化」への反感を塗りこめたつもりである。
同じように反感を覚えただろう人びとが、オウム真理教の信者だちだった。
あれから30余年。
いま会社を退職して、振り返ると、私がいた東京のマスコミ業界には、元「若大将」、元「お坊ちゃん」ばかりがいた。
おそらく、ほかの大企業も、同じようなものではなかろうか。
彼らは、頭がよく、センスがよく、毛並みがよく、人柄がよく、そのうえコネがある。
彼らが私より出世していったのも、仕方ないことだろう。
ホイチョイと安倍晋三
日本を支配しているのが「お坊ちゃん文化」であることは、あまり知られていない。
安倍晋三は、馬場康夫と成蹊の同期である。
安倍晋三が首相を辞任したとき、ユーミン=松任谷由実がラジオで「泣いちゃった」と言って、サヨクから叩かれたりした。
安倍、馬場、ユーミンは同じ1954年生まれで、みんな「同じ文化圏」を生きてきた。
ノンフィクションライターの近藤正高が書いている。
安倍晋三、松任谷由実、ホイチョイ馬場社長は同じ1954年生まれ。3人の親交を辿っていくと、共通点が見えてきた。大学がレジャーランドと呼ばれ始めた時代に青春を過ごし、戦争や政治から遠い文化を享受した最初の世代。
ユーミンが支持を集めたのは、彼女の歌う世界が、ハイソサエティな雰囲気を漂わせつつも、庶民でもちょっと手を伸ばせば届くような気を起こさせたからだろう。そう考えると、彼女の音楽はまさに「一億総中流」と呼ばれた時代を象徴するものであった。だが、経済格差が広がり、中間層が消滅したとさえいわれる今、ユーミンの音楽に違和感を覚える人が増えてもおかしくはない。(近藤正高「54年生まれ、安倍晋三」)
お坊ちゃん文化にたいする異物は排除される。オウム真理教は消え(消えていいのだが)、ユーミンの音楽は残る。
日本の政治も、文化も、依然、彼らのものである。
将来、小泉進次郎が総理大臣になるあたりで、戦後日本のお坊ちゃん文化は頂点をきわめるのだろう。
幸い、そのころまで私は生きていないだろうし、生きていたらボケていたい。
近所のハワイ
余談だが、馬場のYouTube番組を見たあと、たまたま「コナズ珈琲」についての記事が目に入った。
コナズ珈琲は、うちの近くにもある。

「ハワイカフェ」というコンセプトに、
「いまさらハワイか! 昭和か! ハワイの若大将か!」
とバカにしていたが、いつ前をとおっても、店はいっぱいだ。
開店前から客が行列をつくっているのもよく見る。
「ふーん、人気があるんだな」と思っていたが、入ったことはなかった。
上述の記事で、それが丸亀製麺と同じ会社の事業であることを知ったのが、いちばん驚いたのは、価格設定だ。
一番人気という「ストロベリー&バナナホイップパンケーキ」や「アボカドハンバーグロコモコ」、「BBQベーコンチーズバーガー」は1749円(税込み、以下同)。それにドリンクとしてハワイコナ100%のコーヒー(968円)を付ければ、2717円と、相応の金額となる。しかもランチセットなどのお得なサービスはない。
(高橋学「『第2の丸亀製麺』はハワイカフェ 連日満席、非効率経営で急成長」日経XTREND)
パンケーキが(約)2000円!
コーヒーが(約)1000円!
パンケーキなんて、ただの糖質のカタマリだろう。それをコーヒーとセットで(約)3000円のカフェに、あんなに客が来るなんて。
1日の食費1000円の私には、一生行けないところである。
身近にも「ハイソ」な「ハイライフ」があった。
私はリアルのハワイにも、ハワイカフェにも行ったことがない。行けない。
そして、その程度でハイライフか、と笑う文化が、多摩川の向うの23区にはあるだろう。
私だって、極貧というわけではないが、都会の「ハイライフ」との壁は破れなかった。
これを「ホイチョイの壁」とでも呼ぼう。
結局、「若大将」を見ていた子供のころから、「ホイチョイの壁」は存在し、私は一生、超えることができなかったのである。
昨日の午後は、じっと手を見て過ごした。
<参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
