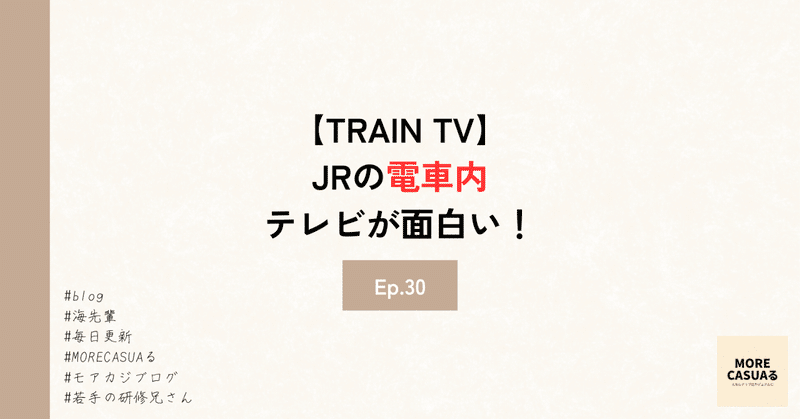
Ep.30 【TRAIN TV】JRの電車内テレビが面白い!
どうも!若手の研修兄さんこと、
海先輩です!
このマガジンでは、毎朝更新しているPodcast番組「MORE CASUAる ~スキルアップはカジュアルに~」の内容を記事として発信しています!
「勉強になった!」「もっと具体的に聴いてみたい!」「海先輩ってどんな声?」と思った方は、ぜひPodcastもチェックをお願いします!
■はじめに
「満員電車楽しい!」
そう思えるようになる日が来ることもあるかもしれないなと思うんです。世の中を変革してきたイノベーションは、常識を根底から覆すようなものばかりでした。犯罪大国アメリカでAirbnbが浸透したのは、良い例だと思います。
満員電車が好きな人はまあ少なく、むしろほとんどの人が嫌いだと思います。その満員電車が長年嫌われ続けてきた常識を180度ひっくり返すアイデアが生まれてくるような社会だと、なんか面白いですよね。
■今日のお話は──「TRAIN TV」について
おはようございます。海先輩です。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。今日は【TRAIN TV】についてのお話です。
みなさん「TRAIN TV」をご存知でしょうか。「毎日の移動に、発見とときめきを」をコンセプトに2024年4月からJR東日本の首都圏主要10路線とゆりかもめの車内で放送している「無音の番組」です。
首都圏生活者が一生で鉄道に乗車する時間は平均約1万時間らしく、この乗車時間をより豊かな時間へ変えてゆき、社会に活力を生み出したい、という想いからTRAIN TVは生まれたそうです。
OOH(Out Of Home)と呼ばれる中吊り広告や駅構内広告には「コンテンツ」の弱さに課題がありますが、TRAIN TVは人気芸人を起用したお笑いやグルメ、情報番組やドキュメンタリーまで、バラエティ豊かな番組により、その課題をクリアしています。
TRAIN TVは老若男女すべてを視聴ターゲットとしているものの、特に若い世代は意識しているそうですね。若者のテレビ離れが言われて久しいですが、若年層向けのマーケティングはメディア業界の課題でもあるそうで、TRAIN TVは通勤・通学で1日2回利用する電車に注目し、若い年代へのリーチを図っています。
僕も通勤でJRを利用するので、ほぼ毎日このTRAIN TVを見るのですが、テレビと同じくらいのクオリティの番組を毎週作るなんて凄いなと思いました。
電車内の広告って、企業向けITサービスのCMや転職サービス、まちづくり系の広告が多いイメージで、正直僕は興味無いものばっかりだったんですよ。
ただTRAIN TVは見てて「へぇ〜」と思えたり、クスッとするようなものだったりするので、つい顔を上げて見ちゃうんですよね。他の乗客を見てても、結構見ている印象があります。
■「昨日アレ見た?」──の面白さがあるTRAIN TV
SNSが広まってから減ったなと思うのが「昨日アレ見た?」から始まるエンタメトーク。僕は98年生まれですが、小学生〜中学生くらいまでは、「昨日はねとび見た?」とか「昨日イケパラ見た?」みたいな会話があった記憶があります。
今はSNSで各々が好きな動画を楽しむようになったので、「多くの人が見ている前提」での会話では無くなりました。面白いコンテンツが増えたのは良いことですが、あの一体感のようなものも、少し恋しくなります。
そういえば久しぶりに一体感を感じたと思ったのは、昨年のWBCでした。決勝の日本vsアメリカ、大谷翔平とトラウトの一戦。仕事中でしたが、職場全員でテレビに夢中で歴史的瞬間を味わいました。あのみんなで感じる興奮が良いんですよね。
話を戻すと、この「アレ見た?」「一体感」を生んでくれるのがTRAN TVになるんじゃないかと思っています。
TRAIN TVの番組に「黙喜利」というものがあります。これは授業中や電車内など、声を出しにくい状況で芸人さんが無音でフリップ大喜利をする番組なのですが、若手向けのアプローチとしてすごく良いなと思いました。
友達と遊びに行くとき、移動の電車で黙喜利を見ることで話題のきっかけになると思います。同じお題で友達同士で大喜利をしたりすることもあるでしょう。
もしくは、TRAIN TVは1週間周期で内容が変わるので、「あーこれ見た!面白いよ!」という話になることもあると思うんですよね。コミュニケーションのきっかけになることはOOHにおいて重要な要素だと思います。
SNSと違って私生活に溶け込んだコンテンツであることが、昔家族の団欒時間に何気なく流れていたテレビと似ているのかもしれません。
■SNSや動画サブスクと──TRAIN TVやテレビの違い
エンタメの楽しさって、そのコンテンツ自体の楽しさもありますが、「周りの人と楽しさを共有している」という楽しさもあると思うんですよ。
音楽フェスの何が良いって、大好きなアーティストを生で見られることもそうですが、生音のグルーヴを大勢の人と体感している空間にも良さがあると思います。
先ほど話したWBCのようなスポーツの世界大会も同じ感覚があって、国を背負って戦う日本代表を、“国民全員で”応援しているというあの一体感が良いんですよね。
フェスやワールドカップほどとは言いませんが、TRAIN TVやテレビも近いものを感じます。
SNSやNetflix・Amazonプライムなどの動画サブスクは個々のユーザに合わせてリコメンドするので、だんだん自分専用の空間へと変わっていきます。
しかしTRAIN TVやテレビは個々のユーザに合わせて内容がカスタマイズされていくことはありません。この差は大きいと思っていて。カスタマイズされない分みんなが同じもの見るからこその一体感が生まれるんだと考えています。
どちらも良し悪しがあるという感じですね。ポイントは「コンテンツ自体を楽しむ要素」と「コンテンツをみんなで楽しんでいる一体感という要素」かなと思いました。
TRAIN TV、まだ始まって1ヶ月なので、今後の展開に期待ですね。個人的にはドラマを作っても面白いんじゃ無いかと思っています。
■おわりに
アイデアは逆説的な思考から名案が生まれることが多いです。TRAIN TVも、「音声がある」という動画コンテンツでは当たり前の常識を覆した「無音の番組」がコンセプトです。「普通は〇〇」と思っているものの逆を考えると、面白いアイデアが出てきやすいんですよね。
満員電車は普通ストレスフルなものだけど、「満車であればあるほど楽しい電車」というアイデアが誕生した際には、それは大革命になる気がします。「そんなのあり得ないでしょ」という声が聞こえてきそうですが、そういう声があるものだからこそ、イノベーションになるんですよね。ちょっと考えてみます。
■海先輩のおすすめ本コーナー
今日も記事を読んでいただきありがとうございます。ここからはおまけ。
このコーナーでは、年間200冊以上の本を読む僕が、最近読んだ本の中から「おもしろかった!」「ためになった!」という本を紹介していきます。
今回ご紹介するのは…
株式会社アンド(著)
『思考法図鑑: ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60』
▼おすすめの理由は?
シンプルに頭が良くなるからです。頭が良くなるというのは、悩みや課題に直面したときに、その解決策がサクッと見つけられるようになるということです。問題解決能力が高い人は、生まれ持った頭の良さがある人だけでなく、思考のフレームワークに当てはめて考えることで難しい問題を解決している人も多いんですね。本書に載っているフレームワークを1つ自分のものにするだけでも、かなり頭が良くなるので非常におすすめですね。
▼どんな人が書いた本?
小野 義直
大学卒業後、6年間勤めた広告代理店の倒産を機に独立。仮説検証と実践サイクルをスピーディーに回し、段階的に完成度を高めていくことを強みとする。これまで小売・サービス業を中心として構造設計からコミュニケーション戦略構築まで1,000社以上を支援。幾多のプロジェクトを支援する中でプロジェクトリーダー養成と組織開発の重要性を感じ、現在は個人と組織の変容支援にも従事している。
宮田 匠
コンテンツマーケティング領域を中心に、クライアント企業の企業立案・運営を支援している。課題整理・アイデア発想の思考促進を得意とし、企業向け研修の設計業務も行う。
▼何が学べる?
論理的思考や問題解決、アイデアを生み出すための思考フレームワークが60個も学べます。論理的に構築したいときはコレ、突飛な発想をしたいときはコレ、分析をしたいときはコレなど、全ての「考える」場面において本書に必ずヒントが載っている本になります。
▼読む前と後でどんな変化があった?
普段仕事をする中で、明らかに思考力が向上したと実感しました。企画を出すような会議でもポンポンアイデアが出たり、すらすら話を進められるようになり「う〜ん」と頭を悩ませる時間が減りましたね。働く全ての人に読んでほしい一冊です。
僕が思考や習慣を変え、自分の好きなことができるようになったのも間違いなく読書習慣のおかげです。ジャンル問わずいろんな本を読んで、ともに人生に彩りを添えていきませんか?ご興味ある方は、↑のリンクからぜひ!
#blog #海先輩 #若手の研修兄さん #MORECASUAる #Podcast #ポッドキャスト #音声配信 #毎日更新 #新卒 #新入社員 #ビジネススキル #仕事術 #恋愛 #美容 #健康 #習慣 #マーケティング #企業note #歴史 #哲学 #ビジネス #文学 #マインドセット #人的資本経営
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
