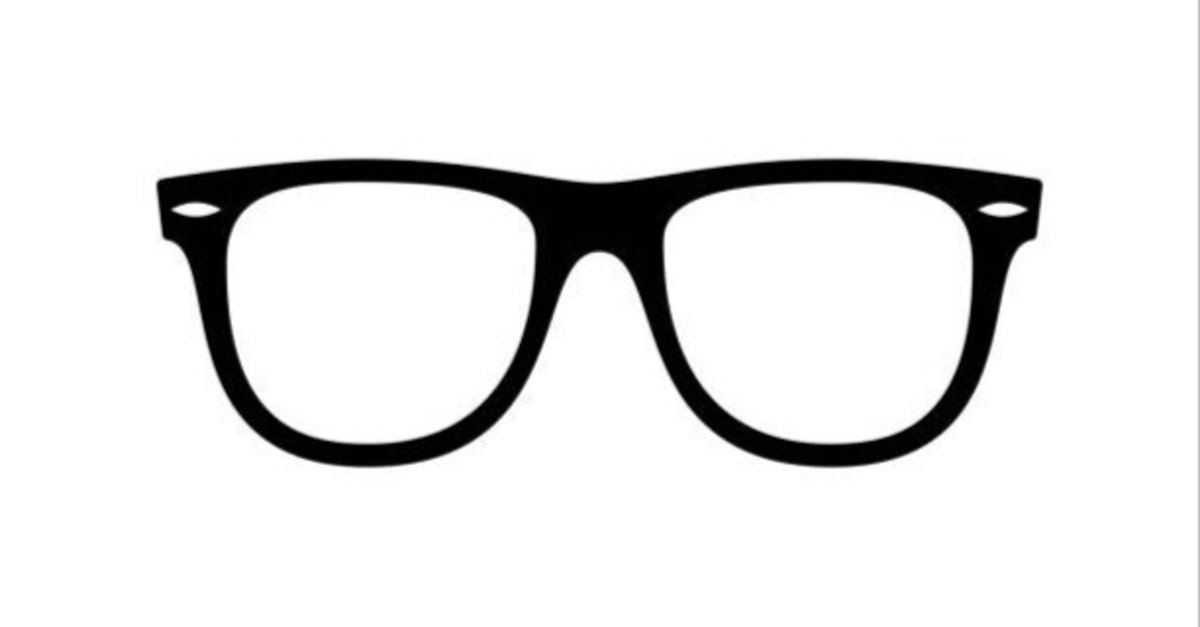
丸山眞男がシュミットを引用した理由
丸山眞男は「超国家主義の論理と心理」(1946)の中で、カール・シュミットの「中性国家」という用語を引用している。
「中性国家」とは、ヨーロッパ近代国家の特徴を表すものである。真理や道徳に関して価値中立的な国家のことだ。
これを日本の超国家主義と対比させ、後者を批判する意図がうかがえる。
しかし内容の正否以前に、ナチのイデオローグと目されたシュミットを引用しては説得力が無くなるのでは?との疑問が当然起こる。
彼はなぜ、戦後日本の再出発に際してシュミットを引用したのか?
その理由は、丸山の『戦中と戦後の間 1936―1957』(1976)という論集を読むと解ってくる。
まず、彼は戦中からシュミットに言及し翻訳もしているのだ。
大学3年時、懸賞論文「政治に於ける国家の概念」(1936)で、1箇所だけだがシュミットの言葉を引用している。
1939年には、ナチに理論的根拠を与えた「国家・運動・民族」(1933)の抄訳を発表。
『戦中と…』には抄訳自体は収録されていないが、丸山本人による掲載当時の「はしがき」が入っている。
それによるとシュミットは、イデオローグのイメージとは裏腹に、1936年頃からナチに冷遇されていたようだ。
彼の理論は、普遍を目指す傾向があり、特殊ナチ的文脈にはそぐわない部分があったからだ。
代わりにケルロイターという学者が、ナチの主張に合致した理論により、イデオローグの筆頭となった。
しかし、ナチ滅亡後の現代においてケルロイターの名は聞かれない。
それに比べ、シュミットは今でも注目されている。
普遍を目指すその傾向により、ナチが滅んでもシュミット理論は生き残ると丸山は予想していたのかもしれない。
では日本の場合、戦後に復権しうるような理論が戦中に一つでも生まれたのか?
こうした問題意識が「超国家主義…」における、シュミットの言説と日本の超国家主義との対比に繋がったと考えられる。
このような対比による自国への批判は、丸山の西欧びいきの表れとも言える。
ただし彼の文章を読む限り、シュミットを賛美しているわけではない。
たとえば先述の、シュミットがケルロイターに代わられたという説明。そこでの客観的な分析と明晰な論理展開は実に見事である。
思想統制の吹き荒れる中にあって、冷静なトーンを失わずに文章を書く能力・姿勢は、まさに知識人と呼ぶに相応しい。
しかしながら、戦中にシュミット理論について書いたり訳したりしたことの社会的意味は無視できない。
それらのファシズム理論研究が、日本のファシズム運営にとっての参考資料になりえたことは、当時の社会的文脈から明らかだ。
『戦中と…』の「あとがき」によると、みすず書房から丸山に本書作成の提案があったのは1950年代だったという。
だが彼は気乗りせず、1976年にようやく出版された。
気が乗らなかったのは、やはり戦中の文章のテーマ選びに思うところがあったからだろうか。
