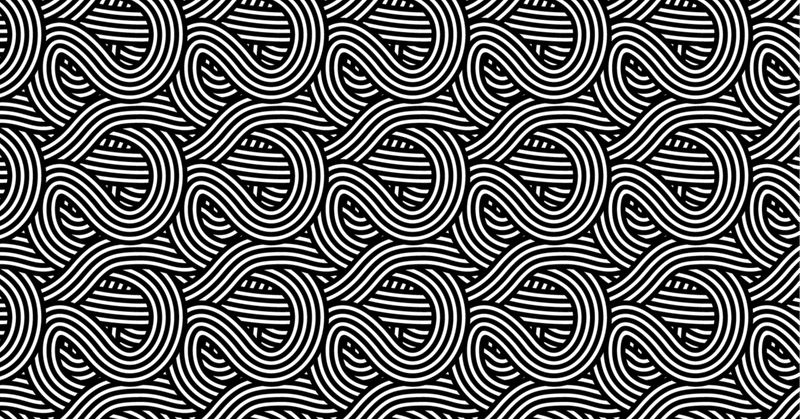
子どもの明日を奪う
2024年6月24日(月)朝の6:00になりました。
誰も学んでいないのに教えたというのは、誰も買っていないのに売ったというのと同じだ。
どうも、高倉大希です。
昨日の教え方で今日教えれば、子どもの明日を奪う。
アメリカの哲学者、ジョン・デューイの言葉です。
子どもを育てる家族は、世代の異なる大人です。
子どもを育てる先生も、世代の異なる大人です。
大人が生きてきた世界と子どもが生きていく世界は、まったくの別ものです。
同じ教え方が通用すると思う方が、おかしな話だというわけです。
友達の話では、欧米の経営者は、自分の時間の七割ぐらいを次世代の育成に使うそうです。経営者の育成は経営者にしかできないという発想なんですが、具体的には、論理を外してあげる作業をしているのではないかと思うんです。
齟齬が生まれやすいので、SNS上での文面のやりとりには注意しましょう。
拡散の恐れがあるので、SNS上での個人情報の扱いには注意しましょう。
SNSなんて使ってこなかった世代の大人が、子どもに向かってこう言います。
べつに何も間違っちゃいないのですが、どうにも説得力がありません。
テレビは、明るい部屋で離れて見ましょう。
子どもたちからしてみれば、こう言われているようなものなのかもしれません。
子どもを「よい子」にしようとする親は、子どものことを思って一所懸命のように見えて、自分が危険に会うのを恐れている利己心を内に隠していることが多い。
だからこそ、悩むんじゃないか。
大人たちからは、こんな声が聞こえてきます。
どう考えても説得力がないのは、わかっている。
どう考えても説得力はないのだけれど、どうすればよいのかがわからない。
これこそが教育の難しいところであり、おもしろいところでもあります。
大人自身が学び続けていなければ、どうしようもないのです。
「うちの子、家でゲームばっかりしてて、なにかやりたいことはないのかしら」かんて心配している親御さん。その子のやりたいことは「家にいたい」「ゲームしたい」なんですよ。
若い世代の参加を願うなら、口は出さずに金を出してください。
本当に、よく言ったものだなと思います。
口を出そうというのなら、ズレているという前提に立っておかねばなりません。
その上で、子どもと共に歩み続けねばなりません。
口を出す大人が歩みを止めたら、むしろ子どもの足を引っ張りかねません。
昨日の教え方で今日教えれば、子どもの明日を奪います。
毎朝6時に更新します。読みましょう。 https://t.co/rAu7K1rUO8
— 高倉大希|インク (@firesign_ink) January 1, 2023
サポートしたあなたには幸せが訪れます。

