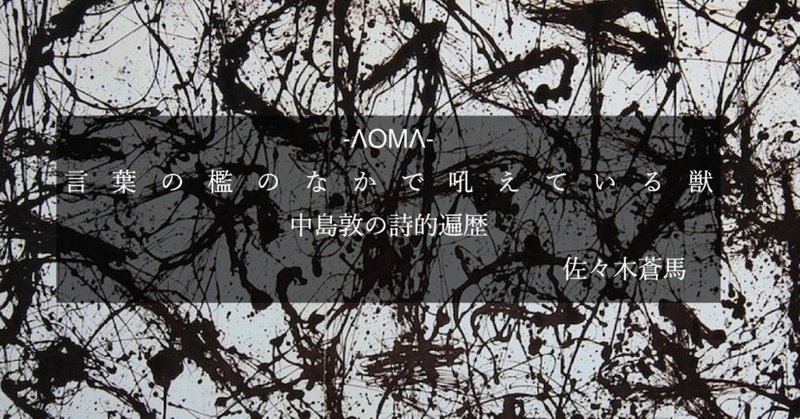
言葉の檻のなかで吼えている獣 中島敦の詩的遍歴 #4 「文字禍」
言語の限界と「現象to現象」
この〈言語〉を超えたコミュニケーションの出現という変化は、既存の言語等の記号を中心に体系化された世界にいると、理解が難しいのかもしれない。しかし、〈言語〉を通して、新しい概念や感覚を表現しようとすれば、その限界は明らかになるだろう。言語の論理体系は周遊的な構造となり、どの言語の組合せが何の言語を生むかという話に行き着いてしまう。言語で記述した瞬間に、その枠組みに規定され、その裏にある非言語的な現象空間、生のデータで表現されるものに接続する回路が無意識的になる。「現象to現象」の多大な可能性が、言語化した瞬間に人間に理解可能な空間に縮退されてしまうのだ。
(中略)
そういった点で「言語」は不可逆圧縮を用いた不完全な情報伝達ツールだ。人間の知覚や体験を、本来の情報量を縮減した単語を用いて交流している。しかし現代では、ARやVRの進歩によって、光や音を使ったコミュニケーションが発達している。空間そのものを他人に転送できれば、わざわざ言葉に変換して意味を削ぎ落とさなくても、空間自体を再生することで情報を伝える、本当の意味での「現象to現象」が実現する。
(落合陽一『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』PLANETS 2018年6月)
僕たちは膨大な情報量の世界を見ています。あるいは、夢を見て、目覚めたあと、誰かにその夢の光景を語ろうとする。ポツポツ……と思い出した光景の断片を言葉にしていく。が、まったく夢の全貌が伝わらなくてもどかしい。などということは日常的によくあるわけで、僕たちはものを「考える」とき、言語外の認識もしているのです。そして、それを、自分なりに「落とし込む」ときに、言語化するんですね。僕もいま、こうして、「言葉」を書いて、「落とし込む」ということをしているわけですね。
とはいえ、この「言語化」という行為がまた、なかなか厄介なもので……、いま、僕の頭のなかはたくさんの「言葉」でいっぱいになっていて、キーボードを打つ指よりも早く、「言葉」が駆けめぐっています。そして、時間差をつけて、こうして「文字」としてあらわれていきます。ずいぶん遅い。しかも、「ローマ字打ち」という、なんとも不思議なことを僕たちはしている。一文字打つために、ときに「3つ」のキーを叩くことがある。この「遅延」。頭のなかの「言葉」は、もうこのときにはどこかに行ってしまっています。残されたものだけが、拾いきれたものだけが、「ここに」残ることになるのです。「文字」として。
「文字」。言葉には、音声がともなう。けれども、こうして僕が書いているものをみなさんに届ける際に目にする「文字」には音声がありません。当然ですが。音声は感情の起伏等も反映しますから、場合によりますが、より情報量の多い表現方法であるとも言えます。さらに言えば、映像にまで拡大すれば、「現象」を「現象」として、より近いかたちで伝達することができるはずです。それなのに、僕たちはなぜこの「文字」を使ってコミュニケーションをとるのか。それ以上に、「文学」が、そうした「言葉」や「文字」を敢えて使っていること。なぜ、「文字」なのか。「文字」とは何だ。「文字」を使うということは、どういうことなのか。それを、考えてみなければならないのではないか。(ああ、こう言っている間にも、「言葉」がどこかに流れていく)。ということで、今回の中島敦の作品は「文字禍」です。「掴みそこね」も愉しみながら先に進んでいきましょう。
「文字禍」を読む
文字の霊などというものが、一体、あるものか、どうか。
アッシリヤ人は無数の精霊を知っている。夜、闇の中を跳梁するリル、その雌のリリツ、疫病をふり撒くナムタル、死者の霊エティンム、誘拐者ラバス等など、数知れぬ悪霊共がアッシリヤの空に充ち満ちている。しかし、文字の精霊については、まだ誰も聞いたことがない。(「文字禍」)
またも僕たちは紀元前のアッシリア帝国末期の世界に旅立ちます。そこでは、たくさんの霊がいる時代なのですが、「文字の霊」というものだけは誰も知らないようです。しかし、毎夜図書館(この時期の本は粘土板)から声が聴こえるという噂がたちました。そこで、アシュル・バニ・アパル大王は、「巨眼縮髪の老博士ナブ・アヘ・エリバ」に研究を命じ、ナブ・アヘ・エリバ博士は毎日毎日文字とにらめっこをすることになりました。すると、こんなことが起こってきたそうです。
一つの文字を長く見詰めている中に、何時しか其の文字が解体して、意味の無い一つ一つの線の交錯としか見えなくなって来る。単なる線の集まりが、何故、そういう音とそういう意味とを有つことが出来るのか、どうしても解らなくなって来る。老儒ナブ・アヘ・エリバは、生れて初めて此の不思議な事実を発見して、驚いた。今迄七十年の間当然と思って看過していたことが、決して当然でも必然でもない。彼は眼から鱗の落ちた思がした。単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有たせるものは、何か? ここ迄思い到った時、老博士は躊躇なく、文字の霊の存在を認めた。(「同上」)
これはみなさんも漢字の練習をしているときなどにも体験したことがあるでしょう。いわゆる「ゲシュタルト崩壊」というものですが、さて、そうしてただの線に見えてきたところで、なぜそこに「音」と「意味」が付与されるのか、と考えたところで、それを統合しているのが「文字の霊」なのではないかとナブ・アヘ・エリバ博士は考えたわけです。そこで、博士は街に出てフィールドワークを行います。そこで得た知見はこうです。
それによれば、文字を覚えてから急に蝨を捕るのが下手になった者、眼に埃が余計はいるようになった者、今まで良く見えた空の鷲の姿が見えなくなった者、空の色が以前ほど碧くなくなったという者などが、圧倒的に多い。「文字ノ精ガ人間ノ眼ヲ喰イアラスコト、猶、蛆虫ガ胡桃ノ固キ殻ヲ穿チテ、中ノ実ヲ巧ニ喰イツクスガ如シ」と、ナブ・アヘ・エリバは、新しい粘土の備忘録に誌した。文字を覚えて以来、咳が出始めたという者、くしゃみが出るようになって困るという者、しゃっくりが度々出るようになった者、下痢するようになった者なども、かなりの数に上る。「文字ノ精ハ人間ノ鼻・咽喉・腹等ヲモ犯スモノノ如シ」と、老博士はまた誌した。文字を覚えてから、にわかに頭髪の薄くなった者もいる。脚の弱くなった者、手足の顫えるようになった者、顎がはずれ易くなった者もいる。しかし、ナブ・アヘ・エリバは最後にこう書かねばならなかった。「文字ノ害タル、人間ノ頭脳ヲ犯シ、精神ヲ痲痺セシムルニ至ッテ、スナワチ極マル。」文字を覚える以前に比べて、職人は腕が鈍り、戦士は臆病になり、猟師は獅子を射損うことが多くなった。これは統計の明らかに示す所である。文字に親しむようになってから、女を抱いても一向楽しゅうなくなったという訴えもあった。もっとも、こう言出したのは、七十歳を越こした老人であるから、これは文字のせいではないかも知れぬ。ナブ・アヘ・エリバはこう考えた。埃及人は、ある物の影を、その物の魂の一部と見做しているようだが、文字は、その影のようなものではないのか。(「同上」)
なるほど。「文字」とは「影」である。このときの「文字」は「言葉」とほぼ同義でしょう。「藝術」という「言葉」を覚えた職人は「藝術」(という概念)を作ろうとして腕が鈍る。「敵」と戦う戦士は目の前の人ではなく「敵」(という言葉)と戦うことになる。猟師は実体としての「獅子」ではなく「獅子」という「言葉」を狙う。男は「女」(というイメージ)を抱く。そういう物の「影」を追うようになってしまう。「言葉」に「落とし込」まれたものは「影」にすぎない。「現象」や「実体」そのものではない、という言語の限界のようなものに、すでに中島敦は気づいていたのでしょうねえ。
そこで、ナブ・アヘ・エリバ博士はある書物狂の老人のことを思い出します。その老人は、あらゆる言語を読むことができ、あらゆる知識を持っています。しかし、今日の天気がわからない、他人の慰め方がわからない、いま、自分がどんな格好をしているのかもわからない。しまいには書物愛が昂じて粘土板を溶かして飲んでしまう。近眼で、臍に顎がつくほどのせむしだが、そんなことには気づかない。しかし、いつも彼は幸せそうにしている。それはなぜなのか、と考えたところ、やはりこれも、文字の霊の魔力に違いないと考えたのです。
そして、ナブ・アヘ・エリバ博士のもとに、若い歴史家イシュデイ・ナブが訪ねてきて「歴史とは何ぞや?」と問いかけます。ナブ・アヘ・エリバ博士は答えません。再びナブは問い直します。「歴史とは、昔、在った事柄をいうのであろうか? それとも、粘土板の文字をいうのであろうか?」。ナブ・アヘ・エリバ博士は答える。「歴史とは、昔在った事柄で、且つ粘土板に誌されたものである。この二つは同じことではないか」。ナブはまた問う。「書洩らしは?」。ナブ・アヘ・エリバ博士は答える。「書洩らし? 冗談ではない、書かれなかった事は、無かった事じゃ。芽の出ぬ種子は、結局初めから無かったのじゃわい。歴史とはな、この粘土板のことじゃ」。さらに言う。「君やわしらが、文字を使って書きものをしとるなどと思ったら大間違い。わしらこそ彼等文字の精霊にこき使われる下僕じゃ。しかし、又、彼等精霊の齎す害も随分ひどい。わしは今それに就いて研究中だが、君が今、歴史を誌した文字に疑を感じるようになったのも、つまりは、君が文字に親しみ過ぎて、其の霊の毒気に中ったためであろう」。
このように説明したあとで、若い歴史家は帰っていきます。そして、ナブ・アヘ・エリバ博士はこう反省する。「今日は、どうやら、わしは、あの青年に向って、文字の霊の威力を賛美しはせなんだか?」「わし迄が文字の霊にたぶらかされおるわ」。実際のところ、博士自身の症状は悪化していったのです。文字が線に見えるだけでなく、あらゆる構成物がなぜそうなっているのか、すべてが疑わしく見えてしまう。気が違いそうになった博士は、このままでは命が危ないと、アシュル・バニ・アパル大王に急ぎ研究報告をまとめて、提出しました。すると、文化人たる大王は機嫌を損ね、即日博士は謹慎を命じられることになりました。これも、博士は文字の霊の復讐であると考えましたが、文字の霊の復讐はそんなものでは終わらなかった。博士が地下の書庫にいるときに、たまたま大地震が起き、ナブ・アヘ・エリバ博士は数百枚の粘度板の下敷きになって圧死してしまったのです。
ああ、また死んでしまいましたね……。ただ、ここで嘆いていても仕方ありません。ナブ・アヘ・エリバ博士が死んでしまった、ということ、その過程についてどういうことなのか考えてみましょう。
絶対無分節の世界
そのために、一回迂回してみたいと思います。
井筒俊彦さんの『意識と本質 精神的東洋を索めて』(岩波文庫 1991年8月)を紐解いていきましょう。この「文字禍」を考えるうえで、重要なことが見えてくるはずです。まずは、最初にサルトルの「嘔吐体験」の文章が引かれるので、そこからはじめましょう。
マロニエの根はちょうどベンチの下のところで深く大地につき刺さっていた。それが根というものだということは、もはや私の意識には全然なかった。あらゆる語(ことば)は消え失せていた。そしてそれと同時に、事物の意義も、その使い方も、またそれらの事物の表面に人間が引いた弱い符牒(めじるし)の線も。背を丸め気味に、頭を垂れ、たった独りで私は、全く生のままのその黒々と節くれ立った、恐ろしい塊りに面と向って坐っていた。(同上)
これはもうすでに「文字禍」のことを語っているようにしか思えないわけですが、急がずに、一旦井筒さんの話を聞きましょう。
絶対無分節の「存在」と、それの表面に、コトバの意味を手がかりにして、か細い分節線を縦横に引いて事物、つまり存在者、を作り出して行く人間意識の働きとの関係をこれほど見事に形象化した文章を私は他に知らない。コトバはここではその本源的意味作用、すなわち「本質」喚起的な分節作用において捉えられる。コトバの意味作用とは、本来的には全然分節のない「黒々とした薄気味悪い塊り」でしかない「存在」にいろいろな符牒を付けて事物を作り出し、それらを個々別々のものとして指示するということだ。老子的な言い方をすれば、無(すなわち「無名」)がいろいろな名前を得て有(すなわち「有名」)に転成するということである。しかし前にもちょっと書いたとおり、およそ名があるところには、必ずなんらかの形での「本質」認知がなければならない。だから、あらゆる事物の名が消えてしまうということ、つまり言語脱落とは、「本質」脱落を意味する。そして、こうしたコトバが脱落し、「本質」が脱落してしまえば、当然、どこにも裂け目のない「存在」そのものだけが残る。「忽ち一挙に帷(とばり)が裂けて」「ぶよぶよした、奇怪な、無秩序の塊りが、怖ろしい淫らな(存在の)裸身」のまま怪物のように現われてくる。それが「嘔吐」を惹き起すのだ。(同上)
なるほど。最初に落合陽一の文章を引いてお話しましたが、たとえば「夢」自体は「絶対無分節」の状態と言っていいですね。すなわち「現象」自体。そして、それを言語化しようとするときに「分節」が起こる。断片断片を、理解できる言葉に置き換えていく。だが、一旦、その言葉が剥奪されてしまえば、その「夢」(「現象」)は「夢」(「現象」)として目の前に立ち現れる。そこで眩暈を感じ、嘔吐体験へとつながっていく。つまるところ、ナブ・アヘ・エリバ博士も、「文字」(言葉)が解体されることによって、あらゆるものがなにがなんだかわからなくなってしまう、「絶対無分節」の世界を覗き込んだということになるのでしょう。そして、中島敦はナブ・アヘ・エリバ博士に「絶対無分節」の世界を覗かせたところで(ほとんど)発狂させました。僕は、これは、今回の主人公がただ単に「研究者」であったからなのではないかなあと思うわけで、また別の存在だったら、この世界を生き抜けたのではないかと思うのです。というのも、もう少し迂回をつづけて井筒さんの話に耳を澄ましましょう。
吉州青原惟信禅師のこの述懐、あまりにも世に有名でいまさら引用するまでもないが、論を進める便宜上、敢えてここに掲げて、無「本質」的分節の分析の手がかりとする。曰く、
「老僧、三十年前、未だ参禅せざる時、山を見るに是れ山、水を見るに是れ水なりき。後来、親しく知識に見(まみ)えて箇の入処有るに至るに及んで(すぐれた師にめぐり遇い、その指導の下に修行して、いささか悟るところあって)、山を見るに是れ山にあらず、水を見るに是れ水にあらず、而今、箇の休歇(きゅうかつ)の処を得て(いよいよ悟りが深まり、安心の境位に落ちつくことのできた今では)、依前(また一番最初の頃と同じく)、山を見るに祇だ是れ山、水を見るに祇だ是れ水なり」(『続伝燈』二十二、『五燈会』十七)
骨身を削る長い修行の年月を経て、ついに「箇の休歇を得」て豊熟しきった青原惟信が禅者としての己れの生涯を回顧して、これを三つの段階に分ける。第一段は禅の道に入る以前の時期。当然、彼は普通の人の普通の芽で、自己の外なる世界を眺めている。山は山であり、川は川。世界は有「本質」的にきっぱり分節されている。同一律と矛盾律によって厳しく支配された世界。ここでは、山はどこまでも山であって川ではない、川ではありえない。山は山の「本質」によって規定され、川はまた川の「本質」にとって規定されているからだ。
ところが、参禅して、一応見性し、ある程度の目を開いて見ると、世界が一挙に変貌する。第一段階であれほど強力だった同一律と矛盾律が効力を失って、山は山でなく、川は川でなくなってしまうのだ。山も川も、あらゆる事物が、「本質」という留金を失う。それまで、いわゆる客観的世界をぎっしり隙間なく埋めつくしていた事物、すなわち「本質」結晶体が融けて流れだす。存在世界の表面に縦横無尽に引きめぐらされていた分節線が拭き消される。もはや山は山であるという結晶点をもっていない。川は川であるという結晶点をもっていない。つまり、山はもう山ではないし、川はもう川ではないのだ。そして、そんな山や川を客体として自分の外に見る主体、我、もそこにはない。すべてが無「本質」、したがって無分節、もっと簡単に言えば、「無」なのである。これが青原惟信の説く第二段階。本論の最初の部分で問題にしたサルトルの、マロニエの木の根を私は憶い出す。だが、これに続いて次の第三段階があるゆえに、禅の存在体験は、サルトル的実存体験とはまるで違ったものになってしまうのである。
第三段階は再び「有」の世界。第二段階で一たん無化された事物がまた有化されて現われてくる。第一段階の世界と一見少しも違わぬ事物の世界が目の前に拡がる。山を見れば、それは以前と同じく山であり、川を見れば、相も変わらぬ川。要するに「休歇を得た」達道の人の目に映るのは、第一段と同じく分節された存在の姿、分節的世界なのである。だが、第一段の分節世界と第三段の分節世界との間には一つの決定的な違いがある。
既に見たように、第一段階でそれぞれに「本質」を与えられ、整然と分節されていた様々な事物は、第二段階で「本質」を奪われ、分節を失う。第二段階から第三段階への移りにおいて、それらの分節は全部また戻ってくる。しかし、分節は戻るが、「本質」は戻ってこない。存在分節があるからには、もはや無一物の世界ではない。山は山として存在し、川は川として存在する。山もあれば川もある。だが、それらの山や川には「本質」がない。言い換えれば、それらの山や川は「本質」的凝固性をもたない山である川であるのだ。(同上)
これは、禅体験によって見える世界が変化する過程をたどっているわけですが、三段階あるとされていましたね。そしてそれぞれにこう名付けておられます。
第一段階「山は山である」(分節Ⅰ)
↓
第二段階「山は山ではない」(無分節)
↓
第三段階「山は山である」(分節Ⅱ)
「分節Ⅰ」というのは、通常の言葉の世界ですね。「根」なら「根」。そして、サルトルの世界観と、この中島敦の世界観は第二段階の「無分節」の世界をのぞくことで発狂ないしは嘔吐するということになるわけでしょうねえ。
よく考えてみれば、中原中也の「名辞以前」というのも「無分節」世界だと思うわけです。「一、「これが手だ」と、「手」といふ名辞を口にする前に感じてゐる手、その手が深く感じられてゐればよい」(中原中也「藝術論覚え書」)。という有名な説明がありますが、「名辞を口にする前に感じてゐる手」というのは「無分節」の「手」ということでしょう。そして、そこから言葉を拾ってきたもの「詩」である。と、すれば、すなわち第二段階の「無分節」から第三段階の「分節Ⅱ」というところまでいくことは、詩人の所業そのものなのではないか、と言ってみることもできると思います。
詩人の四元康祐さんも井筒さんの話を引いて「詩人とは本来言葉の意味分節作用の及ばない世界を改めて言語化する能力を有するもの、すなわち世界の「初め」を非分節的に分節する特殊技能者に他なりません」(四元康祐『詩人たちよ!』思潮社 2015年4月)としています。
「地獄の季節」を生きること
そのように考えるならば、今回の「文字禍」という作品においてナブ・アヘ・エリバ博士が「無分節」で発狂してしまう運命をたどってしまったのは、ほかならぬナブ・アヘ・エリバ博士が「研究者」であったからなのかもしれません。これが、詩人であったのならば、また次の季節を生きることになったのではないでしょうか。詩人は、「文字禍」的世界観のさらに先、「分節Ⅱ」の世界を歩くことだ。と考えだしたとき、ああ、ランボーに行き着くなあ。と僕は思いました。
「手始めは周作だった。私は沈黙や夜を書き記した。ことばには言い表せぬものを書き留めた。そして眩暈を定着した。」(ランボー「地獄の季節」宇佐美斉訳)
この「沈黙」や「夜」という「ことばには言い表せぬもの」はまさに「無分節」の世界ですよね。そんな世界による「眩暈を定着した」というのは、第三段階「分節Ⅱ」にいたったのかもしれません。「地獄の季節」というのは、まさに「無分節」の地獄を歩き、「分節Ⅱ」に定着(?)させていくことなのかも。
「ある宵のこと、私は美を膝のうえに坐らせた。――苦い味がすると思った。――そこでそいつを罵倒してやった。」
「私がつねに劣等種族であったことは、疑いのないところだ。反抗ということが、私には理解できないのだ。わが種族が蜂起したのは、もっぱら略奪のためだった。まるで、おのれの力で殺したのでもない獣にむらがる狼のように。」
「なるほど、そうだった。異教徒のことばを使わないでは、自分の言いたいことが言えないのだから、もう黙っていることにしよう。」
「さあ! 前進だ、重荷、砂漠、倦怠、そして怒り。
誰に仕えたらいいのだろう。どのような獣を崇めねばならないのか。いかなる聖像を攻撃するのか。どのような心を打つ砕くことになるのだろうか。どんな嘘をつかなければならないのか。――どのような血のなかを歩むのか。」(同上)
あらゆる「美」や「神」というものから見放された場所で、「劣等種族」として、「異教徒」として、なんの絶対的なものもない世界、まさに「生のままのその黒々と節くれ立った、恐ろしい塊り」のなかを生きる。そこでの「錯乱」を「言葉の錬金術」によって定着させていく。とても恐ろしい、不安でいっぱいな世界。詩を書く、ということは、そういうことなのでしょうか。そんななかを僕たちは歩いているのでしょうか。
中島敦は、どうだろうかというと、そういうところにまで、無意識では気づいていたかもしれないなあ。こうした「文字」(言葉)に対する恐怖を描きながら、それでも「文字」を綴っていく作家としての姿勢は、まさにその「無分節」の世界を歩き、「地獄の季節」に生きているということに違いないから。だから、「虎」になってしまったのねっていまならなんとなくわかりますね。
ずいぶん長くなりました。もうこれでおしまいでもいいのですが、最後にもう一回。「山月記」に帰っていくことにしますか。それではまた次回、お会いしましょう。
現在、詩集『ENDEAVOUR』作成中です。
先行公開版が以下のマガジンで読むことができます。
マガジンを購入していただくと『ENDEAVOUR』収録予定の新作詩はすべて読むことができるので、一篇ずつ購入するよりもお得です。
おかげさまで早速購入してくださったり、ご支援くださる方もいらっしゃり、感謝の気持ちでいっぱいです。
詩集の出版費用は高額で、なかなか個人で賄える金額ではありません。ここで購入・支援してくださったものはすべて詩集の出版費用にあてさせていただきます。応援してくださる方は、どうぞよろしくお願いいたします。
ツイキャス「蒼馬の部屋」はじめました。
毎週水曜日・日曜日22:00~
萩原朔太郎や立原道造などの詩を朗読し、語っていきます。
Web Magazine「鮎歌 Ayuka」は紙媒体でも制作する予定です。コストもかかりますので、ぜひご支援・ご協力くださると幸いです。ここでのご支援は全額制作費用にあてさせていただきます。
