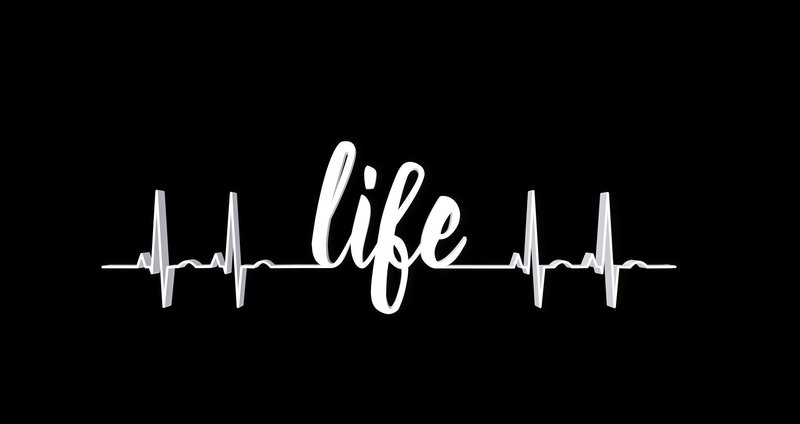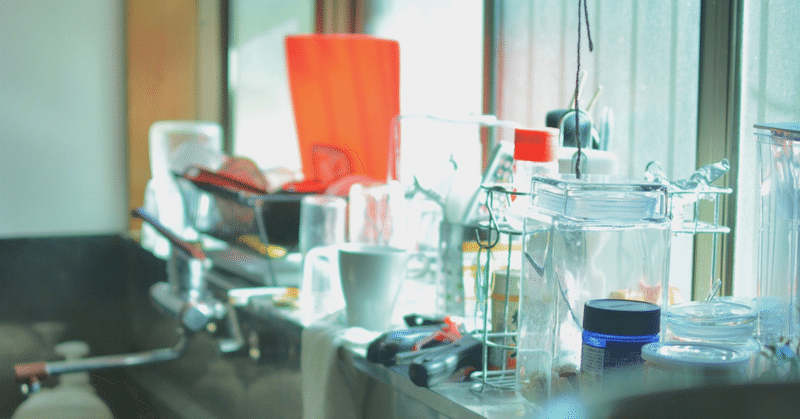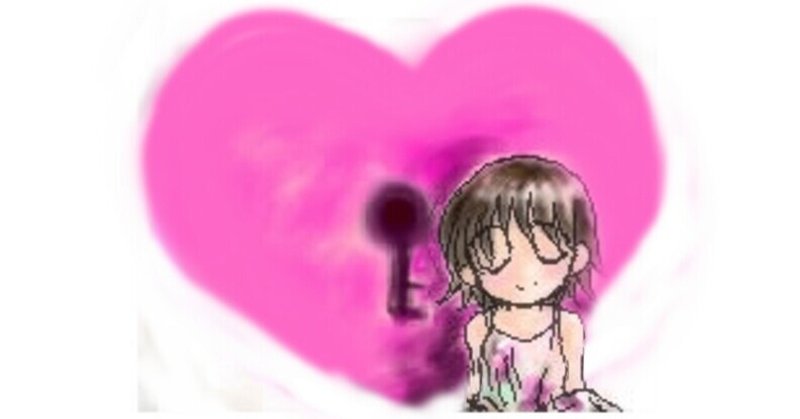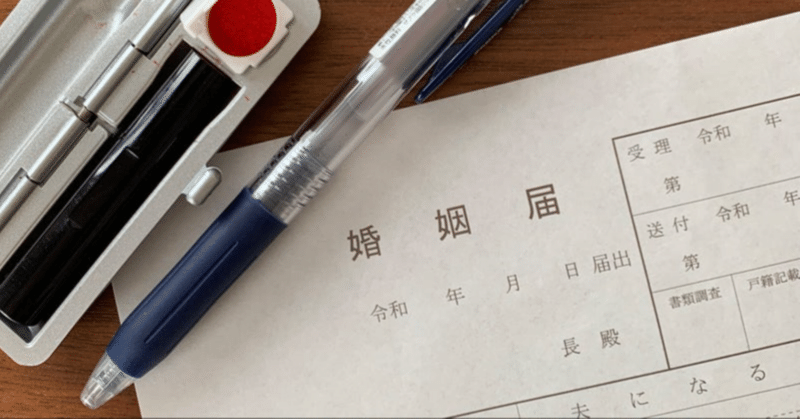2022年1月の記事一覧

今日の名言は、「私にはもう何も残っていませんが、あなたの優しさだけは今も確信しています。これ以上、あなたの人生を無駄にするわけにはいかないのです。今までの私たち以上に幸せな二人は他にはありません。」
パンケーキ大好きなかおるんです。いつもエンピツカフェの決まった席で本を読んでいます。 悩みごとがあるときに、ふっと何か大切なものを気づかせてくれる先人の名言を紹介しますね。 ブルームズベリー・グループとは、1905年から第二次世界大戦ごろまで存在したイギリスの芸術家や学者からなる組織。 革新的で個人の自由意思を尊重する思想をもって、文学、絵画、経済学、政治などの幅広い分野で、非常に大きな影響力をもった芸術家集団なんです。 ブルームズベリー・グループは、性の問題について進歩的