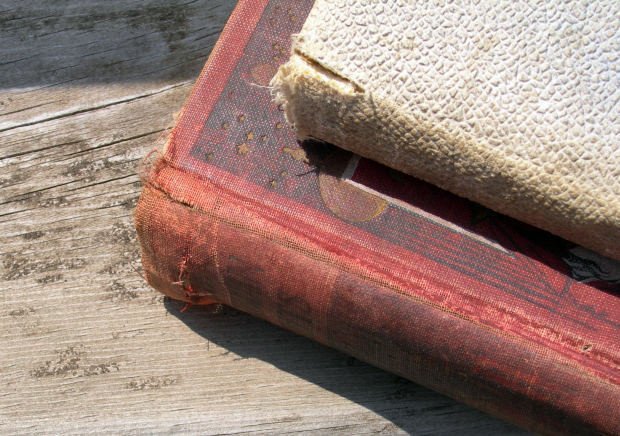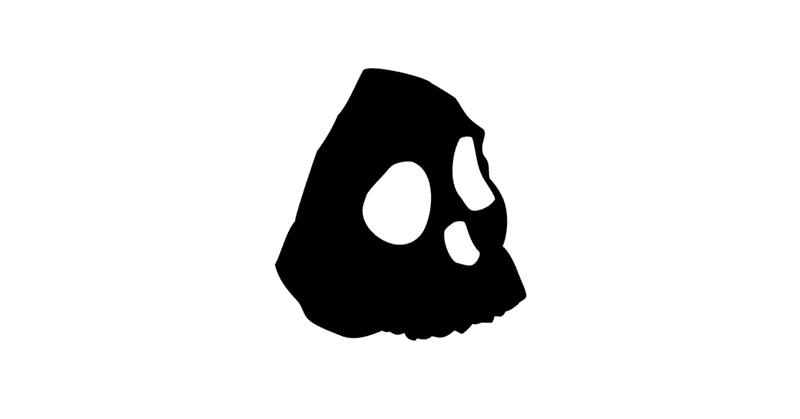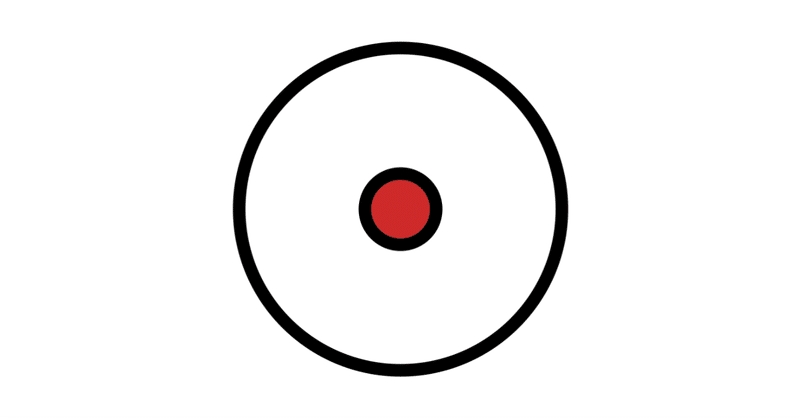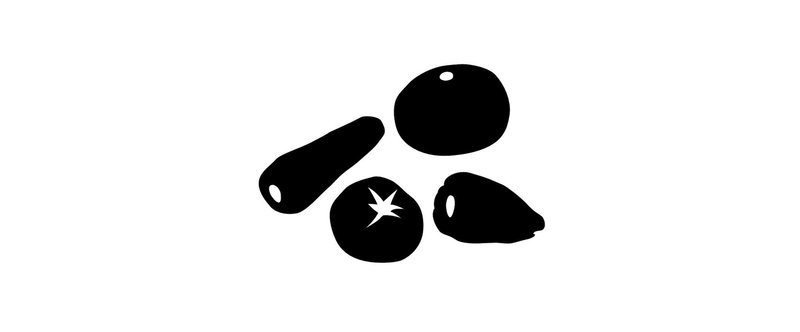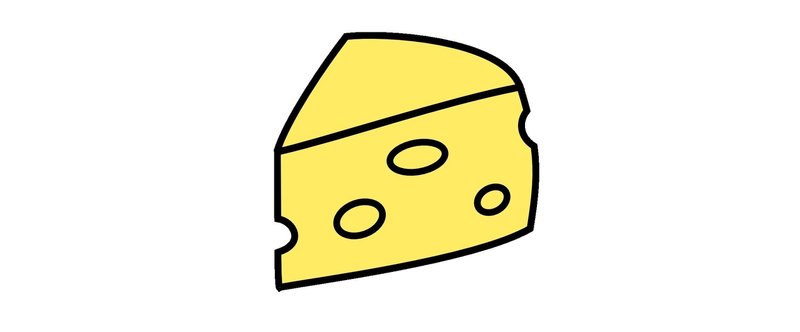#人類学
ネアンデルタール人の贈り物
最近の人類学の研究結果で,最も人々を熱狂させたもののひとつは,やはりネアンデルタール人と,我々ヒトが交雑していたということだろう.このnoteでも,何度かそれに関連する記事を公開している(バック・トゥ・ザDNA, 【書評】ネアンデルタール人は私たちと交配した).ネアンデルタール人と我々ヒトがいったいどんな社会関係を結んでいたのか,という問いも興味深いが,ネアンデルタール人が我々ヒトにどんな遺伝
もっとみる遊びを生む脳のデザイン
仮に人生に意味があるとして、我々は何のために生きているのだろう。子孫を残すため、というのは一応一つの答え方だと思う。少なくとも我々の誰もが、同時代人の中で不釣り合いに多くの子孫を残した祖先を持っている。恋愛、嫉妬、親としての愛情、身内びいきなど、祖先から受け継いだ強烈な衝動に駆られ、ヒトは、他の動物と同様、あたかも子孫を残すことが目的であるかのように生きてきたのではないか。
しかし、社会全体