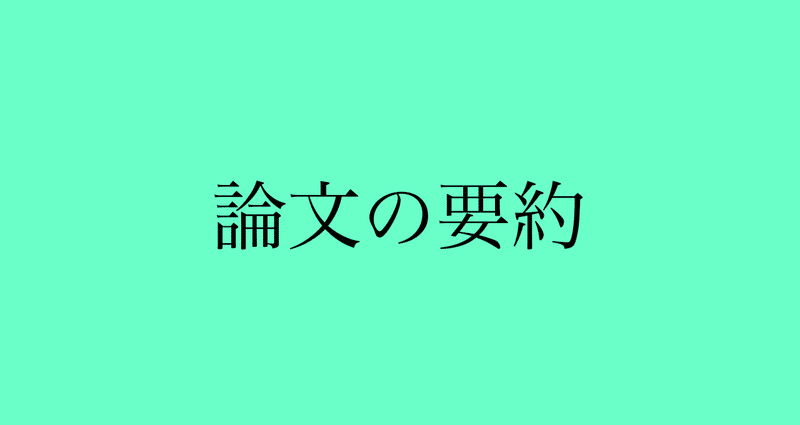2023年5月の記事一覧
【要約と学術的意義】ゴットフリート・ゼムパー(河田智成編訳)「建築芸術の四要素」『ゼムパーからフィードラーへ』
(1)要約
『建築芸術の四要素』(1851)は、ゼンパーによる古代ギリシャ建築のポリクロミー調査研究と、建築物を原始時代に作られた構造までに遡り、建築を成り立たせる要素を4つに分類した建築論となっている。構成は、Ⅰ「概観」、Ⅱ「ピュティア」、Ⅲ「科学的根拠」、Ⅳ「推論以上のもの」、Ⅴ「四つの要素」Ⅵ「応用」からなる。そのうちⅠからⅣまでの前半はポリクロミー表現の調査研究。後半部のⅤ〜Ⅵは建築の四要