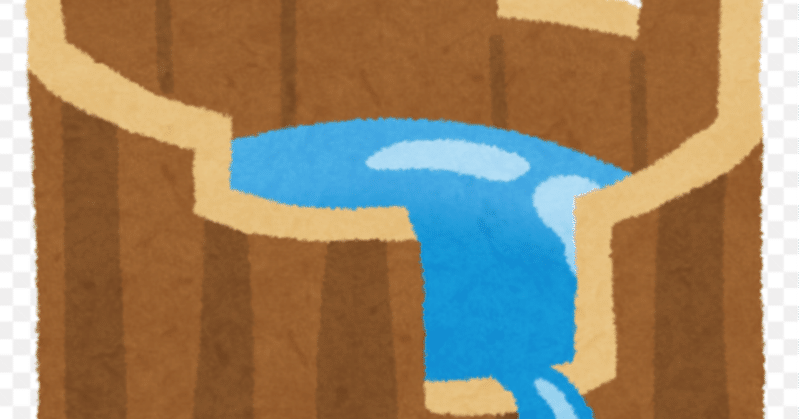- 運営しているクリエイター
2020年7月の記事一覧
授業が上手になるために 学ぶとはまねをすること(辞書にもそう書いてある)
見せてあげてほしい昨今、教員の多忙化がいろんなところで言われるようになった。それがたくさん叫ばれて、現場の必要のない物が削がれていってほしいと思う。まだまだ実際の現場はそうなっていないのだが……。
初任者研修というのものがある。
一日でも早く新任の先生が担任として独り立ちできるようにと、現場を離れて遠くまで偉い先生の話を聞きに行ったり、レポートや指導案を書いて見せたりするモノである。子どもと一緒
授業のちょっとしたコツ6 集団をふりむかせる 大村はま先生に教わったこと
今回は授業だけではなくいろんな場面で使えること。
そして、単純だがすごく効果があったこと。
教室で40人の子どもを前にして、一斉に振り向かせるときあなたはどの言葉を選ぶか。
みなさん!
ちょっと静かにしてください!
いい加減に静かにしなさい!
授業のちょっとしたコツ5にも書いたが、集団意識が働いているとき、子どもは自分のこととして話を聞かない。みんな静かにしてないから良いやなんて思いがち。で、
小学校でも外国語学習が始まっています 授業にはどのようなイメージを……その2
その1での前置きが長くなってしまった。
さて、小学校の英語学習である。
多くの反省?を踏まえて『英語が話せるように』という考えを念頭に置き始まった(はず)。
まず、小学校では英語を教えるのは担任である。
中学では英語の先生がいたと思う。先生の個人差はあるが、英語を専門に教える先生がいる。中には流ちょうに英語を話せる先生もいたと思う。そうでなくても、それなりに英語を専門に勉強してきた先生であり“
小学校でも外国語学習が始まっています 授業にはどのようなイメージを……その1
小学校でも外国語学習が本格的に始まっている。高学年と呼ばれる5年生6年生では、きちんと評価され通知表に評価と評定が記載される。これで、小学校でも9教科の評価評定がされることになった。
さて、そんな小学校での外国語学習だが、どんなイメージをもっているだろうか。
ほとんどの学校では外国語として「英語」を選択しているだろう。中国語やフランス語、ドイツ語などももちろん「外国語」であるが、外国語学習として
新しい観点の本来の目的に即しているか自信が……
知識・技能
思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度
今年度から新しくなった、通知表の評価の観点である。
今までは各教科ごとに観点がちがっていたはず。関心・意欲・態度を筆頭に、数学的な考え方だとか、話すこと・聞くことだとかがそれぞれの観点としてあった。体育とか音楽などは、技能という観点でその技能そのものを評価されていた。
それが、全ての教科において、上に挙げた3つの観点に統一された。国
授業のちょっとしたコツ5 “たち”は使わない 目を見てあなたと言ってみよう
授業をしていると、聞いてくれているのかなと不安になることがある。それは、子どもと目が合わないときだ。
これは、すでに3年生の国語の教科書なんかには具体例とともに学習する事項である。
・言い方に気をつける……同じ言葉でも、口調によって困っているように聞こえたり怒っているように聞こえたりしてしまう(だから、メールなどでは誤解が生まれやすくトラブルの元になり生徒指導の種になっている)
・聞き方に気をつ
授業のちょっとしたコツ3 ノートを持って一列に並ばせて○をつけていきます 気をつけることは……
今回はちょっとした簡単なお話。
どの教科でもやるが、算数の授業なんかでよく、“(問題が)できた子から前にノート持ってきてください”ということをやる。その時に何に気をつけているか。
ありがちなのは、行列が長くなりそこで子ども同士のおしゃべりが始まること。列が長くなるに比例して、声も大きくなっていく。人が増えれば声も増える。静かにしなさいと注意しても、なかなかならない。そりゃそうだ。話す以外やるこ
やらない理由を探すのではなく やる理由を探せる子どもを育てたい
今年になって様々な行事やイベントが中止・または延期になっているのは周知の事実だ。プロ野球やJリーグはようやく始まったが、広く見渡せばこれはかなりレアなケース。多くの競技で大きな大会の中止が決まっている。
高校は春の選抜大会から夏のインターハイ、秋の国体と全てのタイトルマッチが中止となった。中学では同じく春の選抜と夏の全中が中止に。年齢制限のある中高生の大会は、延期にすることなど無意味。ない=二度と
均等・平等ってこんなに足かせになる言葉だったっけ とりあえずやってみようよ
私がいた現場とは少し違うかもしれないけれど、でも、おおよそ同じようなことが上から言われて、苦心している方がいるのだなあと感じました。この記事にあるように、オンライン学習に限らず、“横並び”の意識の強さのあまりに潰されていった企画やお願いが無数にあるのが現場です。
教育の機会は均等であるべきでしょう。現実はお金がかかります。毎日着ていく服や持って行く用具は自費です。給食費も(本当に滞納している方も