
【年齢のうた】かぐや姫、風●「22才の別れ」が映し出す70年代の結婚観
いやいや、昨日はひさびさに神宮球場に行ってきたんよ。おーん。

試合後は去っていく選手が見れる
観戦した席はもっと違う場所だったけど。これは糸原、ミエちゃん、近本の三選手が引き上げていくところね。
試合開始前には、岡田・高津の両監督の握手を見届け、
終了後には、苦労人の大竹投手のいいヒーローインタビューが。
あ、間違えた(武者返し、食べてみたい…熊本のアンテナショップにある?)。ほんとはこっち。
まあ自分は、各ニュースメディアがSNS上の発言を記事の見出しにそのまんま使う風潮に疑問を持つ者ではありますが。この記事はまだいいほうですね。
そういえば神宮、攻守交代の時のブリッジはBECKの曲ですな。
つば九郎の空中くるりんぱチャレンジのあとに流れるのは、エレカシです。
そうして秋風を感じる中、今回は「22才の別れ」について書きます。
この歌は、かぐや姫、そして風の楽曲で、書いたのは伊勢正三。
僕自身は日本の抒情派と呼ばれるフォーク(あまり良くない言い方だと、四畳半フォーク?)とかニューミュージックは明るくないんですが、しかし【年齢のうた】というテーマ的に、どうしても避けて通ることができない重要な曲なんです。
過去に書いた藤圭子や南沙織と同じように。
ところでこの「22才の別れ」を作り、唄った伊勢正三は、どうしてもフォークシンガーというイメージが強いけど、そもそも彼はウェストコーストのサウンドに惹かれていたらしく、風、そしてソロ初期はそうしたAORなどを指向していた模様。こうした楽曲たちは近年になってシティ・ポップの見地から再評価されています。
伊勢の西海岸への関心の高さは、かつて風が出した本『風をたずさえて』の中でも1977年の暮れから1978年の年初までアメリカに行き、サンフランシスコとロスアンジェルスに滞在した日々が語られていることからも明らか。湿っぽいイメージが先行しているアーティストながら、実は当時のアメリカの乾いたサウンドを目指していたことを本題の前に触れておきます。
ということで今回はいつも以上にいろいろ調べながら、おそるおそる書いていきます。
5年の交際を終わらせ、別の人との結婚に踏み切ろうとする女性の心情
伊勢正三が「なごり雪」や、この「22才の別れ」を書いた人だということ、そして「正やん」と呼ばれてきたことも、ずいぶん前から自分は知っていた。このへんの知識は、中学生の頃にフォークが好きな友達がいたおかげだ(彼とは、かなり前に参加した同窓会でも会ってもいないが)。
ただ、「22才の別れ」は、ウェットな曲調と、歌詞の、やはりしんみりした感じがどうにもなじまなくて、とくにハマることも、何か思うこともなかった。
そうしてみると、今回、初めてちゃんと向かい合うようなものである。
伊勢正三のこの曲は、まず最初は3人組フォークグループのかぐや姫のアルバムの中の曲だった。その3作目『三階建の詩』には、「22才の別れ」と同じく伊勢による名曲の誉れの高い「なごり雪」も収録されている。これが1974年3月の発売。
そしてここには、これまた名曲とされる南こうせつ作曲の「神田川」(作詞は喜多条忠)が入っている。この曲は、それこそ社会現象を巻き起こすほどの大ヒットとなり、かぐや姫の名を一躍世に知らしめた。
しかし伊勢の書いた「22才の別れ」と「なごり雪」は諸事情により、本アルバムからシングルとしてリリースされることはなかった。
このへんの背景は複雑なのだが、そうしたことも絡みながら、やがてかぐや姫は解散へと至っていく。そして伊勢は大久保一久(元・猫)とともに2人組グループの風を結成する。
その風のデビューシングルに選ばれたのが、かぐや姫時代はアルバム曲であった「22才の別れ」だった。風バージョンの同曲が世に出たのは、かぐや姫版から1年近くあとの、1975年2月である。
思えば、かぐや姫の「神田川」も多くの議論を呼んだ曲だったが、この「22才の別れ」も、それにイルカの歌唱でやはりビッグヒットとなった「なごり雪」も多くの反響を呼び、歌で綴られている物語を深読みしたり、解析しようとする動きがたくさん起きた。
僕はこの時代はまだ子供だったが、後年まで、いや、今になってもその話が尽きていないのを思うと、それだけ多くの社会情勢が反映された曲たちなのだと思う。とくにこれらの曲に関する感想や意見で目立つのは、70年代半ば当時の世の中の価値観である。
その中で、ここでは「22才の別れ」について書く。
描かれているのは、22才を迎える女性が、5年間付き合った彼に別離を切り出す心情。その裏にあるのは、この当時の恋愛観と男女観。さらには結婚観と人生観である。
では、ここで設定されている22才とは、当時、どんな年齢だったのか。
おそらくは、青春時代が終わろうとしている時期であり、そろそろ社会に出て、将来の設計を考えていかなければならない年齢とされているのだと思う。もし大学4年生であれば卒業を迎える年齢だし、そうでない人ならほとんどは社会人となって数年経つ頃。そして女子であれば、もう結婚を意識しはじめないといけない年齢だった。
以上は、この歌が書かれた、70年代半ばのことである。
先ほど書いたように、僕がこの曲を認識したのはその10年くらい後、80年代のことだったが、その時ですら「ふーん、そういうものなのか」と思った程度だった。そのくらい、そういう考えが当たり前とされていた。
つまり昔は、
早いこと結婚しろ!
とっとと身を固めろ!
いい加減に大人になれ!
いつまでも子供じみたことしてるんじゃない!
という同調圧力……というか社会の空気、価値観が、強固だったのだ。
この感じ、今の若い人たちは、どんなふうに思うだろうか?
これらは、あくまで、そういう考えが当たり前とされていた時代の話だ。
(ただ一方で、こうした思考が、今の世間から完全に消え去ったわけでもないと感じることもある)
さて、「22才の別れ」がチャートの1位になってから2年後。人気デュオとなっていた風は、著書『風をたずさえて』を刊行する(1977年)。この本の中で伊勢が、曲作りについて、こう語っている。
(前略)
だから昔の歌を振り返るということは、自分自身の過去を振り返るということとある意味で同義語でもあるんです。
それは歌に書かれているテーマとか内容ということではないのです。たとえば「22才の別れ」という曲を作ったのは僕が20歳の時ですが、テーマはともかく、その年令の時に感じたこととか、その年令の心情しかやはり書けないからです。だから20歳の時の作品には、20歳の生命が永遠に生きつづけていくのだと思いますね。
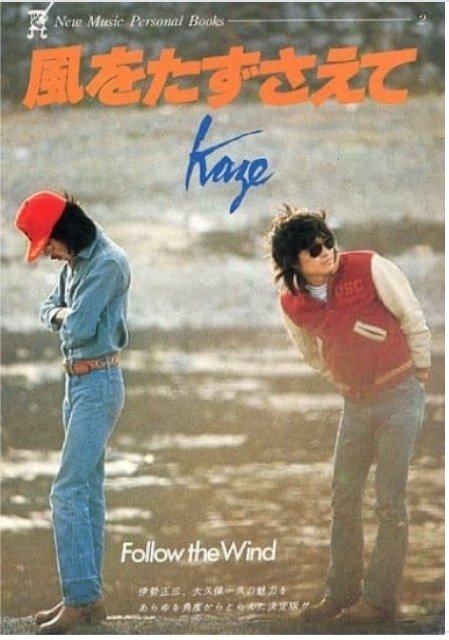
それより僕の作品の場合は、あまりナマに自分が出ていないのではないでしょうかね。そういう直接的な表現法を僕はあまりとらないし、どちらかというと、まわりくどい歌を書くほうですから。そういう意味では、僕の作品はまったくフィクションですから、自分に正直かどうかなんて論じてみてもはじまらないんです。
ちなみに『三階建の詩』を出した頃の伊勢は22歳で、風として再デビューしたのは23歳。「22才の別れ」はその数年前に書いていたことになる。
この曲に関して、彼は別のインタビューで、売れる曲を作ってやろうと思った、ヒットを意識して作った、ということを語っている。
つまり「ナマに自分が出ていない」上に、ヒットを狙ったということは、どこかで職業作家的な感覚を持ちながら書いたわけである。その客観性がうまくいった要因でもあったのなら、それはすごいことだ。
さらに本書では質問が続く。
今、「22才の別れ」を聞くと、恥ずかしいって気がしますか?という質問に対して。
ええ、恥ずかしいですね。あの歌の詩は2番の「…22本のローソクを立て、ひとつひとつがみんな君の人生だねって言って…」というくだりが、みんな一番いいって言ってくれるし、僕自身も一番力を入れて書いたところなんだけど、それ以外は別にたいした詩でもないんですよね。あとは誰でも書いているようなことが書いてあるだけで…。まあ、あの一行があるからこそ、この詩にも生命があり、どうってことないのに、やたら奥行きのある詩でもあるかのように感じてもらえたのかもしれませんが、だからこそ僕は気恥ずかしいんですよ。そこら辺の事情は本人が一番よく知っているから…(笑)。
もっとも今でもこの歌、ステージでも歌っているけどね…。
ちなみにこのインタビューは1977年の1~4月に行われたとのこと。さんざん受けたであろう周りからの大きな反響をくぐり抜け、伊勢本人はつとめて冷静に、淡々と話しているさまが読み取れる。「どうってことないのに」というひとことに、また客観性を感じる。
ともかく伊勢正三はこの曲を書く際に、世間の雰囲気をかぎ取って……もしかしたら自分の身の周りの人たちのことも見つめながら、作中に繊細な心模様を織り込んだのだろう。
この時代に生きる男女のリアルさを物語へと投影した、秀逸な楽曲だと思う。
70年代当時の恋愛観、男女観、結婚観、人生観
先ほども書いたように、この歌については、ヒットした当初はもちろんのこと、この約40年に間にさまざまなことが語られてきたようだ。
『風をたずさえて』の中には、音楽評論家の北中正和による、風に対するレビューが載っている。その前半で彼はこう書いている。
自分にぴったりくる音楽をさがしている時に気付いたことのひとつに、日本の音楽には、大人が楽しめる音楽がとても少ないということがある。特にフォーク、ロック、ニューミュージックと呼ばれている分野の音楽がそうだ。
ちなみに1977年時点で、北中は30歳(この年に31歳になる)。仮に今の時代であっても、大人の音楽というものを意識しても不思議ではない年齢である。
はじめて風の「22才の別れ」を聞いた時、ぼくが感じたのは、この歌には大人の感覚とまではいかなくても、大人になりかけている人の感覚があるということだった。
タイトルに“22才”という年令が出てくるということだけでなく、しっとりとした演奏も含めて歌全体からにじみ出てくるものから、そう感じたのである。
その印象は、デビュー・アルバムに収められた「ダンシン・ドール」をはじめとするいくつかの歌を知った後、いっそう強くなった。
ちなみに、このデビューアルバム『風』には、「22才の別れ」も「なごり雪」も収録されていない。
加えて、やはりこの北中の書き方からも、当時の時代性を感じる。22歳は大人であることを意識するような年齢だ、という事実が見て取れるからだ。
こんなふうに「22才の別れ」に関する多くの評論や感想があるが、今回、自分が見つけた中では、雑誌『サライ』2022年11月号に掲載された数学者の藤原正彦による連載「詩歌(うた)の品格」第73回というコラムの評論が、とても腑に落ちた。
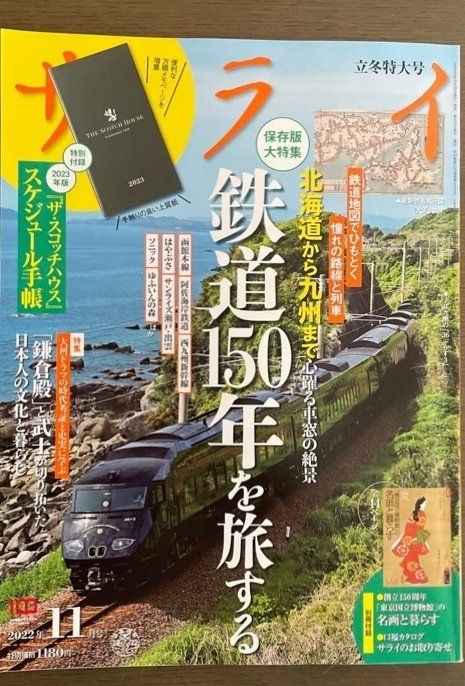
この回の大見出し(副題?)は、「同じ時代を通った人が抱える癒えない傷」とされている。
この原稿を書いた藤原は昭和18年、つまり1943年生まれで、「22才の別れ」が大ヒットした時に30歳を迎えようとしていただけに、その実体験は強烈だったようだ。
彼は、昭和50年(1975年)に留学から帰国して、この歌を好きになったとのこと。ページの中では、歌詞の焦点のひとつである<鏡に映ったあなたの姿>についても書いている。
そしてこの歌の男と女が、共に過ごす未来を見出すことができない状況について、こう述べている。
どうして二十二歳の女性がこんなことを言うのか。当時は二十代前半が女性の結婚適齢期と言われていたからだ。二十二歳というのは、女性にとって微妙な年齢だった。私はアメリカから帰ってきて五回お見合いし、結果は一引き分け四連敗だったが、お見合い相手は全員が二十二歳から二十五歳までだった。その辺りが女性にとって勝負の年齢と、少なくとも親はそう思っていた。たいていの母親は、出遅れてはいけないと娘にプレッシャーを与えていた。
そういう時代背景の中で、この曲の女性は、五年間付き合っていた彼を好きだったのに、将来が見えず、条件のいい見合い結婚の話にのってしまった。多くの女性はこうやってお見合い結婚をしていった。女性は、非情な割り切りを家族や社会から要求されていたのである。私のように、この非情な割り切りに泣かされた男性も多くいたのだ。
非情な割り切り……!
これに、またも時代を感じる。
またまた昔話になるが、結婚という動きの前に、恋愛というものが絡むことが当たり前になったのは、わりと近代になってからではないかと思う。前時代では好き同士でなくても家庭を持つ、身を固めることを優先するために、恋愛以前で縁談が進むことが多かったからだ。
かつてはそのぐらい、結婚、それも早婚が良しとされていたのだ。ちなみに僕の母親は「22才の別れ」の男女よりもだいぶ上の世代だが、お見合い同然の、紹介での結婚だったと聞いている。年齢は23歳か24歳だったはずだ。
だから、おそらく……恋愛結婚が一般化したのは、60年代から70年代ぐらいにかけてではないだろうか(詳細については要調査、か)。それはまた、ラブソングがポピュラーになった時代でもある。
自分はそんなことをなんとなく知っていたので、80年代後半にユーミンが純愛をテーマにアルバムを作ったり、女性誌がやたらと恋愛(と消費)を煽ったりした頃は、時代も変わっていくのだなぁと感じた記憶がある。
そして藤原の連載コラムの後半には、小見出しで「自信のもてない男たち」と振られている。そこから最後までのブロックは、男の側にも向けられているのだ。
とくに重要なのは、歌詞の最後の二行、<あなたはあなたのままで変わらずにいて下さい そのままで>という箇所に込められた痛切な感情についてである。
これは女性の正直な気持ちなのだろうが、男にとって、慰めにもならないつらい言葉だ。辛(つら)く非情な言葉だけれど、男はじっと我慢せざるを得なかった。
この時代、二十代前半ぐらいの男は、まだ自信がもてず不安だらけだった。女性を幸せにするには、やはり、きちんとした経済的裏付けがないと、と私をはじめ多くの男は思っていた。
(中略)
当時の二十代の若者にとって、社会に出るということと自由ということは完全に相反するものだった。
(中略)
多くの男は繊細で弱く、癒えない傷を胸の奥に抱えている。『22才の別れ』が永遠の名曲として心に沁みる所以である。
ちなみに、この中に出てくる自由であることは、忌野清志郎も訴えていた。60年代から70年代に青春を生きた上の世代の人たちが叫ぶ、自由であることの大切さは、よく耳にしたものだ。
そしてこのこともまた、今の時代の若い人たちには伝わりにくくなっている気がする。現在は、人は自由であることが当然だと捉えられている世相のようで(もっとも実際は制限が多く、そうでもないのだが)……この状況の獲得までには先達の大変な努力があったことが忘れられているように感じるからだ。
それはさておき、本題の結婚についてである。
男の側が自信を持てないということ、か。非常にリアルである。
そしてこれは、現代にも通じることである気がする。ただ、今であれば、ここまで「男とは」「女だから」ということで深く悩むこともないのでは、とも思う。主に、お互いがお互いを補うようなあり方が望まれているからだ。
そして22歳で、もう将来を、もう結婚を強く意識しての生き方をしなければならないということ。くり返すようだが、現代でもそういった親御さんや家庭、あるいはそういう考えの若者はいるだろう。それもまた、人生だと思う。
ただ、それだけ藤原が書いている感覚は、70年代に一般的だったものだと思う。その理由は、やはり家父長制がもっと根強くはびこっていた時代だからだ。そしてここでは、そう認識した上で、あの頃はこうだったということがきっちり書かれている。
社会に出たら、自由どころじゃないぞ。就職したら、いろんなことをもう諦めろ。これよりも先に世間に出ていた大人たちの多くは、若者たちに、そんなふうに言い聞かせていたということなのだろうか。
そして、半面、そんな保守的な考え方、生き方が、日本の昭和中期以降の高度経済成長期を支えたのも、また事実ではないかと思う。
ちなみに僕が結婚したのは36歳の時。22歳どころか、32歳になっても、結婚はとくに意識していなかった。若いうちに結婚しとけば良かったと思うようなことは、ほぼない。それに誰もが結婚しないといけないなんてまったく思わないし、そもそも結婚すれば幸せになるというわけでもない。そして、人それぞれの生き方があっていいに決まってる。
ただ、そういった話と、この歌とは、また別の話だ。
流行歌の裏側に、こうした時代ごとの社会情勢が色濃く垣間見えるのは、とても興味深いこと。
そしてそんな時代を映し出した歌と、それが描いたドラマの裏側に宿る感情に、たくさんの人々が心を揺さぶられてきたのは事実なのである。

普通においしかった♪
しかしブツ撮りって難しいですな
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
