
天/地を切り結ぶ太陽*月*ヤマアラシ*三姉妹 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(76_『神話論理3 食卓作法の起源』-27,M455天体の妻たち)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第76回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第五部「オオカミのようにがつがつと」を読みます。
これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
はじめに
レヴィ=ストロース氏が論じる「神話論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のパターンを、波紋のように浮かび上がらせる脈動たちが共鳴する”コト”と見立てて読んでみる。
神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。このΔ1〜Δ4というのは例えば天/地、生/死、人間/動物、男/女、上/下、明/暗、寒/暖といった経験的感覚的に端的に存在すると感じられる物事である。
神話は、こうした経験的な諸々の存在者の「起源」を語ろうとする。つまりこれら諸々のΔがもともと「ない」ところから「ある」ように「なる」経緯を言語でもって語ろうとする。ここで神話はある/ない、有/無の分別の始まりを問うという、きわめて高度な哲学の問いをひっぱりだしてくるのである。


そのためにまずβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。
お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。
そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。
ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。
*
ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。
私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し、今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を生成し直す動きも決して止まることなく動き続けている。。

神話的兄弟喧嘩
一から二へ
結合から分離へ、結合と分離の分離
というわけで、前回に引き続き「天体の諍い」と呼ばれるシリーズの神話をみてみよう。
クロード・レヴィ=ストロース著『神話論理3 食卓作法の起源』の320ページに掲載された神話「M455 グロヴァントル 天体の妻たち」では、上述のマンダラ状のパターンを描く動きを律動させる(リズミカルに動かす)”両義的媒介項(β)二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、両義的媒介項(β)二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という伸縮運動”が見事に描かれている。
まず兄弟喧嘩である。
兄弟とは、異なりながらもよく似た、同じような存在である。
つまり別々に分離しながらも一つにまとまっている。
そのような兄弟たちが喧嘩をし、真逆の二極へと分かれていく。

太陽と月の兄弟は地上の女たちのことで争った。
月は、水の中にも灌木地帯にも住まない者、すなわち人間の女性たちがもっとも美しいと主張した。
「いや、そんなことはない」と太陽は反論した。
「人間の女性たちはしかめっ面で、あれれほど醜いものはない。それに比べれば水の中のカエルの女たちのほうが美しい。彼女たちはわたしを見るとき、まるで自分たちの仲間を見るように、親しげに見る」。
それに対して月が反論する。「カエルは見苦しく、美しくない」と。
+
太陽は地上におりてカエルを連れ帰り結婚した。
カエルは跳ねるたびに体液を漏らし、姑はそれをグロテスクだと思った。
+ +
一方、その夜、空で輝いていた月はある人間の女性の心を乱した。
女は眠ることもできず、落ち着かなかった。
明け方、女は義理の姉妹といっしょに森の仕事に出かけた。
ふたりは森でヤマアラシを見た。
女は針で刺繍をするためにヤマアラシを捕まえたいと思った。
*
ヤマアラシは彼女をまず木の梢に、それから天へと誘い出した。
天に至ってヤマアラシは美しい若者に変身した。そして人間の娘を姑のところへ連れていった。姑はこの娘をとても美しいと思った。
++
太陽と月の母である老婆は、ふたりの嫁をもつことになった。
人間の娘は義母をとてもよく手伝った。
カエルの娘は跳ね回るだけで、義母の手伝いをしなかった。
老婆はカエル娘が本来動物であることを忘れており、ひどく困惑した。
ある日、老婆はバイソンの胃袋の厚い部分をゆでて、ふたりの嫁にわけた。食べるときに大きな音を出したほうをかわいがってやると言った。
人間の女は簡単に勝利をおさめた。立派な歯を持っていたからである。
カエルは炭をかじって音を出そうとしたが、結果は黒い唾が出て、それが唇のはしから流れ出ただけであった。
月はぞっとして「カエルが口からも下半身からもダラダラと何かを垂れ流している、もうたくさんだ!」という。
妻を侮辱された太陽はひどく腹を立てた。
太陽は、妻であるカエルを月の顔に向かって投げつけた。
カエルはそのまま、月の顔に張りついた。
これが月の隈の起源である。
*
それから太陽は月の妻であった人間の娘と、人間の娘が月のために生んでいた息子を奪って自分のものとした。
人間の娘は夫である月を失ったことを悲しみ、子供を連れて地上へ逃げようとした。しかし紐で編んだ綱は地上に降りるのには短すぎた。彼女が宙づりになっているのに気づいた太陽は、石を投げて彼女を殺害した。
石にあたった人間の娘の身体は地上に落ちた。
その子供は母が骨だけになってしまうまで、ずっとそばにいた。
それから子供は旅に出て、ある老婆の菜園を荒らして、食糧を得ているところを老婆に捕らえられ、その養子になった。
*
やがて成長した月と人間の娘とのあいだの息子は、育ての母の老婆の忠告にもかかわらず、この魅力的な女性たちを探しに行った。やがて彼は魅力的な女性を見つけたが、彼女たちはヘビに変身した。
息子は一匹を除いてヘビを殺した。
しかし、残った一匹の蛇が彼の下半身から体内に入り込み彼の命を奪った。
その様子を見ていた父である月は冷たい雨を降らせ、ヘビを追い払った。
そのとき、息子とその母親が同時によみがえった。
この神話は、とても綺麗にマンダラ状の八項関係が描かれていくので、詳しくみてみよう。

兄弟が結合から分離へ
冒頭、太陽と月の兄弟が諍いを起こす。
人間の娘と、カエルの娘、どちらが美しいか、という論争である。
太陽と月はここでは兄弟である。
つまり同じ親から生まれた同性の者という点で、太陽と月とは異なりながらも極めてよく似た、ほとんど同じような存在者である。
このほとんど同じに区別なく=一つに結合している二人が、諍いを起こす。つまり、あちらとこちらに分かれるのである。
その分かれていくための軸が、
美 / 醜
の対立軸である。
美/醜、人間/カエル、陸棲/水棲
興味深いことに、このくだりでは美/醜の対立軸が定まって静止しておらず、くるくると高速回転をしている。
つまり、月は「美=人間の娘 / 醜=カエル」だと分節するのに対して、太陽は逆に「美=カエル / 醜=人間の娘」だと分節する。
1:美/醜
2:人間の娘/カエルの娘(陸棲/水棲)
この二つの二項対立が重なる向きが(つまり人間とカエルのどちらを美の側に、どちらを醜の側に固定するかが)、両方向とも有効になっており、一方だけに定まらないのである。
ここに、分けることはするが、一方を選ぶことはしない、ということがある。
分けるけれども(まだ)選ばない。こここそ、意味が生まれてくるところ、表層の固まった分節体系としての言葉に対する深層の言葉が、流動し差異と同一性の間を自在に行き来する場所である。
太陽と月、それぞれの結婚
さて、この太陽と月の諍い(分離)を決定づけるのが、太陽と月それぞれの結婚である。
太陽は、月と分離して、カエルと結合する。
月は、太陽と分離して、人間の娘と結合する。
太陽==月
↓
カエルの娘==太陽<< / >> 月==人間の娘
カエル/人間の対立を、美/醜の対立とどちら向きで重ねるかは定まらないまま、とにかく太陽と月が、真逆に対立する二極と結婚することで、真逆に対立するようになる。
*
ここで、月が人間の娘と結婚するくだりで、月は刺繍の道具である針を背負ったヤマアラシに変身し、人間の娘を天へと誘い出す。
人間の娘と月とは、もともと天/地に隔たり、分離している。
天 / 地
この隔たりを埋めるために、まず月がヤマアラシという両義的な媒介者(文化の生産手段である「針」をもたらすと同時に、自然のものでもある)に変身し、この両義的に励起された状態で、天から地へと降りてくる。
天 >>月→(下降)→針を背負ったヤマアラシ>> / 地=人間の娘
そして人間の娘に自らの姿をアピールし、おびき寄せ、地上から木の上へ、木の上から天へと、誘い出して連れていく。
天 <<←(上昇)←人間の娘+ヤマアラシ << 地

両義的媒介項たち
ちなみに月は、神話の冒頭では太陽と”異なるが同じ、同じだが異なる”関係において曖昧な両義的媒介項であった(仮にβ1=月と表記しておこう)。それがヤマアラシという別の両義的媒介項に変身するのである(仮にβ3=ヤマアラシとしよう)。
両義的媒介項は、なにでもあってなにでもないわけではない。両義的媒介項は、他のあらゆるものごとと渾然と区別がつかなくなってしまっているわけではない。両義的媒介項もあくまでも項であり、つまり何らかの二項対立関係の中においてのみ、他ではないある項でありえるのである。
そして、それ自身ではないものとはっきりと区別されつつ(つまり月は太陽ではないし、太陽は月ではない)、同時に同じような者として過度に接近したり結合したり、異なったまま区別ができないくらいに重なり合ったりする。
両義的媒介項たちの過度な結合と過度な分離
さて、次に天に、月、太陽、カエル、人間の娘の四者が結集することになった。両義的媒介項が四つ過度に結合した(一点に凝集した)となると、ここから一挙に、直交する二つの軸(十字)を発生させながら、この四両義的媒介項たちが分離していくのだろう、という予感がする。
この話では天/地の分別が語られているが、少なくともこの時点では、天/地は分かれつつも完全に分離はしていない。天地は二つに分かれつつも木登りをすれば往来できる程には近いのである。このときはまだ。
*
ちなみに、太陽と月が両義的媒介項であるのは前述のとおりとして、カエルと人間の娘はなぜ両義的媒介項なのだろうか。その理由は極めて簡単で、要するにβ太陽とβ月のような両義的媒介項と過度に結合しさえすれば、その結合相手のカエルでも人間でも、両義的媒介項と過度に結合しているが故に、両義的媒介項であるのである。カエルや人間にそれ自体として、即自的に、”両義的媒介性”といったようなことが付与されているわけではない。
いちいちの項が「なにであるか」は、他の項目と分離と結合のパターンの組み方(関係を関係付けられる仕方)に依るのであって、項それ自体に何かの自性があるわけではない。これは下記の記事でも紹介した「関係が、もの(項)自体よりも、「先」に存在する」ということである。
βカエルとβ姉妹
カエルはオタマジャクシからカエルになるように、水中に棲む手も足もない魚のような姿から、手足が生えて、地上を歩き回る姿に変わる。カエルは水/陸の間を一方から他方へ移動できるという点で、対立する二極の一方から他方へと移動できるという点で、人間が両義性を読み込みやすい対象ではある。
このカエルに比べれば、人間の娘は両義的な項の位置にはおさまりにくい。
そこで神話は、人間の娘が両義的媒介項であることを示すために、わざわざ彼女が「義理の姉妹といっしょに森の仕事に出かける」というくだりを語るのである。義理の姉妹即ち、非同非異の二者が”いっしょに”結合しつつ、棲家から分離する。二即一一即二の両義的媒介的状態に入りながら、人間の世界/野生の世界の対立する二極の境界を超える。
* * / * *
「Aでもなく非-Aでもない」を平然と言ってのける神話の論理は、通常のロゴス的な論理(排他律、排中律、同一律に基づく)と比較すると、まったく非合理的に見えるかもしれないが、しかし意外にもというか、実に精密に”両義的であること”を”異なるが同じ(非同非異)”を組み合わせてシステマティックに設定していくのである。
++

二人の嫁を比べる義母
さて、太陽と月の実家に結集した四つの両義的媒介項たちであるが、ここから話はこの四者の激しい衝突と、対立の際立ち、分離の確定へと展開する。
β
β * β
β
まず「二人の嫁」が真逆に対立する。
二人の嫁のうち一方は義母をよく手伝う(人間の嫁)。
他方は義母をまったく手伝わない(カエルの嫁)。
なおここでカエルの嫁といっても「老婆はカエル娘が本来動物であることを忘れており、ひどく困惑した」とあるくらいで、一目その姿を見ただけでは「カエルだ」とわかるような姿をすでに(まだ)していないのである。カエルなのにカエルではない。こういうのが対立二極のどちらか不可得な、両義的媒介項らしいあり方である。
一方は好ましいとされる食卓作法で食事をし、他方はマナー違反の無作法を食卓で働く。
(義母からみて)良い嫁 / 悪い嫁
人間 / カエル
食卓作法が良い / 食卓マナーがダメ
まるで「四年ぶりに義実家に帰省したら夫の弟が結婚、同居していて、その嫁が義母と結託して修羅場」という類の現代社会を生きる私たちにも実感しやすい経験的で感覚的な対立である。
ここで、
β人間の娘 <<< / >>> βカエル娘
この間の分離が決定的に確定されるようである。
*
すかさず続いて、太陽と月がまた諍いを起こす(分離する)。
月が太陽の妻であるカエルを侮辱する。
太陽がそれに腹を立てて、月との対立が決定的になる。
分離するところ・結合するところが逆になる
ここでおもしろい展開になる。
太陽が自分の妻であるカエルを、月の顔にむかって「投げつけて」(ひどいなあ)、月とカエルを過度に結合させる。カエルは元々結合していた太陽の方から分離して、月の方と結合するのである。
太陽はさらに、月の妻である人間の娘を自分のものにしようとする。
人間の娘は元々結合していた月から分離して、太陽の方と結合するのである。
分離しているところが結合し、結合しているところが分離する。
分離と結合の両極のあいだで、一方から他方へ急転換が起きる。
これぞ神話における両義的媒介項たちの振動の仕方である。

Δ対立関係の安定化へ
さて、ここでβ月にはβカエルがへばりつき、その結果「隈のある月」が生成する。これは現に経験的に空にみることができるあの月、現世の月のあり方である。二つの両義的媒介項、βカエルとβ月とが接近し結合したところに、Δ「隈のある月」というポジションが析出されたのである。
神話はこのような、経験的にはっきりと定まった対立関係(人間対動物とか、生と死とか)が収まる四つのポジションを、両義的媒介項たちの分離と結合の分離と結合を通じて区切り出そうとする。
*
さてさて、そのためには太陽と人間の娘との関係をどうにかしないといけない。
人間の娘は、太陽から分離して出ていく。
そして綱をつかって、天界から地上世界へと移動しようとする。
ここに
天/地
の分別が出てくる。ここに出てくる天地は、Δ天、Δ地、である。
いやいや、天地の区別は神話の冒頭から、もともとあったのでは?さっきもヤマアラシに誘き出されて昇っていたし・・。と、おもわれるかもしれないが、あの時点では天地の区別はまだない、いや、あるようなないような、であった。木登りしてたどり着けるような天は、Δ天ではないのである。神話の冒頭では、経験的なΔ二項対立は、天/地であれ、生/死であれ、ある/ないであれ、分離/結合であれ、差異/同一性であれ、一切ない、いや、ないでもあるでもない。
天地の分離の過程でもβ脈動を反復
ところでこの神話の場合、天地の分離、つまり人間の娘が太陽から分離する過程は一筋縄にはいかない。
まず縄、綱が短すぎ、人間の娘は天地の中間に宙ぶらりんになる。
この宙ぶらりんというのが重要で、上でもなく下でもなく、そのどちらでもない、というあいまいな中間性こそが、上と下を、上に対する下と下に対する上を、上ではないものではないものとしての上と下ではないものではないものとしての下を、区切り出すのである。
非-天上を、即「地上」に設定するために
そしてこの宙ぶらりん状態から人間の娘が墜落することで、天に対する「地上」がはっきりと限定される。なぜなら天上に対する「下」は必ずしも地上である必要はなく、水界(水中)とか、地下の暗黒世界とか、もっと深い深い「下」を考えることもできるからである。
β人間の娘が太陽によって落とされて、骸骨になってしまった場所、ポジション、座標こそが、天に対する地として分節されたこの地上なのである。
*
さて、β人間の娘が骸骨になってしまうまで、彼女と月とのあいだに生まれた息子が付き添うという話になる。なんと心温まる話だろうと思われる向きもあるだろう。死してなお
母/子
が結合している。通常は生/死の軸上で分離してしまうはずの、死者たる母と生者たる息子が、生死の分別を超えて、結合したままでいる。
経験的には分離しているはずのところが結合している。
これは両義的媒介項の間に見られる関係(β脈動)である。
β骸骨・死者たる母==β生者息子
継母との結合
さて、そこから転じて、詳しい経緯はよくわからないが、息子は骸骨になった母の元から離れる。流石にお腹がすいたのだろう。見知らぬ家の畑のものを食べて、そしてその家の老婆の養子になる。
神話では、男の子が、産みの母ではない老婆の養子になる、という話がしばしば出てくる。これは元々分離されていた、親子ではない二人の人間のあいだに(それも老/若、男/女、という軸上で大きく隔たった二人の間に)これを短絡するような関係が生じる、という、神話好みの分離と結合の急転換である。
骸骨になった実の母から分離して、見知らぬ老婆のもとに結合する。
結合しているはずのところから分離して、分離しているはずのところと結合するのである。
高速回転
やがてβ月とβ人間の娘との間に生まれた男の子は、養い親である老婆のもとで成長し、自分の結婚相手を探すまでになった。
この神話が太陽と月それぞれの結婚話からはじまったことを思い出そう。
ここで改めて結婚という、分離を結合に変換する処理が前面に出てくる。
β月とβ人間の娘との間の息子は「魅力的な女性たち」と出会い、結婚しようとするが、彼女たちは「蛇」に変身する。息子は蛇とあわや結合してしまうのである。息子は蛇を退治するが、しかし一匹残った蛇に下半身から体内に入り込まれて絶命する。なんとも激しい急展開である。
息子と美女の「結婚」:分離から結合へ
美女が蛇に変身したものを息子が退治する:結合から分離へ
蛇が息子の体内に入り込む:分離から結合へ
神話は、両義的媒介項たちが一点に凝集した状態から、反発するように分離して、垂直方向(水平でもいい)に長く伸び、水平方向(垂直でもいい)に長く伸び、とするうちに、四極に分離しその四角形の辺の部分に四つのポジションを区切り出す、という動きを見せるのであるが、この神話の場合、この動きが二度、二周、繰り返される。

月が降らせた雨
そして最後に、息子の父である「月」が再登場する。
月は、兄弟の嫁であったカエルにへばりつかれて、空におとなしく収まっていたわけであるが、ここに至って「冷たい雨」、天から地へと落下する雨を用いて、蛇を息子から分離する。
雨が降る。
これは
天/地
の最終的な分離の確定になる。
そうすると、月の妻であった人間の娘(ずいぶん前に天から落下して骸骨になっていた)と両人の間の息子とが、同時に生き返る。
生き返る?
骸骨になった者が生き返ったり、蛇に体内に入り込まれて喰われた者が生き返るなんて、おかしい、と思われるだろうが、それでよいのである。これは神話である。あえて、経験的感覚的には「ありえない」、経験世界とは真逆のことを言語的に分節したいのである。
生/死未分
ここで神話は、生/死の分別のようなことが未だ固まらない、分かれつつも分かれておらず、分かれていないけれども分かれつつある、というところを言語的に思考しているのである。
骸骨になったものが生き返る、などという荒唐無稽と言われるような話をするのは、生/死の区別が経験的には完全に分離されて固まっているからこそである。
つまりこの神話は最後の最後まで、生/死のような経験的で感覚的な二項対立が”あるようなないような”、両義的媒介項たちが分離したり結合したり、一点に集まったり、彼方向に伸びたり此方向に伸びたり、四角形を描いて付かず離れずに安定したり、という対立関係の対立関係の脈動、躍動を描いているのである。
生/死未分からの生/死の分別、そして生死の海へ
そして最後、二人が生き返っておしまいになるのだが、これはおそらく、「そして母と息子は、幸せに暮らしましたとさ(この現世で)」ということなのだろう。この母と息子は、もう天との間を登ったり降りたりすることもなく、星や動物と結婚したりすることもなく、人間の領分に収まって、あくまでも人間として、Δ人間として、暮らしていくのであろう。
こうして、
天 / 地
生 / 死
という、経験的感覚的なこの世界のあり方を定める基本的な分節が確定する。そして人は「生まれ生まれ生まれ生まれて生のはじめにくらく、死に死に死に死んで死のおわりにくらし」と弘法大師が書いているような世界に迷い込むのである。
以上のように、私たちが理解したり伝達したりすることが容易にできる日常の表層の言葉の直下で、”Aでもなく非-Aでもない”両義的媒介項たちが分離したり結合したりまた分離したり結合したりと脈動しつづけており、そこにパターンが、表層の分節システムの”元型”となる分離と結合の定常的なパターンが、形を表しては、また消えていく。
* *
さて、レヴィ=ストロース氏はここでまた、上の神話の諸項たちのあり方が逆転したバージョンを紹介する。『神話論理3 食卓作法の起源』p.323の「M429a クロー 天体の妻たち」である。
先ほどの神話では、太陽がカエルを妻に望み、月が人間の娘を妻に望んだが、こちらM429aではそこが逆転する。太陽が人間の娘を美しいといい、月がカエルの娘の方が美しい、という。
ある日、月は知りたいことがあって太陽に会いにいった。世界で一番美しい娘は誰かということである。
太陽は彼にもう決めたのかとたずねた。
月は地上ではカエルほど美しい女は知らないと答えた。
「そんなことはない、 一番美しいのはヒダッツア族の娘たちだ」
と太陽は言った。
*
そして、それぞれ自分の気に入った女性と結婚することにした。
*
ちょうどそのとき三人のヒダッツアの姉妹が森に仕事にゆくところだった。
彼女たちはある木にヤマアラシがいるのを見た。
姉娘たちはヤマアラシの針が欲しいと思った。
二人の姉娘は一番美しい末娘に命じて、
木に登ってヤマアラシをつかまえさせようとした。
太陽は、樹上に上がった娘を天に連れ去り、結婚した。
* *
月は一匹のカエルを連れ帰り、母に自分の妻も家族のテントに受け入れてくれるように頼んだ。
老母はあちこち探したが、嫁とおぼしき女性の姿はどこにも見あたらなかった。カエルはしゃべり、自分の居場所を知らせようとした。
けれどもカエルははっきりしゃべることができなかった。
***
太陽は噛み方比べ競争を開催した。
母親はバイソンの臓物を茹で、妻たちがそれぞれその一切れを選んだ。
ヒダッツアの娘は暗闇の中でよい音をたてて噛みはじめた。
カエルは鍋のうしろに隠れ、耳に心地よい音をたてるために炉の薪の皮を噛もうとした。が、うまくいかなかった。
月はカエル娘を追い払おうとし、カエルは抵抗して戻る。
これを三回繰り返した。
そして四度目に、 カエルは月の背中に飛び乗り、叫んだ。
「いつまでも、あんたといっしょにいるわ」と。
その後、太陽の妻になった人間の娘は逃走し死んでしまう話と、祖母と孫の話、太陽の息子が「夜明けの星」に変身する話へとつづく。
一緒にいる太陽と月とが別々に分かれて、それぞれ人間とカエルと結婚する。人間を天界へと連れてくるために樹上のヤマアラシで誘き寄せる。天では人間の嫁とカエルの嫁が真逆の存在であることを強調されるイベントが繰り広げられたのち、カエルは月と過度に結合し、人間は月または太陽から過度に分離され地上に落ちる。この大筋は前掲の神話と同じであるが、しかし太陽と月の結婚相手が入れ替わっているなど、あちこちに「逆転」がみられる。これについてレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。
「したがって、クローのヴァージョンは二重の変形をしめしていることになる。まず第一に、いくつかの細部が弱められる。[…]カエルは月の顔や胸ではなく、背中に張りつく。すなわち、低→高、内→外、前→後となっている。第二に、太陽が人間の女と結婚し、月がカエルと結婚するのだから、これらの移動は婚姻に関する選択とセットで起こる。おろかな天体の役割を演じる月のこの失墜ぶりは、それが性転換して地下の、とは言わないまでも、地上の祖母と混同されるようになるといっそう際立つのである。クローの諸神話では祖母の邪悪さが強調されている。」
結婚相手が逆になるだけでなく、カエルが月に張り付く場所が人体の腹の側か背中側かで逆転している。他にも天体の性別が男/女の対立において逆転したり、天体の年齢が老/若で逆転したり、また天体の子の育ての母が善人/悪人の対立において逆転する場合もあるという。
*

同じように、M430a ヒダッツア 天体の妻たち(一)という神話では、月が人間と結婚し、太陽がカエルと結婚する、という対立の対立の置き方は冒頭の神話と同じだが、カエルが月に張り付く時の前/後、腹/背中の関係が逆転している。
月はヒダッツアの娘たちがもっとも美しいと思う。
太陽はそれに反対する。人間の娘たちは顔が曲がっている、自分は水の娘たち、つまりヒキガエル娘たちの方がよいと太陽は言う。
月は「よし、それでは、それぞれひとりずつ連れてきて、臓物料理を出してみよう。噛み方が上手で、良い音を出す方を手元に置いて、もうひとりは帰そう」と提案した。
物語は、ヤマアラシのエピソード、 ヒキガエルの失禁とつづく。
臓物料理の食べ比べでは、人間の女は臓物の薄い部分を選び、ヒキガエルは厚い部分を選ぶ。
ヒキガエルは自分の食べ物の中にこっそりと炭を入れるが、それでも音をたてることができない。よだれをたらし、黒い唾液で体を汚してしまう。
ヒキガエルは「手でつかまれないように」夫の兄弟の背中に張りつく。
それが満月の中央にある月の隈なのである。
β太陽 / β月
*
(ヤマアラシ+樹木)
*
β人間の娘(姉妹のうちのひとり) / βカエル
この四者が一堂に集まって(臓物料理を食べる会)が開かれる。
そこで、
コリコリと良い音を立てて食べられるか / 食べられないか
という二項対立をもちこんで、この両極に人間の娘とカエルを分離する。
ここで、臓物料理を良い音を立て食べられない方は元いた場所に追い返される(分離される)はずが、なんと逆に、月に飛びついて(背中側だったり、腹や顔だったり)取れなくなる(結合する)。そしてそこに「隈のある月」という、私たちが今日現世で日々眺めることができるあの月が生成する。
私たちにとっての経験的な月(Δ月)は、βカエルとβ月の男を結合したところに登場する
βカエル + β月の男
↓
Δ月
そしてこのΔ月は、この神話では太陽と諍いを起こし、「コリコリと良い音を立てて食べられるか / 食べられないか」の対立軸上で反対方向に分離していく限りで、”太陽と対立するもの”=”太陽と真逆のもの”=”非太陽”である。
ここで月が経験的存在者として限定されると、同時に非月たる太陽もまた経験的存在者として限定されることになる。
それと並行して、いや、直交するように、天体の妻であった人間の娘が天上から地上へと降りる動きをとることで、両極に天/地の対立軸が引かれ、そしてこの地上において、生/死の分離も確定する、という具合に繋がっていく。
仮に八項関係を配列してみると、下記のようになるだろう。
Δ天:長い周期性(生)
↑
β太陽 β月
Δ太陽 ← ヤマアラシ+樹木+綱+姉妹 → Δ月
β人間の娘 βカエル
↓
Δ地:短い周期性(死)
もちろんこのような図式化には誤解を招く恐れがあるので、気を付けていきたいところである。項は特定の位置に固定されて収まっているものではないのである。脈動を観測するために作られたスナップショットだと思っていただきたい。
みかけ上は線状に進むように見えても、じつは複数の平面上で同時的に繰り広げられていて、しかも、それらの平面相互間にはかなり多くの複雑な連接があり、これが全体をひとつの閉じた体系にしている
観測波をどのように振動させるかによって、これとのβ脈動との干渉パターン(曼荼羅)の現れ方は変わるのであり、そこで干渉パターンの差異に他ならない諸項たちの現れ方、並び方もまた変わる。
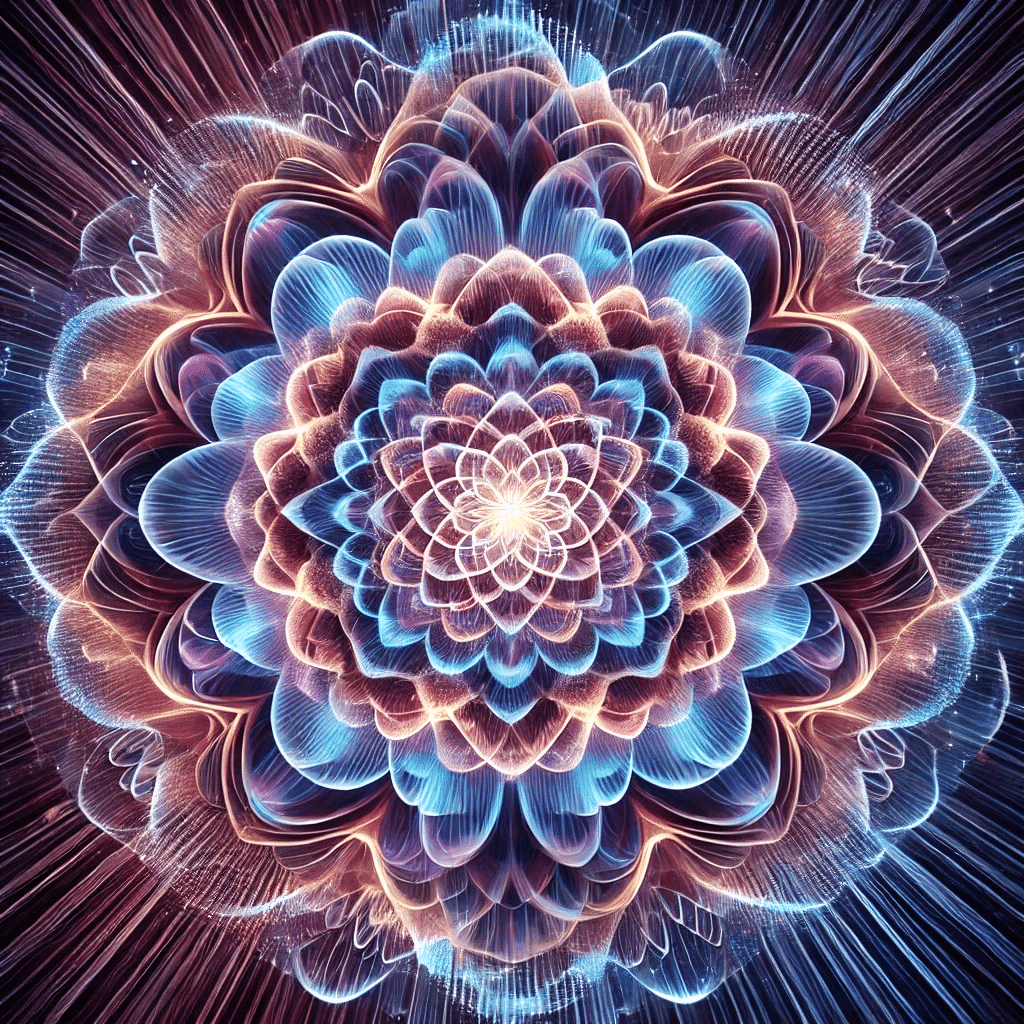
このようにして今回読んだ神話たちからも、項に対して関係が先行していること、項と項を分離しつつ結合することができるために、分離する動きと結合する動きとをまず区切り分けなければならず、この分離と結合の分離と結合を生じさせようとしているのが神話における両義的媒介項たちの兄弟喧嘩であったり結婚であったり、上ったり下りたり、あちらに行ったりこちらに戻ったりする動きなのである。
*
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

