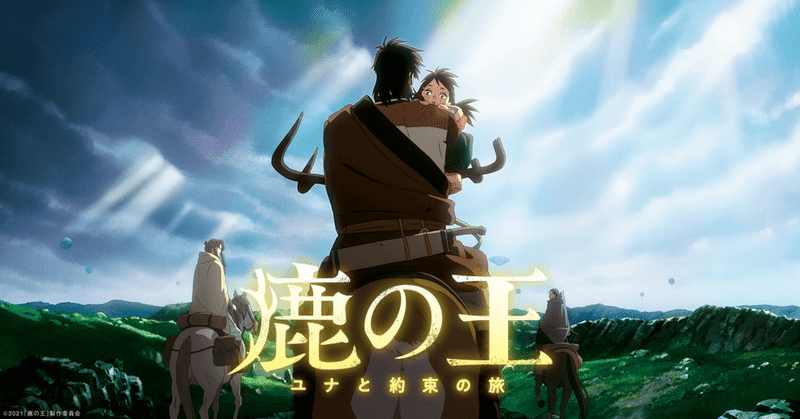
映画感想 鹿の王 ユナと約束の旅
日本最高アニメーター・安藤雅司第1回監督作品!
『鹿の王 ユナと約束の旅』は2022年公開のアニメーション映画だ。原作は上橋菜穂子による小説『鹿の王』。監督はジブリきっての実力アニメーター安藤雅司。『もののけ姫』をはじめとして『千と千尋の神隠し』『思い出のマーニー』などのジブリ作品で作画監督を務め、他にも今敏監督『東京ゴッドファーザー』『パプリカ』で作画監督、新海誠監督『君の名は。』で作画監督……我が国を代表する大ヒットアニメーション映画にはだいたい関わっているだけではなく、作画面で主導的なポジションにいた人だ。その安藤雅司が満を持して監督を務める……というのが本作『鹿の王』。
共同監督を務めたのは宮地昌幸。スタジオジブリで『千と千尋の神隠し』で演出助手を務めた後、独立。2008年に『忘年のザムド』を監督、2012年に『伏 鉄砲娘の捕物帳』を監督。他にも多くの作品に関わる。
世界最高クラスのアニメーターが映画を制作する……これだけで期待が高まる。しかもアニメーション制作もこれまた世界最高クラスの作品を制作し続けるProductionIG。
前置きはこれまでにして、作品を見てみよう。
それでは前半あらすじ。
かつてアカファの国をツオル帝国が強力な軍事力を持って蹂躙した。しかし突如発生した「黒狼熱(ミツツァル)」という謎の病が蔓延し、ツオル帝国は侵攻を断念する。
それ以降もツオル帝国はアカファ国侵略を試みたが、そのたびに病が蔓延し、断念した。
現在2つの国は、緩やかな併合関係にある。あの戦争も、病の禍も過去のものに思えたが――。
とある岩塩鉱。
そこでツオルの奴隷達が過酷な労働を強いられていた。そんな鉱山に、山犬たちの群れが襲撃する。ただの山犬ではない。獣たちに傷を付けられると、瞬く間に体に異常が現れる。澎湃と迫る山犬だけではなく、謎の病に、鉱山の人々は次々に命を落としていく。
そんな岩塩鉱の奥――小さな牢屋に閉じ込められる一人の男がいた。そんな男の側にも山犬が現れる。
ちょうど太い格子が守ってくれている。男はそのままやり過ごそうとするが……山犬が小さな女の子をくわえていた。
男はとっさに手を伸ばし、山犬をつかんだ。口元を強く握ると、山犬は女の子を落とす。
山犬は一度体を引っ込めると、飛びついてきた。男の手に食らいつき、引っ張る。男は抵抗しようとするが、首に巻き付いた鎖が男の首を絞める。男はそのまま気を失ってしまった。山犬は男が死んだと思い込んで、去って行く。
しばらくして――男は目を醒ます。どうやら死なずに済んだようだ。あの女の子も。男は女の子を連れて、牢屋を出る。岩塩鉱は死体だらけだった。生存者は自分たちだけ……。
男は小さな女の子を連れて、岩塩鉱を後にする。
その後、ピュイカと呼ばれる鹿を手に入れて旅をしていると、トマという男を知り合う。男が手に入れたピュイカは、トマの持ち物だったが、しかし気性の荒いピュイカの扱いに難儀しているところだった。
男はヴァン、小さな女の子はユナと名乗り、そのままトマと旅をして、彼の村へ行くことになった。トマはピュイカを飼育し、繁殖させて帝国に売ろうと考えていたが、しかしピュイカの飼育方法がわからなかった。そこでヴァンがピュイカの飼育を務めることになり、ついでに村の仕事を手伝うことで、村で過ごすことを許される。
一方、あの岩塩鉱に一人の男が尋ねていた。“聖なる医師”の異名を持つホッサルだ。山犬に襲撃された後の岩塩鉱は疫病が蔓延し、一夜にして全滅していた。その様子を見て、ホッサルは疫病がかの“ミツツァル”だと診断する。
坑道の奥も調査され、間もなく岩塩鉱に一人だけ生存者がいたらしい……ということが判明する。その生存者は牢屋を脱出し、どこかへ逃げ出したようだ。
謎の疫病とされているミツツァルが蔓延する中で生存者がいる。もしかしたら、その者から「抗体」を作ることができるかも知れない。ホッサルはその何者かの行方をさらに追って欲しい、と頼む。
このあたりでだいたい25分。実際にはもっと枝葉があるのだけど、あらすじ紹介が長くなっちゃうので、この辺りでいいでしょう。
例によって原作を読んでないので、映画だけを手がかりに、どういった世界観なのかを探っていきましょう。

まず2つの国が出てきます。アカファとツオルです。
2つの国の見分け方は簡単。なんとなく“赤”っぽい服を着ているほうがアカファ。“青”っぽい服を着ているのがツオル。ツオル人は髪色も瞳の色もどことなく色素薄め。“アカ”ファが赤だから、この区別はすぐに付くはず。

岩塩鉱で働かせられている人々。彼らはツオルで罪を犯した人たちらしい。
ツオルの人々のもう一つの特徴は額に付けられた“目”。
こういった額に付けられた目は、いわゆるな普通の目ではなく、「神秘的なもの」を見通す目とされている。霊的なものを見たり、神聖なものを感知したり……。そういったものがほとんどすべてのツオル人の額に付けられている、ということはすべての人々の頭・意識に彼らが信仰する神が宿っている……という考え方なのでしょう。

イケメンのお医者さん、ホッサル。彼もツオル人であるのだけど、額に目の入れ墨がない。ということは、ホッサルはツオル人の間で普遍的に信仰されている宗教を信じていない……ということになる。
ホッサルのもう一つの特徴は、赤い布を体に巻いていること。赤はアカファの特徴なので、ホッサルはかなりアカファ文化に入り込んで、その文化を尊重している……ということでしょう。アカファ人の従者を連れて、尊敬もされているので、こういうところからもホッサルの立場がわかる。
ちなみにツオル人は名前の尻に“ル”を付ける習慣があるらしい。ウタル、ヨタル……。名前の尻に“ル”が付けるのがツオル文化的なものらしい。

アカファとツオルの戦争は休止状態にあるのだけど、文化的な交流はかなり進んでいるらしく、トマの村へ行くと意外にツオル人の嫁が何人か入り込んでいる。
この女性は「季耶」というのだけど、こういう漢字名もアカファ文化の特徴。どうやらただアカファ人の村に入って結婚するだけではなく、アカファふうの名前まで名乗っているらしい。ツオル人がアカファ文化を尊重し、同化していこうとしている様子が描かれている。

アカファ側もツオル人文化を受け入れている。それがこの場面。ツオル人文化の象徴である「パン」を食べている。作中では「ファム」という名前。
食べ物、というのはデリケートなもので、飢餓状態に陥っても自分たち文化の食べ物ではないものは食べない……という人は多い(日本人はそこで節操なくなんでも食べちゃうんだけど)。外国文化の食べ物を受け入れるようになっている……ということは、それだけ文化的交流が深く進んでいる……ということがわかる。

アカファとツオルはいつ頃から戦争をやっていないのか?
ちょっと格好がダサいけど、これが10年前のヴァンの姿。10年前、アカファとツオルとの間で激しい戦闘があって、ツオル帝国のほうが優勢であったが、しかしヴァン率いる「独角」と呼ばれる兵団が獅子奮迅の働きを見せて、ツオル帝国の勢いを挫いた。結局はアカファ軍は負けてしまうのだけど、しかしヴァンの武勇があったから、アカファはそこそこ優位な条件を出してツオルを追い返すことができた……ということでしょう。
しかし戦争の英雄であるはずのヴァンは、人知れずツオル側の捕虜となり、岩塩鉱で強制労働をさせられていた。10年前の英雄がどこに行ったのか、誰も知らなかった……。

現状はアカファとツオルとの間に武力衝突はない……ということになっているが、だからといって全く違う文化を持った両者が、わだかまりなく仲良くやっている……というわけではなく。
どちらかといえばツオル帝国側がアカファ人の上に立つようになっている。アカファもそういう状況を受け入れたわけではなく、各地でこういった小競り合いが起きていた。

次に「疫病」について見ていきましょう。
感染したら間もなく死亡……というかなり強力な病であるミツツァル。山犬たちが保有する疫病で、噛みつかれることによって感染する。ツオル人はこの病に対する免疫がなく、幾度となく戦争を仕掛けるが、そのたびにこの疫病が蔓延して断念する……ということを繰り返している。
アカファとツオル間の戦争はどうやら80年前から何度も繰り返しているようだけど、強大なツオルの軍力でもアカファを制圧できずにいるのは、この疫病のためだった。
疫病というのは基本的に動物経由で感染する。家畜や山の獣に噛みつかれたり引っかかれたりすることで発症する。そういうわけで、実は人類は狩猟採取民だった時代はさほど疫病で苦しむ……ということはなく、動物を家畜とするようになってから疫病被害に遭ったとされている。
天然痘が最初に確認されたのは紀元前1600年頃。おたふく風邪が発見されたのは紀元前400年頃。ハンセン病は紀元前200年頃。腺ペスト(黒死病)が確認されたのは西暦542年。腺ペスト大流行が1346年。ポリオ(小児麻痺)は1840年頃。エイズは1959年。人類全体の歴史から見ても、「疫病」というのはわりと最近の時代に入ってから登場している。これも人類が自然を浸食するようになっていった結果である。
『鹿の王』では他文化に侵略しようとしたことが切っ掛けで疫病が蔓延している。こういうった話は、現実の歴史の中に実例がある。
1492年、コロンブスは新大陸を発見したが、この時コロンブスが現地に“お土産”として置いていったのが「天然痘」だった。
1532年、フランシスコ・ピサロはスペイン王の命によって南米大陸へ調査の旅に出て、インカ帝国皇帝アタワルパと戦っている。アタワルパの軍勢数千に対し、ピサロの軍勢は160人。圧倒的な人数差だったが、ピサロは戦いに勝利している。
キリスト教国の話なので「神の奇跡によって勝利が~」とか報告されているが、実際はそうではなく、インカ帝国内に天然痘が蔓延していて、ある研究によれば95%の先住民が天然痘によって死んだという。インカ帝国も天然痘によってボロボロで、王族も何人も死んでいて、ピサロが手を下す前から崩壊寸前だった。インカ帝国の兵士は確かに数千人いたが、病気でまともに戦える人がほとんどいなかった……というのが実体だった。
一方、コロンブスもスペインに戻ったとき、やはり疫病を持ち帰ってしまっていた。それが「梅毒」である。
梅毒というのは性感染症のことで、ということはかなり限られたシチュエーションでなければ感染することはない。そのはずなのだけど、梅毒はヨーロッパ全体に蔓延し、社会を混乱に陥れ、その結果ヨーロッパ人の性習慣を変えてしまうくらいのインパクトがあった。
まったく未知の文化、土地に触れるとき、私たちが真っ先に警戒しなくてはならないのが「疫病」だ。15世紀の時代、ヨーロッパ人にとって天然痘はそこまで恐れるほどの病気ではなかったが、アメリカ先住民の人々にとって脅威の疫病で、この病によってアメリカ先住民の集落はいくつも全滅してしまっている。
一方、梅毒はアメリカ先住民にはそこまで恐れるほどの病気ではなかったが、ヨーロッパの人々にとって脅威の疫病だった。
まったくの未知の土地に立ち入る……という時、一番に直面しなければならないのは「文化の軋轢」以前に、「未知の疫病」だったりする。
だから、“もしも”の話として宇宙人が私たちの前にやってきても、「友好のしるしだ」と握手なんかしては絶対にダメ。宇宙人がどんな疫病を持っているかわからない。宇宙人のほうも、地球由来のどんな恐ろしい病に襲われるかわからない。お互いのために、宇宙人がやってきても、近付かない、触れない、は徹底した方がよい。
(スティーブン・スピルバーグ監督『宇宙戦争』での宇宙人達は地球の風邪で全滅した)

ところが『鹿の王』の世界観の中では、まだ「疫病」の認識はない。人々は「呪い」や「怨霊」と解釈している。だから疫病で死んだ人をこうやって「結界」を貼って隔離すれば、自分たちには罹らない……と信じている。

画面右手に見える祭司医たちが、手でハートを……じゃなくてたぶん「目」の形を作っているんじゃないかな?
あれがなんなのかというと「えんがちょ」。手で目の形を作っていたら、神様が疫病からも守ってくれる……と信じている。「祭司医」という名前からも、疫病を「呪い」や「怨霊」の類いと見なしていることがわかる。
医者であるホッサルは「おまじない」なんて信じてないから、おどけて手ポーズをやったりしている。
ところで、疫病の名前には「黒狼熱」と「ミツツァル」という二つの呼び名がある。たぶん「黒狼熱」がアカファでの呼び名で、「ミツツァル」がツオルでの呼び名。なぜなら名前の尻が“ル”だから。

祭司医は疫病に罹っても、「魂の清らかさ」があれば退けられる……と信じている。疫病を「怨霊」と見なし、お祓いをして気合いを入れれば治ると信じている。まだエリート階級の意識にも、近代医学の知識がない時代。

ミツツァルはアカファ人にはほとんど罹らず、ツオル人だけに対し猛威を振るう。なぜなのか?
勘のいい人はこの場面を見たときにピンと来る。ヒントはピュイカの乳。
正確に言うと、そのピュイカが好んで食べるアッシミという草。たぶん、アッシミは人間には毒素が強すぎて食べることができない。しかしピュイカはアッシミの毒素を分解して栄養に変えられる。そのアッシミはミツツァルに対し強く、人間の体に入れると免疫を作ってくれる。

『鹿の王』はファンタジー作品で、疫病を呪いや怨霊っぽく描いているので、そういうファンタジーだ……と思い込んじゃう人もいるかも知れないが、かなり現実的に捉えられている。
しかし一方でファンタジーとして作られているところがある。ミツツァルに感染すると、低確率で「神秘の力」に目覚めることがある。おそらくは人対人による感染ではなく、山犬に直接噛まれたことによる感染ではないと目覚めることはないんだろう。
この神秘の力に目覚めると、自然のエネルギーと連携が取れて、通常ではあり得ない力を発揮できるようになる。つまり「シャーマン」として目覚め、トランス状態に入りやすい体質ができてしまう。

アカファ国はどうやら「政治上の長」とは別に「宗教上の長」もいるらしい(宗教上の長はどこの国でもいるけど)。シャーマンとして目覚めた者のなかから、宗教上の長が選ばれるようだ。
宗教上の長になると、自然の力をコントロールすることができて、疫病を媒介する山犬たちも意のままに操れるようになる。
ところで「山犬」が「病」を媒介するって、ひょっとしてダジャレだろうか?

そもそもなんで10年間音沙汰のなかった疫病ミツツァルが急に蔓延したのか。いや、アカファの人々は疫病を蔓延させたのか。
それは「玉眼来訪」というイベントがあるから。「玉眼」という言葉がなかなか凄い。日本では天皇の身体を「玉体」と表現することがある。ツオルは「目」が国のシンボルイメージで、その最上級の存在だから、「玉眼」ということになる。つまり「玉眼=皇帝」。
玉眼、つまり皇帝が再びアカファの土地へとやってくる。皇帝の目的は10年前やり残した課題である「火馬の郷」攻略。火馬の郷というのはアカファにとって宗教上の聖地。そこを攻略すれば、今度こそアカファを自分の土地にできる……(政治上の長は、すでにツオルに服従させている)。
そういう脅威が迫っているのを察知して、アカファの人々は山犬たちをけしかけて、疫病を流行らせようとした。

山犬は岩塩鉱の他に、鷹狩中だったウタルのところにも出没した。ウタルは皇帝の親族で、アカファ内部に出張して提督のようなものをやっていた。
アカファ側からすれば、強権的なウタルは邪魔。その弟であるヨタルのほうが御しやすい……。そこでウタルを疫病で殺した。ある意味の「暗殺」である。
岩塩鉱を襲ったのは、そこにアカファ人がほとんどおらず、たぶん塩が外貨を得る手段だったからじゃないかな。外からお金が入ってくる手段を断ってやろう……と、そういう狙いだったんじゃないかと。

アカファ国の王やその近辺は、ツオル帝国に服従しつつ、体制の転覆を模索している。その第1歩として疫病を蔓延させた。
ホッサルは医者として、免疫を持っているヴァンの行方を追う。アカファ国も同じ理由でヴァンの行方を捜しているが、抗体なんて作られたら計画がご破算だから、密かにヴァンを殺そうとする。

そこに現れるのが第3勢力のオーファン。オーファンはミツツァルに感染し、シャーマンの力を獲得した「宗教上の長」だ。しかしその効力は永続ではなく、次第に弱まっていくものらしい。
(おそらくはミツツァルに対する抗体ができてしまい、抗体ができてしまうと神秘の力を行使できなくなる……という意味ではないかと思われる)
そこでオーファンは自分の後継者としてヴァンを仲間に引き入れたい。単にシャーマンの力に目覚めた後継者だから……というだけではなく、ヴァンはめちゃくちゃに強い軍人。アカファ国を守るのに、ヴァン以上の適任はいない。
しかし、シャーマンの力に目覚めた人は、実はもう一人いて……。
ここまでが本編のだいたいの解説。
ここから映画の感想文に入っていきましょう。

最初に岩塩鉱で奴隷がヨロヨロと倒れる場面を見て……うわっ上手い。体制が崩れて、さらに荷物の重さに引っ張られて倒れる……ここまでの身体感覚を異様なリアリティで表現している。
キャラクターを見ると、ジブリ風……というか昔の東映アニメ風で描かれているけど、身体の捉え方はしっかりProductionIG。キャラクターの身体がリアルに捉えられている。一見ジブリ風なのに、リアルな動き方をするキャラクターたちが、どことなく新鮮だ。
エンドクレジットを見て気付くが、参加アニメーターがかなり凄いことになっていた。
監督の安藤雅司は最初に書いたように、ジブリ出身の超一級アニメーター。それ以降のクレジットを見ると……。
井上俊之……『地球外少年少女』総作画監督、『エヴァンゲリオン新劇場版Q』作画監督、『千年女優』作画監督。
板津匡覧……『ボールルムーへようこそ』監督、『百日紅』作画監督。
沖浦啓之……『人狼』監督、『ももへの手紙』監督、『GHOST IN THE SHELL』作画監督。
井上鋭……『人狼』作画監督補佐、『MONSTER』作画監督、『すずめの戸締まり』作画監督補佐。
高士亜衣……『文豪ストレイドックス』作画監督。
和田直也……『ガンダム Gのレコンキスタ』作画監督補佐、『チェンソーマン』サブキャラクターデザイン
瀬口泉……『攻殻機動隊新劇場版』作画監督、『地球外少年少女』作画監督。
河原奈緒子……『若おかみは小学生』作画監督補佐、『明日ちゃんのセーラー服』作画監督補佐。
黄瀬和哉……『天国大魔境』作画監督、『劇場版Fate』総作画監督、『攻殻機動隊』シリーズのキャラクターデザイン、作画監督。
アニメに詳しい人であれば誰もが知っているような超一級のアニメーターが作画監督に名前を連ねている。原画の名前を見ても、『思い出のマーニー』の監督である米林宏昌や、『Gのレコンキスタ』や『地球外少年少女』のキャラクターデザインを担当した吉田健一といった名前が出てくる。国内最高峰のアニメーターが集まって作られた、なかなかとんでもない作品だということがわかる。

ヴァンが猪を素手で止めた瞬間。ぶつかった衝撃が猪自身に戻って、全体に衝撃の波が走る。

斬り合いの瞬間。手に筋が浮かび上がり、親指の付け根にコブができている。少ない線数で力がグッと入っている感覚がうまく表現されている。

高足がバランスを崩し、ヨタヨタと倒れる瞬間。やはり身体の捉え方がうまい。
とこんなふうに、恐ろしく贅沢なアニメーションを堪能できる作品。
しかしその一方で、構図が平凡……という弱点を抱える。

カットによるのだけど、画角が妙に狭く、なんとなく奥行きに欠ける。空間の広がりが感じられない。

空間を見せる場面になると、なぜか遠近感が曖昧になる。立体感が弱く、全体としてのっぺりした印象に見える。
もちろん、うまい構図も一杯ある。いや、むしろうまい構図の方が多い。しかし人物と風景が一緒になるカットになると、どのカットも画角が狭く、奥行き感が感じない。レイアウトが弱いな……と色んなところで引っ掛かる。
監督の安藤雅司は超一級のアニメーターだけど、レイアウトはあまりうまくないのだろうか……。
構図作りの上手い下手は、「絵の上手い下手」と直接結びつくわけではない。例えば押井守監督は自身では絵を描かないが、バチッとはまった構図を考え出すことができる。漫画家の諫山創は絵はさほどうまくないのだけど、初期の頃から構図はやたらと上手かった。諫山創の場合、構図が上手すぎて、絵がうまく錯覚するほどだった。
もちろん「絵が上手い」と「構図作りが上手い」はたいていの場合一致する。絵も構図もうまい……という人の方が絵描きの世界では普通だ。しかし、絵の技術と構図のうまさが分離している……という人もまたいる。そういう「センスがある」と「技術がある」は別問題だと考えたほうが良い。
そういう話で言うと、安藤雅司の構図作りはちょっと「あれ?」と感じるところがある。
次に引っ掛かったのは映画作りの勘。「ここ、いらないよね」って場面が結構あること。

例えば高足との戦闘のあと、なぜか都合良く温泉に行き着いて、そこで一息。キャラクター達が語り合う場面に入っていく。
このシーン、要らないよね。
こういったシーンでストーリーの展開が躓いてしまっている。後半に向けて盛り上げていくところなのに、トーンダウンしてしまう。宮崎駿監督だったらバッサリ切り捨ててる場面だ。
こんなふうに、「このシーン要らないのでは?」というところがぽつぽつ。展開が悪くなってしまっている。こういうところで映画作りの勘所がないな……と感じてしまう。

それぞれの距離感も「あれ?」となるところ。
山犬たちに誘拐されたユナを追って、ヴァン達は数日にわたる旅に出る。その後、サエが離脱するのだが、1日のうちでトゥーリムやアカファ王と合流している。
いや、近すぎないか。
近いのはそのはずで、そもそもツオル帝国はアカファの宗教的な聖地である火馬の郷攻略のために兵団を集結させていた。ヴァン達も火馬の郷に向かっていたので、近くにいた……という設定に矛盾はない。
でも全体を見ると距離感がぼやけた感じに見えてしまう。マコウカンがホッサルの居場所を教えてもらって、その日のうちに火馬の郷に辿り着いてしまうのも、ご都合主義的に見えてしまう。

それ以上に引っ掛かったのは、超常的な現象を見せる場面の画が通俗的なこと。映画作りには「作法」というものがあって、基本的には観察主義的に描いたほうが良い。こういった超自然的なシーンを見せる場合には、思い切った絵画的なイメージが必要になるが……。ただ漫画的にわかりやすくしただけ、というだけで「絵画的」な驚きや美しさは表現されてない。ただシュールなだけで、「なんだこりゃ」という雰囲気になってしまっている。

映画のクライマックスに入ると、この通俗的なイメージがどんどん多くなってくる。これがクライマックスの感動を遠ざけてしまっている。まず、このイメージが『鹿の王』というリアルに構築された世界観に合ってない。そこだけ妙に安っぽいイメージになっている。このイメージの中で作中でも重要なシーンが描かれるのだが、感動できない。重要なシーンなのに美しくない。いいシーンなのに、「何だこりゃ」という感想になってしまう。

クオリティ全体はものすごく高いのだけど、イメージが平凡。そこに引っ張られてしまい、どうしても全体が安っぽく見えてしまう。どこか「70点」という感じになってしまっている。良いか悪いかでいうとものすごく良い。それゆえに、一部のシーンでイメージが平凡になってしまっているところが「惜しいな」と感じてしまう。シナリオもキャラクターもアニメーションも良いのに、しかし「70点」という感じの作品。そこがなんとも惜しい。
表現をもっと突き詰めれば、後の時代に残る作品になったかも知れないが……。
物語はアカファ国とツオル帝国の戦いを描いている。植民地拡大に意欲を燃やすツオル帝国と、それに服従する素振りを見せつつ、反逆を企てようとするアカファ……というのが基本的な構図だ。しかし一方、ツオル人が少しずつアカファ国に踏み込もうとしている姿が描かれる。
現実でも「文化の侵略」は大きな問題となっている。外国に移住した移民達というのは、移ってきた国でも自分たちの文化を守り、習慣を維持しようとする。それが普通の人たちの感覚だ。しかし、そうすると移民先で対立が起こる。それどころか、移民達はその国の文化や習慣を軽んじる傾向がある。移民達にとってその文化は、「守る意味がない」ものだからだ。公共物の破壊とか、平気でやってしまう。そういうところでも対立が起きる。これがいまヨーロッパが直面している問題。遠からず、日本でも大きな問題になるだろう。
『鹿の王』では二つの側面が描かれている。ツオル帝国の人々はアカファ国に服従を迫り、自分たちの文化を押しつけようとする。一方でトマの村のように、ほとんどアカファ国の文化に染まって同化してしまっているツオル人もいる。アカファ人もツオルの文化を少しずつ受け入れている。
エンドクレジットを見ると、アカファのシンボルとツオルのシンボルが合体したような旗が作られている。あれがこの作品の作り手が伝えたかったこと。対立ではなく「同化」していくこと。服従ではなく、平等であること。そのうえでお互いのいいところ取りをしていってアップデートしていく。おそらく世界中の人々が夢見ている理想の姿でもある。
何の因果か、『鹿の王』は未知の疫病が世界に蔓延し、西側東側という昔ながらの戦争が再び始まった……という頃に制作され、公開された。まるで現実世界に起きたことを暗喩的に置き換えたような内容になっている。おそらくは企画段階ではそういう狙いはなかったはずだが、偶然にも今の時代に問うべき映画になっている。
『鹿の王』は表現の面で引っ掛かるところはいくつか見られるが、この作品をヒントに、現実問題をいかに考えるべきか……そのヒントが得られる作品となっている。そういう意味でも見る意義のある1本だといえる。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
