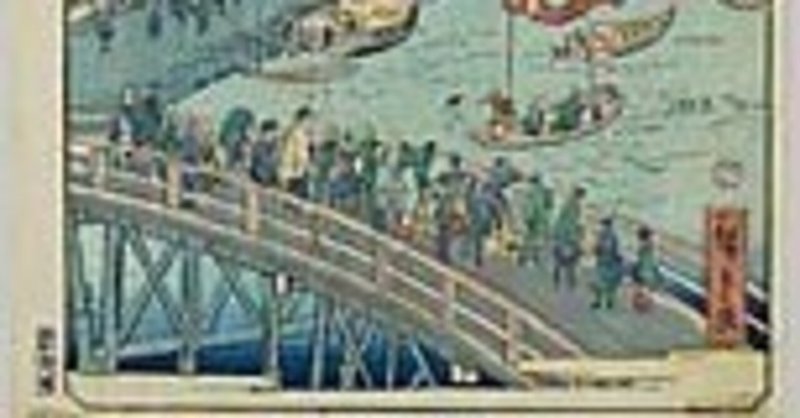#江戸幕府
江戸期~昭和初期の経済成長から見た日本酒の発展(市場経済側の経済的な視点からの日本酒の発展)
※見出しの画像は関西学院大学所有 灘の新酒番船江戸入江の図
江戸初期から中期までの経済状況
2019年現在の日本の人口は約1億2700万人、GDPは約550兆円となっていて、国民一人当たりのGDPが約433.7万円となっている。普通に働いて生活していれば、少々貧しくても一定のお金さえ出せば、欲しいものは買えるし、余程のことが無ければ食に困ることも、ほぼ無いと言えるといえます。
では、1600年
江戸期~昭和初期の経済成長(市場経済側の経済的な視点からの日本酒)その2 本日の紹介酒 櫻正宗 灘の生一本 純米酒 (兵庫県 灘)
※日本酒の画像は、櫻正宗㈱HPより引用
非常に厳しかった市場での酒質の競争
この頃、江戸へお酒を卸すには、上方の銘醸地である伊丹・池田・摂津富田・西宮・灘等の銘醸地の間で熾烈な酒質の競争が行われていて、現代の語の「下らない」の語源は上方から江戸へ下れない酒でありました。
仮に下れたところで仮に下れたところで、上方の酒同士での競争はもちろん、中国酒(愛知県の知多地方や三重県の四日市近辺)や関東
鎖国とは事実上の保護貿易でもあったのではないだろうか?(画像は長崎出島Wikipediaより引用)
鎖国に関しての本当にキリスト教禁教が理由だったのか?鎖国について、表向きの理由はキリスト教禁教ですが、島原の乱以降、キリシタンに対する締め付けは、さほど厳しく行われておらず、建前では禁教としながら、実際それ程厳しい締め付けは行われなかったようで、最近江戸期の経済発展を日本酒研究の部分から見ていて気づいた事は、鎖国の本当の理由とは経済的な理由であり、一つ目が江戸幕府が特権的に貿易の利益を独占する事と
もっとみる