
【ハーブ天然ものがたり】クローブピンク/カーネイション
カーネイションのお母さん
地中海沿岸地域を原産とするナデシコ属、学名 Dianthus caryophyllus はハーブ業界でクローブピンクとよばれるカーネイションの原種のひとつです。

✧
クローブカーネーション(Dianthus caryophyllus)はもっとも濃厚でピリッとした甘い香りがする、エリザベス朝(1558年 - 1603年)の品種。
コテージピンクまたはガーデンピンク(Dianthus plumarius・和名タッタナデシコ)との雑種にオールウッディピンク種があり、クローブの香りがするものはすべてハーブとして使用されている。
ガーデンピンクは現在ある多くのナデシコ属の交配親である。

学名のDianthus属はギリシャ語で、神(ディオス)の花という意味をもち、神々の王ゼウスに捧げられたハーブとして有名です。
古代ギリシャ・ローマ時代には祭りや婚礼の儀式にふんだんにつかわれ、飲みものに花びらを浮かべたり、花冠や衣装にあしらってその香りを楽しんでいたといいます。
現代市場に出まわっている観賞用のカーネイション(栽培品種)は、くらしのなかにすっかりと定着し、だれもが知る植物となりました。
地上部から切りとると、あっというまに香り成分が揮発してしまうので、そのおおくは香りを感じることができませんが、原種であるクローブピンクの名は、クローブ(丁子)のような香りをもつことから命名されました。
クローブについてはこちらの記事に綴っています。
フルーティでスパイシーな香りただようクローブピンクの花は、繊細な料理を彩るハーブとして、砂糖づけにして保存したり、ソースやシロップ、ワインの香味づけに用いられています。
母の日プロモーションに乗じて世界中にひろがった観賞用カーネイションは、近種のナデシコ属である中国原産の石竹(虫につよくて丈夫な種)との交配を契機に、1700年代から品種改良がすすみ、ヨーロッパを中心に世界中でたくさんの品種育成が展開されてきた背景があります。
ハウス栽培によって市場への流通がさかんになった観賞用カーネイションは、季節とわず一年をとおして供給が可能になり、いまではバラやキクとおなじくらいの生産高を誇る業界の稼ぎ頭。
古代ギリシャ時代にダイアンサス(神の花)と呼ばれた芳香ゆたかなハーブから生まれ、色や形状さまざまに3000種にひろがっています。
植物学による分類法がすすんで、「神の花・Dianthus(和名ナデシコ属)」はそのまま学名になりました。
日本で「なでしこ」といえば大和撫子を想起しますが、河原に生えるかれんな花、河原撫子の別名でもあります。

撫でたくなるような愛おしさを撫子と表現し、秋の七草にも詠まれた河原撫子は、あかるくひらけた里山が激減した現代日本では自生地の喪失とともにレッドデータ入りしてしまいました。
石竹との交配種である伊勢撫子の自生地は、わずかながら保護されているそうです。
(河原撫子は)秋の七草の1つであることから分かるように観賞価値を認められた。
栽培も行われ、特に江戸時代には変わり花の栽培が盛んで、古典園芸植物の一つともなっていたが、現在ではほとんど見られなくなり、わずかに伊勢ナデシコと呼ばれる一群などが維持されている。
また、他のダイアンサス(ナデシコ)類の交配材料にも用いられる 。
薬用としても利用されており、開花期の全草を瞿麦(くばく)、種子を乾燥したものを瞿麦子(くばくし)と称する。
利尿作用や通経作用、消炎作用がある。
カーネイションの原種であるクローブピンクも、自生するものは激減していると聞きますが、産業種としての栽培は維持継続されており、香水や石鹸の香料になったり、カーネイションの精油もわずかながら市販されています。
英名のクローブピンクにつかわれた pink は、1500年代にはまだ色のなまえとして定着しておらず、 pink はダイアンサス(なでしこ)そのものを指すことばだったといいます。
カーネイションもなでしこも、花びらのフリフリ感が特徴的ですが、ピンキング(ギザギザに切る)からピンクと呼称された説がウィキに記載されています。
1570 年に記録に登場してから 20 年以内に、その花の名前(ピンク)は、今日英語でピンクとして知られるパステル調の赤を指すために使用されるようになりました。
ピンキングバサミに共通の起源があるのか、それとも(pinkという)花(の名まえ)にちなんで名付けられたのかは不明です。
花の名まえだったピンクがダイアンサス(なでしこ)の色として定義されるようになり、自然界にあらわれるサンゴやあけぼの、鳥や魚や果実などにみられる特有のピンクもどんどん定義されて、なでしこ以外にも薔薇色の頬とか桃色吐息とか、ピンクの気配はバリエーションゆたかに表現されるようになりました。
いろんな植物ピンク、WEB見本和色大辞典からお借りしました。
まるいスペクトラム
carnationは、carnate(肉体)tion(名詞化)という意味をもつということで、ピンクを肉(ラテン語 carn)とみなして肉色の花とする説があります。
すこし脱線しますが carnivalも carn(肉)に由来して謝肉祭と翻訳されます。
肉に感謝するカーニバルということは、飲んで食べて、歌って踊って、肉体を駆使することであじわうヨロコビを甘受するものだとかってに連想していました。
ところがカーニバルは語源説を紐解くと carnem(肉を)levare(取り除く)に由来し、宗教的行事からはじまった「肉に別れを告げる宴」からはじまったことばなのだそうです。
謝肉祭は元々カトリックなど西方教会の文化圏で見られる通俗的な節期のことで、四旬節が始まる「灰の水曜日」の前夜に開かれた、肉に別れを告げる宴のことを指した。
仮装したパレードや菓子や花を投げる行事などが行われてきたことから、現代では宗教的な背景のない単なる祝祭をもカーニバルと称することが多い。
*四旬節はカトリック教会、保守的なプロテスタント宗派の典礼暦にある、復活祭の46日前の水曜日から復活祭の前日までのことで、祈りと断食の期間のことです。
肉の色をピンク(インカルナート)と表現し、色彩は「周囲に生きる存在、あるいはその影(像)である」と綴られている「色彩の本質◎色彩の秘密(ルドルフ・シュタイナー)」には、人の肉色(肌色)の本質についての言及があります。
そのなかに光と闇をあらわす色(白と黒)のなかで、色彩はどのように表出してくるのか説明されています。
黒を描き、その下に白、また黒、その下に白というふうに、黒と白を続けます。
黒と白は静止しておらず、たがいのなかへと動き、入り交じってうねる、と想像してください。
そこに赤の光輝がさしこむことによって、桃花色(肉色・インカルナート)ができるでしょう。

この本のなかでシュタイナーは現代社会で合意されている定義のひとつ、色の三原色である赤・黄・青を「輝きの色」と名づけています。
赤・黄・青は「輝き」をみずからのうちにもっており、そのかがやき方の本質をつねに外にむかって告げるため「輝く」のだ、とあります。
輝きかたは三者三様、黄色は中心から外にむかってかがやき、青は自らの中心にむかってかがやき、赤は放射と凝縮を中和させるかのように均等にかがやきます。

わたしたちの太陽系でみずからかがやく光は太陽です。
地球から空をみあげると空の彼方にある光と闇を、3つの輝く色で知覚することができます。
黄色は昼の光、太陽そのものをもっともよくあらわした色です。
赤は夕暮れと朝焼けの色、闇の空間から光を見るときの色です。
青(空)は太陽の光に満たされている昼の空間から、闇(宇宙空間)を見るときの色です。



二極化設定されている光と闇の舞台では、闇のなかからみる光は赤く、光のなかからみる闇は青く、光のなかでみる光は黄色という色彩で表現されているんだなぁ、と。
ご来光をあおいだり、夕焼けさんぽをしたあとは、日常というフェイズがスライドして、すべてが刷新されたかのような気分になることがおおいですが、自然界がうみだす赤い光には、容赦なく皮膚をこえ、からだのなかに侵入してくるナニモノカがあるように感じています。
赤をみると興奮作用があり血行がよくなる説は一般的になりました。
闇のなかで光を発見したときの気分を想像すると、血わき肉おどる身体反応は自然なことだろうと思います。
本のなかでシュタイナーはヒトの目のなかにある精妙な静脈に赤い光が浸透すると、血液と神経をわずかばかり破壊するので、修復するために血液が頭部に酸素をはこんで吸収し、目が新鮮になると説明しています。
酸素が供給されることで頭が活気づいて全身に作用し、顔色もよくなるよ、と。
反対に光のなかからみる闇、つまり青い輝きは神経を破壊せず、気分を鎮静化して、目にも内的にも安定したよい気分をおくるように身体機能はセットされている、とあります。
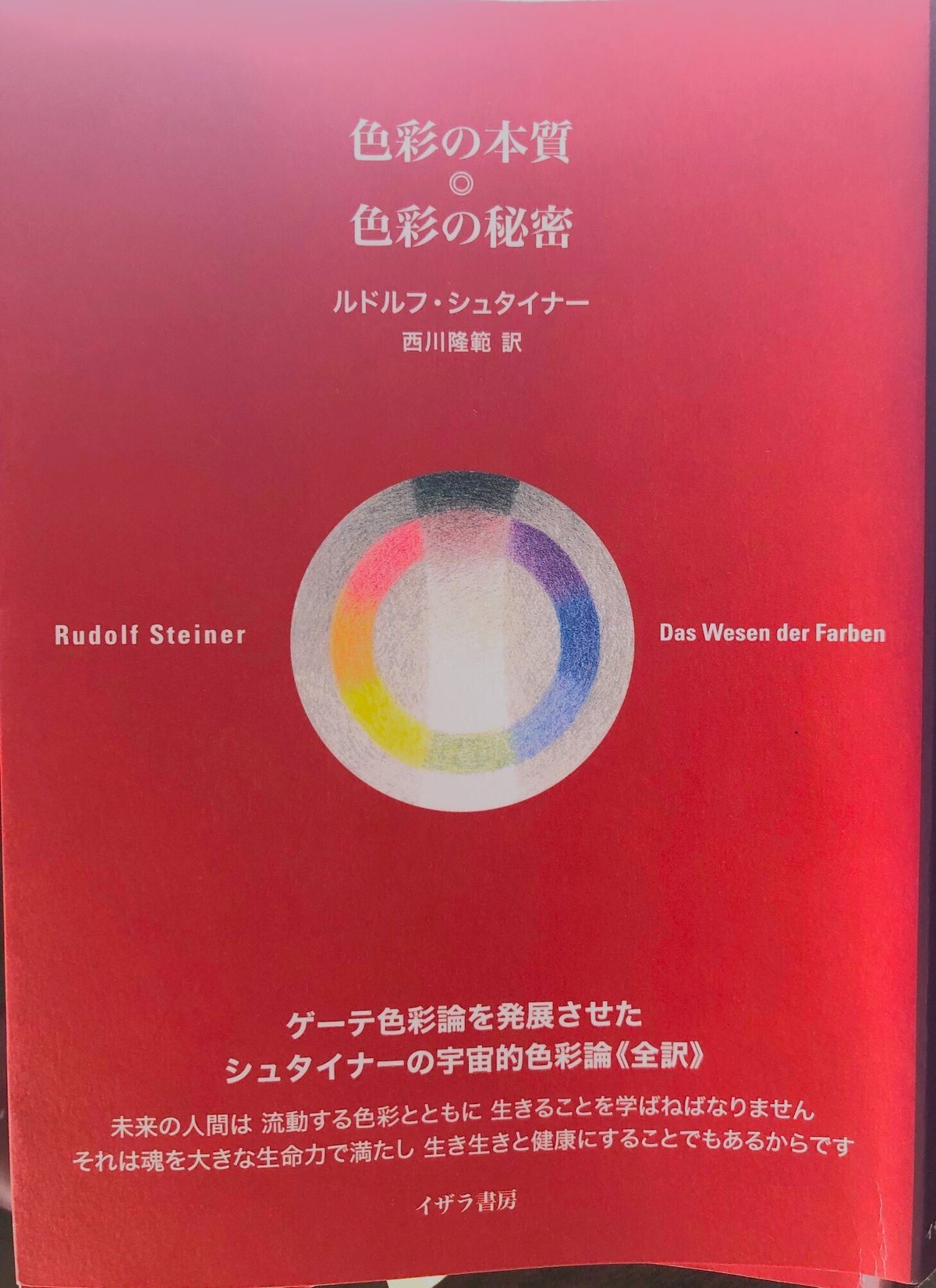
本の表紙にもデザインされている円環のイラストは上に黒(闇の像)、下に白(光の像)があり、人類のピンク色と、植物の緑が対なして、闇からみる光の赤と、光からみる闇の青を区分けしています。
光が創造分化されることで地上世界にひろがった色について、シュタイナー本から引用・要約してみます。
「緑色の植物界があります。
そこに闇が結びつくと緑は青のニュアンスを帯びます。
(緑から)明らむもの、熱に満たされるものが上方へと流れてゆきます。
そこ(緑の対抗にある上方)では人間のエーテル体が桃花色(肉色・インカルナート)をしています。
それは青が赤のなかに広がっていくときに現れる色でもあります。
桃花色は人間自身です。
人間は桃花色のなかにおり、緑に対峙しているということができます。
一方には青い闇があり、他方には明るい赤、黄があります。
思考を光として知覚することが少ない人類は、桃花色のなかに生きているのでほんとうのスペクトルを見渡すことができず、青から赤、あるいは赤から緑をとおって青までしか、色彩の世界を認識できずにいます」
地上からみる虹は半円形で、光色のスペクトラムとして現代脳はピリオドを打ち、それ以上の見解はファンタジー枠で片づけられてしまいます。
虹のたもとにはなにがあるのか?という人類の好奇心はおとぎ話や民話のなかでイマジネーションゆたかに伝承されつづけ、金の壺や酒の樽、竜の栖や妖精の国など、ココロおどる像(象徴)の萌芽は尽きることがありません。
ケルト妖精譚で金の壺をもっているという妖精レプラコーンもたのしいおはなしではありますが、「ここではないどこか」あるいは「いまではないいつか」というエクスキューズがついてまわり、ファンタジーやエンタメの域をでることはありません。
物語はたのしみつつも、と同時につよい信念によってヨソゴト枠へ整理され、「いまここ」とは無関係、ソレはソレ、コチラはコチラ、日常とは区別して、ばっさりきっぱり断ちきっておきましょう、というのが「ふつう」です。
「宇宙から流れこんでくる成分で形づくられた肉体とともに一時代を築き、とくべつなフェイズをとくべつな方法で見聞する人類という器には、心臓という金の壺が配されている」と、古代の叡智とともに生きた先人のことばを聞いても、大脳新皮質をフル回転させている状態では戯言と処理されてしまいます。
古代、密儀の導師は
「人間の心臓は、光のなかに生きている金の成果であり、光のなかに生きている金が宇宙から流れ込んできて、人間の心臓を形成する」と語りました。
光と闇のうねりのなかでさまざまに交流しながら、色彩の円環がカタチとなり、地球につながるあたらしいフェイズ(pink)を創造して、心臓という金の壺をもつ人類が誕生しました、という説明の真偽はさておき、虹のたもとの金の壺は、からだの内にありましたというたてつけは、メーテルリンクの「青い鳥」みたいでおもしろいです。
虹のたもとで、虹をまるくつないでいるのは実のところ人類だったというオチは、うれしいようなくすぐったいような、身のうちをクスクスとふるわせるたのしさがあると感じます。
チルチル・ミチルが光に導かれていろんな国を旅するなかで、妖精からあずかった帽子の魔法で世界の本質を見通して、動物や火や水などの元素にも知性があると知ったように、現代人もピンクの知性をおもいだし、ピンクに生きる振動になることで、異世界と日常世界をまぁるくつないで、「いまここ」に想像できるすべてのものとのつながりを「ふつう」に受けとめられるようになるのかもしれません。
ピンクに生きる振動って、語弊があるかもしれませんがwww
あこがれやときめきに忠実になって、ほんらいの自分がこころから情熱をそそいで、ヨロコビを目いっぱい創造したり表現したりする信念体系に、迷うことなくじゃんじゃん飛びこんでゆく、というような意味でつかいました。
それがほんらいの、人類ポジションなのではあるまいか、と。
ちなみに虹のおはなしは、ポットマリーゴールド(マリア様の金の壺)とともに、こちらの記事にも綴っています。
reincarnation(リインカーネイション)
ピンクという色をこの世界に定義したハーブたち。
クローブピンクは、もしかすると虹をまるくつなぐために、地球世界で進化を遂げてきた色彩存在との共同創造物で、ピンクのたすきを人類につなぐために、植物界で試行錯誤してきた傑作種なのかもしれません。
列車を走らせるためにはさきに線路を敷かなければならないのとおなじように、シュタイナーいうところの心魂(アストラル体、あるいは動物体とも表現されます)が地球に乗りこめるようにと、先陣隊としての生命体(エーテル体)が触手をのばして、あーでもないこーでもないと植物界で練りあげたプロトタイプが、ダイアンサス(神の花)だったのかもしれないな、と妄想はひろがります。
カーネーションは、re(再)in(中へ)をくっつけると、生まれ変わりや輪廻転生を意味する reincarnation になります。
生まれ変わることを、カーネイションに再び入ると表現しているわけです。
地球にクローブピンクが花ひらくたび、地上世界を闊歩するための器が着々と準備されていることを知った光の存在たちは、地球のはなつ青い闇のかがやきに魅せられて、どしどし降下してきたのではなかろうか、と。
ピンキング(ギザギザの裁断)というあたりも、エーテル体の地上的象徴物である布や糸がほつれることなく、ひとまとまりの器として存在できる、とくべつな形態(ギザギザの花びら)を模しているのかな、と妄想はさらにひろがります。
宇宙全体としての円環からピンキングされ、虹の環から切りはなされたかのようにふるまう器にはいっても、ほつれることなく機能する試行錯誤と創意工夫の賜物は、地上世界に没入してさらに創造降下を推進するのにとても便利なシロモノで、光のなかに生きていたことをいっとき忘れるにはうってつけの形状だったのかもしれないな、と。
虹という漢字の語源説に、虫はへびのカタチを字にした象形文字で「つらぬく」という意味の「工」をあわせて「天空をつらぬく大蛇」に見立てた、というのがあります。
物質をより堅固な固体として定着させる創造プロセスのなかで、虹を、龍や空飛ぶ大蛇とみていた古人の知覚は、いつしか「ここではないどこかヨソゴトの物語」となりました。
ピンクの色彩世界をとりもどすとコチラもアチラもなくなって、蛇がしっぽを噛むように円環になり、大団円をむかえるのかもしれません。
それはもしかすると、わたしたち人類が宇宙全体を舞台に循環しているエネルギーだということを、「ふつう」のこととして受けいれる、はじまりの一歩になるのかもしれません。
店先のカーネイションや、野っぱらのなでしこをみかけるたびに、ピンクに生きるポジションを思いだします。
宇宙全体に思いを馳せ、肉体をこえたエネルギーや、それが循環しつづけていることや、すべてがつながっていることなんか思いだして、ピンク色したギザギザ花びらが、かなりとくべつな体験のために用意された器かもしれないことに思い至り、その勇気と冒険心にココロうたれます。
自己想起練習や瞑想をしているとき、からだをこえて意識がおおきくひろがったなぁと感じることがあるのですが、からだのそとから見る自分は肉肌色の器にはいって、とくべつな体験のためにとくべつなフェイズを探検しているチャレンジャーのようにみえることがあります。
だから自分自身に、しいては人類という生命種に、いつでも敬服するばかりです。
☆☆☆
お読みくださりありがとうございました。
こちらにもぜひ遊びにきてください。
ハーブのちから、自然のめぐみ
ローズマリーから生まれたナチュラル・スキンケア
Shield72°公式ホームページ




記事のご紹介、マガジンご収載ありがとうございます
私どもの記事をご紹介、マガジン収載いただきこころよりうれしく思っています。
ありがとうございます♡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
