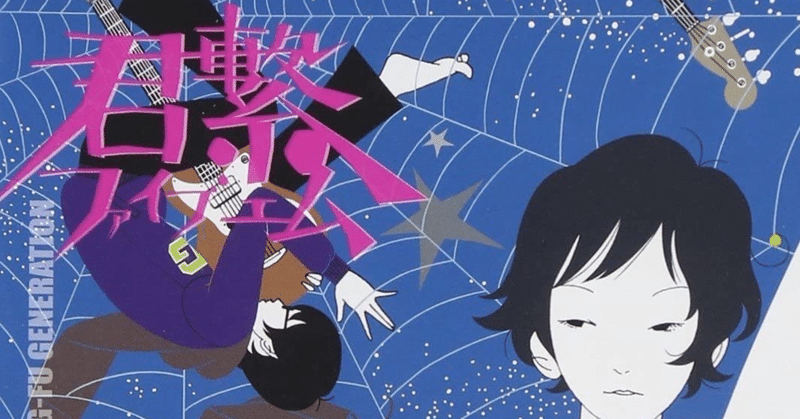
アジカン精神分析的レビュー②『君繋ファイブエム』/世界と向き合う"象徴界“の音楽
今年メジャーデビュー20周年を迎えるASIAN KUNG-FU GENERATION。その作品史を精神分析的視点から紐解いていく、勝手なアニバーサリー記事シリーズです。
1stアルバム『君繋ファイブエム』(2003.11.19)

インディーズ期の曲に加え、2003年4月のメジャーデビュー以降に行われたセッションで作られた曲を多く収録した1stアルバム。音楽的な振れ幅も前作『崩壊アンプリファー』から大きく広がり、以降のアジカンを決定づける指針的な1作となった。そしてオリコン週間5位、35万枚のヒットを記録した。
読み方は「きみつなぎファイブエム」。かなり個性的なタイトルだが、これは君と繋がっていたいという想いと、その限界は5メートルであるという後藤正文(Vo/Gt)の感覚が込められている。その独自性やニュアンスはデビューしたてのバンドゆえにそこに込められたメッセージは伝わりきらなかった。
例えばインターネットの登場が代表するような情報化社会の中で、それぞれの「半径5メートル」が無茶苦茶になってしまうんではなかろうか、ということだった。ひとまずはその「半径5メートル」をしっかりと知覚したり把握したり整理しないとどうにかなってしまうんじゃないか、っていう危機感を反映させてのタイトルだった。
こうした意識を忍ばせた題だったはずが、君と僕だけが繋がっている閉じた関係性で巨大な世界と対峙するというセカイ系的な文脈で消費されるようになったことへの嫌悪を後藤は上記の日記に記した。アジカンは果たしてセカイ系と呼ばれて然るべき表現をしていたのか。本稿で紐解いていきたい。
広がりゆく未来へ
アルバムは『崩壊アンプリファー』の流れを汲む荒々しいサウンドで幕を開ける。意味の連続性をぶった切り《あの日の未来がフラッシュバック》と、時空すらゆがめて後悔と恐れを叫ぶ「フラッシュバック」から1stシングル「未来の破片」に続く流れはインディーズ期の煩悶を砕き、その先へ繋ぐイメージが湧く。サビの《繋いでいたいよ 君の声が聞こえた日から萌える色》とは、リスナーの存在を初めて意識したと思しきセンテンスに聴こえる。
そして3曲目以降、音楽性もメッセージの射程距離も一気に飛躍する。疾走感と瑞々しさ溢れる「電波塔」は、かなり直接的に音楽を届けること/受け取ることを綴っている。パワーポップアンセム「アンダースタンド」では、《歪んだ日の君を捨てないでよ》とアジカンに触れる若い世代や過去の自分に向けて呼びかけてもいる(特に初期のアジカンの歌詞における"君"とは過去の後藤自身、ないしはリスナーのことを指すと個人的には解釈している)。
そんな4曲で始まるのだから、アジカンをセカイ系とみなす視点にはそもそもあまりぴんと来ない。強いて言えば「夏の日、残像」で描いた季節感や過去への目線、「無限グライダー」における無常を悟り現実を辛く思う仕草、「その訳を」にある《絶望の果て 繋いだ手》といった言葉選びなどセカイ系として受容され得るモチーフは部分的にあると思う。しかしどの曲も、自分の内面であり聴き手でもある君という対象へと目線は向いているだろう。
ここから僕のスタート
そうさすべてが窄み行くとも
ここから君のスタート
その手伸ばせば目の前さ、ほら
広がりゆく未来へ
そして極めつけやはり「E」。このストレートなポジティブさは閉塞感や狭小な関係性とは程遠い。インディーズ時代から存在する曲であり、序盤は『崩壊~』に通ずる鬱屈した心象風景が描かれるが、サビは開放的なメロディが広がる。oasisの「Live Foerver」のフレーズを引用し、永遠に続く音楽を想い叫んでいるように聴こえる。この曲のみならず『君繋~』は一貫して未来を鳴らす。過去の自分や近い距離のリスナーと共に未来を想う1作だ。
セカイ系を整理する
セカイ系でないとして、この"5メートル"という僕と君の関わりにこだわった作風はどこから来たのか。ここで精神分析概念を持ち出そうと思う。
精神分析家ラカンの想像界・象徴界・現実界という概念がある。これは我々の生きる”人間世界”を示す概念だ。例えば、生まれて間もない幼児の精神は「想像界」にいる。幼児が親密な保護者と、言葉を交わさずとも一つとなっていると信じている状態、これを「想像界」に精神がある状態と言う。言葉を必要としない、イメージだけで成り立つ世界こそが「想像界」である。
アジカンメンバーは誰も赤ん坊ではないが、世に出たバンドとしては乳幼児の時期だったとも言える。アジカンが『君繋~』で近い距離感のリスナーや信頼できる相手との関係、つまり僕と君という言葉なしで分かり合える近い距離感の関係性を描く楽曲を多く作ったのは人間の精神発達を考えれば納得だ。アジカンとしての心の原風景であり、最も濃く描ける事象だからだ。
言語を用いたコミュニケーションを家族と行うようになり、成長して躾や教育を施され、学校や社会のルールに沿い始めると人の精神は「象徴界」へ向かう。つまり言葉を獲得した大半の人間の精神はこの世界にいると言える。
では「現実界」とは何か。それはイメージしたり、言語で形容することもできない、捉えようのない"認識不可能な世界"だ。言うなれば「現実界」とは超越的かつ観念的な混沌世界と言える。つまり「現実界」はスピリチュアル的な事象や壮大なスケールの"神話"などを内包することにもなる。
精神科医・評論家の斎藤環はセカイ系をこれらの概念を用いて捉えた。僕と君で完結する皮膚感覚で分かり合える関係性=想像界が、社会や家族といった関係性=象徴界を飛び越えて、壮大かつ神話的な世界=現実界に接続するのがセカイ系である、と。90年代以降、インターネットの急速な発達や家族関係の希薄化が進み、自然に想像界と現実界を直結するフィクション作品を生むようになったと考えられる、と。君と僕⇒神話的世界という作品構造が現代社会が抱えるコミュニケーション不全を暗に示していると解釈できる。
社会へ踏み出す
コンフリクトして固まらずに現実と接続するための「半径5メートル」についてのアルバムだとも言える。
後藤はこうした意思を持ち、『君繋ファイブエム』を作ったと振り返っている。セカイ系ではなく、むしろそういった構造の作品からは抜け落ちていってしまう言葉やコミュニケーションを手繰り寄せようとしていたのだろう。"君と僕"の相互理解に甘んじることなく、言葉でその繋がりを確かめ合うような。そう、これは「想像界」から「象徴界」へ移ろうとする音楽だ。日記内にある「現実」とは、「現実界」ではなくこの社会のことだろう。象徴界の音楽≠セカイ系として、この社会に踏み出そうとしているのだ。
ナンバーガールへオマージュを捧げた「N.G.S」でインターネット社会や仮想現実への懐疑を掻き鳴らし、アルバム屈指のラウドさ誇る「自閉探索」では《世界と繋ぐのをよしてしまう》、そんな自意識に警鐘を鳴らし、最後は《壁壊してよ 思い出してよ》と自意識に閉じこもることを拒絶する。たとえそれが《往々にして繋ぐ緩衝材》だとしても、《心に響かぬ言葉》だとされようとも、真摯に言葉として伝えようとするのがアジカンの基本姿勢だ。
君の目にただ光る雫
嗚呼、晴天の霹靂
痛みだけなら2等分さ、そうさ
僕らの色
語らずとも分かるでしょう、ではなく、丁寧にコミュニケーションを紡ごうとする『君繋ファイブエム』は現代にこそ響くべきアルバムだろう。その優しさの極点とも言える2ndシングル「君という花」がアルバム終盤に位置している意義も大きい。《痛みだけなら2等分さ》とちゃんと言葉で語りかける"僕ら”の関係性。過去への拘泥や自意識への逃避を越え、《また咲かすよ 君らしい色に》という眼差しを向けること。四つ打ちのリズムを導入したギターロックのオリジンでもあるこの歴史的名曲は、温かく包み込まれるような高揚感を言葉でも描いていたからこそ今なお愛され続けているのだろう。
アルバムは穏やかでセンチメンタルな「ノーネーム」で幕を閉じる。"君と僕”の距離感を確かめ信頼した『君繋~』を完成させたことで、心も冷え切るような冬を越え、芽吹く春へと進み始めたアジカン。《消えない愛を頂戴》、そして《名前をくれよ》と願ったバンドは想定以上の名前と、そして不確かな愛にまつわる葛藤と自問自答の時期へと突入していくことになる。
【骨芋】人々が繋がって星座のように連なって名前がつくこと。無数の君と僕が連鎖して形作られること。そういうフィーリングを歌ってますね。言葉選びの技術が低かったので誤解されることもあったんだと思います。自分の実力のせいですな。僕からは以上です。 #骨 #ノーネーム
— Gotch / Masafumi Gotoh (@gotch_akg) May 2, 2018
次回レビュー⇒2ndアルバム『ソルファ』(5月下旬更新予定)
過去のアジカン精神分析レビュー
#音楽 #邦楽 #ロック #バンド #ロックバンド #邦ロック #考察コラム #音楽コラム #エッセイ #コラム #ディスクレビュー #アルバムレビュー #asiankungfugeneration #アジカン #AKG #君繋ファイブエム #精神分析 #ラカン #創作大賞2023 #オールカテゴリ部門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
