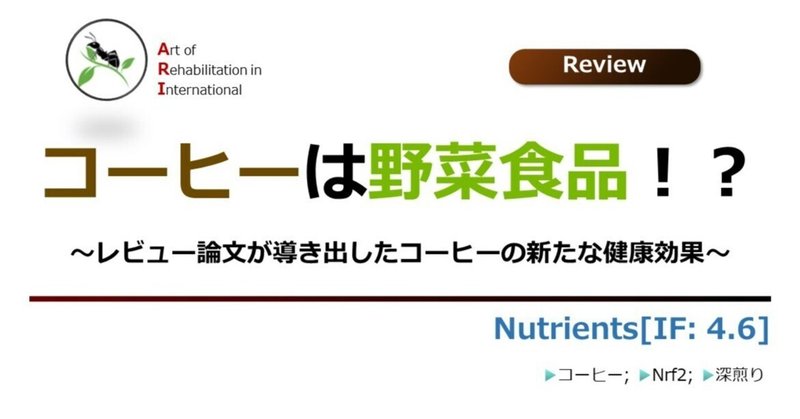
【英論抄読】コーヒーは野菜食品!?~レビュー論文が導き出したコーヒーの新たな健康効果~
▼ 文献情報 と 抄録和訳
コーヒーの健康効果-そのメカニズムが明らかに?
Kolb H, Kempf K, Martin S. Health Effects of Coffee: Mechanism Unraveled? Nutrients. 2020 Jun 20;12(6):1842.
[ハイパーリンク] DOI, PubMed(Full text), Google Scholar
✅前提知識
Nrf2
・活性酸素種などの酸化ストレスや、親電子性物質※4によって活性化する転写因子であり、様々な局面で細胞を保護することが知られている。
・Nrf2活性化の効果として、細胞保護効果に加えて、炎症抑制が知られている。
・・・引用サイト
✅ハイライト
-コーヒーの習慣的な摂取は、多くの慢性疾患や全死亡のリスクの低下と関連している。
-コーヒー成分による酸素ラジカル消去の健康効果への寄与は、明らかに小さい。
-コーヒーは植物性食品であり、先進国で消費される食事性フェノール類の大部分はコーヒーに由来する。
-コーヒーに含まれるフェノール成分は、野菜や果物に含まれるフェノール成分と同様の健康増進効果を示すことが示唆されている。
-コーヒーと同様に植物性食品のフェノール系ファイトケミカルの健康効果の主な経路は、Nrf2システムの活性化による適応的な細胞保護反応である。
-Nrf2依存性の遺伝子は、抗酸化、解毒、DNA修復、抗炎症の機能を持つタンパク質をコードしている。
[概要]
コーヒーの習慣的摂取と2型糖尿病、慢性肝疾患、ある種の癌などの疾病リスクの低下、あるいは全死亡率の低下との関連は、世界の多くの地域における前向きコホート研究で確認されているが、その分子メカニズムはまだ解明されていない。コーヒー成分のラジカル消去活性や抗炎症活性は、このような効果を説明するには弱すぎる。我々は、植物性食品としてのコーヒーが、多くの野菜や果物と同様の有益な特性を持っていることをここで主張する。すなわち、細胞保護に関与するタンパク質、特に抗酸化酵素、解毒酵素、修復酵素のアップレギュレーションによって特徴づけられる適応的な細胞反応の活性化である。この反応の鍵は、フェノール性植物化学物質によるNrf2(Nuclear factor erythroid 2-related factor-2)システムの活性化であり、これにより細胞防御遺伝子の発現が誘導されるのである。コーヒーは、先進国におけるフェノール酸やポリフェノールの主要な食事源であるため、その点では支配的な役割を担っている。補助的な作用として、コーヒーの非消化性プレバイオティクス成分による腸内細菌叢のモジュレーションが考えられるが、利用可能なデータはまだ乏しい。我々は、コーヒーが他の野菜や果物で想定されるような健康増進の経路を採用していると結論付けた。コーヒー豆は健康的な野菜食品であり、食事性フェノール性植物化学物質の主な供給源と見なすことができる。
▼ So What?:何が面白いと感じたか?
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
過去の研究では、コーヒーの”カフェイン”に焦点が当てられてきた。そのため、緑茶などのカフェインを含む飲料を含めた調査は多く存在する。
しかし著者は、コーヒーが媒介する健康効果のメカニズムには、カフェインの作用の主要な役割は含まれないと結論付けている(図1)。

そして、このレビューでは『コーヒーは健康的な野菜食品』というインパクトのあるメッセージを発信している。すなわち、”最近「健康な」野菜や果物について示唆されているのと同じ経路ー体内の細胞の健康増進適応反応の誘導ーを採用していると思われる。さらに、コーヒーの難消化性成分は、他の植物性食品で知られているように、微生物叢の組成と機能を調節する可能性がある。”と述べている。
少し具体的に述べると、
ブロッコリー、ビートルート、ベリー類、ザクロ、クルクマ、ココアなど、他の植物性食品について説明したのと同様の分子経路を、コーヒーが健康増進に用いていることを提案する。驚くべきことに、フェノール化合物の化学構造は大きく異なるにもかかわらず、食後に生体内で観察される濃度のフェノール性植物化学物質またはその代謝物にさらされたとき、細胞には一つの均一な反応があるように思われる。この細胞応答は、抗酸化、解毒または修復メカニズムに関与する多数の遺伝子の発現の増加によって特徴付けられ、これはin vivoでも観察される。
また、深煎りがお好きな方にgoodな情報をお伝えしよう。
まとめると、多くの試験により、コーヒーまたはその単離された成分のいくつかは、抗酸化酵素または細胞保護酵素の発現の強力な活性化剤であることが示されている。この点では、深煎りコーヒーの方が浅煎りコーヒーよりも強力であるように思われる。利用可能な証拠は、Nrf2経路の活性化(ある程度はアリール炭化水素受容体を介して)が主要な経路として関与していることを示すものである。
↑に関しても、過去の研究では浅煎りの方が健康効果が高いとされている論文が多く、驚くべき情報である。
▶臨床への示唆
コーヒーの摂取は運動面においても下記のような様々なメリットが認められている。
こうした情報に加えて、野菜嫌いなアスリートに対して(一つの情報として)、『コーヒーは健康的な野菜食品』だと伝え摂取を促すのもありかもしれない。
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
#理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #論文 #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #健康 #サイエンス #教育 #ARI #ミントライム
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
本マガジンを始めた経緯や活用方法はこちら
↓↓↓
医療従事者と研究活動における道徳感についても記事にしていますので良かったら読んで頂けると嬉しいです。
最後まで読んで頂きありがとうございます。今日も一歩ずつ、進んでいきましょう。
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥
少しでも参考になりましたら、サポートして頂ければ幸いです。
