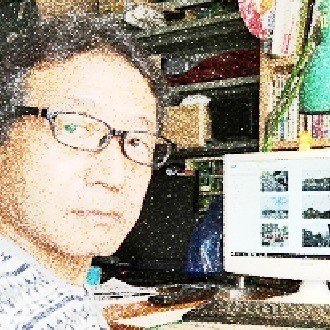#ボランティア
Zoomで自宅から地元小学校へオンライン授業サポート3回目 分かってきた利点と課題
この日は地元小学校4年生の「総合的な学習の時間」授業の3回目私の地元の小学校では3年前から「地域の自然」をテーマにした総合的な学習の授業を4年生に行っていて、住民有志で講師役と授業サポートをしています。今年は感染症予防のためにZoomオンライン授業で大人と子供達は互いに非接触にしましたが、私はこの偶然でしかも不幸な色合いの機会を活用してオンラインが有利になる授業の内容ややり方を研究しようと考えまし
もっとみるボランティアが疎まれる理由「対価ゼロ」でなぜサービスを提供する
ボラ活動が円満だった夫婦の暮らしを破滅させる可能性があるというのはすでに記事にしました。パートナーが空いた時間は家庭のことに使って欲しいという期待が強い場合にこういうリスクが起きやすいということで、我が家にもそのリスクが起き始めていることが分かったので、ボラ仕事はボリュームダウンしているところです。
もう一個、別の理由でボラ活動を広げて欲しくないという家族の意見があり、なるほどな!と思ったので書
総合学習授業支援ボランティアから眺めた先生像
このnoteで「小学校の先生は皆こうです!」などと書く気はまったくありません。だから今まで書かずにいましたが、先生という職業を経験したことが無い会社員経験者が、もし小学校の授業支援ボランティアをしよう!と立ち上がる際に、思い違いやミスリードを私がやった?ように経験してしまうかもしれないので、ここらでいっぺん書いてみようと思います。
小学校の先生だって、それぞれの先生方は十人十色の個性があり、学校
「自然に親しむ」授業とは、どういうことなのでしょう?
昨日は宇治市の小学校で里山体験する「総合的な学習の授業」がありました。ここの学校はもう10年以上に渡って生徒を先生が徒歩20分ぐらいかけて「里山」に連れて来て「自然を体験する」ことを学ばせてる授業をしています。
私は先生ではなくて、その宇治市の小学校の近くにある「里山」を手入れしているボランティアの一人で、この授業がある日にはその里山に出向いて子ども達の相手をするという役割です。そういうボラ