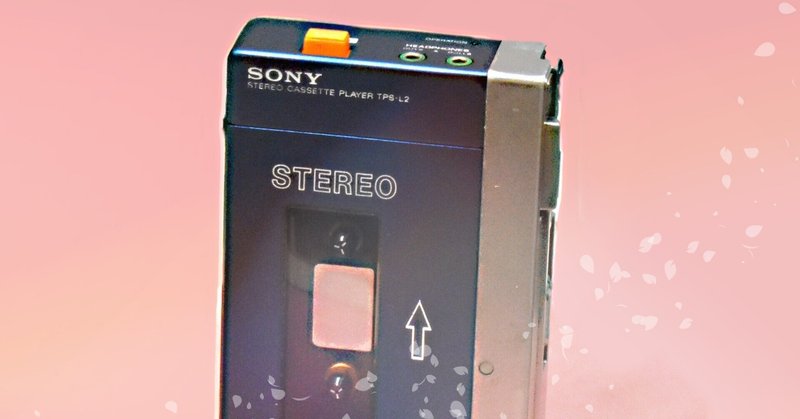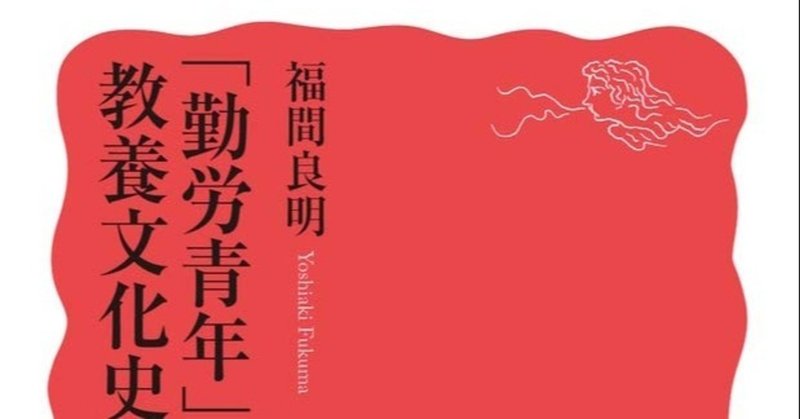最近の記事
マガジン
記事

【書評】渡邉大輔、相澤真一、森直人、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター編『総中流の始まり 団地と生活時間の戦後史』(青弓社、二〇一九)
渡邉大輔、相澤真一、森直人、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター編『総中流の始まり 団地と生活時間の戦後史』(青弓社、二〇一九)は一九六五年に神奈川県の六つの団地を対象として行われた統計「団地居住者生活実態調査」のデータを分析する一書です。一九七〇年代からしばしば言われるようになる「総中流」の生活様式が萌芽した時代において、団地という空間で人々がどのような時間を生きたのか、統計から風景を復元することによって推察してゆくというコンセプトになっています