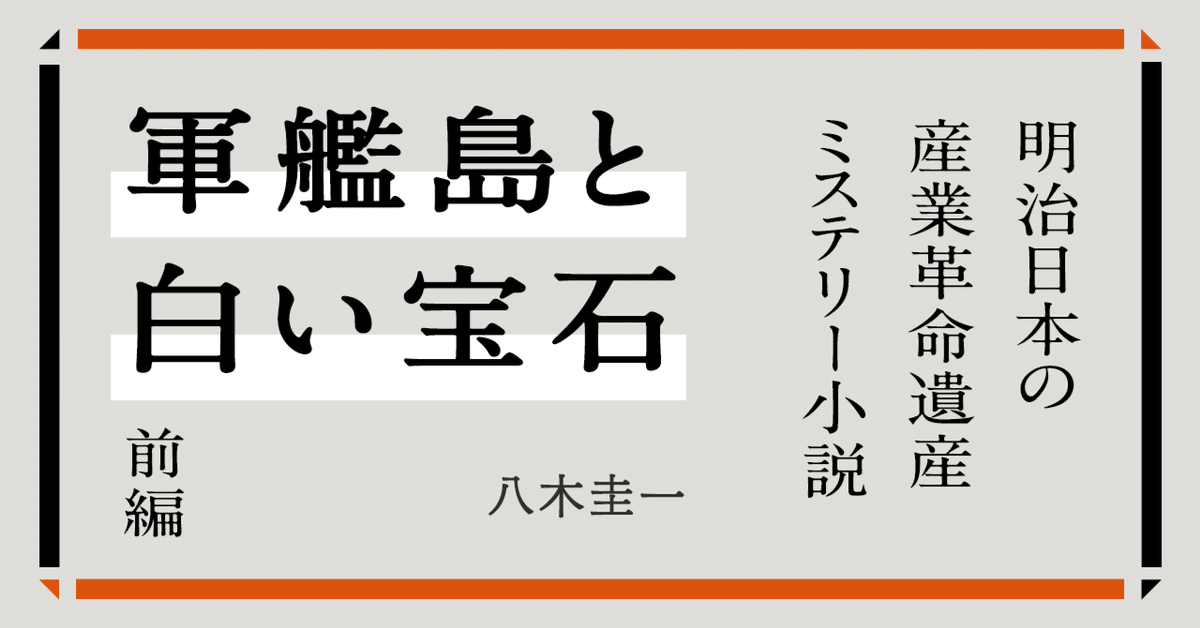
【世界遺産・短編小説】「軍艦島と白い宝石」前編
明治日本の産業革命遺産ミステリー小説
新人ミステリー作家の登竜門『このミステリーがすごい!』大賞受賞者をはじめとした新進気鋭のミステリー作家たちが、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の地を実際に訪れて短編のミステリー小説を書き下ろし。広域にまたがる構成資産を舞台とした物語をミステリー作家陣が紡いでいきます。
ものづくり大国となった日本の技術力の源となり、先人たちの驚異的なエネルギーを宿す世界遺産を舞台にした不思議な物語を通じて、この世界遺産の魅力をより多くの方に感じていただき、価値が後世に繋がっていくことを願っています。
「軍艦島と白い宝石」
八木 圭一
〈1〉

羽田空港を夕刻に発った飛行機は、2時間かけて大村湾に浮かぶ長崎空港に着陸した。松尾美咲は短い髪をかきあげるとターンテーブルから黒いスーツケースを受け取って、早歩きでバス乗り場に向かう。長崎駅までは約40分だ。駅には父親が車で迎えに来てくれることになっている。
到着口を抜けると、「美咲、こっちばい」と聞き覚えのある声が聞こえた。振り向くと父親の善朗が手を振って駆け寄ってくる。呆気に取られて立ち止まった。
「わざわざ空港まで迎えに来なくてもよかったのに。仕事は?」
善朗が「よかたい」と言って美咲の手からスーツケースを奪った。すぐに駐車場に向かって歩き出す。その背中を追う。「何年ぶりかね?」と投げかけてきて、「5年ぶりかな」と小声で返した。
「薄情な娘や」
「仕事忙しくて……」
美咲にも後ろめたい気持ちはあった。仕事が忙しいのは事実だが、年末年始など、帰ろうと思えばいつでも帰れた。だが、帰省しても母はもういない。兄や祖父母は福岡だ。30を過ぎても東京で独身は珍しくないが、地元に帰れば親戚からああだこうだ言われるのは目に見えていた。4年前、善朗に電話で恋人のことを打ち明けてからというもの、認めてもらえず、関係はギクシャクしたままだ。
「それにしても、母さんの故郷に行く理由が仕事とはな」
「お母さんが導いてくれたのかな……。なんだか、不思議な縁を感じる」
美咲の母親である恵美が“軍艦島″の通称で知られる端島で生まれたのは1968年のことだ。恵美の父親は炭鉱員だった。その後、1974年1月に炭鉱が閉山して4月には全島民が島を出た。恵美は幼少期を過ごしただけで記憶は僅かなはずだが、美咲にいろんな思い出話を語ってくれた。もちろん、祖父母はもっとだが。

その端島を舞台に、美咲が働く映像制作会社で、大手時計メーカーのCMを制作する企画が持ち上がったのは数ヶ月前のことだ。名だたる広告代理店の提案を押し退けて美咲の案が通った。プレゼンの場で母が元島民で、父が市役所で端島の管理に関わっていることを話すと、担当者が興奮して美咲と意気投合した。「松尾さんの企画でぜひ」と連絡が来たときは快哉を叫んだ。だが早速、善朗に電話で相談をして愕然とした。
「どんなCM?」
「腕時計のCMで、まだ出演交渉中だから詳しくは言えないけど、大物俳優が記憶を辿って軍艦島を歩くの。かつて島民だったという設定。止まっていた時が動き出すというコンセプトで――」
「そがん簡単に許可はおりんばい」
美咲はてっきり善朗が喜んで応じてくれると思っていただけに、あまりに冷たい一言に「何で!?」と罵倒しかけた。映画やミュージシャンの撮影に使われた話を何度も聞かされていたのだ。
「ちょっと、愛娘の一生のお願いだよ! 聞いてよ」
「男勝りな性格のくせに、こがん時だけ女の子ぶるけんねえ……。縁故だなんて言われかねんっさ」
だが、美咲は必死だった。大見得を切って「撮影許可は大丈夫です」と言ってしまったのだ。ここで断られたら面目が立たない。意地もあったので有休を取り、善朗を説得するため、プレゼン資料を揃えて一人で帰省することにしたのだ。前日になって、波の状況次第で端島に上陸させてくれるという。「脅かしただけ?」と詰め寄りたかった。
善朗とそんな微妙な距離感のまま空港の駐車場に辿り着く。停めてあったSUVの助手席に乗り込む。
「それでな。明日は森田さんに案内してもらうことにした。詳しい元島民がいた方が心強かろう」
森田正利は、善朗の市役所の先輩で、端島の元島民だ。恵美とも昔からの知り合いで、二人を引き合わせてくれた仲人だ。
「おじさん、元気? そろそろ定年?」
「もう定年。再雇用されて今、高島支所で働いとる。老後の趣味を探して、釣りにハマっとるらしいけど、いっちょん釣れんらしか」
高島は長崎港から南西に約14キロメートル、端島の手前にある離島だ。かつて、端島とともに炭鉱業で栄えた。
「おじさんも、もうそんな歳か……」
心優しい森田の笑顔が浮かんだ。クリスチャンだった恵美の一周忌にあたるミサで会って以来だ。
「そろそろ、美咲ちゃんも結婚やなかかって心配しとったけん、する気なからしかと言うといた。まだ、例の役者と付き合っとるとか?」
「うん、ずっと続いている。まだ、売れない役者だけど、直向きに頑張っているし、支えてあげたい」
美咲は語気を強めて答える。恵美には言えず仕舞いだったが、長年交際し、同棲している恋人のことを善朗には覚悟を持って伝えた。そこからだ。予想はしていたが、善朗との関係が微妙なものになってしまった。
「そうか……。またいつ帰るかわからんけんな。今回は、美咲に渡しとかんばいけんもんのある」
「なに?」と、美咲は善朗に聞き返した。
「家に帰ったら渡すけん……」
〈2〉

長崎新地中華街でちゃんぽんと餃子を食べてから、5年ぶりに帰ってきた自宅は、思っていたほど荒れていなかった。善朗が几帳面なので、しっかり一人で独身生活を営んでいるのだろう。
ただ、美咲が高校生までを過ごしていた時とは大きな変化が一つだけある。花がないのだ。特に、恵美は長崎市民に親しまれている紫陽花が好きだった。「雨の日でも気分が晴れるでしょ」と、口癖のように言っていた思い出が蘇る。
恵美が大切に育てていた花は、亡くなってすぐ親戚や友人に譲ってしまった。善朗の判断は正しかったと思う。
真っ先に祭壇に向かう。恵美の遺影を見つめて、手を合わせる。善朗は仏教徒だ。美咲も兄も、恵美によく教会に連れて行かれたが、仏教徒というかほぼ無宗教だ。恵美は何かを押し付けることもなく、人生の選択は自分でするよう育てられた。
恵美は昔から花が好きだったそうだが、緑が少ない端島で育ったことも関係しているのかもしれない。生け花の先生をしていて、「いつかあなたに教えてあげたい」と言っていたが、それも叶わぬまま、6年ほど前、この世を去った。大腸ガンで見つかった時はもう手遅れだった。東京から戻り、最後の数日はずっと寄り添えたし、看取ることもできたが、あまりにも早い別れだった。
リビングに戻ると、善朗が「飲むか」と言って麦焼酎の“軍艦島”を出してきた。善朗のお気に入りだ。飲むつもりはなかったが、ロックで一杯だけ付き合うことにした。今は、気分を損ねるわけにはいかない大事な交渉先なのだ。
お互い弱くはないので、乾杯であっという間に飲み干すと、今度は美咲がつぐ。
「あ、そういえば、さっき言っていたのは? 渡さなきゃいけないものって?」
「ああ、それな……」
善朗がリビングを離れて寝室に戻ると、何かを手にしてすぐに戻ってきた。きっと用意していたのだろう。
「母さんから預かっとったもんさ」
ジュエリーケースが差し出された。美咲は思わず首を傾げる。恵美が亡くなった際に指輪やバッグ、衣類などはすでに直接譲り受けた。なぜ、時間差があるのか。
「なんで、今なの? 新たに見つかった?」
「まあ、そがんところばい……」
善朗は言葉を濁した。ケースを開けると、ネックレスが2つ入っていて、ペンダントトップには薔薇の形をした白い珊瑚がついていた。
「これ、お母さんが大切にしていた五島珊瑚のイヤリング……」
五島珊瑚は、五島列島が誇る伝統工芸だ。薔薇をモチーフにしたアクセサリーを祖父が端島のお店で見つけて祖母に贈り、恵美が引き継いだことを聞かされていた。
「これ、おじいちゃんがおばあちゃんに贈ったものだよね」
善朗が「らしかね」と言って笑うと、グラスを煽った。
「でも、お母さん、なんでわざわざネックレスに仕立て直したのかな……」
ピアスならわかるが、ネックレスだ。しかも、2つ。美咲は昔からよく落とし物をする。だから、予備にと2つ作ったのだろうか。まだ子供扱いされているようで、そう考えると少し笑ってしまう。
「そりゃ、知らんけん、母さんに聞かんね」
語気がやけに強まった。美咲は直感的に、善朗が何かを隠しているのではないかと勘ぐった。昔から、嘘をつくのが下手なのだ。
「大切にせんばつまらんばい」
美咲がじっと善朗を見つめていると突然、大きな声を投げかけてきた。
「当たり前でしょ……」
善朗がお酒をついでくる。美咲は、グラスを押さえたまま、「ありがとう」と伝えた。
後編へ続く
写真提供:(一社)長崎県観光連盟
