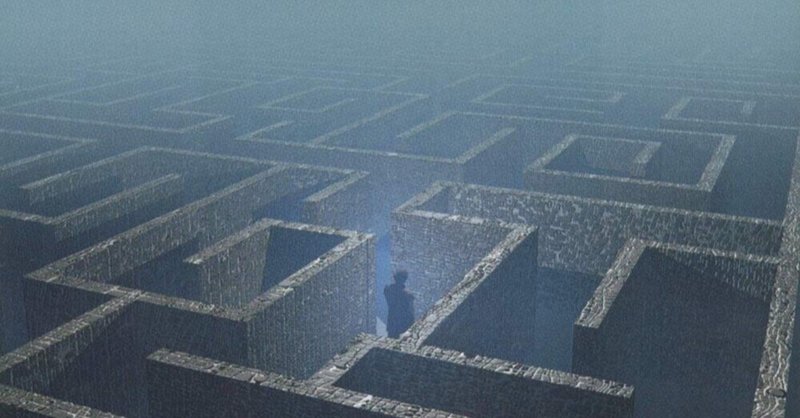
失われた〈リベラル〉像をもとめて
書評:吉田徹『アフター・リベラル 怒りと憎悪の政治』(講談社現代新書)
本書の内容については、先行レビュアー(mountainside、寸鉄、無気力)の三氏が書かれているとおりで、実用的にはかなり幅広い概念である「リベラル」というものを、その成り立ちと時代状況の変化に伴う覇権から劣勢までの立場上の歴史的変化を、じつにコンパクトに解説していて、とても見通しのよくなる快著である。
私自身は、政治思想について、なんら専門知識を持ち合わせていないから、ごく一般的なニュアンスで、自身を「リベラル」だと紹介していたが、その意味するところは「個人主義的自由主義者」くらいの意味でしかなく、自分がなぜ、「左翼」に好意的でありながら「左翼」そのものではないのかとか、「ネット右翼」は大嫌いだが「(戦前の)右翼」にはシンパシーを感じるとか、「保守」の穏健思想は理解できるが、その自己中的な守りの意識が好きではないなどといったことを、場当たり的かつ泥縄式に、自分なりに考えてきたのだが、それらをかなりスッキリと整理してもらえ、とてもありがたかった。
結局、私の「リベラル」も、あれこれの良いとこ取りにすぎないのは間違いないが、しかしまた、私の「気分」の根底にあるのは、「党派性を嫌う個人主義」と「〈弱きを助け〉という美意識」であり、そのあたりが、党派的政治思想としての「リベラル」を含むいずれにも、ぴったりと嵌らなかったのだと、そう了解された。
そんなわけで、実際のところ、自分を「リベラル」だとか「リベラル左翼」だなどとは呼びたくないのだが、さりとて他者と議論やケンカをする場合は、ある程度は自分の立ち位置をわかりやすく紹介しなければならないので、それもやむを得ないところだった。
「私は私だ」と主観的に言ってみても、それは自己満足であって、議論にはならず、「当事者」の位置に立てないからだし、無論こうしたこだわりは、当事者意識のない、お気楽な(傍観者的な)論評家という立場が、なにより嫌いだったからである。
つまり、自由を求める「個人主義」者ではあるけれども、だからと言って「自分さえ好き勝手やれれば良い」とも思わない。そんなことは、現実には不可能だというのはわかっているし、他者の不幸を見過ごしにできる人間は、幸せになどなれるはずがない、とも思う。
こうした観点からすれば、これまでの「リベラル」の弱点は、(著者も指摘するとおり)「自由のための自由」を求めて、「人の幸福の追求」という根本目的を見失っていたからではないだろうか。
「他者」に関わることは、面倒であり束縛ともなろうが、しかし、人は一人で生きているわけではない。
古い言葉で恐縮だが(また原義とは逆だと言う人もいようが)、やはり「情けは人のためならず」。他者の苦しみに配慮できない政治思想が、人の生きやすい社会を作ることなどあり得ないのである。
○ ○ ○
