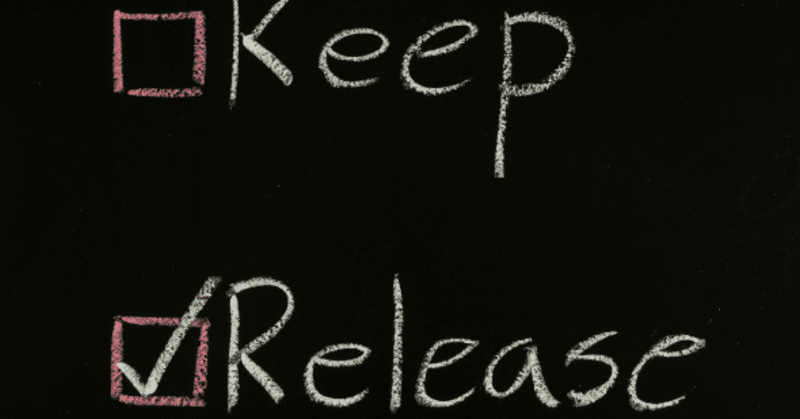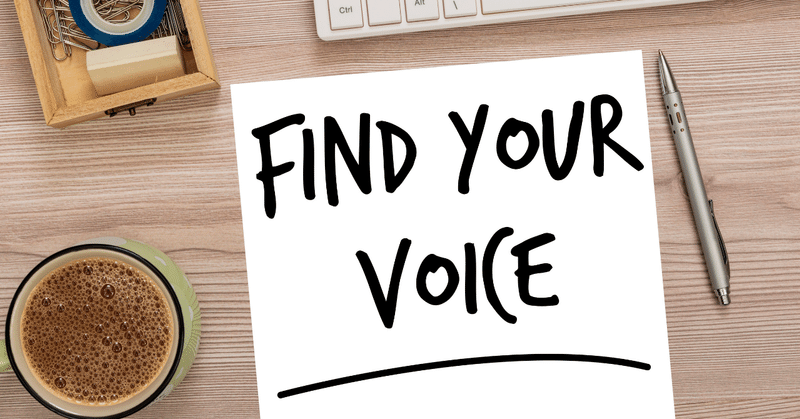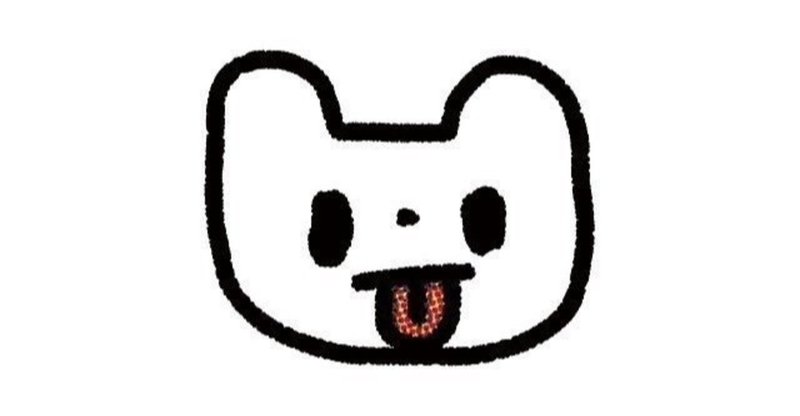#発声
横隔膜と多裂筋に尽きる
最初から少し厳しい言い方をしてしまうのですが…まず横隔膜のアプローチ無しには何も始まらないと思います。横隔膜が下がっていないと、音程は一瞬もはまりません。"その音のあたり"を歌っているようにしか聞こえません…上ずるか、上がりきれないか、押さえつけているかにしか聞こえません。横隔膜を下げる必要性の程度の差はありますが、どのジャンルも一緒だと感じています。
また息の長さに決定的な役割を果たすのも横隔
身体と声のウォーミングアップ
ウォーミング・アップを効率よく行うために約30分のプログラムを考えてみました。数多くある効果的なものの一例です。文章で説明するだけでは、なかなか正しく理解するのは難しいかもしれませんので、以下は参考程度にお読みください。4以降は歌の演奏時同様に骨盤底筋と身体の軸を意識しながら行います。
1.ひねり運動(3分):腰をひねり、両腕を左右に振る。振る両腕も上や下など角度を変えたり、頭の動きを伴ったり、変
歌う前のウォーミングアップの大切さ
これを読んでいる皆さんは、どのくらいの世代でしょうか?20歳前後の声楽の学生かもしれませんし、40歳以降の趣味で合唱をされている方かもしれません。年配の方でしたら、若い頃の方が何も考えずに楽に声が出せたのに今は出しづらくなったと感じている方も多いのではないでしょうか?
10代から25歳くらいまでの若い歌手の中には「歌う前にストレッチや発声練習をしてもしなくてもあまり変わりない」と感じている方が多