
おかしの行進曲と音楽ソムリエの珈琲店
「なあ達也、ばあちゃんの様子が最近おかしいんだ」
僕はテーブルの上のテレビのリモコンを取って、音量を小さくした。「ばあちゃん、どこか悪いの?」
父さんは、小さくため息をついた。
「毎日、電話を掛けてきて『心が痛い』って言うんだよ。先週、ようやく総合病院で心臓の検査をしたんだけど異常ありませんって言われてね」
「ふうん」
「心電図も血液検査も、CT検査までしたんだけど、どれも正常だったんだよ」
「正常って言うんなら安心なんじゃないの?」
僕は母さんが淹れてくれた珈琲をひと口飲んだ。父さんは広げていた新聞を折り畳んでテーブルに置くと真顔になった。
「ばあちゃんが受話器の向こうで泣くんだよ。『心が痛い』ってね」
『心が痛い』なんて言っても、『心』なんてどこにあるのさ? ばあちゃんにつっこみを入れたくなる。見かねた母さんが口を挟む。
「『心』を診てくれるお医者さんなんてないって言うのよ。心療内科を勧めてみたんだけどね。お義母さんは、『そうじゃない』って言うの」
母さんは困り果てた顔で僕を見た。
漢方も併用してあらゆる病気や症状を治す内科医がいるっていう噂を聞いたことがある。たしか・・・・・・「アカデメイア診療所」だったかな? でもそこは予約がいっぱいで、大抵の場合、受診は半年先になるらしいから黙っておいた。
昨日、大学から帰省したばかりの僕は、待ってましたとばかりに家族の相談窓口となった。翌日、隣町のばあちゃんを訪ねることにした。
翌朝、父ちゃんが仕事に出掛けるのと同じくらいの時間に出発することにした。玄関でビジネスバッグの中を覗いていた父ちゃんが、名刺入れから一枚のカードを取りだした。
「なぁ、達也。父ちゃんも調べてみたんだよ。ほら」
手渡された小さなカードには「音楽ソムリエの珈琲店」と記された喫茶店らしき案内が載っている。
「ばあちゃんって珈琲好きだったかな?」
「珈琲は昔から変わらず好きなはずだけど・・・・・・」
父ちゃんは口ごもった。その「音楽ソムリエの珈琲店」の噂は仕事のお得意さんから聞いたらしい。「詳しく言えないけど」と断りを付けておきながら、とにかくばあちゃんをその店に連れて行くよう頼まれた。
僕は愛車に乗り込むとその小さなカードに記された住所を携帯のグーグル先生に読み込ませ、見やすい場所に固定した。中古で買ったこの車には、カーナビが付いていないのに、今時珍しくMD再生が付いていた。唯一新しいものと言えば、僕の財布に収まっている運転免許証ぐらいだ。いつにも増して緊張した顔で証明写真に写っている自分を見るとなんだか気恥ずかしい。僕は注目を浴びるのが苦手で、写真に写るのも苦手。どちらかというと、目立ちたくない。自分から物事を始めることも苦手。でも、運転をするのは得意ではないけど嫌いではなかった。車内は個室だから安心できる。地下鉄に乗る時みたいに、誰かの視線を気遣わなくていい。僕はリュックの前ポケットからチューインガムを取り出した。眠気覚ましというだけでなく、集中するのにもいいらしい。自動車学校の先生が教えてくれた。エンジンの音は、今日も快調だ。
平成の車は、落ち着いた色合いが多かったのだろう。紺色具合を主張するメタリックさも、パール感もなくそこにある感じが好きだ。だが一番気に入った点は格安だったところ。僕のバイト代で賄うことができた。
カーラジオを聴きながら隣町への道を急いだ。音楽ラジオ番組から理生 -りお-さん作曲ベース協奏曲「むしば」という曲が流れてきた。ベースとドラムの組み合わせのインスト曲は、どことなく僕を不安にさせた。初心者マークの僕は、ただでさえ自分の運転が恐いというのに、その音楽は僕をさらに心細くした。後から、後からみんな僕の車を追い越して行く。僕は、平常心をどうにか保ちながら海岸線の道に軽自動車を走らせた。ハンドルを握りしめた手は、ぐっしょり汗で濡れていた。
隣町に入ると、すぐに目に入ってきたのは祭りの準備をしている人達だった。大きな看板には「祝 令和版百人一首恋の巻完成 花火大会」と書いてある。ばあちゃん家はアパートに駐車場がないから、その祭り会場の駐車場に車を停めて歩いて行くことにした。町の人達は忙しそうに準備をしている。バンドマン風の男の人達とすれ違った。みんなネコミミを付けていた。大きな黒い袋に入った荷物はキーボードだろうか?
「つるさん、今日の会場、どのくらい人入りますかね?」
「そうだなぁ。五十人は入るんじゃない? あかうまさんはどう思う?」
「そうですね・・・・・・八十人くらいかな」
人気バンドが出演するらしい。
露店もたくさん並んでいた。リンゴ飴に、ソフトクリームに、ポップコーン、それにマシュマロも売っている。浴衣を着た華やかな女性たちは、愉快そうに笑いながら、露店前に並べられた長いすに腰掛けていた。紺色の浴衣の女性が手にしたリンゴ飴が美味しそうだ。チョコソフトをおいしそうに頬張っている女性は、カラフルなソフトを頬張っている女性と、ソフトクリームの思い出話をお喋りしているようだった。ソフトクリームにはウェハースが添えられている。ドーナツを食べている女性は、淡いサイダー色の浴衣を着ていた。四人の浴衣姿が眩しくて、自分の顔が少し赤らんでいくのが分かった。僕は女性と話すのが苦手なのだ。
せっかくだから、ばあちゃんにおみやげになるようなものはないかな? いい臭いに誘われるように奥の方へと歩いて行った。気付いたら、炭火で竹に巻いた白い物を焼いている店の前に辿りついた。
「何を焼いてるんですか?」
竹串を火で炙っている女性が振り返った。
「これはねコルネって言うの」
「コルネ?」
すると、店の前で椅子に座った威勢のいい男性がこっちを向いた。
「そうだよ! 兄ちゃんこれはね、大きくなると快獣に変身するんだよ!」
「大石さん、面白いこと言っちゃって! 手作り炭焼きパンなのよ」
もう一人の女性が愉快そうに笑った。
そのコルネという巻きパンを買っておみやげにしたかった。だが、1メートルほどの細く割った竹ごと渡されるらしく持ち運びにくいのであきらめた。ふと横の店に目をやると、隣に和菓子を置いた露店があった。祭りの露店にしては珍しい。あんころ餅と、鬼あられにドロップス、それにナッツ入りチョコのヌガーまで売られていた。甘納豆はまるで金平糖のように透明なお洒落なパッケージで売られていた。僕は、そのお洒落なパッケージに惹かれて、甘納豆をばあちゃんへのみやげに選んだ。
「ケンちゃん、あたしにあんころ餅こうて」
「ええっ? さっきホットケーキ食べたばかりじゃない」
「別腹なん」
僕はお金を払いながら、旅行で来たらしい優しそうな男性と関西弁を操る女性のテンポ良い会話に耳を澄ませた。
「兄ちゃん、おまけに金平糖も一袋入れといたよ」
「あ、ありがとうございます」
突然、「兄ちゃん」と呼ばれてどぎまぎしながら答えた僕は、ばあちゃん家の方向に歩いた。
祭り会場中央に来ると、アナウンスブースが設置されていた。運営スタッフの拠点になっているようだ。パステルブルーのワンピースを着た女性と、人の良さそうな男性がマイクの前に座って打ち合わせをしているようだった。
「三羽烏会長さん、和歌を詠み上げる音量はこれくらいでいいかしら?」
「いやKeiさん、もっと上げよう。花火の音で掻き消されちまう」
女性は大きく頷いて、音量ツマミを上げている様子だった。
「私、ちょと練習してみるから聞いてて下さいな」
「ああ、いいとも」
どんな和歌を詠んでいるのか気になった。でも、ばあちゃん家に急いでいた僕の耳にそれは、喧噪の中に紛れて届かなかった。
祭り会場を出て商店街を歩いていると、前方に人だかりがあるのに気付いた。祭り会場で、東京からもアナウンサーが来ると案内を見た覚えがあった。確か、朝の情報番組に出演している二人だったと思うけど・・・・・・。黙々と歩いていた僕は、その人だかりとすれ違う時、速度をゆるめた。反対側から見ても誰がやって来たのか分かった。TBBアナウンサーのこんたさんと、ももまろさんだ。毎朝その番組を見ている僕は、嬉しくなって自然に歩くペースがが速まった。
ばあちゃんの住むアパートは、商店街を抜けた先にある。小さな古いアパートだ。僕が高校三年生になった頃までは、じいちゃんも生きていたから、一軒家に住んでいて、夏休みや冬休みの度に泊まりに行ったものだ。じいちゃんが亡くなってから程なく一軒家を引き払い、今の小さなアパートに住むようになった。アパートに住むようになってから、僕は数回しかばあちゃんを訪ねたことがないことに気付いた。
近づくにつれて、ばあちゃんにどんな風に「音楽ソムリエの珈琲店」のことを切り出したらいいか迷い始めた。僕の脈拍は少し上がっていた。「どうしよう?」「うまくばあちゃんを誘えなかったら?」任務の重さにようやく気付いた。額からは汗が噴き出している。真夏日の暑さだけが理由ではなかった。
そう言えば「歩きながら考え事をするといいアイデアが浮かぶ」って本で読んだことがある。背中のリュックに、僕はエアーポッズが入っていたことを思い出した。立ち止まって装着すると、最近聞き始めたクラシックを流した。ばあちゃんの住むアパートの屋根が見えて来た。
「もうすぐ昼になるから、昼食を食べる口実で誘ってみようか?」
僕は、アイデアが浮かんだことに安堵した。
一階奥の部屋の呼び鈴を鳴らした。ばあちゃんはなかなか出て来なかった。留守なのかな? 建物の反対側に回ると窓が開いていた。窓に近づいて中の様子を覗いてみると、ばあちゃんはリビングで死んだように眠っていた。
「ほんとに死んでいたらどうしよう?」
僕の脈拍は小刻みになり、全身に震えが走った。
「ばあちゃん・・・・・・」
ばあちゃんは気付かない。
「ばあちゃん」
もっと大きい声で呼んでみた。
「ばあちゃん!!」
三回目に呼んだ時に、ようやく気付いたようで頭を持ち上げてきょろきょろしている。こんな場所に僕がいるなんて思いもしないだろうから。
「ばあちゃん、達也だよ!」
ばあちゃんは、ようやく窓の方を見た。テーブルを掴んでゆっくり立ち上がると一歩ずつ近づいて来た。
「たっちゃんの声の幻が聞こえたんかな?」
淋しそうに呟いたばあちゃんは、視線の下の僕に気付いていなかった。
「ばあちゃん、幻じゃないってば」
ようやく気付いたばあちゃんは、びっくりしてその場に腰を抜かして座り込んだ。
「ばあちゃん、玄関のベルを鳴らしても気付かなかったから、裏に回ったんだよ」
「そうかね、そうかね。玄関、今、開けるから上がって行きなよ」
玄関にはばあちゃんの靴が一つ、ぽつんと置いてある。玄関から引き戸一枚で区切られた部屋は、ほとんど物がなく片付いていた。主なものはテーブルとテレビ、小さな本棚くらいだった。テーブルの上には食べかけの柿の種と、ポテトチップスの袋が置いてあった。仏壇代わりの小さな本棚の上でじいちゃんは小さく笑っていた。好物のカステラがお供えされている。
「たっちゃん、久しぶり。よう来てくれた」
僕は勧められるままに、テーブルの椅子に腰掛けた。ばあちゃんは、対面した場所に座った。きっとじいちゃんがいた頃、こんなふうに向かい合って座っていたに違いない。
「父ちゃんが、ばあちゃんのこと心配しとったよ」
「最近、『心が痛くて』起きられんようになった」
それでさっきばあちゃんは寝ていたんだ。
「『心が痛い』ってどういうこと?」
「この辺りがぎゅっと締め付けられるように痛むんよ」
ばあちゃんは、右胸の辺りをさすっている。たしか、心臓は左側にあったと思うんだけど。
「ばあちゃんは、なんで『心』のある場所、分かるの?」
「分かるよ。じいちゃんとの「思い出」を思い出そうとしても、思い出せへんようになった。そうするとぎゅっと締め付けられるんよ、この辺が」
ばあちゃんは、さっきと同じ場所をさすっていた。僕は『心が痛い』原因がちょっと分かってきたような気がした。
「思い出したいのは、どんなこと?」
ばあちゃんは、静かに目を閉じた。
「じいちゃんと見た、美しい景色を思い出したい」
目を閉じたまま言うばあちゃんは、まるで少女のような表情だった。
「美しい景色って例えばどんなの?」
「山頂から見た景色とか、山野草、見たいのぉ」
僕は、じいちゃんとばあちゃんが山登りが好きだったと初めて知った。
「ばあちゃんは、また山登りしてみたいの?」
「たっちゃん、そんなことはもう、できへん」
「そっか・・・・・。さすがに体力がいるものね」
「そうじゃない。たっちゃんは、ようわかっておらん」
そう言えば、ばあちゃんから「そうじゃない」って言われているって、母ちゃんから聞いてたな。
「一番思い出したいのはな・・・・・」
ばあちゃんは、何かを言いかけたまま黙ってしまった。僕はそれ以上聞くこともできなくて、待つこともできなくて話を反らした。
「ばあちゃん、昼飯を食べに行こうよ」
「たっちゃん、外食なんてもう、いつ以来になるかなあ」
心なしか、ばあちゃんはさっきよりも血色が良くなったような気がした。いそいそと外出の準備を始めた。奥の方から出してきた外出用バッグは埃にまみれていた。
「ばあちゃんは、食べ物はどうしてるん?」
「ネットで弁当の定期コースいうのに申し込んどる」
毎日決まった時間に弁当を届けてくれるわけだ。
「もう、ばあちゃんは料理なんか危なくてできんからねぇ」
調理済みの弁当は楽で安全だけれど、どこか味気ない気がした。
ばあちゃんちのアパートの裏にはバス停がある。そこから二駅ほどで「音楽ソムリエの珈琲店」の最寄りのバス停になる。車窓から見る風景は、昔、じいちゃんに連れて行ってもらった店が見えて懐かしかった。緋海書房で、ヤバ猫さんの絵本を買ってもらったなぁ。ちょうど、ましゃこさんの「推しごと展」で僕の好きなヒーローに会えて感激した記憶がある。あそこの四つ角の洋菓子店は、仲のいい夫婦が経営していて、たしか「続気楽な散歩。」という店名だった。手作りのシュークリームや、クッキー、バウムクーヘン、ショートケーキなどが並んでいた。バースデーケーキの予約も受付けていた。僕は食べれなかったけど、じいちゃんはよく、ボンボンというお酒入りのチョコレートや、マロン・グラッセというお菓子を食べていたっけ。
「たっちゃん、ほら、あそこの『散歩道』いうお店、覚えとる?」
「覚えとるよ」
「あそこでな、たっちゃんがどうしても『バケツプリン』が欲しい言うからある時、買うてみたんだけど、たっちゃん最初しか食べんくて」
「そうそう、ばあちゃん。あん時は、じいちゃんとばあちゃんで残ったプリンを全部たいらげてくれた」
「そうなんよ」
ばあちゃんは、今日一番の笑顔で笑った。
「あれから、もうプリンが見たくなくなるほど一時期嫌いになっとったわ」
「えっ! そうだったの?」
「そうなんよ、じいちゃんなんか、夜中に全部戻してしもうてね」
僕は、その当時知らなかった話を聞いて、『バケツプリン』をおねだりした日のことを久しぶりに思い出していた。あの頃のじいちゃんが、でっかく見えていたことも、ばあちゃんがよく僕の大好物の食べ物を料理してくれていたことも思い出した。それから少しずつ、会う度にじいちゃんがだんだん縮んで、次第に小さく見えるようになった。今なら分かる。じいちゃんは、縮んでなんかいなかった。僕が少しずつ大きくなっていたのだ。
目的のバス停留所に到着した。バスから降りると、そこには小さな森が広がっていた。そしてその森の入り口に、木造の小さなお店があった。近づいてみると「音楽ソムリエの珈琲店」という看板があった。
「ばあちゃん、ここが昼食の店だよ」
窓の木枠は美しい光沢を宿している。朱色っぽい明かりが、店内から漏れていた。
「上品な店だねえ。じいちゃんがいたら喜ぶだろうに」
ばあちゃんは、お店の看板を見上げた。
カラン、カラン
ドアを開けると、涼し気なベルの音が店内に響き渡った。
「いらっしゃいませ。音楽ソムリエの珈琲店へようこそお越しくださいました」
マスターらしき人に案内されて、カウンターにほど近いテーブル席に案内された。椅子はゆったりとした大きさで、クッション性も抜群だ。マスターは、ばあちゃんと対面の座席ではなく、隣同士に座ることを勧めてきた。
「私は、当店の音楽ソムリエのバンです。どうぞよろしくお願いします」
とても姿勢の良いマスターは、実際よりも身長が高く見える。白いワイシャツに、黒いギャルソンエプロンが膝下まで覆っていた。その黒いエプロンは光沢があり、品良く見えた。胸には音符のマークがついた名札が光っていている。「和田」と記されていた。
「バンさんというのは、下の御名前でしょうか?」
バンさんさんは、店の奥に掲げている肖像画の方を振り向いた。
「私が、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンを敬愛していることを周囲の者が知っていまして、お名前から文字っていつの間にか『バンさん』と呼ばれるようになった次第でございます」
なるほど、「音楽ソムリエ」というのはクラッシック音楽に精通しているということを意味しているんだな。
奥の方の席には、女性の三人連れと、僕と同じくらいの年だろうか、学生風の男性が一人それぞれの座席で過ごしている。みんな軽く会釈をしてくれた。
お水を運んできたスタッフさんがはにかんだ笑顔を浮かべる。
「ようこそ、私はスタッフのふみと申します。こちらの来店時アンケートに御回答をお願いします」
お水と、水色の用紙と虹色のペンをそれぞれの前に用意してくれた。水色の用紙には、今の気分などを聞く質問が並んでいた。自分の分を素早く回答した僕は、ばあちゃんの分を一問ずつ聞き取りながら回答した。その様子を穏やかな笑顔で見守っていたバンさんは、店内の音楽を切り替えた。そしてにっこり微笑んで、アンケート用紙を受け取った。
「今、店内に流れていますのは、バッハの「ブランデンブルク協奏曲」で先ほどのアンケートに基づいて流しております。当店は小さな演奏会も開いておりまして、生演奏を聞ける日もあるのですよ」
バンさんは、肖像画と反対側の店の奥に視線を促した。飾りだと思っていたそれは、美しい彫刻が施された本格仕様のチェンバロだった。その横には、猫足の木目調アップライトピアノがある。珍しさに店内を見回した。
「当店は先ほどの来店時アンケートに基づいて、お飲み物とランチメニューをこちらでセレクトしてお出ししております。少々お待ちくださいませ」
バンさんが穏やかに言い残して厨房に戻って行った。
先ほどの女性客がお喋りしている声が聞こえてきた。白いブラウスの女性は、同席した女性にチョコレートの箱を渡している。
「これ、旅行先で見つけたんですよ。ほんのり苦いチョコなんですよ。えんぴつさんお好きじゃないかしら?」
薄桃色のワンピースの女性は、嬉しそうに頬を染めた。
「Nねこさんは、どうしてそんなに活動的なんですか?」
「ほら、この手帖があるとね、自由自在に時間を使うことができるのよ」
もう一人の美しい黒髪の女性が思わず身を乗り出した。
「Nねこさん、好奇心旺盛ですね! 最近、MicrosoftCopilotでAIアートにはまっていまして、お二人共、良かったら試してみませんか? 今ここでちょっとプロンプトを作って生成してみますね・・・・・・」
「睦月さーん! さすが工学系女子」
二人の歓声をよそに黒髪の女性は、タブレットPCを操作していた。
とても楽しげな会話に思わず聞き耳を立てた。ばあちゃんは、店内の装飾品をぐるっと見て周り戻ってきた。
バンさんがトレーに陶器製の珈琲カップやミルクピッチャーを用意してこちらへ歩いてくる。ホテルのラウンジに居るような心持ちになる。僕とばあちゃんの前に、珈琲を置いた。
「どうぞお飲みください。それぞれの今に合った珈琲となっています。ところで当店には、常連さんを除きましては何か困りごとのあるお客様しか来店なさらないものでして・・・・・・。」
期せずして本題を迫られたので、言葉に詰まり黙ってしまった。目の前にある珈琲を一口飲んだ。フルーツ系の風味で酸味がはっきりしている。ほどよいコクのあるこの珈琲は僕に勇気を与えてくれた。ゆっくり深呼吸をした。
「あの、こちらにいる祖母が『心が痛い』と訴えるのですが、病院ではどこも悪いところが見つからないんですよ」
バンさんは、じっと耳を傾けている。僕は話を続けることにした。
「心電図も血液検査も、CT検査までしたんだけど、どれも正常だと言われて家族は今、何をしたらいいのか途方に暮れています」
頷きながら聞いていたバンさんは、テーブルの横に椅子を持ってきて座った。
「そうですか。それはお困りですね、おばあ様も御家族も」
「ねえ、バンさんと呼んでいいのかい?」
ばあちゃんが口を開いた。
「ええ、もちろんです。それでおばあ様はどんな時に特に『心が痛む』のでしょう?」
ばあちゃんは、不自然な瞬きをしながら話し始めた。
「夫に先立たれて一年三ヶ月。死んだじいさんのことばかり思い出して暮らしておった。ところが、最近はだんだんとじいさんのことが思い出せなくなってしまって・・・・・・」
「なるほど、御主人のことを思い出せなくなってしまったんですね」
「そうなんじゃよ。思い出そうとすると、『心が痛くなる』」
「そうなんですね。どの辺りが痛むのでしょう?」
バンさんは、優しい目で問い掛けた。
「この辺りなんじゃよ」
ばあちゃんは、アパートの時と同じように、胸の右側を手でさすった。
「実はですね、心臓というのは左側にあると思われているのですが、実際には、体のほぼ真ん中に位置しているんですよ」
バンさんは自分の胸の真ん中をさすりながら僕の顔を見た。
「心臓の左側は体中へ血液を送り出しているのですが、送り出す血管にはより高い圧力がかかるので左側だけどきどきしているように感じるのですよ」
僕は大きく納得して頷いた。
「そういう訳で、心臓は左側にあると思われているのです」
「なるほど!」という言葉が漏れてしまった。
「ところが、心が感じるというのは機能的な話ばかりではないんですよ」
そこまでバンさんが話をすると、奥から学生らしき男性を呼んだ。
「彼は『心』について研究をしていましてね、今は夏休み中ということでうちでバイト兼、研修のようなことをしているのです。彼から説明をさせて頂いてもよろしいでしょうか?」
突然の申し出に戸惑ったものの、僕と同じ大学生だと知って安心した。タブレットPCを抱えた彼は、笑顔でこちらにやってきて椅子を追加して腰掛けた。
「はじめまして。僕は『心』の研究をしている望辺と申します。どうぞよろしくお願いします」
会釈をした彼は、早速タブレットPCをテーブルの上に開いた。
「おばあ様の『心が痛い』は『心』について知ることで、きっと快方に向かうものと思われます」
望辺さんは資料を見せながら説明を始めた。そして動画も使って「心」について解き明かしていった。僕はその話に引き込まれていた。
「今の段階でしたら、おばあ様の大切な思い出や日常生活のささいなことを誰かに話す、聞いてもらうというのが一番の薬ではないかと思います」
望辺さんは穏やかな表情で説明を終えた。
「え! 話すことで治るんですか?」
僕は驚いて声を上げた。すると、一緒に説明を聞いていたバンさんが会話に入ってきた。
「そうなんです。実は心と体というものは密接につながっています。一日中誰にも会わずに、誰とも交流せずに過ごす日が増えれば増えるほど、心は元気を無くしてしまうものなのですよ。たとえ心臓が元気でも」
「たっちゃん・・・・・・。その通りなんじゃよ」
見ると、ばあちゃんは涙ぐんでいた。
「寂しいんじゃ。毎日、心が締め付けられる」
僕は小さくなったばあちゃんを抱きしめた。
「ごめんね・・・・・・」
「でもたっちゃんにはたっちゃんの人生があるけん。迷惑はかけられん」
BGMの音楽が歌謡曲に変わった。坂本九の「見上げてごらん夜の星を」だった。ばあちゃんはなぜだか一層激しく泣き出した。曲が終わるまでずっと涙が止まなかった。
「じいさんが最後に私に伝えてくれた言葉を思い出した」
ばあちゃんの表情は、今朝会った時と違って生き生きとして見えた。
そこにスタッフのふみさんが、ランチを持って来た。ランチ皿の上にはふわふわのオムライスとサラダが載っている。僕のランチ皿にはオムライスに加えて豆腐ハンバーグも載っていた。女性は珈琲のお代わりを淹れて厨房に戻って行った。
「どうぞお召し上がりください」
バンさんは僕たちにウインクをした。ふわふわのオムライスは舌の上でとろけていく。僕の心もふわふわの優しさで包まれたような感覚があった。ばあちゃんも、とてもいい表情でオムライスを食べている。
「おばあ様、御主人からの言葉を思い出すことができて良かったです。懐かしい曲や、思い出深い曲は様々な感覚に働き掛けて、記憶を司る海馬を刺激してくれるらしいのです」
「バンさん、音楽はまるでタイムマシンのようですね」
望辺さんも嬉しそうだった。携帯からその場で望辺さんにFacebookの友達リクエストをした。自分からこんなことをするのは、僕にとって珍しいことだった。
「あの・・・・・・」
白いブラウスの女性が話し掛けてきた。食事も会話も終わって店を出るところらしく鞄を肩に掛けていた。
「私、こういう者なのですが。このお店で定例会を開いておりますので、御都合が良い時によかったら御参加くださいね」
ばあちゃんに渡された名刺には連絡先と「note ホワイトな学校へ」と記されていた。
「ありがとうございます。バスで二駅なので自分で来られそうじゃ」
ばあちゃんは元気に答えていた。三人の女性客は「音楽ソムリエの珈琲店」を後にした。
「ねえ、たっちゃん、あのNねこ先生ね、若い頃の母ちゃんに似とる」
「え? どういうこと?」
「ばあちゃんの母親も学校の先生じゃった。なんだか母ちゃんが会いに来てくれたみたいで嬉しかった」
きっとばあちゃんは、これからNねこ先生の定例会に参加するに違いない。僕は安心した。
食事が終わり帰ろうとしたその時、テーブルに一人の女性がやって来た。ブラウンのカフェエプロンに、栗毛色の髪の毛、白い肌が印象的だ。
「私、この店のショコラティエのはるやと申します」
女性は、テーブルにチョコ・バーの見本表を置いて説明をしてくれた。
「このチョコ・バーの開発に三年の月日を要しました」
三年間かけてようやく7つの効能と理想の味を編み出したのだという。
「カカオ成分を増やし糖質を減らしています。その代わりに、ナッツやドライフルーツを加え苦味が気にならない味になっています」
「どうして太るのか」なんて気にせずに食べることができそうだ。僕は、その7つのチョコ・バーの中から、No.5のラベンダーとラズベリーというチョコ・バーを選んだ。はるやさんの説明によると、「ラベンダ-は心身のリラックスに、ラズベリーは眼精疲労に効く」のだという。ばあちゃんは、はるやさんに、どれが若返るか質問をして困らせていた。結局、No.6のオレンジ「ビタミンCで酸化防止」を選んだ。酸化防止をすればきっと何らかの効果はありそうだ。お土産のチョコ・バーは、魔笛のお菓子がプリントされたかわいらしい紙袋に入れられた。このチョコ・バーのお土産もお代に含まれているのだという。
「バンさん、望辺さん、ありがとうございます」
「とてもいい店じゃった。じいさんと一緒に来たかったねえ」
支払いを済ませた僕たちは、名残惜しみながら別れを告げた。
「また、気軽にお越しくださいね」
「はい。また来ます」
僕は露店でもらった「金平糖」を、お礼代わりに渡した。バンさんは微笑みながら受け取ってくれた。望辺さんは、僕の通う大学と同じ市内に通っていると分かり、また会う約束をした。
帰りのバスに揺られながら、ばあちゃんに思い切って提案してみた。
「今日、うちに泊まりにおいでよ」
ばあちゃんの目は少し光って見えた。僕は渡しそびれていた「甘納豆」をそっと渡した。 (了)
最後までお読み下さりありがとうございます。

コメント欄へどうぞ
感想もお気軽にどうぞ(^^)
【「ゆる募 お菓子の物語」に参加された皆様】
この度は御多用の中、記事をお寄せ頂きありがとうございます。それぞれの「お菓子の物語」に込められた「思い出」や「感情」に思いを馳せながら読ませて頂きました。また、交流させて頂き感謝しています。皆様の益々の御活躍を願っています。今後もどうぞよろしくお願い致します。
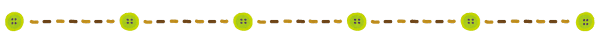
こちらに詰めてあります(^^)/
22名で48個の「お菓子の物語」が
集まりました💗
友情出演
「ゆる募」に関わらずお話に出演して頂いた方
日頃の交流ありがとうございます。記事を御紹介させて下さい。

