
遥宮 「伊雑宮」の創建 元伊勢一三六 神話は今も生きていることの葉綴り四六七
新月のデトックスウォーター
こんにちは。真夏日が続いておりますが、お元気でしょうか?
遠出はできませんが、今朝、電車に乗り郊外の神社にお参りして、ご神水も頂戴してきました。
ありがたい! そのご神水で、今夜の新月の金環日食の「デトックスウォーター」をつくろうと思います(^^)。
さて、今日も、神話の物語に入ります。

<ことの葉綴り>ご案内
神さまも“失敗して成長した”と、“神話は今も生きている”を感じる魅力的な神様の物語と、二千年前、伊勢の神宮ができるまでの物語「神話の物語」(『古事記』『元伊勢』の物語)。そして「エッセイ」と、マガジンを分けてあります。
下記のトップページから、スクロールしていただくと、物語別、神様べつに「マガジン」が選べるようになっております。
神さまの名前や、ご興味あるものを読んでいただけると幸いです。

天照大御神御霊をお祀りする「伊雑宮」の創建
嶋の国伊雑の方上に在り。
其の処に、伊佐波登美神(いさはとみのかみ)、宮造奉り、皇太神(すめおほみかみ)の摂(ふさ)の宮と為す。
伊雑宮(いさはのみや)、此也。
倭姫命さまは、志摩国の伊雑(いさわ)の方上の、千の穂を茂らせる稲が茂るところを、「千田(ちだ)」と名付けられました。
倭姫命さまが、天照大御神さまに奉るお供えものを採るところをお定めになるために、志摩国へとご巡幸された後、
この伊雑(いさわ)の地元の神の伊佐波登美神(いさわとみのかみ)さまは、この地に、天照大御神さまをお祀りする神社をお造りされて、五十鈴の宮とご縁の深い摂宮(せつぐう)とされました。「伊雑宮(いさわのみや)」といいます。
三重県志摩市磯部町にご鎮座する「伊雑宮」(いざわのみや)さまの起源となります。皇大神宮(こうたいじんぐう、内宮)の「別宮」である「伊雑宮(いざわのみや)」さまは、いぞうぐうとも呼ばれます。

真名鶴は、五穀豊穣の大歳神さまに
彼の鶴の真鳥を号(なづ)けて大歳神(おほとしのかみ)と称(まを)し、同じ処に祝ひ宛て奉る也。
又、其の神は、皇太神(すめおほみかみ)の坐(ま)します朝熊の河の後之(しりへの)葦原中に、石にして坐(ま)します。
彼の神を、小朝熊(こあさくま)の山の嶺に社造て、祝い宛て奉り、坐(ま)さ令(し)む。大歳神(おほとしのかみ)と称(まを)す、是(こ)れ也。
そして、あの鶴の真鳥(まどり)を、五穀豊穣の大歳神(おほとしのかみ)と名前をつけて、伊雑宮(いさわのみや)の近くに場所を割り当ててお祀りされました。また、大歳神(おほとしのかみ)は、皇太神(すめおほみかみ)さまのいらっしゃる朝熊の川の後方の葦原の中に、「石」としていらっしゃるともいわれています。
小朝熊山の頂にお宮をつくり、そこにも大歳神さまをお祝い申し上げ、ご鎮座なさいました。
この真名鶴を大歳神としてお祀りしているのは、「佐美長(さみなが)神社」さまです。
「伊雑宮」さまから約800㍍。真名鶴を、五穀豊穣の「大歳神」と称えたことから、「大歳社」。また真名鶴が稲穂を加えて飛んできて、その穂を落としたことから「穂落社(ほおとしのやしろ)」と呼ばれています。
また「伊雑宮」創建に尽力された、伊佐波登美命(いざわのとみのみこと)と、その子孫をお祀りしているとも伝えられています。
また朝熊山は、標高555㍍。山頂の展望台には「足湯」があり、伊勢湾の島々や鳥羽市街を眺めることができるそうです。
足湯しながら、志摩半島を一望って、いいですね~!!
近くには、伊勢の神宮の鬼門を守る「朝熊山金剛證寺」もあります。
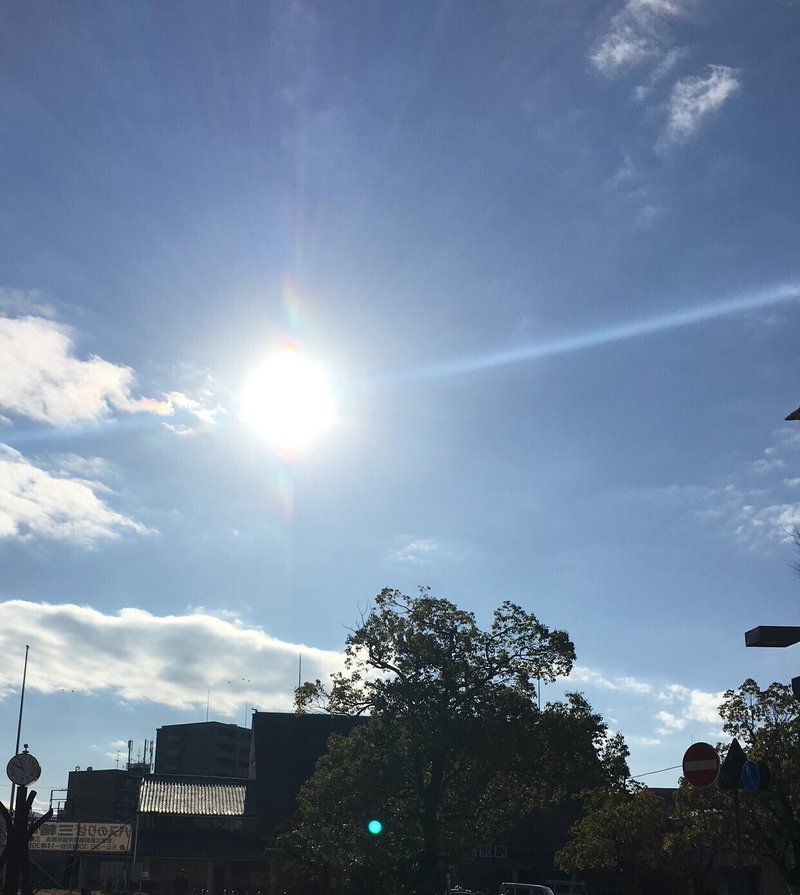
遥宮(とおのみや)の伊雑宮さま
今回ご紹介した「伊雑宮」は、古より、「遥宮(とおのみや)」として、崇敬されており、志摩の地元の方々により、伊勢の美し海の幸、山の幸の豊穣をお祈りされてきています。
また六月二十四日の「御田植神事」も有名です。
次回、「伊雑宮」さまのことをもう少し!
いつも、ありがとうございます。
新月&金環日食の夜、ゆっくりお過ごしくださいね。

―次回へ
#一度は行きたいあの場所
#私の作品紹介
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
