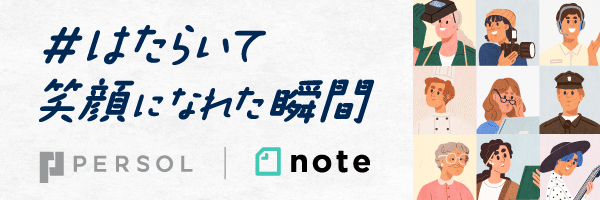「あなたが店員さんでよかったわ。ありがとう。」
大学時代にアルバイトをしていた場所は、なんというか、魑魅魍魎が集まるものすごい所だった。
そこは、ラウンドワンのようにビリヤードやダーツ、卓球、カラオケなんかができるのに加え、かなり古いものではあったがアーケードゲームなんかも設置されていて、ネット席と呼ばれるインターネットができるブースもあれば漫画も置いてあるという、いわゆる複合型アミューズメント施設というような場所だった。
そこで起こった出来事や、来店した摩訶不思議なお客さんの話はこれまでにも何度かここに書き記したことがある。
そのコンテンツの多さもさることながら、私が働いていた時間が深夜帯だったこともあり、夜な夜なそこに集まる人達はとにかく多種多様で、夜通しゲームをして画面の中のアイドルを一生懸命育てていたり、パソコンで検索したと思われるいかがわしい画像を大量にプリントアウトしたり、酔っぱらいの若者集団が散り散りになってダーツやビリヤードに興じながら始発を待っていたり、1ヶ月間立てこもるかのようにブースを借り続けて悪臭を放つような人がいたりと、まぁどれだけオブラートに包んで表現しても、とてもじゃないが心が華やぐような素敵な職場ではなかった。
話のネタは尽きなかったが。
歩行者用の信号機なんて国道沿いの横断歩道にたった1つしかないような片田舎から上京してきた私にとっては「な、なんじゃここは...」「都会...コワイ」「トーキョーの人は、みんな寝ないの...?」なんて思いながらも、初めて目の当たりにした今までの世界とはまるで違う都会の施設に驚き、いや、だからこそ耐性がなかったし物珍しかったのか「私、こんなすごいところ(?)で働いちゃってるぜ...」なんて謎の思いでそのアルバイトに励んでいた。
深夜勤務で時給がよかったことと、自分の日常では巡り合わないであろう人たちを眺めるのが新鮮だったのも、その当時の私にとっては魅力だったのかもしれない。
そんな、とてもじゃないがほっこりするようなエピソードなんて生まれないと思われたアルバイト先だったが、私はそこで働いている時に一度、ちょっと素敵な体験をしたことがある。
それはある夏の日。
夏休み中で大学の授業がなかったこともあり、どうしても昼のシフトが足りないと言われて仕方なく初めて昼の時間帯にシフトインした時のことだった。
夏休み期間だったため、高校生や大学生などの遊びたい盛りの若者でごった返す店内。
深夜のお客さんとはまた違った客層と混み方に「なかなか昼間も忙しいんだなぁ」なんて思いながら仕事をする私。
もう一人同じ時間帯に入っていたフリーターの村木さんは、この忙しさに「ったく。学生は家でおとなしく勉強でもしてろよ!」なんて悪態を付きながらも仕事にあたる。
村木さんは何もない平日でほとんど客も来ず、いい感じにサボれることが魅力で昼のシフトに入っていると公言していたため、夏休み期間の混み具合にうんざりしているようだった。
もともとぶっきらぼうなところもあり接客態度はあまりいいとは言えなかったが、やるべきことはテキパキとこなす割と仕事ができるタイプの彼。
私が店内を巡回していると、そんな彼からインカムが入った。
「すいません、受付カウンターの対応入ってもらえますか?」
また大人数の学生などがご来店して受付がてんやわんやになってしまったのだろうか。
私は「はい!」と返事をして急いで受付に駆けつけた。
カウンターには数名のお客さんがいたものの、そこまで大変なことにはなっていない。
どうしたのだろうかとカウンターに入ると村木さんは言った。
「ごめん、そこのばあちゃんの対応してくれる?俺、ああいうの無理だわ。こっちさばいとくんで、お願いします。」
そこのばあちゃん...?
そう言われて受付の端っこを見ると、私よりも背が低いのではないだろうかという小さなおばあちゃんが会員カードの申し込み用紙をしげしげと眺めている。
「えっ。村木さん、この人は1人で来たお客さんですか...?」
私は村木さんに小声で話しかける。
上品なお化粧をして、手編みのようなハンドバッグを持った、正直この店には似つかわしくないような高齢のご婦人が、眼鏡をちょっと上にあげたりしながら申し込み用紙と睨めっこをしていた。
「そう。さっき1人で入ってきて、入店するって言うんだけど、システムの説明とかしても全然わかってなさそうだからさ。あと、よろしく。」
そう言って村木さんは逃げるように違うお客さんの対応に向かってしまった。
そんなことを言ってはなんだが、なぜ、こんなところにおばあちゃんが...?
どう見てもダーツの名手にも見えないし、アイドルを育てるゲームなんて見たこともなさそうである。
彼女は何を目的にここに来たのだろうか。
「あの〜、これでいいのかしら?」
一通り申し込み用紙を書き終えたおばあちゃんが私に言う。
びっくりしながらも用紙を受け取る私。
「ありがとうございます。確認いたします。身分証はお持ちでしょうか?」
あらあらはいはい、というような感じでおばあちゃんはゆっくり編み編みのバッグからお財布を取り出し「これでいいかしら?」と住基カードのようなものを見せてくれた。
色々な疑問はありながらも、お客さんなのであればといつも通りの作業をする。身分証といっても、年齢確認のような簡単なものなので、氏名と生年月日が書かれていればなんでもよかったため、私はそのカードを受け取った。
というか、明らかに未成年でないことは明白だったので、もはやいらないと言えばいらないのではあるが、そこは一応ルールに乗っ取り、名前、生年月日など申し込み用紙との整合をとっていく私。
そして私は申し込み用紙に書かれた生年月日を見て、目が点になった。
え...。は、89歳...!
私はおばあちゃんを見ながら目を丸くした。
おばあちゃん、89歳なの...?
私がその店で遭遇した最年長の新規会員である。
いや、今までのこの店の歴史の中でも、もしかしたら最年長かもしれない。
とはいえ、未成年には利用時間の制限などがあるものの、年齢の上限というのは聞いたことがない。
びっくりしながらも失礼なリアクションをしてはいけないなと思って、私は粛々と内容を確認し「ありがとうございます」と身分証を返した。
登録を済ませ、会員カードを発行する。
先程の話だと店のシステムは説明したものの、あまりわかってなさそうとのことだった。
何をどこまで説明したのかわからなかったため、私はおばあちゃんに聞く。
「こちら、会員カードになります。場所を移動する際はこちらの受付へこのカードをお持ちください。えーと、まず最初に、何をご利用なさいますか?」
「ごめんなさいね、さっきあちらのお兄さんにもお伺いしたんだけど、ちょっとよくわからなくて。ここでは何ができるのかしら?」
お、おぉ...そこからか。
どうやらおばあちゃんは目的なくここに入ってきたらしい。なぜ...。
そう思いながらも、ひとしきり説明をする私。
「ここはパソコンでインターネットができる席があったり、マッサージチェアの席で漫画やそちらにある雑誌なども読めます。
ゲームもご自由にご利用いただけます。ただ、番号がついている決まった席のところとか、卓球とかカラオケとか、場所の予約が必要なものはあらかじめこちらで席を取っていただくという形になります。」
勝手にダーツ、ビリヤードなどはやらないかなと思った私は、おばあちゃんが興味を示しそうなものを簡単に説明する。
「あら〜そうなのねぇ。ここにあるもの、予約をすれば時間の料金だけで全て利用できるってことかしら?」
案外理解が早いななんて失礼なことを思いながら「はい、そうです」と答える私。
「どこかの席には絶対入らないといけないの?」
「いえ、ブースをご利用しないということであれば、フリー席という形でお取りして、ゲームをしたり、あの辺にある椅子とかに自由に座って本を読んだりはできますけど...今日は結構お客さんが多いので、騒がしいようでしたら足が伸ばせるフラットの、えーと平らなマットが敷いてあるような個室の席の方が落ち着くかもしれないですね。
パソコン、触らなくてもそこでお休みするとか、本を読むだけでも入れますよ?」
「へぇ〜そうなのねぇ〜。すご〜い。」
おばあちゃんは私の説明がわかったのかわかっていないのかよくわからない口調で店内マップを見つめながらそう答えた。
「じゃあ、そのフリーっていうのを1つ、ください。」
「は、はい。フリー席ですね。パソコンの席が埋まっちゃったりすると後から入れませんけど大丈夫ですか?」
「えぇ、大丈夫。色々見て歩きたいの。」
おばあちゃんはそんなことを言って、フリー席のしかも3時間パックで入店した。
入店処理が終わり、魑魅魍魎たちがいるアミューズメント施設に89歳のおばあちゃんがキョロキョロと周りを見渡しながら進んでいく。
だ、大丈夫だろうか...。
入店したのを見計らっておばあちゃんから逃げ出した村木さんが私に話しかけてきた。
「あのばあちゃん、大丈夫でした?よくシステムわかってなかったでしょ?っていうかここがどういう場所かもわかってないんじゃない?」
「まぁ...最初はそんな感じでしたけど、説明したらちゃんとわかってるっぽかったですよ。フリー席3 時間パックで入店されました。」
「えー!フリー席!?しかも3時間パック?マジで何しに来たの?」
「さぁ...。まぁ、ダーツとかはやらなそうだったので危なくはないだろうし、いいんじゃないですかね?…っていうか、おばあちゃん、身分証提示してもらったんですけど、89歳でした。」
「マジで...?えーほんとに大丈夫かなぁ?ちょっと、なんかあったら、日野さんよろしくね。俺は無理だよ無理。」
村木さんが一体何を懸念しているかはわからなかったが、めんどくさいことは極力やりたくないのが彼の性格のため、悪気があって言っている訳ではないんだろうなと私は村木さんの話を聞き流した。
そうは言ってもおばあちゃんの動向が気になってしまった私は、早速店内巡回のふりをして後を追う。
おばあちゃん、一体何しに来たのだろうか。
おばあちゃんは施設内をぐるっと見て回っていた。
「へぇ〜すごいわねぇ〜」という言葉が今にも聞こえてきそうなキラキラした目で高校生や大学生が遊んでいる姿をふむふむと眺めていく。
他の利用客も、明らかに異色を放っている野生のおばあちゃんを見て「え、あれ、誰かの付き添いのおばあちゃん?なんでいるの?」みたいな顔をしている。
高校生たちの動揺の顔も面白いが、おばあちゃんも面白い。
この人、本当にここの施設はどんなところなんだろうと思って入店して、色々眺めて楽しみに来たんだ。私はそう思った。
なぜおばあちゃんがここに1人で足を踏み入れることになったかはわからなかったが、私はおばあちゃんが3時間、楽しみきれるといいなと思いながらホールの仕事をこなした。
おばあちゃんは入店処理をして顔見知りになったと思ったのか、店内を動き回る私を見かけるたびに「このゲームはどうやって遊ぶのかしら?」と聞いてきたり、漫画の棚はどこにあるのかなんて聞かれたりした。
この店に入店した人は、大体自分でそれなりにそれっぽい場所を見つけて勝手に過ごすため、事細かに説明をしていなかった私は、その都度おばあちゃんの質問に答え「すいません、さっき言い忘れてたんですけど、上の階にドリンクバーがあるのでそれも自由に使ってくださいね。あの、ファミレスにあるような飲み物を自由に取りにいけるところがあります」なんて教える。
おばあちゃんは「まぁ〜そうなの〜?ご親切にありがとう。」と言って、いそいそと上の階に向かった。
なんだか私は、今までここで働いてきた中で一番接客らしい接客をしているな、なんて思った。
おそらく初めて見るであろう色々な新しい世界を、おばあちゃんは心底楽しんでいるように見える。
こうして3時間きっかり楽しみきったであろうおばあちゃんは、入店時に案内した時間通りにカウンターへ戻ってきた。
「お会計でよろしいですか?」
「えぇ。とっても楽しかった。ありがとう。」
おばあちゃんはにっこりと笑う。
「いえ、こちらこそ、最初にあまり説明ができていなくてすいませんでした。ドリンクバー、見つかりましたか?」
「コーラと、紅茶をいただいたわ。あと、漫画も読んだし、あっちにあった麻雀のゲームもやりました。」
おばあちゃんはニコニコと答えた。
す、すごい。おばあちゃんは私が何も説明しなかった古ぼけたアーケードゲームコーナーの中から麻雀ゲームを見つけ出し、プレイしたと言う。
あれ...確か脱衣麻雀のゲームだったと思うのだが、大丈夫だっただろうか...。
私が趣味で置いたわけでも私が脱衣したわけでもないが、なんだか気まずい。
「そ、そうなんですね...!楽しんでもらえてよかったです。こちら、お会計になります」
そう言って私は伝票を渡した。
おばあちゃんはお金を払い、そして私にこう言った。
「初めてお邪魔してみたけど、とっても面白かった。あなたが店員さんでいてくれてよかったわ。どうもお世話様でした。ありがとう。」
ちょっとはベンチなどに座ってゆっくり本でも眺めたりしたかもしれないが、おそらく3 時間フリー席で色々なところを見て歩いたおばあちゃんは、くたびれた様子もなくしゃんとした姿勢でぺコリとお辞儀をし、お会計を済ませて、退店していった。
またしてもおばあちゃんから逃げていた村木さんがいつの間にかひょっこり現れ、帰って行くおばあちゃんの後ろ姿を眺めながら言う。
「いやぁ...すごい客が来たな。」
「あはは。ですね。でもそれなりに楽しんでましたよ。多分。」
「あっそう。すごいね、ばあちゃん」
私はその日の夜、家に帰ってから今日来店したおばあちゃんのことを思い返していた。
私はあの歳になってから、見たこともない知らない世界に1人で飛び込んで、あんな風にキラキラした目で楽しめるだろうか。
できないかもしれない。
今まで生きてきた安心の、勝手知ったる空間でゆっくり余生を送ってしまう気がする。
そして、何より思ったことがあった。
私はこのお店であんなにもお客さんにお礼を言われたのは初めてだった。
それが当たり前なのかもしれないが、こういうアミューズメント施設のようなところで、どれだけギャハハとはしゃいで笑って楽しく過ごしても、店員に対して「楽しかったです」と言ってくれたり、退店する際に「ありがとうございました」なんて声を聞くことなんて滅多にない。
ありがとうございましたを言うのはいつもこちら側だけだ。
私は、おばあちゃんが言ってくれた「あなたが店員さんでよかった」「楽しかった」「ありがとう」という言葉を反芻していた。
すごく嬉しかった。そんな言葉を聞かないのが日常だった私のアルバイト生活で、おそらく初めて聞いた「ありがとう」。
私はそこで働いていて初めて、嬉しいなぁ、よかったなぁ。と思ったのだった。
おばあちゃんはとっても笑顔だったし、笑顔で「ありがとう」と言ってくれて、きっと私もおばあちゃんが退店する時いい笑顔で見送っていたと思う。
私も何歳になっても、臆せず自分の興味のままに色々なことを楽しめるような、かっこいいおばあちゃんになりたい。そう思った。
ここから先は
この記事が受賞したコンテスト
サポート、嬉しいです。小躍りして喜びます^^ いただいたサポートで銭湯と周辺にある居酒屋さんに行って、素敵なお店を紹介する記事を書きます。♨🍺♨