
美術史第65章『アンダルスとマグレブの美術』

8世紀中頃、シーア派やペルシア人の反乱によりウマイヤ家が根絶やしにされアッバース朝の時代にれ繁栄したというのは先述の通りだが、ウマイヤ家で唯一カリフの孫だったアブド・アッラフマーンだけが母親の出身地だったマグレブ(北西アフリカ)の先住民ベルベル系民族の元に逃げ延びる事に成功していた。

彼はベルベル系民族を引き連れてウマイヤ朝の領土となっていたイベリア半島地域を征服し、当時その中心地だったコルドバを首都とする「後ウマイヤ朝」を樹立、その後、9世紀後期には勢力拡大や経済発展を達成したアブド・アッラフマーン3世がアッバース朝のカリフと同じカリフの称号を名乗り始め、それ以降、アッバース朝と後ウマイヤ朝の二つのカリフが存在する事態が続いた。

後ウマイヤ朝ではキリスト教徒とイスラム教徒、アラブ人、ベルベル人、ラテン人、ユダヤ人などが共存し、哲学や科学を学べる大学が数多く創設されイブン・ルシュドという世界史上でもかなり重要な哲学者なども輩出されている。

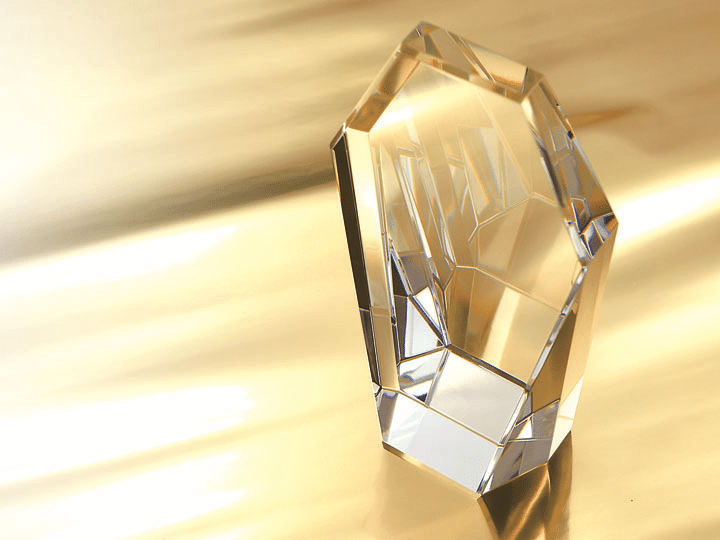
さらに、首都コルドバはバグダードから招かれたズィルヤーブという人物の活躍などで洗練された文化の都となり、イスラム文明でバグダードに次ぐ2番目の人口を誇るまでに成長、クリスタル・ガラスの製法はコルドバで誕生したとされる。



後ウマイヤ朝で作られた著名な建築物として「メスキータ」と一般的に呼ばれるスペインで唯一現存する大モスク建築があり、他にも後ウマイヤ朝のカリフの宮廷として使われた「ザフラー宮殿」などがある。


その後の11世紀初頭に後ウマイヤ朝が瓦解しタイファと呼ばれる小国家が乱立するようになると、西アフリカの大国ガーナ王国を併合したマグレブのベルベル系イスラム王朝「ムラービト朝」がイベリア南部を征服、12世紀初頭にはキリスト教徒のアラゴンとカスティーリャ、そしてイスラム教改革を掲げムラービト朝に反乱した「ムワッヒド朝」によりムラービト朝が崩壊、ムワッヒド朝はイベリア南部を侵略しマグレブ全域にまで拡大し大繁栄した。

このムワッヒドとムラービトの美術については余り知られていないが、装飾の全くない壁のモスクなどからわかるようにシンプルさを重点とする様式だったと言える。

13世紀中頃にムワッヒド朝が滅亡した後にはマグレブの領土はマリーン朝モロッコ、ハフス朝チュニジア、ザイヤーン朝アルジェリアに分裂、マリーンとハフスは多くの建築や彩色・彫刻・象嵌を施した木工品を生み出した。

マワッヒド朝の領土だったイベリア南部は再びイスラム小国家乱立の時代を迎え、これらをキリスト教国家のカスティーリャ、アラゴン、ポルトガルが次々征服、いわゆるレコンキスタが行われていき、イスラム勢力はイベリアから消えていった。

しかしカスティーリャの内戦やアラゴンとカスティーリャの対立により唯一、グラナダを首都とするイスラム国家ナスル朝グラナダ王国のみがイベリアの南海岸地域に残り、このナスル朝で作られた重要な建造物として世界で最も著名な建築物の一つでもあるグラナダの「アルハンブラ宮殿」がある。

これは宮殿と言いつつグラナダのスルタンが暮らした住宅、官庁、軍隊、厩舎、モスク、学校、ハンマーム、墓地、庭園が内部に存在する要塞都市で、材料はレンガ、木材、粘土などの脆いもので彫刻が少なく、中心部は中庭(パティオ)に置かれるなど典型的なイスラム建築になっている。

カスティーリャやアラゴン、ポルトガルの支配下に置かれた後のイベリア南部でもイスラム教徒達は税を払ってそのまま居住を続けており、イスラム建築様式は壁面に幾何学模様を施すことが特徴とされる「ムデハル様式」として受け継がれ続け、キリスト教の宮廷、聖堂、邸宅に使われ、世界遺産の「アラゴンのムデハル様式の建築物」などが作られた。

イスラム勢力の支配下のイベリアの工芸ではマグレブから入手された象牙を用いた象牙細工が発展、「ムギーラの小箱」など精緻な箱や宝石箱がカリフなどの富裕層に向けて作られ、イスラム美術全体で殆ど見られない彫刻の分野に関しても丸彫り彫刻が繁栄、金属製のものは動物や人物の形をした水差し(アクアマニレ)や噴水の吐水口、石製のものは例えば噴水を支えるライオンなどのような比較的大きい彫刻に用いられた。


また、織物、特に絹もヨーロッパ諸国に多く輸出し、焼き物ではラスター彩を用いた化粧板やる壺の制作に用いられ、北アフリカのムラービト朝やムワッヒド朝の支配下では彫刻と彩色を施した木工器も作られムワッヒド朝により首都マラケシュに建てられた「クトゥビーヤ・モスク」のミンバル(説教台)はその中でも有名な作品となっている。


また、黒人系で初めてのイスラム教国家で、北西アフリカ南部から西アフリカ北部にかけてを支配した「マリ帝国」という大帝国では、学問が大きく栄えヨーロッパで「黄金郷」と呼ばれるほど繁栄した首都のトンブクトゥに建てられた「ジンガリベル・モスク」などのような「スーダーン様式」と呼ばれる巨大で壁面から突き出た多くの梁を持ち、日干し煉瓦や日干し漆喰で作られているという特徴のある建築様式が繁栄した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
