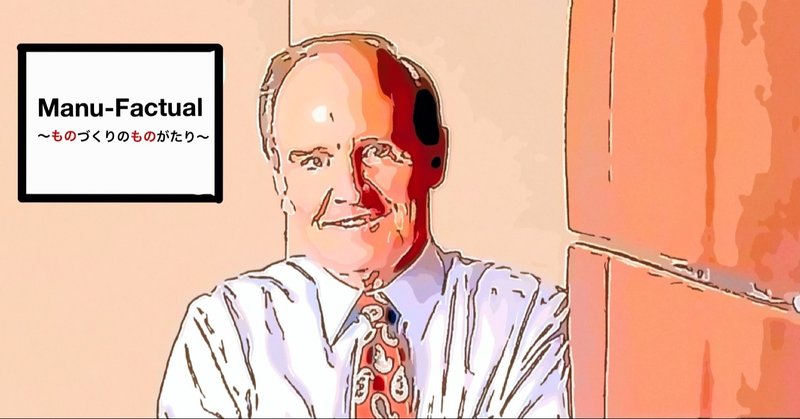
【ビジョナリーカンパニー編14:生え抜きの経営者】
前回までの投稿を上記に入れています。
ある日、入社20年になる健は工場長の哲也に呼ばれ工場長室に行く。健はここ数年、全社が注目する新規事業の計画・プロセス立ち上げをこの工場で行ってきた。立ち上げが終わり、そのまま課長をするよう内示を受ける。それと同時に工場長からビジョナリーカンパニーについての解説・指導を受けます。1章でビジョナリーカンパニーの定義、2章で時計を作ることの大事さ、第3章で時計のための理念の重要性、AND思考重要性、そして、第4章でその理念をどう維持、進歩させていくか解説してきました。第二部として具体例を5、6、7章と解説してきましたが、今回は、第8章「生え抜きの経営者」を解説します。
・・・・・・
◆生え抜きの経営者
🧒;おはようございます。
👨🦳;おはよう。今日は、第8章は、生え抜きの経営者が必要って話を解説していくよ。
🧒;経営っていうと今流行りのプロ経営者とか浮かびますが、だめってことですか?が、だめってことですか?
👨🦳;だめってことはないのだが。でも、それはビジョナリーカンパニーの中では、外部からの落下傘的経営者はほぼいなかったということだ。君はGEのジャックウェルチは知っているよな?
🧒;はい、知っています。だいぶ構造改革をしていますから外部から来たようなイメージがあります。
👨🦳;いや、それが彼は生え抜きなんだ。
🧒;この流れからはそうかと思いましたが、やはり意外ですね。
👨🦳;1981年、ジャック・ウェルチがゼGEのCEOになって、その10年後には、生きる伝説の経営者になっていた。様々な改革を行っていったんだ。
🧒;変わらなかったものを変える、まさに外部から登用されて、しがらみなく経営改革を行ったと思ってしまいます。
👨🦳;そう、でもそれはウェルチの経歴、GEの歴史を知らないからだ。実際、ウェルチは今でいう新卒でGEに入社している。そこから、CEOに就任したのは、入社して二十年たってからであった。そしてGEのCEOは皆GEで育った人材なのだ。
🧒;え、40代半ばでCEO、、それはそれでとんでもないですね。そして、GEのCEOはすべて生え抜きなのか。
👨🦳;ただ、注目すべきは、ウェルチ以外の経営者もエクセレントなんだ。GEが悪い会社だったわけではない、ウェルチの前CEOのレジナルド・ジョーンズは、引退したとき、「もっとも尊敬されているアメリカの経営者」とされていた。GEの歴代のCEOのなかで、企業変革をもたらし、経営の革新をもたらしたのは、ウェルチだけじゃない。過去のCEOジェラルド・スウォープが経営していた1922年から39年の間、GEは家電事業に劇的な進出を果たしているということもある。
🧒;なるほど。要するにウェルチは、突然変異のように現れたわけでなく、GEの伝統のなかから生まれた人物ということなのですね。非常にレベルの高いばらつきの中でさらに高い位置にいたのがウェルチであると。
👨🦳;そう。ウェルチのような特出した経営者がいるのは、すばらしいことだ。そしてさらにすばらしいのは、長きにわたって、ウェルチのような経営者が輩出し、その全員が生え抜きだってことだ。これは、GEがビジョナリー・カンパニーだと言える主な理由のひとつであるといっていんだ。
🧒;素晴らしい経営者が生え抜きで、かつ継続して輩出されているということですか?
👨🦳;行ってしまえばそうであるが、その過程が本質なんだ。ウェルチがCEOに選ばれた過程が本に書かれている。ここにこそ、GEの伝統の最高の部分が発揮されている。ウェルチは確かにGEの将来を変えたが、同時に、GEの伝統を受け継いだ経営者でもあるんだ。GEのコンサルタントを長く務めるノエル・ティシーとフォーチュン誌の編集者、ストラトフォード・ シャーマンの共著、『ジャック・ウェルチのGE革命』には、こう書かれている(*)。
歴史のあるゼネラル・エレクトリックの経営がウェルチにゆだねられるまでの後継者選任の過程は、同社の古くからの企業文化のなかでも、最良で最重要な部分を示すものである。〔前任者のレジナルド・】ジョーンズは多数の候補者のなかからひとりを選び出すために、何年も費やした。最後に、最高の人材を選ぶにあたっては、論理的な判断だけに頼ることにした。
🧒;何年もって、すごいですね。具体的にどのように選抜したのでしょうか。
👨🦳;ジョーンズは「CEO引き継ぎの道筋」という文書をつくったという。これは、ウェルチがCEOになる七年前のことだ。そして、96人からウェルチらの6人まで絞り込んだ。この6人をテストし、見極めるために、全員を「事業部門責任者」にし、経営委員会の直属にしたんだ。それから三年間、ジョーンズは徐々に的を絞っていき、候補者に厳しい課題を与え、面接しエッセー・コンテストを行い評価していったんだ。
🧒;そこまで考えているというと、外部から登用なんて全く話がでてこないですよね。GEは経営幹部の育成と後継計画に力を入れる伝統になっているのですね。
◆社内の人材を登用し、基本理念を維持する
👨🦳;わかっていると思うけど、どんな人物でもビジョナリー・カンパニーを経営できるわけではない。ビジョナリーカンパニーの経営者は基本理念を維持しながら、改革を行い発展していく、これが大事なんだよな。
🧒;理念を維持し進歩させる経営者が必要ですね。
👨🦳;ああ。ビジョナリー・カンパニーは比較対象企業よりはるかに、どうやって社内の人材を育成し、昇進させ、経営者としての資質を持った人材を育成していくか、見つけいていくかに注力している。後継者の育成が基本理念を維持するための大きな軸とも言っている。
なお、ビジョナリー・カンパニーの延べ千七百年の歴史のなかで、社外の人材が最高経営責任者になった例は四回しかなかったという。
🧒;なるほど、要するに、経営者はもちろん非常に重要。でもさらに重要なことは、優秀な経営陣の継続性が保たれていることなのですね。それによって基本理念が維持されていくのですね。つまり、前回までの、BHAGや大量のものを試すという環境であったり、強いリーダーシップでのカルトのような文化の継続などですね。そして、経営者の育成が重要ということになりますね。
👨🦳;そう。育成し、候補を作り、選抜し理念を継続できる経営陣を継続的に排出する、経営者の継続性が断たれてしまうと、外部からCEO招かざるせざるを得なくなる。こうなれば基本理念から離れざるを得ない。コントロールできるわけがない。
🧒;「経営者の継続性をもたらす好循環」がビジョナリーカンパニーにはあるということですね。
👨🦳;比較対象企業には、これの対照的なパターンが共通してみられ、著者たちは、これを「経営者の断絶と救世主の悪循環」と呼んでいる。
ただ、例外もある。ディズニーは外部から経営者を招いたことがある、だが、基本理念にぴったり合った候補者を探してきた。そういう人物なら、経営のスタイルは違っていても、基本的な価値観を心から信じる。これができれば引き続きサイクルを回すことができるのだ。とは言え、当時ディズニーはとんでもない苦境に陥った。
🧒;しかし、ここで言いたいことは、社外から経営者をトップ企業になることも、その座を守ることも、きわめて難しいということですよね。そして、生え抜きを昇進させるから変化しないということも言えないということですね。
👨🦳;そうだな。私もそうだが、大手企業の経営者や取締役にとっては、非常に重要な示唆なんだよな。うちの会社にもあるが、経営幹部育成のための制度を設け、長期的な後継計画をつくって、次世代を育てなければならない。著者は下記のように結論づけている。
外から、経営のトップをもってきて、変化に対してリーダーシップを持たせるというのは落とし穴で、この罠にひっかからないようにすべきだ。社外から迎えた経営者が、基本理念をなし崩しにしたり、くつがえしたりすることになりかねない。カギになるのは、健全な変化と前進をもたらしながら、基本理念を維持するきわめて有能な生え抜きの人材を育成し、昇進させることなのだ。
とね。
🧒;これは、私のような中間管理職にとっても重要なことですね。自分の課、新規事業においても、育成とその計画を最優先で考えるべきなのですね。明日自分がけがをしたらどうなるのか、だれが自分の代わりをやるのか。その後任のために何を準備し、努力しているのかを明確にしなければならないです。
👨🦳;そうだな。私も明日ケガした君に引き継げるようにしておかなければならない。(今回の教育もその一環だが)。
🧒;もし、この会社が自分にぴったり合っているビジョナリー・カンパニーであれば、転職するよりも、その企業のなかで自分の能力を伸ばすことを考えてみるべきですね。
👨🦳;そうだな。ビジョナリーカンパニーであればの話だがな。おっと、天に唾を吐くようん発言だな。ところで、この考え方は、中小企業にだって言える。中小企業でも、経営幹部を育成し、後継計画を立てることはできる。すべてのビジョナリーカンパニーは最初は小さかったそれでも飛躍してトップ企業になったからな。つまり、すべての組織に対して言えてしまうんだ。
🧒;ですね。ビジョナリー・カンパニーを築く、時計を作っているということであれば、問題は、いまの世代、自分の世代で会社をとらえてはいけないですね。次の世代、その次、そしてさらに次でどうなるかですね。いかに行動と姿勢で理念を維持、進歩を積み上げていけるか、その仕組みが作れるかですね。結局、またここに戻ってきました。
👨🦳;そう。偉大な指導者もいずれ寿命がくるからな。しかし、ビジョナリー・カンパニーは何世紀にもわたって発展を続けている。この事実が各々の経営者に勇気を与えると思うよ。さて、これで8章は終わりだ。残り後2章。あと少し、頑張っていこう。
・・・・・・
今回は、第8章の生え抜きの経営陣について解説しました。いつもより短いものになりましたがエッセンスは入っているかと思います。次回は、9章の“決して満足しない”について解説します。いよいよ終わりが見えてきました。スキ、フォローお願いいたします。
また、下記にこれまで作成した別マガジンを記載します。ぜひ覗いてみてください。
#製造
#理論と実践
#ものづくり
#成長
#5S
#トヨタ生産方式
#ジャストインタイム
#自働化
#リーンプロダクション
#ザゴール
#制約理論
#ドラッガー
#ビジョナリーカンパニー
#アドラー
#コーチング
#情報リテラシー
#要件定義
#会計
#損益計算書
#決算書
#損益分岐点
#原価低減
#平準化
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
