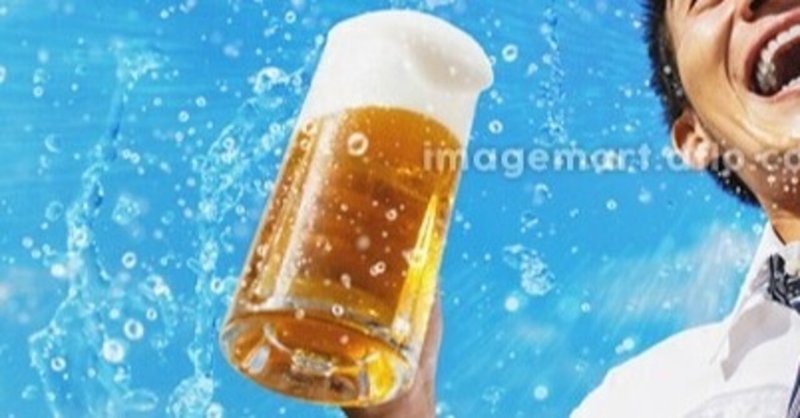2021年8月の記事一覧
ホットドッグ 中の具材はカレー味
ホットドッグ、長らく食べてませんがパンの中に挟む具材は、当然のことながら主役はウィンナーソーセージであります。そして、副素材としてキャベツの千切りを炒めたもの、それもカレー味のを挟むのが普通だと思ってました。
ところが、広く一般的には違うらしいのです。世界の標準は、副素材はピクルスであったり玉ねぎのみじん切りを炒めたものとのこと。そして、この日本の中でもどうやらこのカレー味キャベツを挟んでいるの
酒飲みにとっては朗報?!
厚生労働省の研究班が発表したところによりますと、適度の飲酒はリンパ系の腫瘍の発生リスクを低減させる作用があるとのこと。
万歳~!
でも、適度といっても…
やっぱり日本酒にして、一日一合ほどらしいですね。
そんなん、適度すぎる~!(笑)
↓
http://www.stellamate-clinic.org/blog/2013/07/2010521-563046.html
飲食店不況の打開策は、低価格ではない
今の疫病が流行る前のお話です。飲食業界にも不況の波は押し寄せてますが、その対応策として価格を下げるというのはすでに限界に達してます。業界では、消費者はもはや安さだけを求めているのではなく、付加価値のある商品に惹かれるのだというのが定説になってきているようです。
その付加価値というのが何であるかを巡って、各店舗・業界とも試行錯誤しているのが今の状況でしょう。
その中で、実際に成功している事例があり
調理は脳の活性化に寄与
脳科学者の茂木健一郎氏が、料理を作ることは脳の活性化に大変よいことだとして、自身が調理してその効果?を披露してました。その料理も、既存のありふれたものよりも、あっと驚く発想の新機軸的な料理を考え作ることが、より前頭葉の刺激に結がり活性化が促進されるというのです。
もっとも氏は本職の調理人ではないので、その料理の腕前はというとはっきりいってお世辞にも上手とは言えないなものでした… 。しかし、脳科学