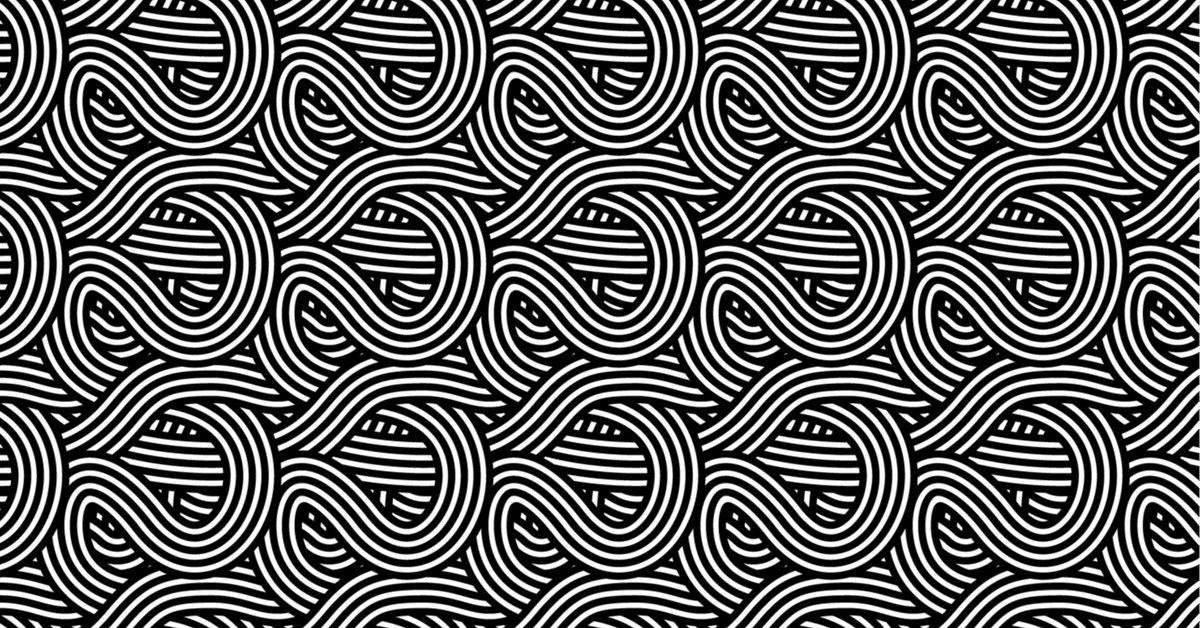
生活そのものがインプットですよ
2023年9月17日(日)朝の6:00になりました。
間違えるのはかまわない。だけどキチンとやりなさい。
どうも、高倉大希です。
おなじものを食べたはずなのに、おなじ映画を観たはずなのに。
おなじ経験をしたはずなのに、得る情報量がまったくちがう。
その人から出てくる言葉が、明らかに自分のものとは異なっている。
そんな人と会うたびに、いつもちゃんと驚かされます。
その人は、食べて考えるわけでも、観て考えるわけでもありません。
きっと、つね日頃から考えているのです。
そこから吉本さんのご自宅をしばしば訪ね、いわば門前の小僧のように話を聞きに行くようになりました。仰ぎ見るような「師」ではなく、「近所にいる、宝物のような普通のおじさん」として、話を聞いていたんです。
ビジネス書のブームと共に、インプットという言葉が随分と流行しました。
効率的なインプットがどうだとか、アウトプットとの最適な比率がどうだとか。
インプットのために本を読もう、インプットのためにセミナーに参加しよう。
インプットという言葉のせいで、それ以外がインプットではなくなりました。
ほんとうは、生活そのものがインプットであったはずなのに。
手に届くところに、いくらでも発見があったはずなのに。
『子ども』の発明とは、大人と子どもの間に線が引かれたことを意味する。同じような分割線は『仕事』と『遊び』の間や『公』と『私』の間にも引かれていった。そしてこの区別こそが人間の生活を貧しくしたのだ。
言葉は、世界を狭めます。
世界の一部を小さく囲って、「それ」と「それ以外」に分断します。
決して、分断がわるいわけではありません。
人間が認識するには、この世界はあまりにも大きすぎます。
人間が認識できるサイズに小さく囲って、どうにかこうにか整理します。
そのおかげで、わたしたちはこうしてコミュニケーションをとれています。
相対性には絶えずわたしたちの足元をすくう要素がひとつある。わたしたちはものごとをなんでも比べたがるが、それだけでなく、比べやすいものだけを一生懸命に比べて、比べにくいものは無視する傾向がある。
あとは、その分断を忘れてしまわないように気をつけなければなりません。
自分たちで囲っておきながら、ついついはじめから囲われていたかのように思い込んでしまいがちです。
生活すべてがインプットであったはずなのに。
本を読むことや話を聞くことだけが、インプットだと思い込んでしまうあの現象とおなじです。
自分の思考が、どんな枠に囲われて、なにに影響を受けているのか。
出てくる言葉がちがうあの人は、きっとここに敏感なのだろうなと思います。
毎朝6時に更新します。読みましょう。 https://t.co/rAu7K1rUO8
— 高倉大希|インク (@firesign_ink) January 1, 2023
サポートしたあなたには幸せが訪れます。
