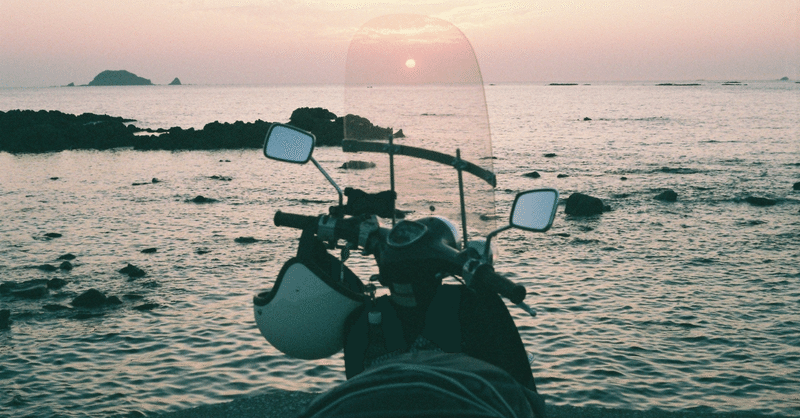
【実体験】僕の曾祖父は罪人だったのかもしれない~先祖を探す高校生のひとり旅~
高校二年生、健全な男子であれば必死になって女の子を追いかけているころ、僕は必死になって「墓石」を追い求めていた。
十七歳、僕はちょっとだけおかしかった。
それを自覚したうえで一応言い訳をしておくが、もちろん僕が追い求めていたのは、そんじょそこらの墓石ではない。それは、僕にとってとびっきり価値のある墓石。僕に血を繋げてくれた先祖たちの墓石に他ならない。
僕は当時、自身のルーツを辿る行為に夢中になっていた。理由なんて分からない。いまから思えば、僕は大学受験という人生の分岐点を目前に、なにか自分という存在を補強する、説得的な理由を求めていただけなのかもしれない。先祖を知れば自分が生まれた理由が分かる。それが心地よかったのかもしれない。とまれ、二〇一一年夏、僕は大した理由もなく先祖調査を始めた。そして、父親に懇願して五万円の旅費を捻出させると、ひとり水俣市に向かったのだ。
熊本県の南端、鹿児島県との県境に位置する水俣市は、僕の曾祖父の出身地だ。僕の曾祖父である梁本喜太郎(仮名)は明治の半ばに水俣で生まれ、大分県で会社勤めを始めるまでの十数年間を、彼の地で過ごした。

昭和10年ごろ撮影か。このころの暮らしは豊かだったと聞いている。
水俣市と聞いて、ほとんどの人は「水俣病」を想起するだろう。それは水俣に与えられた負の勲章だ。実際、水俣行きのバスに揺られる僕の脳裏には、いつか社会科の授業で見せられた、水俣病患者の少女の姿が浮かび上がっていた。小刻みに痙攣する細い身体、空きっぱなしの口、長く糸を引いて母親の腕に滴る唾液。白黒の映像は、僕の頭のなかでカラーに転換され、脚色を繰り返しながら何度も上映された。
僕と妄想の少女を乗せ、バスは水俣の市街地に入っていく。
町はもの静かでありながら、往時の繁栄の残り香を十分に携えていた。かつて、この地は近郷に類を見ない一大企業城下町だったのだ。
水俣発展の歴史は、「電気化学工業の父」と呼ばれた実業家、野口遵がこの地にカーバイド工場を設立したことに始まる。このカーバイド工場は、水俣病を引き起こした「チッソ」の前身だった。水俣に出現したカーバイド工場は、人々の生活を激変させた。長きに渡ってこの地で半農半漁による慎ましい生活をしていた人々に、職工という職業選択が生まれたのだ。工場はあっと言う間に拡大し、気がつくと水俣の人々にとって工場での雇用は、なくてはならないものになっていた。
だから、忌まわしい水俣病の原因が明るみに出ても、人々は一概に工場を悪の根源として糾弾することができなかった。娘の身体に毒を流し込んだのは、枕元でその手を握っている父親自身であるかもしれなかったからだ。
いまだ止まらぬバスのなか、僕は自分の一族が工場の関係者だったのではないかという空想をする。曾祖父や、僕に連なる「誰か」が自らの手で不知火海を汚した可能性は、十分に想定できた。それほどに、水俣市民とチッソの関係は深い。
――僕の一族に、海を汚した罪人はいただろうか。
そうした空想は、僕に堪え難い憂鬱さを与えるのだった。その日の夕刻、市内での一連の調査を終え民宿にたどり着いた僕は、夕食も食べずに泥のように眠り込んでしまった。
翌朝、僕は八時ごろに目覚めた。立て付けの悪い民宿の扉を開けると、鋭い日差しが眼をさす。天気はすこぶる良かったが、朝が早いため視界はなんとなく薄ぼんやりとしていた。あたり一面には、胸がすっとするような夏の朝の匂いが漂っている。
僕は、自転車屋さんでレンタサイクルを申し込むと、勢い良くペダルを漕ぎ始めた。目指すは除籍謄本に記載された住所、僕の先祖が暮らした場所だ。
トラックが行き交う大きな国道を十分ほど走った。僕は一旦自転車を止めると、二万五千分の一の地図を取り出して道筋を確認する。どうやら、ここからは山へ続く坂道に入るようだ。ゆっくりと自転車を押し進めながら、坂道を登った。ところどころに立ち並んでいるのは、黄櫨の樹であるようだ。この樹は幕末期に肥後藩がおこなった産業奨励政策の一環として植えられたものであるらしい。黄櫨の果皮は蝋燭の原料となる。
吹き出る汗を拭いつ坂道を登ると、やがて丘の上の小さな聚落にたどり着いた。除籍謄本曰く、このあたりが僕の先祖が暮らした場所だという。
僕は夏の空気を胸いっぱいに吸い込むと、ぐるりとあたりを見回した。視界に入るのは民家、畑、黄櫨の樹。そして、至るところに植えられた鮮やかな花々だった。これは、このあたりの住民の趣味なのだろうか。名も知らぬ真っ赤な花々があちこちで風に揺られている。この地に生まれた僕の曾祖父は、花が大好きだったそうだ。自宅の周りにあまりにも沢山の植木鉢を並べたため、娘婿(僕の祖父)からきつく怒られたことさえあったらしい。なるほど、彼の花好きは生まれ育った環境から来ているのか。
僕は名も知らぬ花の脇にそっと自転車を止めると、聚落を散策することにした。
太陽を背負いながら聚落を歩いていると、何度か住民とすれ違った。僕はその度に先祖について調べている旨を告げ、同姓の家の有無を聞いた。こういう場合、高校生という僕の身分は先方に不信感を与えにくいらしい。なかには、わざわざ家にまで戻って古いことを調べてくれる人までいた。しかし、情報は皆無だった。

結果的に、この聚落において僕と同姓の家は一軒も見受けられなかった。これは、僕の先祖が比較的新しい段階で、この地にたどり着いたであろうことを示している。はるか昔からこの地で暮らしているのならば、その子孫は時代を経るごとに増加しているはずだからだ。僕の一族発祥の地は水俣(ここ)でないのかもしれない。
それでも、僕の先祖がこの聚落で暮らしていたこと自体は紛れもない事実だ。そうであるなら、彼らの残した足跡が、きっとどこかにあるはずだった。
――墓石を見つけなければ。
僕は改めて自身の目的を確認すると、その使命感に高揚した。
ただ困ったことに、この聚落に墓地と呼べるような大それた区画は見当たらなかった。村人たちの墓石は、一ヶ所にまとめられることなく、思い思いの場所に点在していたのだ。だから、僕には聚落を歩き回って、畑の片隅だの人家の庭先だのに置いてある墓石をひとつひとつ確認していく必要があった。
これは恐ろしく難しい作業だった。まず、墓石自体を見つけることが大層難しい。そのうえ墓石がちょっとでも入りにくい場所にあると、確認作業は大変骨の折れるものになった。民家の脇にある墓石を発見する度に、僕は内心で土地の所有者と死者に詫びを入れながら、えっちらおっちら歩を進めなければならなかったからだ。
そうして罪悪感を積み重ねていっても、探し物は見つからない。僕は次第に聚落を大きく離れるようになり、人々に打ち捨てられた畑にまで足を踏み入れるようになった。茂る下草をかき分け、僕は荒れ地をゆく。ふと、何かに躓いた。足下を見ると、それは横たわった墓石だった。刻まれた文字は風化していて、最早読むことができない。ふいに現実世界に引戻された気分になって、僕は周囲を見回す。すると、至る所で墓石が倒れているではないか。そこは墓の墓場だった。
しかし、打ち捨てられた無数の墓石を眼前にしても、不思議と僕が恐怖心を抱くことはなかった。だから僕は、その場から逃げ去ることはなかった。それどころか「南無阿弥陀仏」とつぶやきながら、畑のなかに散在する墓石をひとつひとつ立て直すことさえ出来たのだ。倒れた墓石は、精気を放ちきった骸のように重かった。墓石を抱きかかえるかのように持ち上げる度に、恐ろしいほど大量の汗が滴る。そうやって僕は、自分の若いエネルギーを、墓石を立て直す行為に浪費した。にも関わらず、僕の先祖の名前を刻んだ墓石は一向に見つからない。
――僕の先祖はここにはいなかったのか。
急に、見知らぬ土地で墓石を探し求めている自分に、そこはかとない恐怖心を覚えた。
それでも、この作業を辞めるわけにはいかなかった。あっちの墓石を確認しては、向こうの墓石を確認する。そうやって僕は、何度も何度も同じ場所を行ったり来たりし続けた。
ふと、見覚えのある自転車が目の前に現れた。いつの間にか、僕は初手に自転車を止めていた場所に戻っていたのである。なんだか拍子抜けしてしまい、僕は一息いれようと自転車の脇からサドルに腰掛けた。そして、先に登って来た坂道を振り返って、驚いた。

僕の眼下には、息をのむ程に美しい不知火海が広がっていたのだ。目の前にあるのはまっすぐと伸びる灰色の一本道、風になびく赤々しい花々。その先には静かな海が悠然と揺蕩っていた。
それはかつて、この地に暮らすあらゆる生命に、大きな災厄をもたらした不知火の海だった。
この地に暮らした僕の一族のなかにも、不知火海を生業の場とした者もいたことだろう。不知火海を自らの手で汚した者もいたことだろう。そして、不知火海の水銀に身体を毒された者もいたことだろう。その全て、僕に連なる全てを抱いて、不知火海はそこにあった。
既に飛行機の搭乗時間は刻一刻と迫っていた。そろそろバス停に向かわないと、帰りの飛行機には間に合わない。それでも僕は、もう少し、もう少しと自分に言い聞かせ、ずいぶんと長い間不知火海を見つめていた。目に見える先祖の足跡がなくとも、小高い丘のうえから不知火海を見つめ、そよ風に吹かれているだけで僕は満足だった。
あんなにも爽快な景色を、僕は他に、しらない。(円)
北山:1994年生まれ。ライター。「文春オンライン」、「幻冬舎plus」などに寄稿。文系院卒。世の中で一番尊い出版社は河出書房新社だと思っているが、まだ依頼はない。署名は(円)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
