
続 脳科学的、自己肯定感・セルフイメージ、自信の上げ方
こんにちは、脳と心体革命大学です(^^)
前回はセルフイメージ、自己肯定感についてかきました。
https://note.com/chikenrevo/n/nc066ed0ca8e8
セルフイメージとはなにか?セルフイメージが身体にどう影響を与えるのか?などについて書きましたが、今回はセルフイメージ、自己肯定感の具体的な上げ方について書いていきたいと思います。
今回紹介する方法は、前回のセルフイメージについての記事と、もう一つ最近あげました、扁桃体についての記事を融合させ、脳科学的に解説した内容となりますので、まだ読んだことがない方はそちらを読んでから読むことをオススメします。
1.脳科学的に、自己肯定感、自信とはなにか?についてのおさらい
ここでは前回セルフイメージについて書いた記事について少しおさらいしたいと思います。
まず自己肯定感、セルフイメージとは脳神経回路であると書きました。
例えば学生時代、テスト前に勉強をしっかりして準備し、試験を迎える人は、試験の当日は自分の実力を早く発揮したい、緊張感がいつもより少ない、というような感情になるかと思います。
この事例で何が頭の中で起きているかというと、まず勉強という行動を繰り返し行うことで、勉強した情報、知識のほかに、勉強している自分像が脳神経回路に記憶されます。
そうすることでこれだけ勉強してきた自分がいるから大丈夫だろうという回路が生まれ、自信が出てきます。
試験当日はそういうセルフイメージができているので、幸せホルモンであるドーパミンが分泌されます。ドーパミンはリラックス効果もあり、脳波でいうとα波(集中するときに必要な脳波)がでる条件でもあります。

α波とは目の前のことに集中できる脳波で、逆に不安感や恐怖感が出るとき、脳からはノルアドレナリンなどがでており、脳波はβ波となります。
例えば勉強をあまりしてこなかった場合は、当然試験に対してきんちょうしたり不安が大きいと思いますが、このとき試験中、β波になってしまうと問題が頭に入ってこなかったり、周りのことが気になる、試験に落ちた後どうなってしまうかなどのネガティブなイメ-ジがわいてきたりなど、目の前のことに集中できない事態に陥ります。
ここでまとめると、つまりセルフイメージとは、行動の積み重ねによって記憶される脳神経回路であり、+ドーパミンが出ている状態といえます。
自分が行った行為・行動を自分の脳が認識し、自分の自分像を作り上げるのです。
ドーパミンは個人的にキーワードだと思っていて、例えばめちゃめちゃ勉強していても、当日ドーパミンが出ていなくて、不安・緊張していてはせっかく行動してきたのに台無しですよね?(例えば、まわりを見渡して、自分より全員賢そうに見える、朝家を出ていくときに、親から落ちたら許さないよ!などと言われたなど。。)
あとは自信がないとき、自己肯定感が低いときってうつむきがちですよね。

そういったときは漠然と不安感とかがあることが多いですが、脳科学的にはドーパミンではなくノルアドレナリンやアドレナリンがでている状態だといえます。
(実際、脳の視床下部には、ホルモン袋というものがあり、身体の傾き具合で、脳内ホルモンの種類は変わってきます。背筋がいいと表情がいい人が多いのはホルモン袋が傾いておらず、ドーパミンがでているからです。)
なので行動+ドーパミンがセットで自信、自己肯定感につながると思います。
2.「1日脳波6万回」を活用せよ
前回の記事において、ノミの実験の話をしました。
ノミはとても高くジャンプできるのに、コップにしばらく入れておくと、そのコップの高さしか飛べなくなると。
ここでポイントなのはコップにジャンプしてぶつかったのは、1回でなく、何回も同じ行動を繰り返したということです。
ここで人間の脳について書きます。
私たち人間は五感を使って、1日の中で見たり、聞いたり、味わったり、動いたりを数えきれないほどしていると思います。

例えば腕を動かすとき、なぜ腕が動かせるかというと、脳から電気信号が腕に発信されることでうごかせることができるのです。
見るということも同じく、シンプルに言うと、外界からの情報を目の中の網膜を通して、電気信号が脳に届くためです。
つまり私たちの行動、思考というのは全て脳の電気信号によって処理されているのですが、その電気信号は1日6万回も流れているとされています。

ここでノミの実験に戻りまして、なぜノミが高くジャンプできなくなってしまったか?といいますと、脳からみればコップの上にあたり続けた、つまり失敗を何回も繰り返す(脳の電気信号が何回も流れる)ことで、その行動・習慣が脳神経回路に強く記憶されたといえるのです。つまり自分が行った、思考した内容を自分の脳が、認識しそういう自分を自己として認識するというイメージです。
他に事例を出すと、親から「あんたはほんと馬鹿でドジだね」と習慣的に言われ続けると、子供は「僕は馬鹿でドジなんだ」と習慣的に思うように刷り込み・記憶されてしまいます。行動だけでなく思考でも脳の回路に影響が出ます。
脳波は1日6万回と書きましたが、人間が思考する回数ももちろん含まれており、思考がネガティブに使われ続けるとノミのように自分の可能性を大きく制限してしまうことになります。では逆にプラスに思考・行動をかえるとどうなるでしょうか?
自分の脳の記憶情報をプラス、ポジティブなものに変えるためには、脳の使い方、行動習慣を変えなければなりません。
次はその変え方について解説します。
3.だれでもできる最強習慣は「笑顔」とメリットについて
セルフイメージについて考察していた時に、例えば何事も早く行動するとか、いつもハキハキ声を出す、歩くときは胸を張るなどのようなことをかいてある本がありまして、一応はそういう行動習慣は効果はあると思いますが、脳は1日6万回の視点から言えば、そういう習慣はずっと長時間できるか?といえば無理だろうな、他にもっといい方法があるはずだと思い、いろいろ探していた時に、一冊の本に出合いました。それが「笑顔の魔法」という本です。
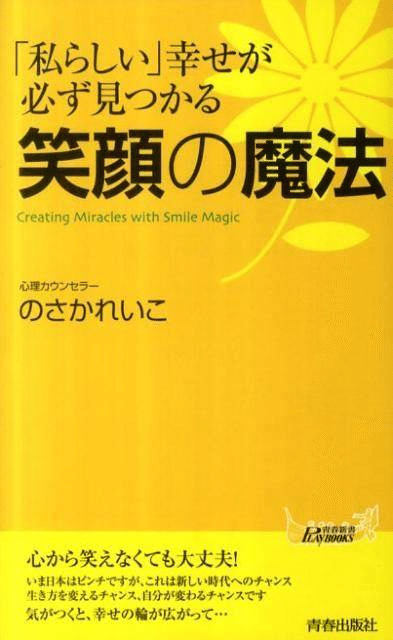
笑顔、口角を上げる方法なら誰でもタダでいつでもどこでも何回でもできるすごい方法だと思います。本ではいろんな方が笑顔を作るだけで、悩みが解決した話が載っていておもしろいです。
単純に笑顔を作るだけで自己肯定感があがる?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思いますが、ここで脳科学的に笑顔のメリットを紹介しますと
・笑顔を作ることでドーパミンがでる(上でかきました、自信をつくる脳内化学物質です。)
・ドーパミンが出ることで交感神経が抑えられ、副交感優位になるためリラックスした状態で生活できる。
・副交感神経が働くので、筋肉緊張電位が下がり、肩こり(交感神経優位だと、血管が筋肉を締め付けるので)、高血圧、慢性疲労にも効果がある。
・α波がでやすくなり、雑念(煩悩、β波)が減少。無駄な思考が減る。
・思考にはエネルギーを使うため、甘いものの摂りすぎ、過食やアルコール依存にも効果がある。(交感神経優位な時は、扁桃体からの命令で、細胞内から血管内に脅威に備えて、糖を分泌し続けます。そのため交感神経優位な人は甘いもの好きがおおいです。)
・長期的に見れば、笑顔を作る→そういう自分を自分が(脳が)認識する→脳神経回路の変化→セルフイメージ(潜在意識)の変化
・笑顔のよるいい周波数により、自分の周波数が変わるので、引きよせの法則の視点からみればいいことが起こりだす。
・コミュニケーションがうまくいく
など多分まだまだありますがこの辺で。
この習慣を取り入れれば、必ずだれでもモチベーションや能力、パフォーマンスはあがります。
ぜひお試しください。
ただし笑顔だけでパフォーマンスが上がらない場合もあります。それは5.マインドフルネスのところで解説します。
加えて参考になる記事も紹介しておきます(^-^)
4.セルフトークをかえよう(アファーメーション法)
セルフトークとは頭の中で行う独り言です。
笑顔の次は頭の中の独り言もチェックしましょう。
頭の中の独り言も思考で、そしてそのもとは電気信号によって作られているもので、繰り返すことでそれが習慣になり、脳に記憶されます。
「だるいなー」「疲れたー」「私はダメだ・・」とよく言っている人は多いですよね?
結構前の記事ですが、手を組んで縮まれと繰り返すと縮まっていく不思議な実験の紹介をしました。
https://note.com/chikenrevo/n/n8ad4f6cdeb9d
セルフト-クは脳にも身体にも影響します。
ここで面白い動画があるのでご紹介します。
https://www.youtube.com/watch?v=AO2Yrcoe5iA
幼稚園の発表会での様子ですが、最初飛べなくてべそかいていた子供がみんなからできるできる!!と言われた後になんとすぐ飛べたんです。それほど言葉の力というのは強いんです。
松岡修造さんもよく自分に「できる。俺はつよい」とか試合中言ってますよね。
これはある種、自己暗示ともいえます。なりたい自分をイメージしてそこから自分にあった言葉を選び、自分に言い聞かせます。
これをアファーメーション法と言います。

セルフトークの設定の仕方ですが、一番の基礎は「リラックスした、落ち着いた自分」が最優先です。ここをクリアできていないと、目標が強い自分で「私は強い」といいきかせていても、「ホントに私は強いんだろうか・・・?」とう雑念が出てきます。なのでベースの「リラックスした自分」をつくってから、自分のなりたい自分像にあった言葉を選んで、繰り返し唱え続けて脳に記憶させましょう。
強い自分づくりについては「いつも胸を張る」「ハキハキ大きな声で喋る」「背筋を伸ばして歩く」などの習慣を取り入れるといいと思います。
実際に胸を張りながら生活していると不思議と気分が変わってきます。
できる人がどんな行動をしているかを観察して取り入れてみることも面白いと思います。

5.自己肯定感におけるマインドフルネスの重要性について
4において、少しふれましたリラックスした自分づくりがベース、最優先で大事だと書きました。
そして笑顔という習慣にも触れましたが、これでパフォーマンスが上がらない方もいます。その原因は扁桃体にあると考えます。

扁桃体とは脳の中にある、外界からの危険に対して情報処理を行う部位です。そして脳が危険やストレスを感知すると扁桃体からの命令で不安感や恐怖感、興奮、イライラなどのもとになるノルアドレナリンやアドレナリンが分泌されます。
この部位は人間が狩りをしていたころには有効に働いていました。
例えば狩りをしていて、蛇に遭遇した時などは扁桃体によって、蛇を危険なものと認識し回避や攻撃するというしくみです。
扁桃体がないサルは蛇をみても怖がらず好奇心から口に含んだりするそうです。

しかし現代において危険はとても少なくなっており、かといいて扁桃体が全くなければそれはそれで支障が出ます。
厄介なのは長期的なストレスや危機が去った後も扁桃体はリラックスしていると認識しない限り、活性化しつづけてしまう働きがあるということです(これを長期記憶といいます)
少し極端な事例かもしれませんが、戦争から帰還した兵士によく発症したPTSDという病気があります。これは戦争という危険な場所に居続けることによって扁桃体がずっと活性化し続け、それが続くと脳に記憶され、扁桃体は「外界は危険で一杯であるから、いつでも対処できるように交感神経を優位にしてノルアドレナリン、アドレナリンを出しておき準備しておこう」という風に解釈します。
それは戦争が終わった後、帰還した後も扁桃体がその記憶を持ち続けている限り、その状態は日常の穏やかな生活が続いた後も続きます。
ノルアドレナリンやアドレナリンが多く出てしまう状態は、いわゆる自律神経失調症、うつ病の状態になります。
(余談ですが、うつ病の「うつ」はうつむくということからきていると思いますが、扁桃体が外界が危険と判断している場合、その脅威から回避するため、相手から見つからないようにするために姿勢を低くしてうつむくからではないかと思ったりもします。)
今は戦争の話を出しましたが、現代にも多く当てはまります。
例えば職場で嫌な上司から日常的に怒られ続けるとどうなるでしょうか?
扁桃体は嫌な上司を脅威とみなしそれに対応するため、ノルアドレナリンやアドレナリンを出して活性化し、それが続くと常に活性化することが記憶され交感神経優位になり、気分障害、食欲不振、睡眠の質の低下など多くの問題を引き起こします。

いじめの問題も当てはまるでしょう。いじめられ続けると扁桃体に外界は危険であると認識され、学校に行かなくなり、危険を回避するため家にとじこもってしまうなど。
あとは最近でいえば長時間労働・食の乱れによって栄養状態が悪くなる(質的栄養失調)・電磁波を浴び続ける・SNSなどによって思考しすぎると身体は酸化し、疲れやすくなります。そういう状態は狩りの時代まで遡れば、外敵に狙われやすくなっている状態なので、扁桃体が活性化し、外敵に対応するため不安・イライラのもとであるノルアドレナリンやアドレナリンを出しやすくなります。それが続けば扁桃体に記憶され、自律神経失調症などを引き起こしてしまうなどが考えられます。
昨今、多くの人がメンタルを崩す理由の一つではないかと思っています。
そこで扁桃体に「自分はリラックスしていますよ」と学習させ、記憶させること、記憶を変えることが重要になってきます。自信の元はドーパミンであると書きましたが、扁桃体が過活性しなくなるとノルアドレナリンやアドレナリンは少なくなり、自然とドーパミンがつくられるので自信も勝手に出てくると思います。
扁桃体が過活性してしまっていて長期記憶化されている人はまずここにアプローチしないかぎり自己肯定感は生まれないのではないかと思います。
(ちなみに脳の記憶を変えることを「脳の可塑性」といいます。一昔前までは年齢を過ぎると脳の神経回路は変わらないとされてきましたが、昨今ではその節は否定されています。)

そこで出てくるのが、マインドフルネス(腹式呼吸法)、自律訓練法になります。扁桃体の記憶を変えるにはうってつけの方法です。
瞑想などもありますが瞑想よりかは、腹式呼吸の方が横隔膜を動かすトレーニング内容も含まれているので、おすすめします。(自律神経と横隔膜はつながっているので横隔膜を鍛えることで、扁桃体を鍛えることにもつながります。)
些細なことでクヨクヨなやんだり、ネガティブ思考が多い、緊張しい、人見知り、HSPのかたというのは扁桃体が過活性の状態にあるのではないか?と思っていて、性格の問題ではなく扁桃体の問題だといえます。
この辺は「身体はトラウマを記憶する」「人は皮膚から癒される」などの本を参考にしています。(ちなみに本の中で筋肉隆々の患者さんがでてきます。いくら筋トレしても扁桃体が活性化していたら、問題は解決しない、パフォーマンスは上がらない事例だと思います)


呼吸法や自律訓練法(フェルデン法)のやり方は前回の記事に詳しく書きましたので詳しくはそちらを参考にしてください。
https://note.com/preview/ne1f8baa206ae?prev_access_key=48f703cc7166d97fd298365e6edb5b71
6.まとめ
ざっくりまとめますと
①マインドフルネスのトレーニングで扁桃体の働きを正常化する
②笑顔の習慣を取り入れる
③加えてなりたい自分像に合わせて行動する、もしくは言葉がけを行う。(アファーメーション法)
この三つを行えば脳科学的には自己肯定感、自信はアップします。
もっとシンプルに言えばドーパミンがでればいいのです。
ドーパミンの出し方は色々他の記事にも上げてますし、他の本でも腸内環境だったり、運動、睡眠、食事についてあるとおもうので色々読むことが大事かなと強く思います。
ですがやっぱりベースは何度も言いますが、扁桃体の安定・自立神経系の安定があってこそだと思います。
記憶を変えるのには少なからず時間が必要です。1日2日でかわるものではありませんが、続けると必ず変化します。継続は力なり。頑張りましょう。
今回は以上になります。
どうでしたでしょうか??ここがわかりにくいなどあればコメントくだされば、必ず返信します。(^-^)
Twitterもやってるのでよかったらフォローよろしくお願いします(#^^#)
やる気が上がります笑
次回は
・なぜ社交的な人、アクティブな人や非社交的・消極的な人・人見知りの人とわかれてしまうのか?
・タッピング法、フェルデン法、ペットセラピー、皮膚感覚、マズローの5段階欲求説などから性格の秘密を紐解く
などについて書いていこうと思います。
これに気付いたときは自分でもびっくりしたというか、他にこういうことを書いている人を見たことがないので、早く書きたくてうずうずしてます。
ではまた次回の記事でお会いしましょう。(^^)v
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
