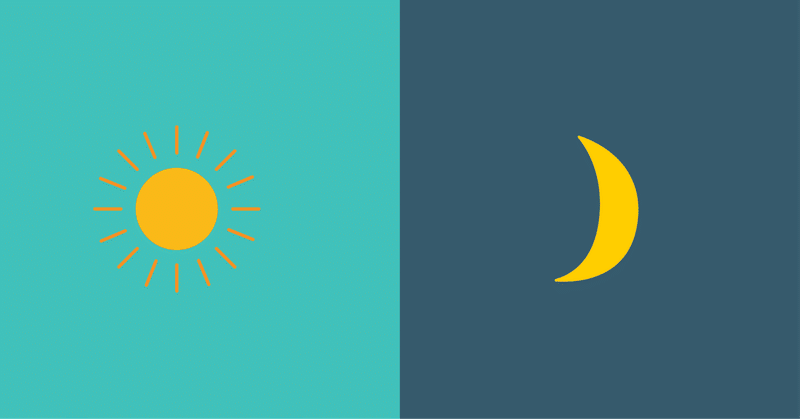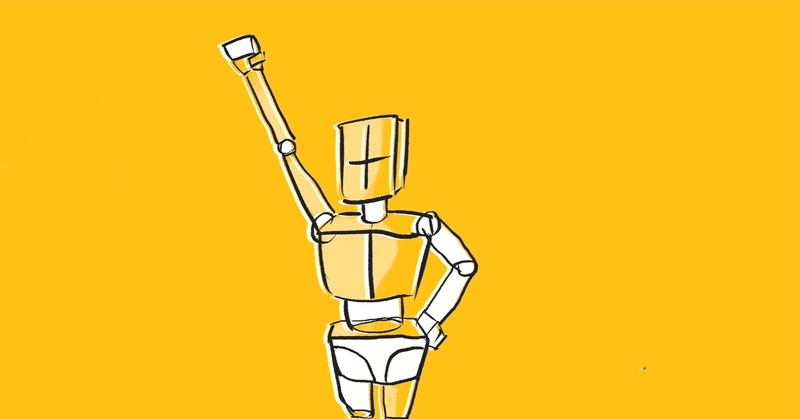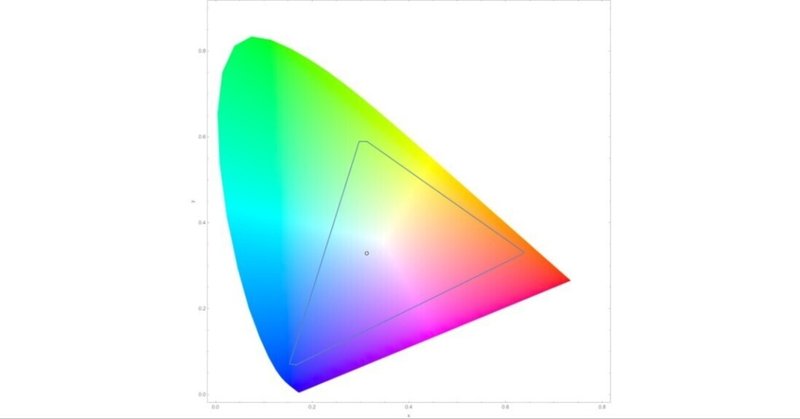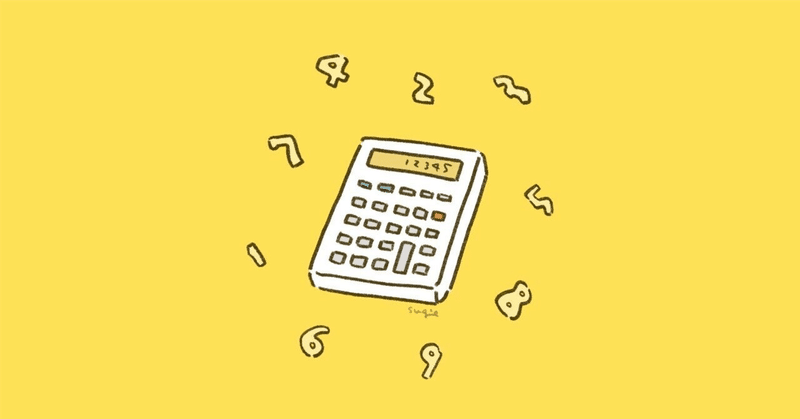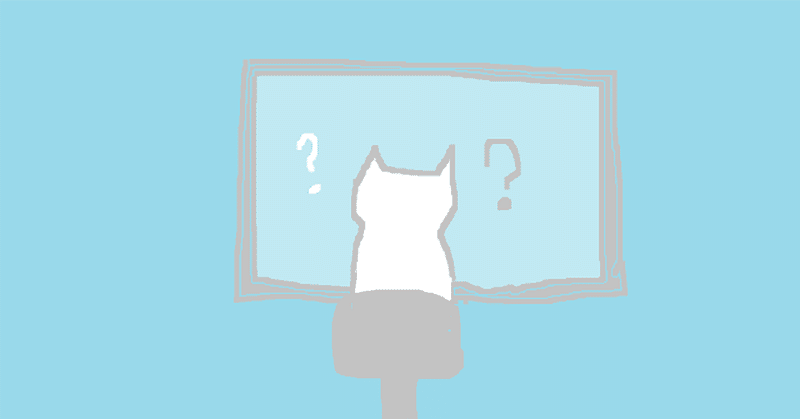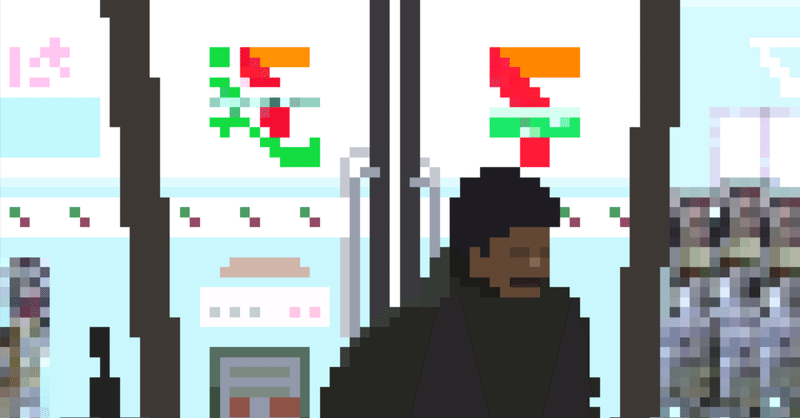記事一覧
緊縮財政に苦しむミュージアム業界
ミュージアムの財政難
昨年2023年は博物館の財政難がますます悪化していると印象付けられた年だった。まず、この年の1月に東京国立博物館館長の藤原誠が『文藝春秋』に「このままでは国宝を守れない」というセンセーショナルな見出しで寄稿したことが話題となった。藤原は、現在、博物館は光熱費高騰によって深刻な財政的危機に陥っているという認識を示し、補正予算を承認しようとしない財務省を批判するに至ったのだ。
練馬区立美術館「池上秀畝」展の感想
まず、池上秀畝展のほか、安井仲治展、木村伊兵衛展も一日でめぐったので、かかった費用を記録しておく。
練馬区立美術館 池上秀畝展
特別展大人1000円、図録3080円、駐車場料金1200円
東京ステーションギャラリー 安井仲治展
大人1300円、図録3760円、駐車場料金1000
東京写真美術館 木村伊兵衛展
大人1200円、駐車場料金960円
食費で2000円ほど、その他交通費がかかった。
画像をコモンズにアップするだけで満足していませんか? WikipediaでSEO向上計画
このような煽りタイトルをつけておいて難ですが、初めに断っておくと、この記事は、Wikimedia Commonsに美術品の画像をアップする活動をしている私のような変人が、コモンズにアップするだけではGoogle検索に載ってこないのでそこで満足しているのは拙いのでは?という疑問点について、その解決を模索する内容となっています。つまり、この記事の読者として想定される日本人はほぼいません。1億数千万の人
もっとみる三の丸尚蔵館が作品画像利用のトンデモ規制を取り下げてくれてめでたい件
11月3日、三の丸尚蔵館がリニューアルオープンした。それに合わせて、国立文化財機構所蔵品統合検索システム「ColBase」に三の丸尚蔵館の収蔵品が公開されたとニュースになっていた。
だが、この記事はあきらかに問題含みである。というのは、もともと何百年も昔の美術品には著作権などなく、画像の商用を含む自由な利用が法律で禁じられていたことなど一瞬たりともないからである。それが今このときになって、はじめ
日本美術史botのゴールについて
TwitterがXとかいう名前になって、ほんとかどうか知らないけど全部有料になるなんて囁かれている。
今年の初めには、ボットを動かしたり外部サービスと連帯したりするAPI機能が一部有料化された。突然の告知で外部サービスを連帯しているアプリ開発者や、bot運営者といったAPI利用者たちは寝耳に水を食らい、無料で利用できる範囲で活動を続けられることが判明するにも時間がかかり、二転三転する仕様変更の対
作品画像に文字をかぶせるのやめてください【美術館の中の人へ】
最近、美術館が広報用の作品画像として、画像の上に文字をかぶせはじめたので、そういうのやめてほしいという話です。
まず、直近の事例として挙げられるのが、現在、大阪中之島美術館で開催中の「生誕270年 長沢芦雪」展です。ポスターにもなっている長沢芦雪《牛図》(鐵齋堂所蔵)を見てみましょう。
画像の左下に小さくではありますが、作品情報が記載されているのがわかりますね。こうした画像は、ここ1年くらいの
ネットで使う美術品の画像は、カラープロファイルをsRGBにしようよ、Adobe RGBじゃなくてさ、という話
カラープロファイルの設定が不適切だったがために、ディスプレイに表示した作品画像がくすんでしまうことがあるので、その報告。
まずそういった事例の紹介。
10月から始まる竹内栖鳳の回顧展ですが、それを宣伝するウェブメディアで、彼の代表作《アレ夕立に》の画像の色がくすんでいるのを発見(後に説明するようにAdobe RGBを出せるディスプレイで表示すれば正常な色合いになりますが、一般のディスプレイだと
簡単に美術品画像のライセンスを確認する方法
前回、美術の著作権を詳しく解説する記事を書いたのですが、これを一回読んで、さぁこれであなたは自由だ!法律の範囲を最大限活用して美術品を利用しよう!と言われても、内容が難しかったかもしれないと思ったので、簡単にライセンスを確認する方法を紹介しようと思います。
とはいえ、一番確実なのは、著作権保護期間の計算ができるようになることなのは間違いないので、最初は大変かもしれませんが慣れるまで練習したほうが
未だネット上に存在しない日本美術史について
作品とどう出会っているか
有名な美術品に私たちはどのように出会っているでしょうか。
おそらく現代においては、本物の作品を見ることが初めての作品経験であることは稀でしょう。チラシやポスター、ネット上で画像を見たりするのが、最初の接触であることがほとんどです。
一昔前なら、美術全集だったり、美術雑誌に掲載された図版だったりしました。たとえば大正時代の画家たちが、セザンヌやゴッホといったポスト印象
広報用作品画像の解像度について
美術品の画像は、高精細であればあるほど価値が高い、とおそらく一般に考えられていると思います。どうせなら細部まで細かく見ることができて、本物との違いが少なければ少ないほどいいはずだからです。
作品のイメージを棄損しないようにブランディングをするという意味でも、質の高い画像を提供することは重要になるでしょう。展覧会のポスターに印刷する画像が、細部が荒っぽくて、色も不正確だったら台無しになってしまいま
仏教について学んだら仏教美術がよくわからなくなってきた
日本美術の特に前半を占める仏教美術について、これまでnoteでもたびたび取り上げてきた。仏教を信仰しているわけでもないのにどうして仏像を拝見しに寺に詣でるのか。それはその時代の高度な精神性に触れるためだと言ってみたり。仏像のデジタル画像はなんで使っちゃいけないの?という疑問から、仏像写真の歴史についてまとめたり。
しかし、まだまだ仏教美術はわからない。それを受容する仕方がまだよくわかってない気
美術図版、スキャンのすすめ
図録などの美術書から、作品図版を上手くスキャンする方法について、まとめておきたい。
スキャンするには、まずスキャナーが必要になる。しかし、スキャナーを自前で用意するのは難しい。用意したとしても、家庭用機種の性能なんてたかが知れている。
そこでおすすめなのは、コンビニのスキャナーだ。なかでも現在、一番性能が良いと思われるのが、セブンイレブンのスキャナーだ。ただし、店舗によっては最新機種でない場合
【備忘】Wikipediaって使いにくくない?
ひさしぶりにWikipediaをさわってみると、もういろいろ忘れてしまっているので大変だ。
というか、そもそも使い方が誰でも気軽にできるようなものでは到底ない。
こういうふうにしたいんだけど、どうすればいいんだろう?と思っても、まず調べ方がわからないので途方に暮れてしまう。
誰かが過去にやっていれば、そのページを参考にして真似することで対処できるけど、これから新しいページとか、カテゴリーを整
【備忘】Wikimedia Commonsのファイル名について
あーえー、Twitterがそろそろクソなので、Twitterは備忘録であったり、ふと思いついたことをメモしておく程度の使い方だったけど、それをこっちで今後はやろうと思います。タイトルに「備忘」とかつけるので、そういうのは読まなくてよいですというサインってことでお願いします
さっそく、最近さぼっていたWikimedia Commonsへのアップロード作業なんだが、これをぼちぼち再開しようかなと
日本と美術をめぐる呪い 映画『岸辺露伴、ルーヴルへ行く』
映画『岸辺露伴、ルーヴルへ行く』は、肝心のルーヴルのシーンが少なめで、映されるのはモナ・リザとサモトラケのニケくらいという程度で拍子抜けしてしまうかもしれないですが、美術史の知識が多少あれば細かなモチーフやセリフの意味が理解できるようになっていたので、ちょっと解説してみようと思ってこの記事を書き始めました。
しかし、書き始めてみるとどんどん一般的な解説を逸脱して、この作品には国家と美術という隠さ
【活動報告】2023年6月日時点で登録ツイートが857になりました。フォロワー数は5,146になりました。もう梅雨ですかね。今月末頃に関西へ行こうと思っています。どこへ行くかはまだ思案中です。