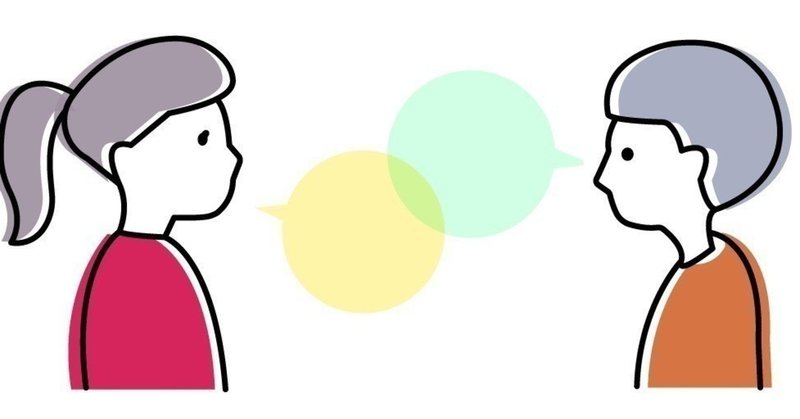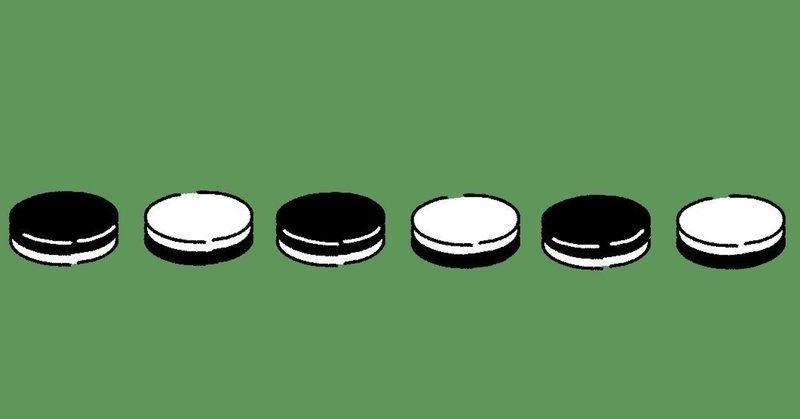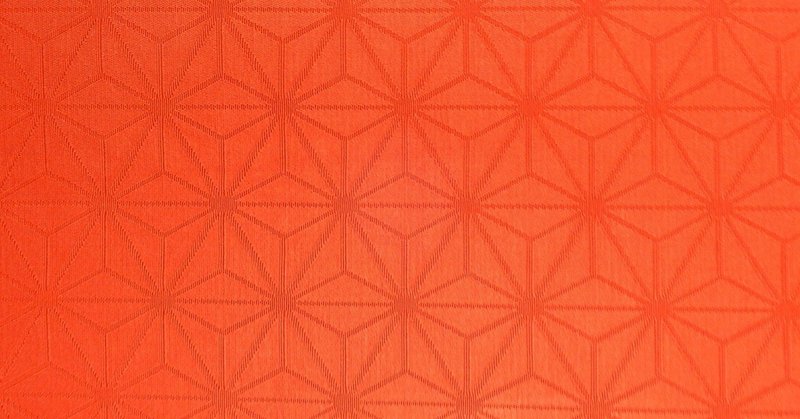#茶の湯
茶道をやれば、お花も上手に生けられるようになるの? ― 生け花との違い
茶道を通じて、日本文化のあれやこれやも学べるよ、ということはこれまでもお伝えしてきました。
では、生け花も?茶室の床の間にお花もあるし。
実は、茶道で床の間を飾る花と、生け花は別物です。
茶道では花を入れるといいます。生けるとはいいません。
なので、お花を上手に生けられるかといいうとNOとなります。
生けてないから。入れているから。
うわっ!めんどくさっ! と思われてたでしょうか。
もう少
和の意匠06 取扱注意!《つぼつぼ》 | お茶を通じて学べること 番外編
日本人は「もふもふ」とか「ふかふか」とか「ほわほわ」とか、繰り返しの擬態語が好きですよね。
「ぺこぺこ」 「ふわふわ」 「るんるん」 「しとしと」 などなどいくらでもでも。
ご先祖さまも同じようです。
つぼつぼ最初にみたときは、目が文字を正確に捉えられずに、「ぶつぶつ」と読んでしまい、仏像の螺髪のようなものかしらと想像しました。
つぼつぼ、こんな図柄です。
なんの意匠でしょう?
小さな食器
Design of Tea Ceremony |「アートとデザイン」と「おしゃれと身だしなみ」から「茶の湯」を捉えられるか
今日、入社式という方も多かったのでしょうか?
新入社員研修でおなじみなのが、「身だしなみとおしゃれの違い」。
身だしなみは相手目線、おしゃれは自分目線というような内容だったと
いつの日かの新入社員は記憶しています。
さて、入学式にはきっとまだ早いですね。
デザインや建築系に進まれる方は、きっと最初に「アートとデザインの違い」というのを教わるのではないでしょうか?
アートは自分本位、デザインは顧客