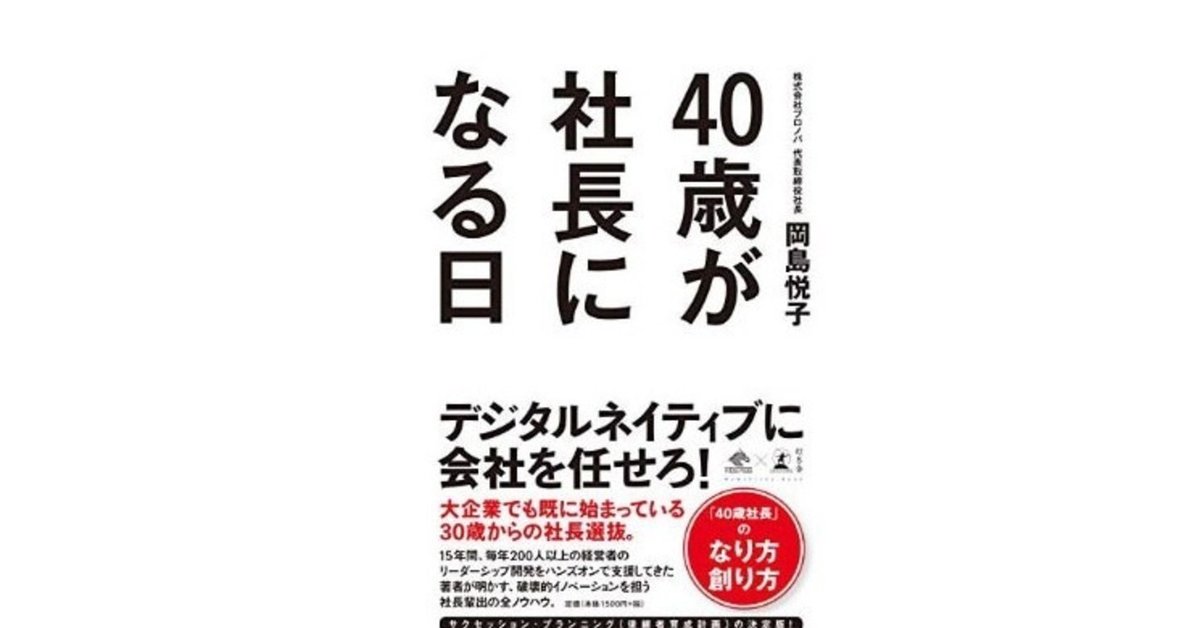
【読んでみた】40歳が社長になる日
本日も読みました!
今回は、タイトルからして、
自分とかぶるところがあるので、
即読みしました!!
本日も鍛錬します。
内容をささっと書きます!
1.本の情報
40歳が社長になる日
ジャンル:スキルアップ、リーダーシップ、人事
ページ数:249 ページ
著者:岡島悦子(おかじま えつこ)
株式会社プロノバ代表取締役社長。
経営チーム開発コンサルタント、経営人材の目利き、リーダー育成のプロ。
また、「日本に“経営のプロ“を増やす」ことをミッションに、経営のプロが育つ機会(場)を創出し続けている。
ダボス会議運営の世界経済フォーラムから「Young Global Leaders 2007」に選出される。
主な著書に『抜擢される人の人脈力』等がある。
出版社:幻冬舎 (2017/7/28)
誰に向けて読んでほしいか:事業承継で悩んでいる人。これから会社の幹部として会社を支えていく人。
2.主な内容
①消費者のニーズが多様化している今、重要なのは顧客とともにビジョンを創っていくことだ。そこで求められるのは、既存製品を改善する「持続的イノベーション」ではなく、課題そのものを特定し抽出する「破壊的イノベーション」である。
②これからは、リーダーが先頭に立って旗を振るスタイルではなく、現場が見つけ出した顧客インサイトを意思決定に役立てる「逆転のリーダーシップ」が必要になる。
③ダイバーシティとは、属性の多様性ではなく、視点や経験の多様性を指している。それらを経営判断に活かすことが重要だ。
3.もっと掘り下げ!
★外部環境の変化とイノベーション
〇不確実な時代の顧客インサイト
未来は極めて不確実である。これは、ビジネスの現場では共通認識となって久しい事実だ。消費者ニーズは多様化し、移り変わりも速い。当然、商品やサービスの寿命は短くなっている。
このような時代では、企業は顧客とともにビジョンを創っていく必要がある。ビジョンとは、ミッションを実現するために具体的に何に取り組むかという指標だ。顧客の消費活動や購買意欲を促す潜在的な欲求のスイッチ、すなわち「顧客インサイト」をあぶり出し、商品やサービス開発に反映させていかなければならない。
〇イノベーションと知の探索
組織を変えるのは容易ではない。特に大企業や成熟企業では、いわゆる「大企業病」にかかるのが定めだと著者は経験則から考えている。「内向き、上向き、縦割り」の影響で組織の部分最適化が進むと、どうしても組織の隙間に落ちたボールを誰も拾わないということが起こってしまう。
だが、この隙間こそがイノベーションの源泉なのである。イノベーションとは、経済学者ジョセフ・シュンペーターが「新結合」と表したように、既存の知と既存の知の新しい組み合わせから生じる。イノベーションには「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」の2つがあり、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄准教授は、前者を「知の深化」、後者を「知の探索」と呼んでいる。
持続的イノベーションでは、課題が明らかなので、その解決方法を深掘りしていくことが求められる。一方、破壊的イノベーションでは、課題の特定または抽出が求められる。今の時代に求められるのは後者だ。
とはいえ、破壊的イノベーションは収益に結びつくかどうか不確実であり、仮説検証と失敗を重ねていかなければ真の課題が見えてこないケースも多い。しかし、だからといって、既存製品の改良ばかりになってしまわないよう、注意を払わなければならない。
★新時代のリーダーシップの形
〇逆転のリーダーシップ
既存の技術や製品の改良にとどまらず、新たな価値を生み出し続けるには、どのようなリーダーシップが適しているだろうか。
これまでのリーダーシップは、リーダーが先頭に立って旗振り役を務め、下のメンバーにビジョンを示して顧客に価値提供していくピラミッド型スタイルが主流だった。しかし、顧客とともにビジョンを共創していくには、顧客に最も近い現場で顧客インサイトを探り、最終意思決定をするリーダーへと情報を流していくという構造をとらなければならない。そうでなければ、顧客インサイトにもとづいた経営判断は不可能である。
ハーバードビジネススクールのリンダ・ヒル教授は、これを「逆転のリーダーシップ」と呼んでいる。この新しいリーダーシップでは、異なる領域において高度なスキルを持った人材を集めるのが理想的だ。富士フイルムの例にあったように、ある技術が思いもかけない領域で応用されたときこそ、破壊的イノベーションが起こるからである。
〇組織の硬直化を避ける「ゆらぎの設計」
イノベーションは、1人の天才から際限なく生まれるものではない。だからこそ、イノベーションの創出を促すような組織文化と仕組みが必要不可欠だ。
組織設計のヒントとなるのは、「ゆらぎの設計」である。組織の中に不安定で落ち着かない状況、居心地のよくない環境をあえてつくることを大切にするべきだ。
たとえば、米スリーエムには「25%ルール」というものがある。これは、新規事業の売上高を5年以内に全体の4分の1にするという目標だ。こうした目標があれば、組織の目は必然的に外に向けられることになる。
〇イノベーションを引き出す4つのポイント
次に、組織文化の観点から、イノベーションを起こすための4つのポイントを紹介しよう。
1つ目は「善意の失敗を許容する」ことだ。メンバーが発案したアイディアをリーダーが率先して面白がり、やらせてみる。そして、あれこれ言い合いながら良いものに育てていく。そうした空気感がなければ、新しい発想はなかなか出てこない。
2つ目は「相互信頼」である。たとえば、映画の制作現場ではスタッフも俳優陣も互いにプロフェッショナルとして認め合っている。だからこそ、それぞれが専門性を活かし、面白い作品をつくり上げることができる。
3つ目は「自由と規律」だ。イノベーションが起こる組織では、まず小規模なチームをつくり、各分野の高度な専門知識を持つ人材を配置し、自由にやらせてみることが多い。このとき、投資金額の上限やKPIを設定するなど、ある一定の制約条件を設けて緊張感を持たせるといいだろう。
最後は「理念、文脈づくり」である。これまで、ビジョンの追求はリーダーの仕事だった。しかし、変化のめまぐるしい時代において、ビジョンは顧客とともに創り上げていくものになった。だからこそ、自分たちは何のために会社に集い、どのような価値を顧客に提供していくのか。そういった文脈づくりが、きわめて重要になる。
★新時代のリーダーの育て方
〇デジタル・ネイティブ時代の到来
不確実な状況下で意思決定を迫られる経営トップの役割は、以前にも増して高まってきている。今後はさらにその難易度は高くなるだろう。
このことに気づいている会社は、すでにサクセッション・プランニング(後継者育成計画)の取り組みを始めている。社長交代のタイミングで「その時点における最も適切な人材」を選び出せるように、前もってポテンシャルを見極めて育成し、後継者になれる母集団をつくっておくためだ。
実際のところ、大企業でも対象者の選抜は30歳くらいから始まっている。時期尚早だと感じるかもしれないが、この世代は物心ついたときから携帯電話が存在していた「デジタル・ネイティブ」だ。デジタル革命が進む現在、この世代を経営層に取り込まなければ、会社が時代についていけなくなるリスクが生まれる。
〇修羅場体験が未来を分かつ
ITリテラシーの高さは若い世代にとって武器になるが、それを活かして次のリーダー候補に入るには、早いうちから進んで修羅場体験を積んでおくことが重要だ。
著者が推奨するのは、20代の社内異動でポジションを3つ経験することである。異なる業種や職種を経験できれば尚よいだろう。自分の適性など考える必要はない。やってみないことには、自分の適性や強みはわからないのだから。
社内をローテーションする仕組みがない企業の場合、組織横断プロジェクトのような、世代や部門を超えた環境で仕事をするのもお勧めだ。そのような場所におけるコミュニケーションはストレスもあるだろうが、後のキャリアで必ず活きる。
とにかく、修羅場にこちらから飛び込んでいくことだ。苦しい状況下で意思決定をする訓練をどれだけ積んだかが、未来を分かつのである。
★イノベーションを促す多様化された組織
〇真のダイバーシティとは
かつて日本企業は、終身雇用や年功序列、新卒一括採用を通じて人材の均質化を図ってきた。この利点のひとつは、マネジメントのしやすさだ。だが、人材が同一化してしまうと、全員が一度に集団食中毒にかかった場合、組織全体が倒れてしまうことになりかねない。最悪の事態を避けられるようにするためには、人材を多様化させ、凝り固まった常識を見直したり、無意識のバイアスを外せたりすることが必要不可欠だ。
ダイバーシティとは、性別や国籍といったような「属性」の話ではない。「視点」や「経験」の違い、その多様性を指してダイバーシティというのである。多様化した組織はたしかに面倒だ。居心地の悪さも感じることもあるだろう。しかし、大切なのは居心地の悪い状況をつくり出すことであり、それこそが多様化された組織の証である。
〇多様性を企業経営に活かすということ
「企業経営に多様性を活かす」とは、「固定概念や既存の成功モデルに対して疑問を投げかけられる人を入れる」ということだ。とはいえ、どんなところにでも多様性を加えればいいというわけではない。たとえば、オペレーションについては、多様性を加えるのは合理的ではない。
大事なのは、意思決定において多様性が確保されているかどうかだ。このことは、現場でダイバーシティが実現されること以上に重要である。意思決定における多様性を増やすには、前述の「ゆらぎの設計」がカギとなる。適切にゆらぎを設計することによって、オーダーパラメーター(秩序変数)が臨界値に達して「相転移」が起こる。この相転移こそが、破壊的イノベーションであるといえよう。
4.学びや気づき/一読のすすめ
自分も今週で40歳になる。そして、今年の秋で社長就任の予定である。あくまで予定ではあるが。。。
新しい時代のリーダーシップやイノベーションを促す組織のつくり方、ダイバーシティの本質とその活用方法、さらには後継者育成まで、幅広く網羅されていて、本当に参考になった。
若手から人事部門、経営陣にいたるまで、幅広い層のビジネスパーソンにお薦めできる一冊だと思う。
下にURLを貼りましたので、
是非、買って読んでみてください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B073W57G18
#書評 #読書感想文 #日記 #ブログ #note #コラム #ライフスタイル #ビジネス #生き方 #人生 #社長 #読書 #ダイエット #子育て
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
