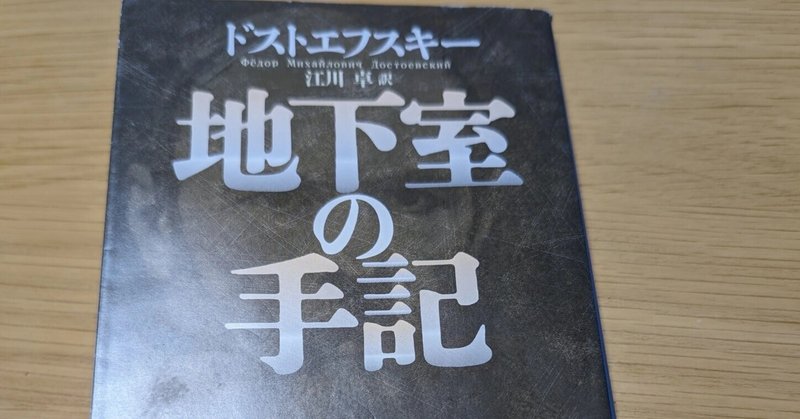
ドストエフスキー「地下室の手記」を『子ども部屋おじさんの慟哭』と捉えて考える|場所:理容おいしん、バーバーミノル|読書記録
3月に入ってから、冬がやってきたかのような積雪を見る日が増えた。温暖な2月を経て、花粉症に見舞われる日々を過ごす中、唐突な積雪の日々に驚愕を禁じ得ない。
巷で地球温暖化が叫ばれて久しいが、今筆者たちが直面しているのは、温暖化というよりも気候の異常化でなかろうかと思わずにいられない。そこまで考えて、なるほど、気候変動リスクとは言い得て妙であると思うのである。

理容店以前に理容師の減少が叫ばれている中、理容店と言えば低額のチェーン店に行く機会の増えた人々が多くなっていると思われる。いわゆる1,000円カットと呼ばれる店舗群の話である。
しかしながら、大船渡市には1,000円カットの店舗はない。2,000円カットのお店はあるといった状況である。釜石市に行けば1,200円くらいのお店があるくらいで、その業態でとりわけ有名なQBハウスなどは見当たらない。
そもそも人口減少が著しい大船渡市にあって、客数を必要とするような内需型の商売は成立が不可能に近くなっており、旧くからの常連が存在しているでもなければ営業するのが難しい。
観光客や移住者でも増えれば、そうした状況も幾分変わるのだろうが、東日本大震災から早13年。ありとあらゆる施策で近隣の市町村にさえ遅れを取り、知名度も劣る大船渡市に、それを期待するのもまた不可能に近くなっている。
さておき、髪型というものを気にする必要がなくなった筆者にとって、理容店などは髪を短くできればそれで良いものとなっている。だから、先述した低額の理容店で何ら問題がない。それゆえに普段はそうした店舗を利用している。
しかしながら、回転率こそが命題となる低額の理容店では、およそ頼めない内容がある。提供できないわけではないと思われるが、メニューから外されているものと言った方が正確かもしれない。何かと言えば、頭部の剃毛である。
つまりスキンヘッドにしたいとふと考えたとき、低額の理容店は選択肢から外れる。そんなわけで「理容おいしん」を訪れた。なお、おおふなと夢商店街には、「バーバーミノル」という理容店も存在する。
実はこの2店舗は、スキンヘッドを提供している。今や低額の理容店のみならず、剃毛を提供していない理容店が増えている(経験がなくやれないといった声をよく耳にする)。だからこそ、スキンヘッドに対応しているこれら2店舗には、希少価値を感じている。
以前、「バーバーミノル」を利用したため、今回は「理容おいしん」を利用した。両店舗は、昔ながらの懇切丁寧なサービスを受けられる。それでいてスキンヘッドを頼んでも4,000円以内に収まる。とてもありがたい存在である。スキンヘッドを所望する人々には、ぜひお勧めしたい。
理容おいしん
住所:岩手県大船渡市大船渡町字野々田12-34 おおふなと夢商店街
電話番号:0192-26-3248
※予約必須
※電子決済利用可能(PayPay)
営業時間:9時-18時
休業日:毎週月曜日
バーバーミノル
住所:岩手県大船渡市大船渡町字野々田12-34 おおふなと夢商店街
電話番号:0192-27-5457
※電子決済利用可能(PayPay)
営業時間:9時-18時
休業日:毎週月曜日、第三日曜日
ドストエフスキー「地下室の手記」を読んで考える愛されない人間の結末
前置きが長くなった。改めて読書記録を綴ろうと思う。
前回は夏目漱石の「こころ」を読み、その難解さに頭を抱えながらも長々と思いのまにまに言葉を綴ったわけだが、今回は前回と比べて一層難解で頭を抱きかかえそうになった程である。

本書を読み、何らかの理解を得ようと思ったとき、時代背景やドストエフスキー本人を取り巻く情報の多くを知る必要性が大いにあると考える。そうした情報なしに本書を読んだとき、恐らく抱く心持ちは面倒臭さや鬱陶しさといった、ネガティブなものになるのでなかろうか。
何せ本書は、冒頭から延々と厭世の念が続くのである。深い怨恨さえ感じさせるほどに鬱屈とした一人語りが、主人公の若かりし日の苦々しい過去が語られるパートまでずっと続く。それだけ見れば『よく回る舌だ』とでも思いそうになるが、書かれている内容自体は世の真理を突いたような話だったりするので軽々に読み捨てられない。
「二二が四」に連なる言葉の数々は、ある側面から見た人間の本質を突いており、それこそ著者が至った境地のようなものを垣間見させてくれる。確かに筆者たちが生きるこの世界では、「二二が四」が素晴らしいものであるように考えられており、多種多様なことに「二二が四」が立ちはだかる。
それらの事実がもたらす幸福、そして絶望は、常に筆者たちを一喜一憂させ、天上からの支配のように筆者たちの一挙手一投足を操るのだから、全くもって堪ったものでない。だからこそ主人公が語るように「二二が五」でも良いではないかと、思わせられずにいられないのである。
とまあ、そんな「地下室の手記」を読めば誰もが思うだろうありきたりな読書感想文を書き並べたところで、ググって出てくる本書の解説や考察を押しのけてまで読むような内容にはならないし、それこそ最近スマートフォンに搭載されたGeminiのような生成AIに出力される考察や要約感想文の後塵を拝するだけである。
何より、本noteに書かれるべき内容ではないし、筆者の言葉なのかさえ疑わしくなってしまう。そんなわけで、ここまで2,000字弱に至る文字の羅列を前置きとして、「地下室の手記」を読んで筆者が感じた想いを赤裸々につらつらと書きたいと思う。
「地下室の手記」は”子ども部屋おじさん”の慟哭
本書で語られる『地下室』とは、『孤独の牢獄』であり『俗世から隔絶された自分だけの世界』なのだと思う。分厚い自尊心の殻を被った臆病な精神と言っても過言ではないかもしれないが、本書の多くの箇所で描かれているように、『地下室』とは主人公の脆弱な心の支えと見られる。
淡々と読む限りにおいて、本書の主人公は、言ってしまえば単なる嫌な奴である。気位が高く、自己評価が他者と著しく乖離するほどに高騰している。厭世家であり厭人者であり、自分以外の人間を好ましく評価することも信じることもできない。とんでもないひねくれ者だ。
だが、一寸立ち止まって主人公を読み解こうとすると、彼を通じて”愛されなかった人間の行き着く先”が見えてくる。つまり、なぜ主人公が主人公たる様相になってしまったのかと考えたとき、彼が他者からの愛を知らなかったからでないかと考えさせられるのだ。
筆者たちが生きる現代で言えば、彼は”子ども部屋おじさん”、あるいは”無敵の人”と呼ばれる存在ではなかろうか。そんな心持ちにされてしまうのである。主人公を単なる嫌な奴ではなく、愛されなかった人間の末路と見ると、本書は些かばかり見え方が変わってくる。
愛されなかった故に世を疎み、愛されなかった故に自己への愛を拠り所にし、愛されなかった故に他者を上手く愛せない。それでいて心の内にどうしようもない淋しさを抱え、他者を求めずにはいられない。とどのつまり、彼は筆者たちが生きるこの世界のどこにでもいる孤独な中年男性である。
「地下室の手記」をそのまま読むと、鬱屈とした一人語りが延々と続く物語に思えてならない。しかしながら、『子ども部屋おじさんのブログ』と思って読むと、現代が抱える孤独の病の一端を垣間見えてきて、心痛むほどの思考を掻き立てられるようになるのである。
ところで「地下室の手記」は、本noteでこれまで書いた読書記録に照らし合わせたとき、「変身」と類似点があり、「人間失格」「愛と死」と対極となる点がある。
「地下室の手記」同様に「変身」もまた、愛されなかった人間の末路が窺える作品である。「変身」は愛されなかった故に理解もされず、胸の痛む悲しい結末を迎えることとなった。
一方で、「人間失格」「愛と死」は、胸の痛む展開こそあったものの、愛された主人公たちは、穏やかな結末を迎えている。著者たちが意識していたものではないと思われるが、この対比は現実そのままである。
つまり愛されなかった人間は、多くの場合その人生を暗いままに終える。人間によっては壊れ、”無敵の人”として社会を恐怖に陥れる事件を生じさせてしまう。一方で、愛された人間は、山あれど谷あれど何や彼や温かな人生を送っていく。
愛だの恋だのいったもののを賛美するつもりは毛頭ないが、さりとて他者から愛された事実の有無が斯様な差異をもたらすのは、多くの人間が知るところであり、ある種の真理と呼べるほど、決まり切ってしまっている現実であるように思われる。
「地下室の手記」で描かれている多くの話を、愛されなかった故に至った境地として読んだとき、本書は愛されたいと願うちっぽけな人間の悲痛な叫びに変わる。そして、読めば読むほどに胸を抉られるような想いに駆られ、自身の人生、その在り様を顧みるように警告されている気分になるのである。
愛されないから愛せないのか、愛せないから愛されないのか
本書の主人公を通して生き方のようなものを考えたとき、恐らく誰もが『主人公は他者を愛そうとしないから愛されないのだ』と思うのでなかろうか。目線を本書から離して世の中を見回したとき、婚活に成功できていない人々が見える。そうした人々も多くが『他者を愛そうとしないから愛されない』状況に至っており、そんな景色を見ている人間ならば一層思うに違いない。
だが、本書の主人公について言えば、あながちそうとも言い切れないようにも感じられる。そもそもの話、主人公の心持ちが語られる中で、自身が温かな家庭で育てていたら自分は周囲の人間のような生き方、考え方ができためいた言葉が伝えられている。
それはすなわち、『愛される環境を経験していないから、他者を愛せない』あるいは『愛を受けてこなかったから、他者の愛し方を知らない』と言っているに等しいように思われる。突き詰めれば、鶏が先か卵が先かめいた話になってしまうが、だからこそ本書の主人公において、どちらか一方が正ではないと考える。
ここで話をまた本書の外にある世の中の話に戻すと、筆者たちが生きる現実においては、『愛されないから愛せない』のか『愛せないから愛されない』のか、どちらが正かを論じるのは極めて難しい問題である。もっとも『他者に愛を向ける人間は愛されやすい』は一定正であり、『他者を愛そうとしない人間が愛されにくい』も一定正ではあると考える。
けれども他者を愛そうとしない人間とて誰かに愛される可能性はある。何せ人間が愛される要素など無数に存在するし、人間の好みなど千差万別である。また、他者に愛を向ける人間が愛されない可能性も当然にある。誰彼愛するような人間に向けられる感情には、疑念や不信が憑き物だからだ。
結局のところ、先に述べた通り『愛されないから愛せない』のか『愛せないから愛されない』のかといった議論は、鶏が先か卵が先かめいた話に落ち着くわけだが、「地下室の手記」から何らかの教訓を得ようと思うならば、『愛されたいなら他者の愛を素直に受け取る努力をした方が良い』くらいは言えそうなものである。
何せ、少なくともリーゼは、多少なりとも主人公に愛情めいた感情を(一時の気の迷いかもしれないにせよ)抱いていたのは確からしく、その感情を素直に受け入れ、彼女を愛することさえできていたら、主人公は何も地下室に籠もり続ける必要はなかったのだろうから。
それほど単純な話でもなかろうが、扉を開けて外に出ようとしない人間に、誰かが手を差し伸べてくれることはないのである。
以下は、広告です。ぜひ読んでみてください。
皆様のサポートのお陰で運営を続けられております。今後もぜひサポートをいただけますようお願い申し上げます。
