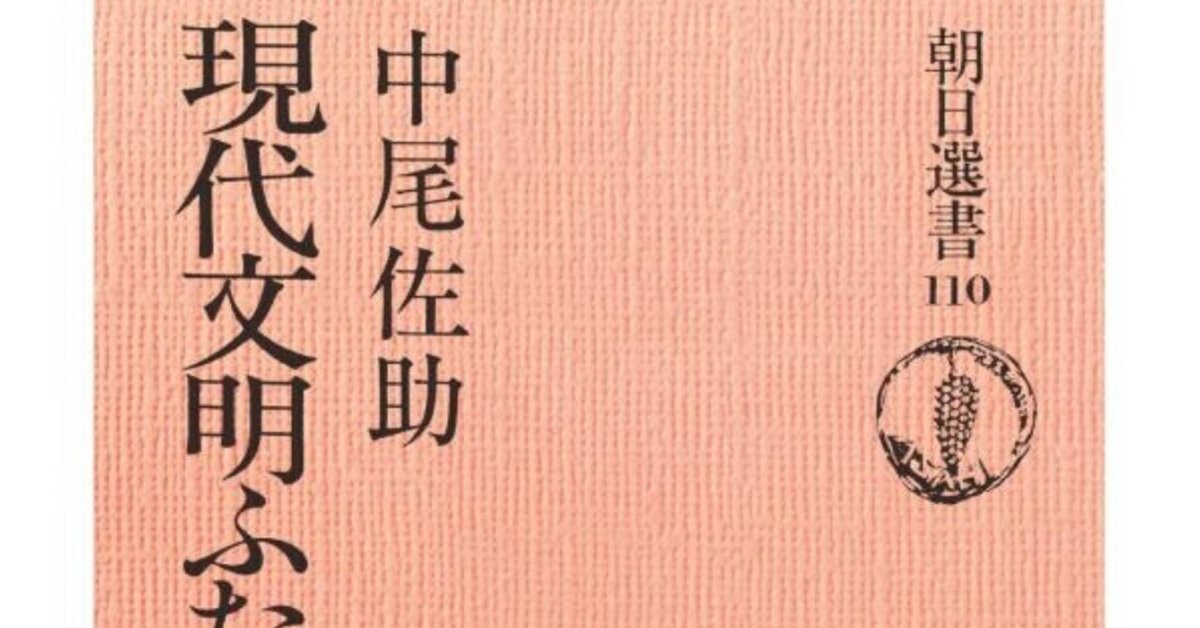
読書感想 現代文明ふたつの源流/中尾佐助
民俗植物学者であり、探検家でもある中尾佐助先生が「照葉樹林文化論」を思いついたのは、ネパール・ヒマラヤの探検が始まりだった。
1952年、日本山岳会マナスル踏破隊は今西錦司博士を隊長に、同行者5名で現地へと旅だった。中尾佐助先生はその探検隊のマネージャーだった。
当時はイギリス製航空用百万分の1地図しかなく、地図の通りにその場所を通れるのか、登路があるのかどうかもよくわからない旅だった。マナスル踏破隊はその調査のために派遣されたのだった。
中尾佐助先生は植物学者として現地の植物調査を担当していた。当時のネパールの植生について、イギリス人やドイツ人が書いた資料がぽつぽつあるだけで、現地の生態系がどういったものかも未知であった。
現地に降り立って最初の頃は周りの自然が奇異に感じていたが、数日滞在して、観察をし続けていると、次第になんの植物かわかるようになっていった。道端に時折見かける青葉をこんもり茂らせている木はシャクナゲの大木だ。電柱のように切り込まれた木は沙羅双樹だ。ヌスビトハギやウワバミソウもある。よくよく見ると、ヒマラヤ中腹の植物は、日本と同類の植物から成り立っていることがわかってきた。
ヒマラヤ中腹の谷を進んで行くと、道の両側には常に人家が見え、段々に刻まれた水田や畑が見えた。ネパール・ヒマラヤは高度1000メートルから1500メートルの間はカルチベーション・ゾーンと呼ばれている。ネパールでは1000メートル以下の河谷は二等地で水田はあるが、部落はかえって少ない。ネパール人は山肌に数百段、時に千段といった段々の水田を作り、その間に人口過密の高い村落を作って住んでいた。
(カルチべーション メディアの情報を受け続けると、次第にメディアに提唱されたとおりの文化観になっていくこと。ここでは耕されて周辺の中心地になっている土地……という意味)
そんな道を歩いていると、自然林というものにほとんど出くわさない。点々とした茂みなどがあるくらいで、頭の中でそれをつなぎ合わせて、自然がどのようになっているのか考えながらの旅だった。
12月の終わり頃、ヒマラヤの旅もいよいよ終わりという時を迎え、明日は首都カトマンズに入ろうというとき、そのカトマンズの都市を見下ろす峠に座り込んで、中尾佐助先生は今西錦司博士と長く話し込んだ。
カトマンズの盆地を取り囲んだ山々に、もくもくとした森林が生育しているのが見えていた。はじめの頃はわからなかったが、3ヶ月旅をした今なら、その森が常緑のカシ類を主体とした照葉樹林であるとわかる。日本の南半部に見られる照葉樹林と、植物の種類や構成、生態的構成もほとんど共通している。それだけではない。ヒマラヤ中腹の森から、東部ヒマラヤ、雲南省、湖北省、浙江省(せっこうしょう)、九州、日本本土南部とずーっと連なっているのだ。
これが「照葉樹林文化」を思いつく切っ掛けとなった瞬間だった。
照葉樹林の分布と特徴
東アジアの照葉樹林の中心は常緑性の樫の木である。地中海地域の広葉樹林ではオリーブが中心になっているが、これは栽培植物であって、本当の中心は常緑の硬葉樫である。つまり照葉樹林の主要構成樹木も、硬葉樹林の主要構成樹木も、どちらもドングリをつける常緑カシ類という点で一致する。
違いと特徴は、照葉樹林のほうが葉が大きく、葉の表面がテラテラと輝いているところだ。硬葉カシでは若葉以外は葉が厚く、表面が白茶けて見える。また照葉ガシはすらりと丈高く伸びていくが、硬葉は樹幹が曲がりくねる傾向がある。

他にも照葉樹林の特徴として、大木の森になりやすく、葉は黒々として、その下に入ると薄暗くなり、落ち葉がたまって足元は湿っぽくなりやすい。地表の草は密生しないが、ひょろひょろと丈が高くなり、灌木類もやはり多く生える。
地中海周辺の硬葉樹林であると木は低く、地面は乾いて草木が少ない。上から見ると、ノコギリの歯のようにギザギザに尖ったようになる。照葉樹林だとモクモクしたシルエットになりやすい。
日本の南半部の海岸に近いところは照葉樹林帯に入っている。しかし発達したよい照葉樹林はあまり残っていない。残っているところは、伊豆、房総半島の山の中、関西の三笠山、紀伊半島や九州の山の中。いずれも交通不便なところである。
しかし日本には照葉樹林を気楽に見ることができる場所がある。それは村々にある鎮守の森である。日本は信仰上、照葉樹林を神社林として現在まで残して来た。こんな自然保護はキリスト教にもイスラム教にも、本来の仏教にも中国の道教にもなかった。もしもこれらの宗教が日本のように森を残していたら、中国の黄河下流域のように原始林が消滅したり、ヨーロッパで自然植生の森林がまるごと消滅する……ということは起こらなかったはずだ。
ただしインドにはヒンズー教以前の信仰には神聖林を崇拝する習慣がいくらかあり、本来の植生を持った森が残されている。そういった様子は、日本の神社林とよく似ている。
日本でよい神社林をもとめると、東京であれば明治神宮、関西であれば奈良県の橿原神社の森がある。この2つの森は太古から残ったものではない。ここ最近、数十年程度で育ったものに過ぎない、しかしそれでも立派で風格ある森となっている。日本古来の風土が再現された森である。
明治神宮の森は本来ものより自然構成が複雑になっているが、ほとんどは日本原産の樹木から構成されている。これは日比谷公園の樹木と比較してみるとわかりやすい。日比谷公園には世界中の樹木が集められており、あたかも植物園のような光景になっている。もしも日本らしい森を求めるなら、明治神宮の森へ行ったほうがよい。
照葉樹林は四季緑の森で、林内は薄暗く、ジメジメとしている。林床(りんしょう)には落ち葉が堆積し、下草は多くない。照葉樹林は若葉の頃から快活性もなく、花を咲かせることもない。クスノキ科には花弁があるが、小さな花なので、見栄えはよくない。
照葉樹林の中にも見栄えのよい花を咲かす木もある。オガタマ、サカキ、シキミ、シイラギといった、日本神道に結びついた木はいずれもなかなかの花を咲かせる。
これらのうち、シキミは平安朝以降は仏教の花となった。サカキは万葉の頃には常緑樹の総称となっていて、神道の儀式として使われ続けている。
ツバキは照葉樹林の中では例外的に大きく立派だ。
こうした照葉樹林の中でも美しい花を咲かせる樹木は、儀式のなかに採り入れられていった。ここに日本特有の「樹木信仰」というべきものが隠れているように感じられる。





日本の南側半分は照葉樹林となっている。しかし縄文時代から一面照葉樹林に覆われていたか……というとそういうわけではない。
地質学的に考えると、照葉樹林は第3紀旧熱帯植物群の一部として東南アジアの山地に成立し、北方へと伝播し、やがて日本へ到達した。
(第3紀旧熱帯植物群 恐竜が絶滅した後の時代「第3紀」に栄えた植物群のこと。生きる化石といわれる樹木メタセコイア、世界で最も巨大な樹木センペルセコイアなど)
インドネシアのボルネオ山地を見ると、低地は熱帯雨林地帯だが、1500メートルの山地に入っていくと照葉樹林になっていく。マレーシアのサバ州にはマテバシイ属が60種、クリカシ属が25種、常緑カシ属が20種もあるという。
これらのブナ科の先祖というべきカクミガシ属が東南アジアの島々や山地で見られる。照葉樹林の本拠地は東南アジアやインドネシアの島々だったのである。ここから森林が北へと広がっていき、西はヒマラヤ山地、東は日本と膨大な地域を独占するようになっていった。
今からおよそ2万5000~1万5000年前頃が最終氷期と呼ばれる時期で、海面は今より130メートルも低かった。その頃の照葉樹林は鹿児島より南方の屋久島、種子島あたりまで来ていたと考えられる。
その後、気候は温暖化し、海面は上昇し、照葉樹林の北進が始まった。
1万年前頃から気候は現代と同じくらいになり、照葉樹林の分布も現代と同じようになったのだと推定できる。照葉樹林は1万年ほどの間に、直進距離1000キロ近く北上していったことになる。1年辺りの平均100メートルだ。
過去の森林の変化を研究する方法に、「花粉分析法」というものがある。これは地層に埋まっている花粉を詳細に調べて、それぞれの時代の植生を復元する手法のことである。この研究によると、照葉樹林の移動速度は1年辺り50メートルほどだったという。
樹木というものは生育に非常に時間が掛かる。立派な幹を作り、ドングリをつけるようになるまで20年。はて? 20年かけてようやくドングリをつけるようになる樹木が、どうやって年間50メートルも移動するのだろうか? いや、100メートル以上移動しなければ、現在のように照葉樹林が広まらない。
考えられる説が「鳥」である。ドングリを食べる鳥には、ハト、キジ、カラスがいる。これらがドングリを食べるのだが、柔らかい部分は消化されるが、固い部分である「種」は残り続けることになる。
樹木の種ばかりじゃない。鳥はトウモロコシ、ソバ、その他の種を胃の中に入れて運ぶ。当然だが、胃の中に入ると、やがて消化され、消滅されてしまう。しかしキジやハトや天敵であるタカやハヤブサに襲われることがあった。タカやハヤブサはキジやハトの肉を食べるが、内臓には手を付けない。内臓の中には、未消化の種が残っている。やがてキジやハトの死骸から、その死骸を養分とする形で種が芽を出し始める。こうやって樹木は年間50メートルや100メートル近く北進していったと考えられる。
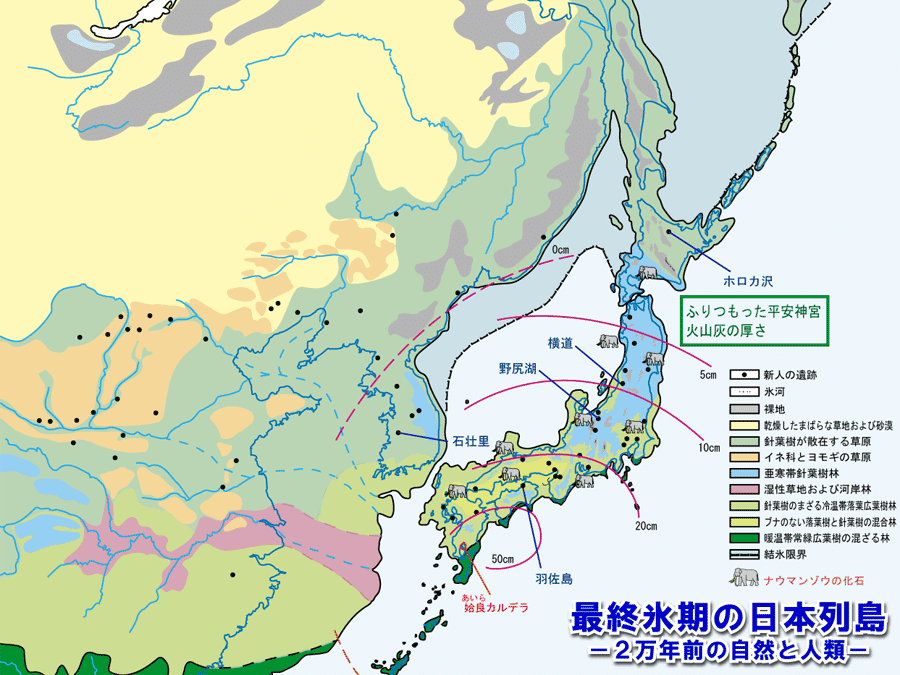
日本に照葉樹林が入ってきたのは今から1万年とすこし前辺りからだが、この頃から日本では「縄文文化」が栄え始めるようになる。日本人は照葉樹林とともに日本へと入ってきたのだ。
その頃の縄文人はたぶん、積極的に森林に火を点けていただろう。なぜならシカやイノシシは、深い森の中よりも、山火事跡の草原や二次林の中のほうが食べ物となる植物が豊富にあるので、より狩猟がやりやすくなるからである。
中国東北部の狩猟民であるツングース系のオロチョン族は、しばしば意図的に山火事を起こすことがあった。山火事の後にはノロジカが火事の後に姿を現すようになり、森の中よりも狩猟が楽になるからだった。ノロジカのほうも火事が起きた後のほうが自分の食べ物を探しやすかったから、姿を現すことが多かった。縄文人も同じようにしたであろう。
最終氷期以降、照葉樹林が北上し日本列島に入っていき、縄文人がそれを破壊する。これを繰り返していたから、日本列島全体にビッシリ照葉樹林に覆われていた時代はなかっただろう。おそらくは鬱蒼とした森林と、その焼け跡の草地、二次林といったものが混在していた。そうした中で縄文人達が過ごしていたのだと考えられる。
「米」の変遷
硬葉樹林地帯の主食がムギであるなら、東アジアや照葉樹林帯の主食はイネである。このイネに対し「稲」という字を当てているが、旧字では「稻」であった。この「稻」は古来、なにを現していたのだろうか?
中国の本草学で、明代の李時珍の集大成と呼ばれる『本草綱目』(ほんぞうこうもく)を見てみよう。
(李時珍(りじちん) 1518年~1593年 『本草綱目』は1578年に脱稿、死後の1596年に南京で上梓された。李時珍が26年の歳月をかけ、700の文献を調査し、1900の薬物について記載した本である)
『本草綱目』の穀部22巻にイネにあたるものが「稻(ト)」、「粳(カウ)」、「秈(セン)」の3つが記載されている。本草学では稻は糯(モチ)とするのが正式だったようだ。粳はウルチといい、これが日本でいうところのコメであった。秈はジャポニカ型ではないイネの総称のようだ。
つまり稻という文字が示していたのは、もともと「モチイネ」だったようだ。稻がもともとモチイネを示していた、というのは字の成り立ちからも推測できる。偏である「禾」は穀類が穂を持って立っている象形、つくりの上部分は「爪」であるが、これは掌を示している。その下は「臼」。稻は臼の中に手を突っ込んで作る穀物を示している。つまり、日本でいうところの「餅」のことである。だから「稻」という字が示すのは、餅を作る穀物、すなわち糯のことである。
漢代(紀元前206~紀元後220)の頃、洛陽ではモチゴメを蒸して食べる、つまり「オコワ」が米食の標準となっていた。
中国王朝が後漢(25年~220年)から隋(581年~618年)に変換されるまでの期間、北方民族が中国に侵入し、多数の小国家が興亡していた。隋の煬帝(ようだい 在位は604~618年)が大運河を作り、江南の米を大量に華北へ運んだときには、その米はウルチになっていたとされる。こうして中国では米の種類転換が起こった。
秈はその後、ベトナムから輸入されている。中心品種は占城種(チャンパ)という。これは小粒で味は悪いとされるが、非常に早生で、不作に備えた品種として採用されていた。チャンパは日本にも伝来し、「たいとうごめ」という名前で栽培された記録はあるが、現在では途絶えている。
中国では秈の栽培がずっと続いていた。1911年の辛亥革命により中華民国が誕生した頃、江南では食糧増産のために稲二期作と麦1作の1年3回作の農業政策が採用され、早生である秈が主作となった。秈は1940年頃まで中国で主流だった。
こうして見ると、中国では稲から粳へ、粳から秈へと2回にわたる大転換があったというわけだ。食味の見地で見ると、粘りのあるモチからウルチへ、そこからパラパラとした米へと移り変わった。一方の日本では、粘りのあるウルチが主流とする独自の進化を進んで行く。
日本では縄文から弥生にかけて大量の土器の蒸器が出土しており、古代では米を蒸して常食していたと推測される。
奈良朝(710~784年)、平安朝(784~1185年)といった時代になると、モチゴメを蒸した強飯(コワイイ)が正式の食事だった。この時代からウルチの固粥(カタカユ)、別名「姫飯(ヒメイイ)」と呼ばれるものがあった。鎌倉時代からこの姫飯が普及していき、これが現代の私たちが食べている「ご飯」となる。モチゴメの強飯は、「オコワ」として儀式用に残っていった。
日本で定着したのは、粳の中でももっとも粘りのある品種であった。
本の感想
本書の紹介はここまで。「照葉樹林文化論」を生み出した中尾佐助先生の著作だが、本書はかっちりした学術書ではなく、半分くらい旅行記という性質を持っているので、ややまとまりがなく、とりとめのない話が続く。
今回まとめたのは、本の中間あたり、中尾佐助先生が「照葉樹林帯」の構想を思いつく切っ掛けとなったヒマラヤ探検隊のエピソード。次に最終氷期後の照葉樹林がどのように北進したか。氷河期の頃は日本のような森林はインドネシアあたりにあっただったが、その後温暖化していき、インドネシアは熱帯雨林へと植生が変わっていき、照葉樹林帯は北へと移動していく。花粉分析法によれば照葉樹林は年間50メートル以上移動したということになっている。1万年前の森は自分の足で動いたのか……みたいな空想をしてしまうが、そうではなく野生の鳥(ハト、キジ、カラス)が種をついばんで運んでいった。
3つ目には日本人には切っても切り離せない「米」に関する話を持ってきた。日本で食されている「ご飯」というのは本来「姫飯(ヒメイイ)」といい、分類としては「固粥」であり、これは鎌倉時代から広まったもの。日本に米が入ってきたのは縄文後期から弥生初期頃とされているが、その頃から食べられてきたのは強飯。モチゴメを蒸したものを食べていた。
一方の中国で食されている「ご飯」は同じく稲であっても別モノ。本文中ではベトナム原産の「秈(チャンパ)」を取り上げたが、これはたぶん、元になった本が出版された時期が関係しているのだろう。ネットで確認してみると、中国でチャンパ米が盛んに生産されたのは1920~1940年代頃のことで、現在の中国ではジャスミン米、粳米が中心となっている。ジャスミン米は長粒種でインディカ米。タイ、カンボジア、ラオス、ベトナムなどで生産されている。日本ではずっと同じタイプの米が好まれているが、中国はその後も変遷があるようだ。
ではどうして稲が東アジアの社会に広まっていったのか? それは何度でも連作可能な作物だからだ。小麦ではこういうわけにはいかない。それに蛋白価も高い。
人口を増やすためには食糧事情の解決が必須だが、稲作のほうが都合が良かった。事実、稲作を採り入れた民族は次第に生活のレベルが上がっていったという。
本書のタイトルに『現代文明2つの源流』とあるが、そのもう1つの文明が地中海を中心に広まった「硬葉樹林帯」。古代エジプト、古代メソポタミアといった「古代オリエンタル文化」が生まれた地域を本書では「豊かな半月弧」と呼んでいる。現在でいうとシリア、イラクといった地域で、砂漠のイメージのあるこのあたりの地域はもともとは豊かな森であった。その豊かな森を背景に、栄華を誇ったメソポタミア文明を紀元前3000年頃に築き上げ、そして自然を消費し尽くすと同時に衰退していった。

要するにヒマラヤ山脈という大きな障壁を境界にして、西と東に文化観が分かれた。東側文化では稲に出会ったように、西側文化では麦と出会い、文明を築いていく。
しかし西側文化で最初から麦、小麦が食生活の中心だったというわけではなく、古代ギリシアや古代ローマ時代でこれらの地位は低かった。小麦を粥のようにして食べていたが、これは上手いものではなく、食卓の主役になり得なかった。
そんなローマに焼いた「パン」なるものが登場したのが紀元47年頃。この頃、パンを売る店がローマに登場し、広まっていったと記録される。ただパンの製法については古代エジプトにもすでにあったので、そのあたりから入ってきたのだろう。
人口を増やすためには食糧問題を解決せねばならず、軍事力を増強するためにも食料は重要な要素となる。パンを獲得したことによってローマは力をつけたし、遠くへ遠征もできるようになり、次第に一大帝国を築き上げるようになる。
しかし西洋においては、食の中心はどちらかといえば果樹だった。聖書にはブドウが193回、イチジクが52回、アマが47回、小麦らしきものが40回、オリーブが40回登場してくる。小麦や大麦よりも、果物類の登場回数が多い……というところから西洋の食糧事情を推測することができる。
地中海地域ではオリーブはよく食されているが、昔からそうだったわけではない。オリーブの野生種をオレアスターと呼ばれるが、これは果肉が薄く、渋みが強く、あまり食用に適さない。これがある時、野生種ではなくなり人間の手で栽培されるようになっていく。
豊かな半月弧を中心に広まっていった西側文明は、その中心地である森が完全に途絶えてしまい、文明は古代ギリシャ、古代エジプトに移り、次にローマ帝国へと伝わり、最終的にヨーロッパ全体に広まっていく。しかしその文明を築き上げた中心地の自然が途絶えてしまっているので、その起源を遡るのが難しくなっている。今では「かつてあったらしい」……というふうに語るしかないものになっている。
そういう話が本書に結構なページ数で書かれているのだけど、どうにもまとまりを感じなかったので、サクッと省略することにした。
この本で面白かったのは「金魚型文化」を語る章だった。
日本に長く定着して、世界的にも「日本的」と思われている多くは実は日本発祥ではない。その多くが実は大陸から渡ってきたものだ。
その代表格として取り上げているのが「金魚」。金魚は10世紀頃の宋王朝の頃から飼育されていたが、これを愛玩動物として定着したのは日本の方。今でこそ熱帯魚文化があるが、「魚を鑑賞物にする文化」など昔は世界中どこを探してもなかった。西側文明は早いうちに森が枯渇し、水不足にも陥ったから、この環境下では魚を鑑賞物にするなんて余裕がない。東側の照葉樹林にはたっぷりの水があったからこそ、発達した文化だった。その中でも爆発的に広まり、品種改良を推し進めていったのが日本。日本はそういう国だった。
金魚だけではなく、「花」もそう。花を愛でる文化は西側にもあり、古代エシプトの庭園を見るとスイレン、ヒナギク、ヤグルマギクなどがあり、異国の草木も植えられていた。
これがギリシャにいくと、植物を観賞する文化がなく、庭には花壇もなければ木もなかった。ただ例外はあって、「アドニスの園」と呼ばれる聖所があって、アドニスは植物の神であったから、そこは鬱蒼とした木が生えていたらしい。
ローマでも花文化はあまりなく、例えばバチカンの広場へ行っても柱が立っているばかりで木も花もない。
世界で特に注目されることもなかった草木は、日本にやって来て評価されるようになってくる。ウメ、マダケ、キンモクセイ、フヨウ、キク、スイセン……どれも日本文化になくてはならないものだが、すべて外来のもの。一応確認を取ってみたが、確かにすべて外来種だった。
植物の学名を見ると、「ジャポニカ」と名付けられているものも多いが、実は日本原産ではない……というものも多い。日本で定着し、日本で報告されたから「ジャポニカ」と呼ばれるようになった、ということだった。エンジュの学名をソホラ・ジャポニカ、ビワがエリオボトリア・ジャポニカ、ニワザクラをプルヌス・ジャポニカと呼ぶが、どれも本来は中国原産なので「チャイナ」と呼ぶべき。しかしこの件についてあまり異議を唱える人はいない。それくらいに日本で定着し、文化を深く結びつき、広まったからだった。
ついでに雑草も外来種が多い。セイタカアワダチソウ、ヒメジョン、アレチノギク、ブタクサ、セイヨウタンポポ……。どれも中国、アメリカ、ヨーロッパから入ってきたものだった。

金魚にしても花にしても、もともとになっている国では特に注目されず、雑に扱われたり途絶えてしまったものも多い。そういうものの多くは日本にやってくることで「愛でる対象」となり、一つの文化として発達していく。これを中尾佐助先生は「金魚型文化」と本の中で書いていた。
そんな話を聞くと、漫画文化もゲーム文化も同じだ。漫画ももともとはイギリス発で、明治頃、報道画家として日本にやって来たチャールズ・ワーグマンから始まって、それを日本人が面白がって継承し、そこから飛躍的な進化を遂げることとなる。ゲームも同様に、基礎を築いたのは西洋だが、日本にやって来て爆発的に進化した。日本は昔からそういう「金魚型文化」の国で、そういう性質はこれからも変わらないのだろう。
どうしてそれぞれの国が、そういう文化を持つようになったのか。どうしてそういうものを食べるようになり、その地域特有の思考方法を身につけたのか……。それは自然環境が関係してくる。背景に自然の環境があったから、それぞれの文化はその自然に沿った性格を身につけていった。
東アジアにおいては、その元素となるのが照葉樹林。照葉樹林というものがあって、東アジア的な文化や様式が生まれていった。
例えば「信仰」。日本は儀式や神事といったときにサカキやシキミといったものを使うが、なぜそういったものを使うのか……というと古来から日本にあったから(ヨーロッパではクリスマスツリーにヒイラギを飾る風習があるが、これはキリスト教由来のものではなく、ゲルマン由来のものではないだろうか。本来のキリスト教文化圏には、植物を祭に使う風習はない)。こういう古来から自然世界にあったもののなかから宗教は生まれる。その宗教を軸に文化観が生まれてくる。稲作があったから、稲作を祀る者として天皇家が出てくる。昔からあるものは、そういう自然との関わりを根拠に生まれてきたものだった。
西洋文化は自然を破壊して最後には文明も自滅していく……という運命を辿っていくが、しかし日本はそうならなかった。それはおそらく自然を信仰と文化の発信地としたから。森を「鎮守の森」として手を付けずに保護したから。この考え方が長くあったから、日本は今も自然の豊かさを守ってこられたのだろう。
最近、特殊な日本語として注目を集めたのが「もったいない」。これは日本に可住面積が少なく、「捨てる余地がなかったから」考え出されたものだった。
一方、広大な砂漠地帯を持つエジプトになるとどうなるのだろうか。エジプトでは壊れて使われなくなった車や家電や航空機といったものを、砂漠に捨ててしまう。街から離れて無限にあるように思える砂漠地帯へ行くと、使用済みになった車や家電や航空機が山ほど捨ててあるという。その感覚が古代エジプトの頃から当たり前だから、「リサイクルする」という発想が生まれない。こういう自然環境の中では「もったいない」という感覚が生まれないのは、当たり前の話だった。
人間は自分の自由意志で考えて答えをだしている……というつもりだが、実際には環境に大きく影響されている。なぜ自分がそのように考えたのか、自分の思考や文化の元素を考えてみると、自ずと「自然」が出てくる。日本の場合は照葉樹林。照葉樹林が私たちの元素だった……ということが自然を調べることで見えてくるのだった。
ところが、最近は自分の出自を考えず、本当に「頭」だけで考えて、奇妙な理想論を唱える人々が増えてしまった。
このブログの中でも触れたように、明治神宮の森は日本本来の植生を今に伝える貴重な森だ。この森を一部破壊し、ソーラーパネルを作ろう……という計画があると聞いた。森を破壊し、ソーラーパネルを作ることで、「持続可能なエネルギーは素晴らしい」……なんてバカなことを言っている。こんなバカな計画を、「環境に関心を持った進歩的な人々」が考えている。しかもそういう人ほど、普通の人よりも教養高いエリート達であるという。
環境活動家ほど、「環境」を理解していない。彼らは日本の森林信仰が森を守ってきたことを知らない。「現実」を喪失させ、「頭」だけで物事を考え、結論を出す人が増えた結果だ。偏差値が高い人間ほどバカになっている。理想を唱える前に、現実を見て、自分たちがどういう世界の上に暮らしているのか……その原典をいま一度考えてもよいのではないか。
この記事が参加している募集
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
