
数寄者どもが夢の跡~『パリの音楽サロン』に寄せて~
今月の岩波新書・新刊に、青柳いづみこ(著)『パリの音楽サロン――ベルエポックから狂乱の時代まで』があり、早速購入した。
聞きなれない人名も少なくないだろうが、新書らしくまとめられており、各サロンでの重要人物を起点に、様々な出来事が物語られる。
往々にして、有名な作曲家などについては、音楽史・時代の流れとして「縦の繋がり」を見聞きしがちだ。モーツァルトが神童と呼ばれ、ベートーヴェンは楽聖であり、ハイドンの弟子である云々。
だが、本書では19~20世紀の音楽家の「横の繋がり」、すなわち交流や恋愛、意欲を取り扱っているため、意外と知らなかった関係が見えてくる。
そして、その横の繋がりを捉える軸こそ、「(音楽)サロン」なのである。
以前から、僕は文芸サロンへ強い関心と憧れを持っている。
それは今日のオンラインサロンのような、時として宗教じみたものではなく、むしろ、宗教的な権威から脱した、前衛と貴族的保守の入り混じった「創作のるつぼ」なのであった。
上記の記事でも取り上げたが、サロンと音楽を分かりやすく紹介した新書に、新潮新書・浦久俊彦(著)『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』がある。
これを参考図書とすることと、もう一つ、「楽聖ショパン」という1945年のアメリカ映画を強く推薦したい。これらによって、ショパンらを中心に、その時代を精神的に体験できるとさえ言いたくなる。

フィルムポスター(Wikipedia・英より)
もともと僕は、クラシック音楽が好きなのだが、ショパンはさほど関心が無かったのだが、とある出来事から、ショパンを少しずつ聞き始め、この映画を観てからは、代表曲でもあるポロネーズ「英雄」が大好きになった。
伝記映画なので、当然ながら、ショパンとリストとの交友や、ジョルジュ・サンドとサロンで出逢い、彼女との日々が描かれている。
ショパンはその繊細な音楽から、楽団ではなく、サンドの勧めもあって、サロンでの活躍へと長らくシフトしていったのだった。
リストは別だが、僕はどうやらショパンだけでなく、多くのピアニストに、それ以前のウィーンなどの作曲家とは違って、さほど関心を持てなかったようだ。
例えば、本書でも一章あてられているドビュッシー。勿論、曲の素晴らしさは言うまでもないが、さりとて、人物そのものへの興味やCDなどで何度も聞いた経験はこれまで無い。
正確ではないものの、あえて個人的な概観を述べてみる。
音楽の都ウィーンで、各音楽家が群雄割拠していた時代。それは、ある者は宮廷楽団におり、ある者は貴族をパトロンとしてはいるが、自律的でもあった。これがあえて冒頭と結びつけるならば、縦の時代だ。
一方、サロン文化が花開く、フランス、そして東欧からのピアニスト誕生の時代。ここでは、サロンの女主人を基点に、各界の知識人・文化人が集い、ひとつの文化潮流を形作っていく。
これは横の時代であるとともに、偉人的英雄視ではなく、美的個性の世界とも言えるのではないか。
つまり、悪癖までもが偉人たらしめていた孤高の時代から、美への関心は当然あるものとして、その上で、どういった作品を遺したかという個性にようやっと着目される、極めて現代に近い感覚・視野で顧みられる時代なのだ。
それでも、サロンは時代を経るごとに、様々な在り方・活躍を示してきた。それが創作の場であったからだ。
だが、ピアニストが職業化し、かつ、詩人が衰退するともに、文芸サロンもまた影を薄くし、創作から消費へと移行していったのではないか。
事実、今日「文化人」と呼ばれる人々の素性は案外、傍からみても分からず、消費行為が推し活という免罪符を得てからは、「趣味人(≒ディレッタント)」なる存在もあまり意味をなさなくなった。
それをして、かつてより僕は「数寄者どもが夢の跡」という標語を抱いているのだ。
数寄者(すきしゃ)は、芸道に執心な人物の俗称。「数奇者」(すきもの)と書く場合もある。現代では、本業とは別に茶の湯に熱心な人物、特に名物級の茶道具を所有する人物として用いられる。
わが国におけるサロン的な雰囲気は、もしかすると平安宮廷から出でてはいるが、江戸期の読書会や近現代の左翼における勉強会と融合し、時代の移り目と一緒に潰えたのではあるまいか。
「おたく」の登場により、また新たな形態でサロン的な関係が復活したかに見えたが、繰り返すように、二次創作から、徹底消費的鑑賞となったことで、サロンからの分化と捉えねばならないし、かつまた、もはや個々人で消費することから、横の繋がりはネットというシステムに変化がないだけで、もはや、コミュニティとしての帰属意識は薄れているだろう。
さればこそ、オンラインサロンとして、中央分散型の関係となっているのである。『パリの音楽サロン』を読めば分かるように、参加者は芸術家であり、貴族女主人自らも、ピアノなどの名手であった。
今は、主催者のみが重要であって、参加者はそのまま、参加料を払って交流権を得る消費者であるに過ぎない。
これは単純に、量より質を意識した貴族的世界から、ブルジョワ階級、そして市民社会化した上で、質より、とは言わないまでも量を欲してきた、この大量消費社会の黄昏に生きる者の宿痾なのだろう。
かつて僕は、サークルなどには入らないとnoteに書いた。だが、サロン文化の復興は、少なくともまずは自身のnoteやカクヨムでの創作に注力することで、いずれは発信が、相互関係を生み出すこともあるのではないか。
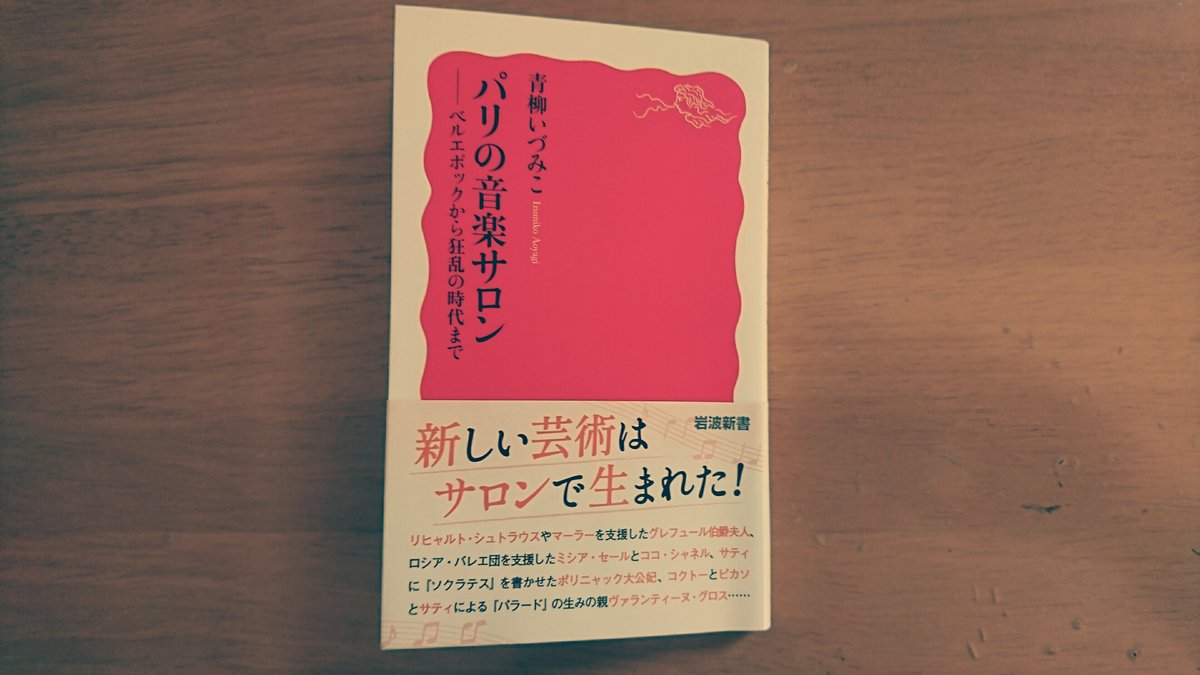
若く、無名でお金のない芸術家が世に出る手段は、そう多くはない。21世紀のこんにちでは、それがショパン・コンクールだったりチャイコフスキー・コンクールだったりするわけだが、19世紀は貴族やブルジョワのサロンがその役目を果たしていた。‥‥サロンでデビューしなければ、文壇・楽壇の大立者や文芸の庇護者に出会うこともできなかった。
最後になるが、本書のオビには大きくこう書かれている。
「新しい芸術はサロンで生まれた!」
ならば当然、問われて然るべきだろう、サロンを失った今日、新しい芸術はどこで生まれるのか、と。そう、数寄者どもが夢の跡なのだ。
いいなと思ったら応援しよう!

