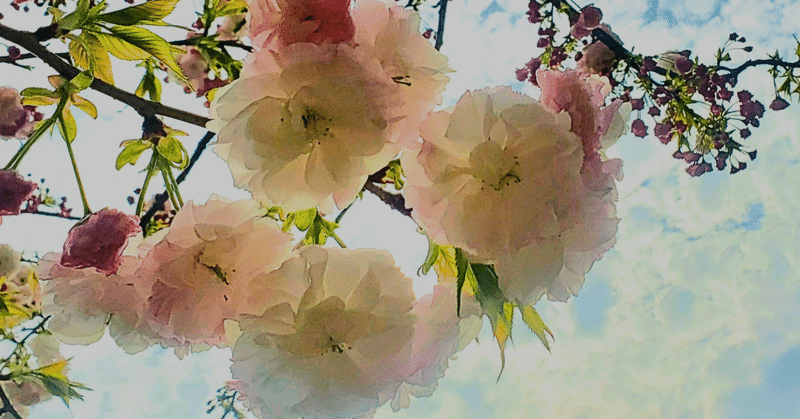
【小説】同じ空の保田(やすだ)さん 34
人生、何があるのかわからない。明日、いや、今この次の瞬間すら。だからこそ、人は今を精一杯生きるべきだ。
今あることと、それに向き合ったことの積み重ねの末に、命尽きるまでの道が出来上がってゆく。
何かの偶然が重なっても、実はそこに意味なんて無い。
あるとしたら、願望とこじつけた、後付けの解釈だ。
ただ、その偶然も含めて、歩き続けたから、今ここに立っている。
だから、その偶然達は、何一つ欠かすことのできない大切なもの。
そして、ふと、立っている今の場所に何も不満がないと気づければ、それで充分なのだ。
弁護士事務所で働くことになるなんて、夢にも思っていなかった。
雇うから事務所の事務員さんとして働いてほしい、と彼から告げられた時、どんな仕事をするのかよくわからない、とちょっと尻込みした。
すると、大手企業で普通に何十年も働けていたのだから何も問題はない、と彼は屈託なく笑った。
「 先生、準備書面のチェックしました。もう相手の先生に提出してもよろしいですか?」
わたしの弁護士先生に声をかけると、彼は、あぁ、お願いします…と呟きながら、向かっていたPCから眼鏡を外して目を擦った。昨日も夜遅くまで裁判記録のコピーを読み込んでいたらしい。
「 …………コーヒーでも入れましょうか 」
わたしは、事務所の備え付けのミニキッチンで、湯沸かしポットの電源を入れる。
「 ……梢さん 」
先生が、わたしの背中に声をかける。
「 今年の誕生日、その日の昼間にランチでもして一緒にお祝いしようよ 」
***
退職したら、平日の朝に起きて最初に頭に浮かぶ、『 今日も仕事か 』というネガティブ思考はなくなった。
その代わり、今日は何をしようかな、と自分の心に相談しながらやりたいことに思いを巡らす。
今日はあの友達に連絡してみようかな、とか。
気になる映画を観に行こう、とか。
とぴ君が昔出ていた映画の撮影場所の喫茶店が隣駅にあることがわかったから行かなくちゃ、とか。
スポーツジムに入りたいからちょっと会費を調べてみよう、とか。
ずっと気になっていた一眼レフも欲しいな、とか。
瑞季の高校生活が落ち着いて、予定が立てやすくなったら今度こそ旅行に行こう、とか。
起き上ると、必ず朝の空気を吸いにベランダに出る。
雨は大嫌いだったけれど、それは通勤で濡れるのが嫌なだけだった。
雲から透ける微かな日差しで銀色に光る細い雨を見ていると、『 浄化の雨 』『 恵みの雨 』という言葉が思い浮かぶ。
──── なんだか、いい事が始まりそう、流れとか運気ってこういうことかな。
わたしは無職だけど、とりあえず食べるのに困るほどお金に苦労しているわけじゃない。
うんざりする仕事から解放されて、もやもやも苛立ちもなくなって、周囲にいる家族にも、ちょっと優しくできるようになった気がする。
といっても、貯金を食いつぶす訳にもいかないから、ある程度は計画的に。そのための、資産管理の勉強も多少しようか。
資格講座も受講してみたいな、次はどんな仕事に就けるのだろう。
もう45なのだと思いつつ、いや、まだ45なのだから、きっとやりたいことが見つかるはずと自分を励ます。
それまで焦らず、しばらくのんびり過ごしてみよう。
空を見上げては、保田さんのことを思い出す。
その辺で暮らしているはずの彼は、きっと今日も青砥の駅から日本橋まで通勤している。もしも偶然彼に会った時に、恥ずかしくないように生きていたい。
………通勤をやめて動かなくなったら、ちょっと太ってしまった。既に恥ずかしいじゃん、痩せないと。
とりあえずは、朝日が昇り、夕方になれば日が暮れて、刻々と闇に色が満ちて。
それがまた、やがては東の空から黄金の日が射し、それに照らされる闇夜は透明感のある青さを徐々に取り戻してゆく。
毎朝の空の色を確認しながら、つらつらと色々なことを考える穏やかな時間のある日々。
──── とりあえずは、こんな時間が自然と続くものだと信じてた。
***
退社した年の、6月9日のこと。
母の定期通院に、珍らしく姉が付きそうと自分から申し出た。
姉は車の運転免許がないので、タクシーで行くという。
それこそ、仕事をしていないわたしが自分の車で送迎してもよかったのだけど、「 いつも梢ばかりじゃ大変だから 」とやけに乗り気で役目を引き受けたがっている。
わたしのいないところで、母にお金の工面の相談でもする気なのだろうか。
わからないけれど、まあ好きにしたらいい。
それなら、と姉にまかせることにした。
午前10時に家を出て病院に向かった二人は、予定どおりには帰宅できなかった。
帰り道に乗車したタクシーに、対向車線から後期高齢者の男性が運転する車がいきなり突っ込んできて、一瞬のうちに二人とも命を落としてしまった。
タクシーの運転手さんも一緒に。
わたしが連絡を受けたのは、母の通院先ではなく、別の救急病院だった。
二人の遺体の顔だけわかるように見せられて、間違いないと茫然と答えた。
わたしが瑞季の学校の連絡を入れ、早退してきたあの子も二人と対面した。
おかあさん、と一言つぶやくと、瑞希は一気に崩れこみ、声をあげて泣き続けた。やっぱり、なんだかんだで、子供は母が一番好きなのだ。
瑞季の様子を見ていたら、わたしも溢れる涙が止まらなかった。けれど、いつまでも泣いてはいられない。
身内の死から葬儀が終わるまで、それが近しい関係ほど泣く暇もないというか。病院が次から次へと、申し訳なさそうにくぐもった声で、でも事務的なことを次から次へと告げてくる。
父が亡くなった時も、そんな感じだった。
葬儀屋は、父のお葬式をお願いしたところがあるから、そこに連絡をして、………誰に訃報を伝えるべきなのか……静岡の清水で暮らす母の伯父にはとりあえず連絡しなければ。
……と考えながら、独りで廊下の待合の椅子に座っている時だった。
視界に、黒っぽいスーツのズボンと、綺麗に磨かれたこげ茶色の革靴が目に入る。
そして、そのスーツ姿の男性が
「 あの、………奥井様のお嬢様でしょうか? 」
と、母の名字を告げながら声をかけてきた。
彼は、母と姉が乗っていたタクシーの運転手さんの息子だと名乗った。
それを聞き、わたしは立ち上がって、頭を下げた。
しかし、それ以上、何を言葉を交わせばいいかわからない。
「 もしかしたら不要なことかもしれませんが………、一度にお母様とお姉様を亡くされたと伺いました。これから、色々と大変だと思います、加害者の方とのお話もありますし 」
「 加害者? 」
「 事故の原因となった運転をした方です 」
ああ、そうか。
ハンドル操作を誤って対向車線から母と姉が乗るタクシーに突っ込んできた高齢者の男性が『 加害者 』。
こちらは『 被害者 』なのか、と疲れた頭でぼんやり理解する。
黙っていると、彼の方が名刺を取り出して、裏面に何かを書き込み、
「 僕でよければ、お力になります。いつでも連絡してください。表は事務所の方の番号です。この番号が僕の個人の連絡先ですから。どちらでも構いません 」
と、裏側のままの名刺をわたしに差し出した。
そこでわたしは、初めて顔をちゃんと上げて彼の顔を見た。
…………背が高い。
斉木さんと同じ、180センチ近くありそうで。
30代……半ば、といったところだろうか。
少し短めの髪を、整髪料できちんと整えて。
少しだけ日焼けしていて、いかにも学生時代何かスポーツやってました、みたいな体格で、スーツの肩幅がしっかりと張っている。
誠実そうで人のよさそうな、好感の持てる顔と言えばいいのだろうか。
ものすごいイケメン、とは違うけれど、少し太目の眉毛がすっと伸びて、芯が真っ直ぐな瞳をこちらに向けている。
真摯で信用できる人だ、と直感した。
自分も『 被害者 』の遺族なのに、事態に戸惑う様子もなく、随分と毅然としている。
わたしは、受け取った名刺をひっくり返した。
『 弁護士 寺崎善哉 』と印刷されている。
「………弁護士…さん、なんですか?」
「 はい、寺崎善哉と申します 」
こんな場なので、彼はものすごく愛想よく笑ったのではない。
けれど、仕事柄なのか、わたしが安心するような、頼りたくなる力強さを持った笑顔を見せた。
───── これが、善ちゃんとの出会いだった。
***
母と姉の事故をきっかけに、善ちゃんと連絡を取るようになった。
姉が亡くなった時、わたしは瑞季が望むなら一緒に暮らし続けようと心に決めていた。
そして、瑞希も、実の父親の方へ行くとよりも、青砥でこのまま暮らしたいと言った。
そんなわたし達を、善ちゃんはとにかく気にかけてくれた。
善ちゃんが言ったように、お葬式をする以上に、外のことが本当に大変でしんどかった。
運良く、というべきなのか、軽傷で済んだ加害者の80歳の男性は、わたしと瑞季と善ちゃんの前で、見ていられないくらい号泣しながら土下座していた。そんな人から賠償金を払ってもらう気持ちにはなれない。けれど、わたしはともかく、まだ未成年者の瑞季はこの方の不注意で母親を失ったのだ。結局、この方との交渉は、全部善ちゃんに委ねてしまった。
親権者がいなくなってしまった瑞季のための、後見人というものを選ぶ手続をする必要があった。
瑞季の養育費を払っているはずの実父にも連絡を入れなければならない。
そして、わずかばかりだけど、母と姉のそれぞれの財産の相続の手続。
──── とにかく、煩わしくわからないことばかりで、わたし一人では絶対に抱えきれなかった。
それを、すべて弁護士をやってる善ちゃんが一緒に、時には表に立ってこなしてくれた。
もちろん、大事なことを決定するのは、わたしの判断や瑞季の意見によるものだ。けれど、やらなければならないことをわかりやすく説明してくれて、書類は署名だけ書き込めばいいように手筈を整えてくれたのは、善ちゃんだった。
彼が弁護士さんで本当に良かった。
一人で一気に不幸のどん底に落ちた気がしたけれど、その中で善ちゃんの存在はまさに神様だった。
しかも、彼は不思議な居心地をくれる人。
話しやすくて。
話のテンポも、笑うタイミングもわたしと何となく同じで。
千葉の方の出身の人で、兄弟はいない。お母様は、彼が大学生の時に病で亡くなったとのこと。
お父様は、善ちゃんが幼い頃からずっとタクシーの運転手さんをしていたそうだ。亡くなったわたしの父の晩年と同業だ。
30代半ばくらいだと思っていたら、わたしよりたった二歳年下の男だった。
「 独身で好き勝手に暮らしているから、若く見えるのかもね 」と年齢を明かしながら善ちゃんは笑った。その顔は、わたしが親しくしてきた人達の中にはいなかった部類。いかにも爽やかなスポーツマン、みたいな眩しさみたいなものがあって、彼と出会った頃のわたしは辟易することが多かった。
彼は荻窪に住んでいるのに、何か手続の打ち合わせをする必要があると、青砥までわざわざ会いに来てくれた。
色々な手続を手伝ってくれる中で、二人で会ったり、瑞季も含めた三人でご飯を食べたりする時間が増えていった。
世の中のことに詳しくないと仕事柄生き残れないと言う彼は、最先端のものに詳しかった。
そのお陰か、イマドキの若い子にも理解があり、瑞季ともすぐにうち溶けた。お互い茶化しながらよく喋る。瑞季に言わせると『 学校の体育教師にありがちな、友達感覚で話せる人 』らしい。
元野球部だという彼の誘いで、気分転換に夏の夜のナイター観戦に出かけた。瑞季も一緒に三人で。
すると、瑞季が一番ハマってしまった。初めて生で見た試合でホームランを連発した四番バッターに惚れてしまったのだ。
推しができた瑞季は、高校生女子なのに野暮ったいな……とわたしが内心思っていたような見た目から一転した。
「 『 こんな地味な子がファンなのか 』と他の人達に思われたら、推しに恥ずかしい思いをさせてしまう。だから絶対に綺麗になって毎年スタジアムに通う」と宣言した。
SNSのフォロワーがうん十万単位のプロ野球選手が、瑞季一人のことで恥ずかしい思いをする事態なんて絶対になさそうなのに、毎日朝晩ジョギングをし、家の中で筋トレもし、朝晩は豆腐とキムチしか食べないという彼女の愛と熱意はすさまじかった。
そして、本当に痩せて可愛らしくなったのだ。
わたしもなんだか浮かれてしまい、野球の応援グッズを瑞希に買ってあげたり、ちょっとした流行りのメイクを一緒になって楽しんだ。
そして、そんな瑞季に同じ学校の同級生の彼氏ができた。プロ野球の話で意気投合したらしい。
彼と遊びに出かけるという土日に、あんまり遅くなるんじゃないのよ、と母親のように声をかけつつ、不要な傷のつかない程度に、今の幸せをめいいっぱい楽しんでほしい、とわたしは心から願った。
***
煩わしい諸手続が終わってひと段落したら、紅葉が舞い落ちる季節になっていた。
色々な事が片付けば、必要以上に善ちゃんと会うこともなくなるのだろうと思っていた。
でも、彼はその後も、週に一度は瑞季と二人で暮らしているわたしに連絡をしてくれて、なんだかんだで会う機会は続いていた。
『 被害者遺族 』という言葉で繋がった、同志にすぎないと思っていた。
けれど、彼と過ごす時間は、穏やかで安心できて、素直でありのままのわたしでいられる、かけがえのないものになっていた。
一緒に映画に行けば、わたしよりも彼の方が泣いたり笑ったりして楽しんだ。
スキーに関しては、インストラクター資格者だった。
外食したら、どんなお店でも必ず何かしら一品は「 すげぇウマイ! 」と言って、一緒に食事をしているとどことなく楽しくなる人だった。
…………ふと気が付けば、保田さんどころではない日常になっていた。
そのことに気づいたのは、カレンダーを見て12月の自分の誕生日を意識した時。
保田さんも、弁護士になりたいような話を退社の日に次長がしていた。
司法試験、受かったのかな……とぼんやり思った。
そして、それ以上の感情が浮かばなかった。
あんなに、保田さんがどうしたこうしたと昨年の春から今年の春先まで考えていたのに。
あまりに色々なことがありすぎて、それまでのわたしが上書きされてしまったようで。
それに、退社した以降、近所で偶然保田さんに会うことはまったくなかった。
一年くらい前に保田さんの車に乗ったあのことも、振り返れば心を穏やかにしてくれる記憶の一つになってしまっていた。
今のわたしが彼に会ったら、どんな感情に陥るのだろう?
***
波乱ともいえる年が明けると、4月になったら青砥に事務所を移すつもりだと善ちゃんから告げられた。
一緒に荻窪で事務所をやっている弁護士さんが、実家のある京都へ戻ることになったそうだ。
他の事務所に入れてもらうのも面倒だし、一人でやるならどこでもいい。青砥が結構気に入ったし、都心より断然家賃が安いから、と善ちゃんは話した。
そして、少し照れ臭そうに、「 ……梢さんを雇うから、俺の事務所の事務員さんとして働いてくれないかな? 」とわたしに打診してきた。
「 弁護士事務所なんて、どんな仕事をするのかよくわからないんだけど 」とちょっと尻込みした。
すると、彼は、「 大手企業で普通に何十年も働けていたんだから、何も問題ないよ 」と屈託なく笑った。
その笑顔も、出会った頃と比べてすっかり見慣れた。むしろ、今ではわたしを嬉しくさせてくれるもの。
***
善ちゃんが本当に青砥に事務所を構えて、わたしは本当にそこで働き始めた。
事務所は、わたしの家から3分程度。駅までの一本道の途中にある。
電話番、書類の郵送、メールチェックや添付ファイルの保存、善ちゃんが作った書面の誤字脱字の最終チェック、領収証の管理、お客さんへのお茶出し、事務所のお掃除、など。そして、たまに郵便局や裁判所や登記所にお使いに行く。
うちの近所で、朝の9時半から夕方の4時半まで、そんなことをして過ごす。それで、善ちゃんからお給料をもらう。
毎日じゃなくてもいいと善ちゃんが言うので、週4日。わたしには、本当にちょうどいい働き方だ。
仕事中は善ちゃんを「先生」と呼ぶ。
善ちゃんは、別にそんな堅苦しい言い方をしてくれるなと苦笑いしているけど、仕事に関しては慣れ合いは何となく不真面目になりそうだし、何よりも、善ちゃんと彼のお仕事に敬意を示したいから、そう呼ぼうと自分で決めた。
母と姉の事で本当に助けてもらったうえに、お仕事までくれた彼を、天から降って来たギフトのように感じた。
だから、感謝して大切にしようと思ったのだった。
そんなふうに働きながら、瑞季のご飯を作って家も掃除して、お休みの日には好きな花を買ってきていけたりして、寝る前にとぴ君を見るのは相変わらずで。
………あの会社を辞めて一年ちょっとで、そんな生活になっているなんて、あの頃は夢にも思わなかった。
そして、特別に不満はなく、今以上のことを特に望んでいなかった。
そんな状態を、『 しあわせ 』と呼ぶのかもしれない。
***
「 今年の誕生日、その日の昼間にランチでもして一緒にお祝いしようよ 」
そう言うと、善ちゃんは、外したメガネを放り投げる。
「 あー、やっぱり邪魔だな、ブルーライトカットの眼鏡なんて。
……あ、悪い。そうそう、誕生日のランチ、どっか予約しておくよ。何か食いたいものある? 」
善ちゃんはネットをいじり始めた。さっそくお店を探しているらしい。視力のいい彼は、メガネもコンタクトもせず、いつも裸眼だ。
「 ……わたしの誕生日、12月ですよ?
まだまだ先の話じゃないですか 」
「 知ってるよ。でも早めに決めとこうと思って。去年は俺が地方に出張だったから、今年はその日何も予定入れないようにするし 」
「 ……それは嬉しいんですけど、先生、お仕事進んでます? 」
彼は壁掛け時計をチラッと見る。
「 ああ、もうお昼じゃん、お昼休みね。はい、休憩休憩 」
部活動を適当にさぼろうとする学生みたいなノリだ。
それでも、世の中の平均的なサラリーマンよりも断然多い金額をひと月に稼ぐ。純粋な利益は、平均すると毎月100万近く。
弁護士は、法人事務所でない限りは自営業だ。
それなりには、休みや眠る時間をさいて、記録を読んだり書面を作ったり調べものをしているけど、いつ働いていつ休むか、予定を立てる裁量もある程度は持っている。
大手の事務所の弁護士と比べたら雀の涙、って善ちゃんは言っている。でも、自力の収入がこんなにあるなんて。
傍にいればいるほど、組織に触れ回されるのではなく、自分の頭脳と知識と人脈を巧く使って稼ぐ彼を、ただただ凄いと思うようになった。
そして、頭脳を使うのは疲れるし組織に振り回されたくもないわたしは、こうした特定の人のために、指示されたことの範囲でマイペースに考えながら働くことがむいているのだと身に染みていた。
誕生日か、わたし、47になるのか……いつまで善ちゃんはわたしを雇ってくれるのだろう?その気になれば、もっと若い子をいくらでも雇えるだろうから。
しいていえば、この不安定な立ち位置が、今のわたしの一番の心配事だ。
──── 気がつけば、善ちゃんがすっかり黙り込んでいる。
そして、PCの画面を見つめたまま口を開く。
「 ………梢さん 」
「 ん? 」
「 ………新着メールなんだけどさ、これ、どう思う?ちょっと画面見てよ 」
善ちゃんに促されて、彼のPCを覗き込む。
──── 画面のメールに、司法修習希望で連絡したとの依頼文言が並ぶ。
「 これ、なに? 」
「 ああ、司法試験に受かるとさ、裁判所とか弁護士事務所とかで、研修みたいなのをやるんだよ。それも、今はいろんな種類があるみたいでさ。長いのやら短いのやら………で、秋くらいに2週間ここで研修したい、ってさ。
普通はそういう修習希望者の募集出してる、もっとデカい事務所を探して連絡するんだけど 」
「 大きい事務所じゃなくてもいいの? 」
「 普通はあんまりないけど、駄目ってわけじゃないよ。ただ、勉強にはあんまりならないと思うけどな。
別に俺、一人でやってる事務所だし、修習生の面倒なんてみてられねぇし、断っていいかな? ここで修習したい理由なんて、どうせ近所で都合がいいから、ってだけみたいだし 」
わたしは、メール文を目で追ってみる。すると、末尾にある差出人………修習希望と申し出ている人の名前が目に入った。
『 第77期司法修習生 保田佳佑 』
終
(約8000文字)
※地名などは実在の場所に由来しますが、物語とは一切関係がありません。
<前話までの一部です。よろしければ> ↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
