
479.みんな~言葉ってね、心の中に描く絵なんだよ~
新シリーズ「coucouさんのお仕事論」②、478の後編。
前編、後編ともどもお願いしますね~
1.言葉は絵なんだよ
言葉って言うものは不思議なもんだね。
電車やバスに乗り、ぶら下がった広告の言葉や、街を歩けば言葉だらけだと感じるよね。
(注意して意識したら街中が文字と言葉だらけ)
本を読んだり、テレビやラジオ、又はインターネット、スマホや新聞などを眺めていると、ふとした瞬間にその言葉が目に入る時があるよね。
みんなも、わずかな短い言葉が心に引っ掛かり、思わず考えてしまう時があるよね。
その時に、今の自分の状況にピタリとあてはまる言葉と出くわす場合があるよね。
そのわずかな言葉って、一見読んでいるかのように思えるけれど、観ているはず。
活字であれば太い書体の場合、細い書体の場合、または手描き文字の場合など、言葉はその文字によって変化して観える。
だから、小説であっても、文学であっても詩であっても、広告のキャッチフレーズであったとしても、その言葉文字は〈絵〉であると思うんだ。
みんな、年賀状などは、相変わらず洗練された美しいパソコン文字で、写真や色使いなども多くの人たちはまるでプロ級の腕前。
新聞のチラシなども同じ。
有名なデザイナーやカメラマンたちがデザインをして美しいモデルさんたちを使い営業をしている。でもね、膨大な新聞折り込みチラシなど必要としなければ誰も見ないよね。
何よりも心に残らない。
これではムダ金を支払っているようなもののような気がするね。
美しく、キレイさを追求したものだけで、心に伝える事ができなった気がする。
ホームページやブログなども同じ。
パソコンをお使いの皆さまもこれから改めて見てみてはどう。
特に大切な人にはね。
2.文字なんて美しくなくてもいいんだよ
ある、知り合いの政治家なんだけれど後援組織などなかった。
スタッフなどもいない。
それでも、毎回当選する不思議な政治家がいた。
彼は印刷物など作らない。
本人はお金がないからと言う。
そのため、大量に便箋を購入して家族一同で手紙を書いた。
最初は丁寧に上手く書かれていたけれど、あまりの量の多さのため、腕や手に豆ができ、段々と雑になり下手くそな文字となった。
でもね、それでも有権者へ、一人でも多く心を伝えようと考えて書きつづた。
最終的な数は一万枚以上となったという。
あとはポスティング活動。
郵送料がかかるから、郵送はしていないと本人はいう。
街頭演説なども背中に旗を付けてマイクとスピーカーを自分で持ちながら、毎朝7時30分にたった一人で街頭演説を続ける。
選挙があるからではなく、当選後も毎朝街頭演説を続けていた。
やがて、彼には「朝7時30分の男」というあだ名が付いた。
(coucouさんもそれをマネして朝7時30前の男となった)
ポスティングの手紙内容はね、「私は○○です。無所属での候補者です。お願いします。皆さんの力を貸して下さい」〇〇家族より、長男より、娘より、妻○○よりと書かれてた。
色々な言葉のバージョンがあるけれど、文字はミミズのような下手くそな文字。
その、ミミズのはったような下手くそな文字は、あまりにも下手なため読む側は観よう、読もうとする。(読みにくい文字ほど、読もうとする)
これがもし、パソコンなどの美しい文や文字だったなら、果たして読もうとしたかなあ?
彼は、組織もなく当選し続けている。
彼の当選の秘密はね、きっと、その下手くそな手書き文字への共感だと思う。
(※当時5000~8000票獲得、当選ラインは約3000票)。
言葉と、文字って馬鹿にはできないんだよ~
人の心を動かすことができるものだよ~

3.文字を読ませる
活字ってね、しっかりと読もうと意識しないと、なかなか読めないもんだよね。
ましてや、長い小説や文章などは、よほど読みたいものは別だけど、気合を入れないと読めないもんだよね。だから、文字の機能には読ませるだけでなく、観させる機能も必要になる気がする。
思わず読んでみたくなった。
読んでしまった。
見てしまった。
忘れられない。
すぐに思い出せる文字や文は、美しいだけでは心に残らない事がわかるはずず。
下手な文字や個性的な文字は、文字が話しかけてくる気がする。
私たちはパソコンで楽をしているけど、大切なものや、どうしても伝えたいことなどは、やっぱり手描きの方が心に強く残るよね。
4.文字を視る
文字、文章というと、どうしても読むというイメージが強いものだけど、実際は人間の機能上からいえば、最初は観るんだよね。
つい観てしまうよね。
観てから読み、理解するのだけれど、観て理解させる方法が手描き文字なんだよね。
活字だらけの世の中、活字が氾濫して、活字に溺れてしまうかのような世界で、観よう、観させる、読ませる技術が必要な時代ともいえる気がする。
嫌でも、観てもらう、読んでもらう。
伝える作業の一番手っ取り早い方法が、この単純な下手くそな手書き文字にあるような気がする。
だから、文字が達筆で習字が上手い人は失格かもね。
下手であればあるほど「味(個性)」が目立つ。
こんな人もいた。
いかに下手に描くか~
口で書くか、利き手でない方で書くか、書きにくい筆やペンで描く人もいる。
〈ことば〉いうのは、読ませて、見せるだけではないよね。
魅せることが必要かも。
〈ことば〉は視覚、聴覚をめざして飛んでくるものだもの。
その〈ことば〉の響きが音に変わる気がする。
音楽などまさにその一例で、歌なども〈ことば〉に様々な音となり、その音から、その言葉の響きから、視覚に訴える事ができるものだからね。
こんな例でもわかると思うけれど、〈ことば〉は様々な商品化が可能な〈著作権ビジネス商品のひとつ〉だよね。
5.note一部作品展(「繭の言葉」より 繭工房)





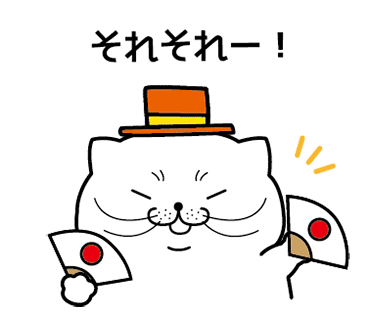
coucouさんでした~
みんな~
前編、後編を読んでくれた、みんな~
ありがたき~
noteのクリエイターさんたちの中にも、たくさんの素晴らしい言葉を送り続けている人たちがいるよね。詩や、詞、短歌や俳句、川柳、短文。筆文字、手書き文字、絵やイラスト。
みんな素晴らしいよね。
確かに、どんなに素晴らしいものでも現在の商業主義の世界では評価が低い。だけど、出版社の人たち、目がないよね(全部でないけれど)。
いい内容はいい内容、いい本はいい本~
でもいい本でも売れなければ暗闇に葬り去られる。
でもね、それでもいいんだよ~
この繭工房さんはね、自費出版ではないんだよ~
「自主出版」なんだ。
この言葉はcoucouさんが勝手に名付けた言葉なんだけれど、心ある人たち、作品に共鳴してくれた人たち、応援をしてくれる人たちによって印刷費を賄い、その日たちの力で売るんだ~
それが本当の売り方なんだよ。
それでも予算がなければ「電子書籍」もいい。
私たちクリエイターさんたちはね、noteもそうだけれど様々な独自の表現媒体が現れた素晴らしい時代だと言える。
これからはね、目に見えない、形とならない、意識しないとわからない風のような、風の時代~これは、無形の財産を作り続けるクリエイターさんたちにとっては追い風となる気がする。(ネットの世界もおんなじ)
coucouさんはね、マリー・フライエさんの「千の風」を信じている。買い物の紙袋を破いてその破れた紙に、母を亡くした女の子を慰めるために言葉(詩)を書いた。
そのたった一枚の破れた紙がネットを通して世界中に広がった実話を信じているんだ~
言葉ってね、人を救う場合だってあるんだよ~

6.付録:千の風の本当の作者「マリー・フライエ」さんの物語
Jefferson Airplane - Somebody To Love, American Bandstand, 1967
coucouMagazine|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/m5ba19b0e7afb
coucouさんのおすすめマガジン①|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/mdf0316a88e8e
coucoさんのおすすめマガジン②|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/m295e66646c4c
coucoさんのおすすめマガジン③|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/mf98f9bd1801c
coucouさんのおすすめマガジン④|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/mf79926ee9bb1
https://www.theyesproject.biz/https://www.theyesproject.biz/
Production / copyright©NPО japan copyright coucou associationphotograph©NPО japan copyright association Hiroaki
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
