
77.著作権のとなりの権利って何?
歌を作詞した人、作曲した人には「著作権」があります。
でも、作詞、作曲だけでは世の中に広めることはできませんし、さらに大切な人は歌い手さんがいます。
歌う人には著作権はありませんが、その歌い手さんの個性や独自性などがその歌のヒットに結びつきます。そのために歌い手さんには「著作権」はなくとも「著作隣接権」というものが与えられています。このように、著作者、著作権者のとなり(隣)にある権利のことをいいます。
では、「著作隣接権」のある「著作隣接権者」とはどのような人たちのことを言うのでしょう?
それは「実演家」の人たちに与えられた権利です。
では、「実演家」ってどんな人たちか?といえば「歌手」はもちろん、「俳優さん」「舞踏家」「演奏家」、「演出家」その他実演する人のすべてにこの「著作隣接権」というものが与えられているのです。
フォークソングなどのように自分で作詞、作曲し、一人がギター演奏して、歌も歌うという場合がありますが、この場合はすべてにおいて「著作権」「著作権者」があり「著作者」となります。
さらに「実演」とは、
「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む)をいいます。人形劇や大道芸、パフオマンス、踊り、振り付け、伝統芸能なども含まれます。
つまり、何かを歌ったり踊ったり、朗読したりする人が実演家となります。
この実演は音楽や脚本などの著作物だけに限らず、例えば手品やモノマネなどの著作物以外のものでも該当します。
※注画像はオリジナルの「ペイント・アート」です。終わりに説明がありますのでお読みくださいね。
今回は「教育者・先生特集」ですので、みなさまはこの「ペイント・アート」をお楽しみください。
誰にでも簡単にできるアート。
幻想的な世界です!

1.著作隣接権って一体何だろう
これは、実演家(俳優、舞踏家、演奏家、歌手などの実演を行なう者、及び実演を行う者を指揮・演出する者)、レコード製作者(レコード原盤製作者)、放送事業者(放送を業として行う者)、有線放送事業者 (有線放送を業として行う者)の経済的利益を保護するための権利の総称といわれているものです。
著作隣接権とは一言でいえば、「伝達者の権利」です。
また、実演家のみには公表権を除いた、氏名表示権、同一性保持権が著作者人格権として与えられています。
さて、著作者の死後における人格的利益の保護とはどんなものでしょう。
著作者人格権は著作者の死亡と同時に消滅します。
しかし、著作権法は、著作者の死後においても著作者の尊厳を保護することは文化の保護継承という意味において重点を置いています。
たとえば、著作者の死後であっても、もし著作者が生存していたとすればと想定し、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと定めています。(著作権法第六十条)
つまり、生前、著作者が明らかに拒否していた作品を公表してしまったり、死後において氏名表示を怠ったり、死後において著作物や題号を勝手に改変することは、生前であれば侵害行為となっていることに対し、これらの行為は死後においても禁止されています。
そのため、著作者が死亡していたとしても、その遺族 ( 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹 ) が法的手段を取ることが定められています。
また、これは親告罪ではないので、告訴がなくても検察官の判断で訴訟が提起されうるといわれています。 ( ※著作権の切れた作品に関しては問題ありません)
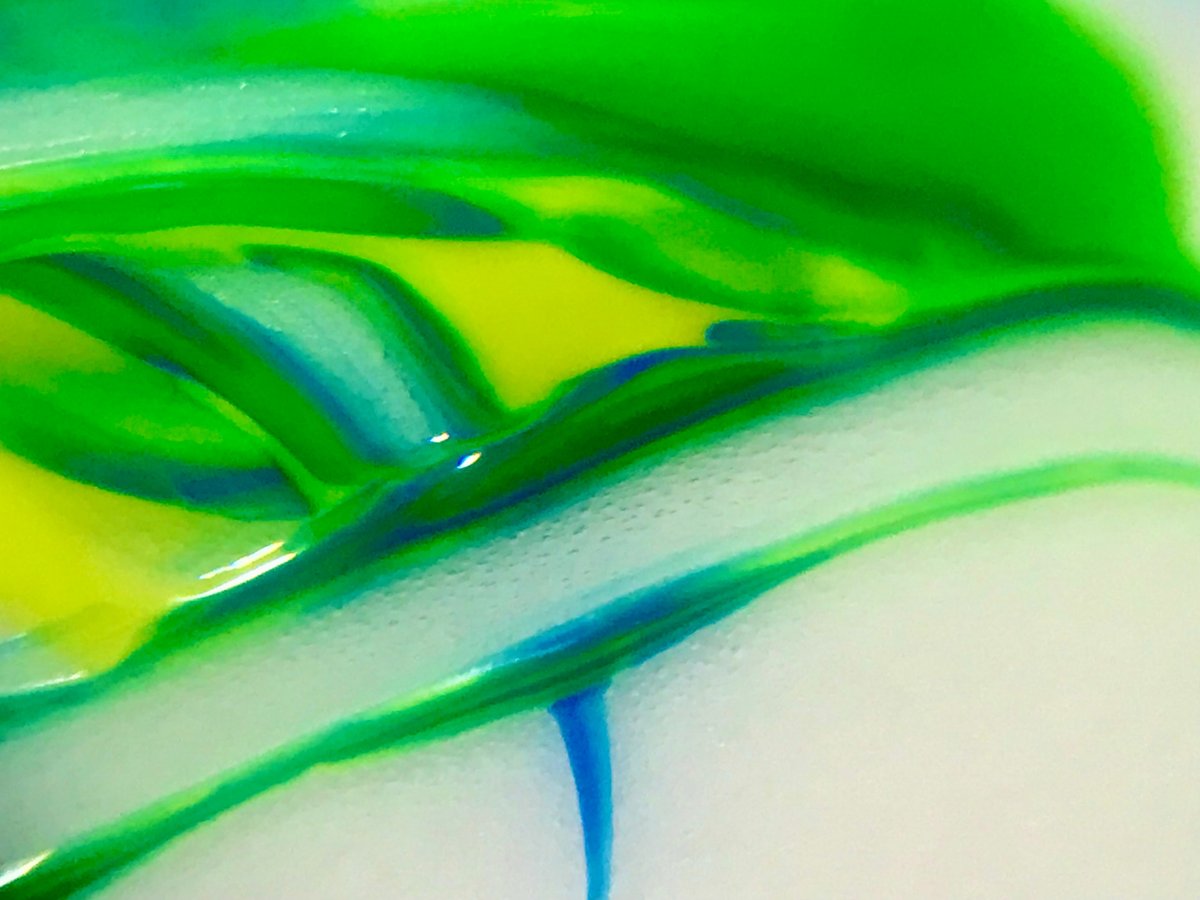
2.気をつけようその他身近な著作権侵害例②電子教材差し止め請求
平成16年6月3日、大手出版社「学習研究社」が全国展開するフランチャイズ方式の学習塾が、小中学生向けの電子教材で文学作品を無断使用し、著作権を侵害したとして、著者の作家たちが、学研と教材の委託製作・販売業者を相手取り、教材間使用差止めなどを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
電子教材については著者側による無断使用のチェックは難しく、使用料の支払ルールも確立されていない。
このような著作権侵害が問われるのは初めてのことで、司法判断が注目された。
仮処分を申し立てたのは、児童文学者の宮川ひろしさんたち三人。
この申し立てによると、学研は、学習塾「学研CAIスクール」をフランチャイズ方式で全国三百カ所に開設。
開発した専用サーバーの製作やスクールへの販売・貸し出し業務を業者に委託していた。このスクールでは、各机ごとに置かれたパソコンを使い、サーバーに組み込まれた電子教材を生徒が自由に利用できるようになっている。
この電子教材の中で、宮川さんの作品が画面に表示されたり、音声で朗読されたりして使用され、印刷することでプリント教材らもなっていたという。
宮川さんは、「学研側はスクールにサーバーを数百万円で販売したり、月額約十万円で貸し出し、数万人の児童、生徒に自由に使用させ、著作権を侵害している」と主張。
このように、今までは書籍の形で販売された学校や塾の教材、インターネットで配信された入試問題を巡り、著者側が出版・送信停止や損害賠償を求めた例はあったが、この電子教材に対する訴えはなかったという。

3.どうやって著作物を活用すればいいのだろう
個人的な利用であればどんな著作物でも自由に利用できるのでしょうか。
著作権法では「個人的又は家庭内その他これに準じる限られた範囲内で使用することを目的とする場合、使用者は著作権者の許諾を得なくても構わない」とされています。(著法三〇条一項)
この「個人的」の意味は、それを使用する者が自らの学習や趣味娯楽、調査や研究のためにということを指しています。
そのために本や雑誌の一部を複写したり、CDやFM放送から音楽を録音したり、テレビで放送された映画やドラマをビデオに録画したりすることは「個人的」であれば自由に利用できます。
また「家庭内」とは、あくまでも家族などで楽しむためにという意味です。
「これに準じる限られた範囲内」とは、友人間で楽しむためという意味で使用する範囲はプライベートな極少数の範囲に限られるもので、会社内の内部資料として配布するための複製や他に販売などをするために複製する場合などは、たとえその複製部数がわずかであってもこの私的複製の範囲には入りません。
このように「個人的又は家庭内その他これに準じる限られた範囲内」であれば著作権者等の許諾を得なくても自由に複製することができます。

たとえば、パソコンでインターネット上の音楽を取り込むことも自由。
パソコン内部に蓄積するだけでなくCD—ROMなどに保存することも自由。
ただし注意しなければならないことは、取り込んだ音楽を自分のホームページのコンテンツとしてインターネット経由で公衆に送信することは著作権者の公衆送信権や演奏家・レコード制作者等の送信可能化権が適用されるため、著作権者の許諾を得なければなりません。
つまり、ホームページ上のコンテンツとして使用する範囲を越えてしまうからです。
それでは「学校やその他の教育機関の場合はこの個人的な使用範囲を越えてしまっているのではないだろうか」という疑問もあります。
しかし、著作権法第三十五条では「学校その他の教育機関『非営利目的』において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」と定めています。
ここでいう「学校その他の教育機関」とは、小、中、高、大学、高専等の学校教育法に定められた諸学校(国公私立は問いません)のほかにも、継続的に教育活動を行なっている機関も含まれます。
ただし、教育機関には営利を目的として設置されているものがありますが、非営利でなければこれらの規定は適用されません。
これは営利目的であれば、その著作物利用によって得た利益は著作権者に還元するべきものであるためだからです。
たとえば、民間の営利会社が主催するカルチャースクールや講座等などはこの規定の適用範囲外となります。
私塾なども同様です。
「教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的」とありますが、この意味は学校等における使用といっても授業用に複製する場合に限られます。
授業の範囲には通常の授業のほか、特別教育活動である文化祭等や運動会、修学旅行などの学校行事や必修のクラブ活動も含まれます。
しかし、任意の部活動などはこの授業の中には入りません。
「複製を行うことのできる者は授業を担任する者」であり、小学校などにおける教論、大学における教授や助教授、その他の教育施設における講師など、その名称に関わらず、授業を担当する者はすべて含まれます。

これに対して注意しなければならないのは、事務職員、学校を管理している教育委員会などは授業を担当していないので含まれません。
教育委員会が独自に発行する学校の副読本作成のために著作物を複製することは認められません。
また、もうひとつの注意点としては、学校等で教員が授業用に複製する場合であっても、未公表の著作物は無断で複製することはできません。
さらに前記の条件を満たしていたとしても、「著作権者の利益を不当に害する場合」には適用されません。
これは著作権者の利益を保護するためのものであり、せっかく販売しているものが、授業目的だからといって大量に配布されてしまったりすれば著作権者の利益に影響を与えてしまうからです。
そこで、「複製の部数及び態様に照らし」』というように何百人も受講するような場合、その人数分複製物を作成するわけですから、著作権者には大きな影響があります。
そのため、たとえ教育目的であったとしても権利者の利益を不当に害すると認められる場合には、その複製には権利者の許諾が必要になります。
ところで、試験問題には著作権があるのだろうか。
入学試験、学期末試験などで試験問題を作成する場合、既存の著作物を試験の題材として利用するケースが多いが、試験問題として複製する場合には事前に著作権処理をすることがむずかしい。
これは、試験問題が事前に漏れる恐れがあり、著作権法三十六条では事前に許諾を得なくてもよいように権利制限が設けられています。著作隣接権も同様。
また、この規定は学校等における試験だけでなく、入社試験、各種の資格試験、検定などの試験問題として複製する場合も含まれます。
しかし、営利を目的とした試験 (業者による模擬試験など)は権利者へ相当な額を支払うことと許諾を得なければなりません。
また、試験問題として利用する場合には出所の明示が必要になります。つまり、作者名や作品名のことです。
また、試験問題に使用するからといって、その作品を勝手に改変することは、著作者人格権侵害になるおそれもあります。(同一性保持権)
他人の著作物を利用するとき、よく「引用する」という言葉を聞くが、引用って何だろう。
著作権法でいうところの引用とは、自分の著作物の中に他人の著作物の一部を抜粋して転載するようなケースをいいます。
つまり、自分の著作物がなくて、単に他人の著作物を転載することは引用とはいいません。
著作権法では「公表された著作物は引用して利用することができる」。
この場合において、その引用は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲で行われるものでなければならない」と定めています。この条件は、
(一)「 公表されたもの 」
つまり未公表の著作物は引用の条件にはあてはまりません。
(二)「公正な慣行」
社会通念に照らし、引用であると認められる場合でなければなりません。これは、自分の著作物がなく、ただ単に他の著作物を転載したにすぎない場合は引用として認められません。しかし、報道、批評、研究などの引用目的には様々なケースもあり、少なくとも引用部分と自分の著作物との明確な区別をするために、引用部分にはカッコで括るなどして十分に区別できる方法で引用することです。また、出所 (出典)の明示、
記載なども重要です。
(三)「正当な範囲」
これは自分の著作物があっても、ほんのわずかしかなく、主たる内容が他人の作物の転載によって占められているような場合は正当な範囲とはいえません。つまり、「主従関係」が成り立つ必要があります。主は自分の著作物でなければならないということです。



4.ペイント・アート
特非)著作権協会です。
ここまでのおつきあい、感謝します。
今回は教育、学校の先生がテーマでしたので、読むというよりも保存してください。
そこで、「ペイント・アート」を協会メンバーさんの作品です。このために作ってもらいました。
水にインクを垂らす「インク・アート」というものは以前からあるようですが、「ペイント・アート」というものは珍しいものです。
水にインクを浮かせてが流すのではなく、ペイントをお皿に取り出し、少量の水と筆だけで模様を創ります。
画像はスマホで十分ですね。
素敵なアート著作物となります。
このアートは人によってまったく違うものができてしまうように、偶然性もありますが、写真のシヤッターチャンス、光、反射、角度などを意識した接写です。
みなさんも一時試してみませんか?
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~著作権トラブル110番~「著作権事件簿」③〉①~⑰巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。


この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
