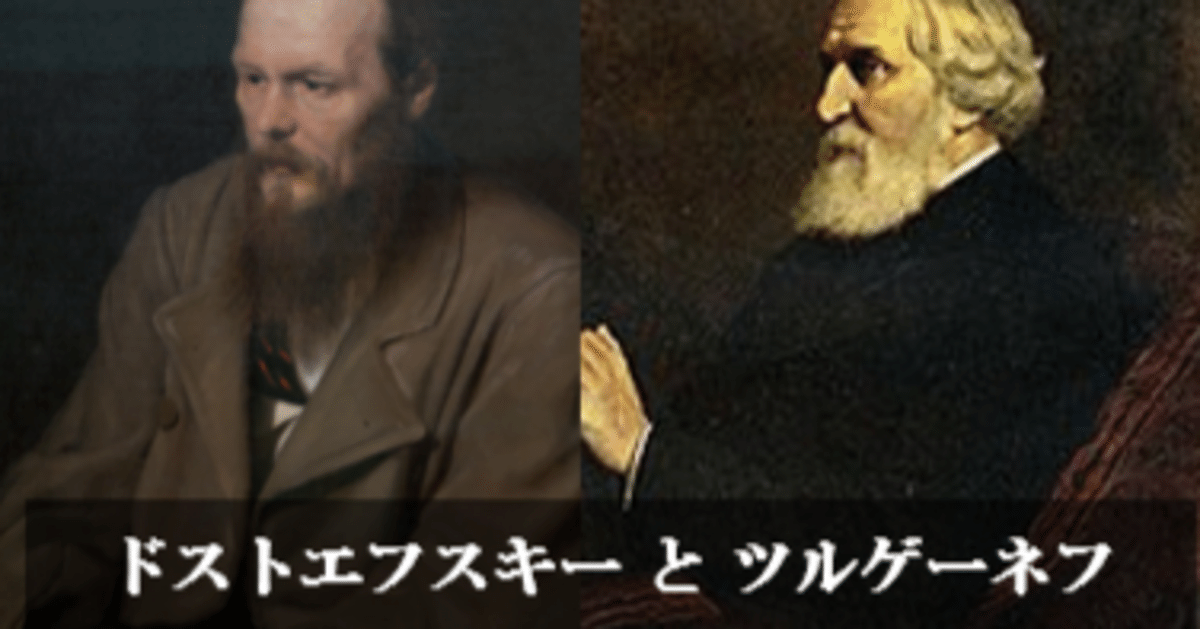
ロシア文学秘話:ドストエフスキーとツルゲーネフ
ドストエフスキーとツルゲーネフの仲が悪かったのは有名で、特にドストエフスキーは激しくツルゲーネフを憎み自作の小説で彼のスキャンダルさえ取り上げてぼろくそに貶していた。ツルゲーネフもまたドストエフスキーを軽蔑し彼の性格とその小説をロシア版サドだと言って忌み嫌っていた。
しかしこの二人は最初のうちは互いに非常に好意を持っていたのである。処女作『貧しき人々』を出した新人作家ドストエフスキーは兄への手紙でツルゲーネフが自分の作品を激賞してくれた事を綴っているが、その褒められたことに対する感激をあからさまに綴った文章は読んでいて気恥ずかしくなってくるほどである。その手紙の中でドストエフスキーはツルゲーネフを詩人と書いているが当時のツルゲーネフは作家としてより詩人としての名声が高かったようだ。ドストエフスキーはツルゲーネフの詩を好んでいたらしく、短編『白夜』のエピグラフにツルゲーネフの詩を載せている。
だがその二人のバーデン=バーデンで大喧嘩して決裂してしまったのだった。その決裂に至るまでの経緯はこんな風だったと言われている。ドストエフスキーは十年にもわたるシベリア流刑を終え『罪と罰』で本格的に文壇に復帰を果たしたのだが、しかし長い獄中生活のうっぷん晴らしか賭博にハマってしまったのだ。せっかく手に入れた印税も博打で瞬く間に消えてしまった。借金が嵩んでロシアにいられなくなったドストエフスキーはスイスのバーデン=バーデンへ逃げ出したのであった。そのバーデン=バーデンにはあの尊敬すべきツルゲーネフもいた。ドストエフスキーはツルゲーネフが滞在していると聞いて喜び彼に救いを求めて金を無心したのであった。ドストエフスキーはまずはツルゲーネフが最近出した小説『煙』を褒めちぎり、それから彼の小説の登場人物そのままにこのままだったら首を吊るしかないと訴え、最後に十字を切って私の苦境を救えるのはあなたしかいないと涙を流して懇願したのだった。
根っからの貴族であり金もたんまり持っていたツルゲーネフはこのドストエフスキーの懇願を聞き入れ、とりあえず手持ちの金をいくらか融通したのだが、その時彼はドストエフスキーのような人には絶対に言ってはならない事を言ってしまったのである。
「ほら、とりあえずこれでも受け取り給え。君もいい大人なんだから、賭博なんて下らんことはやめるんだな」
ツルゲーネフとしては苦境に喘ぐかつての知り合いを憐んで窘めたつもりだっただろう。しかしドストエフスキーはツルゲーネフのその窘めとそう言いながら貴族が浮浪者にお恵みを遣るように金を渡したその態度に自分への果てしない軽蔑を感じたのだ。ドストエフスキーは怒りに身を震わせた。これほどの屈辱は初めてであった。目の前の空かした貴族野郎を殺してやりたいとさえ思った。ドストエフスキーは貰った札束をポケットにしまうとツルゲーネフに向かって絶交を言い渡した。あなたはこの私をまるで物乞いか何かのように扱った!こんな屈辱は今まで受けたことはない!そうだ!あなたは昔から私を軽蔑していた!あなたは私をほめそやしながらその実陰で私を貧乏人とバカにして仲間と笑っていたのだ!だが私は貧乏であっても決して物乞いなどではない!私は貧しくも高き理想を持ったキリスト者なのだ!だが貴族のツルゲーネフはこのドストエフスキーの無茶苦茶な罵倒に激高せず、ただ礼儀正しく頭を下げドアを開けてドストエフスキーに部屋から出て行くよう促したのだった。
プライドが高く妬み深いドストエフスキーは生涯この屈辱を忘れることはなかった。彼はツルゲーネフから金を融通してもらった事に激しい屈辱を感じあの出来事を思い出す度に気も狂わんばかりになった。しかし彼は金を返そうとは一度も考えなかった。借金はあらかた片付け生活が安定してもツルゲーネフへの憎しみは収まらなかった。ドストエフスキーはツルゲーネフに手痛い傷を負わせる機会を狙っていた。あの貴族野郎だけは許せない!二度と外を歩けないようにしてやる!そしてドストエフスキーはとうとうその機会を掴んだのである。
ドストエフスキーは彼の五大長編の一作であり彼の最大の問題作と呼ばれる『悪霊』でツルゲーネフを思いっきり彼を茶化したのであった。ドストエフスキーは酷いことにツルゲーネフが若いころ母親の小間使いを妊娠させたことまで暴露している。さらにこれは出版社に猛烈に反対されて完成原稿から削除されたが彼はツルゲーネフがカツラだとまで描いている。ドストエフスキーによると名前からもうハゲだとバレているというのである。ツルツル頭に毛なんか乗せてカッコつけてもバレてるんだよというわけである。これは明らかにドストエフスキーの猛烈な思い込みであるが、当時ドストエフスキーは自分が薄毛だったので髪がふさふさでイケメンであるツルゲーネフが妬ましくてこんな妄想を抱くようになったかと思われる。
このドストエフスキーとツルゲーネフのエピソードは作家というものがどういうものであるをよく語っている。作家とはどんな酷い人間でも崇高なまでの名作を書くことが出来るのである。実際のドストエフスキーは被害妄想に囚われた憐れな人間でしかないかもしれない。またツルゲーネフもドストエフスキーがそう思ったように鼻持ちならない貴族であったかもしれない。だがそんな人間が時として不滅の芸術を生むことがある。それは文学という芸術の不思議である。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
