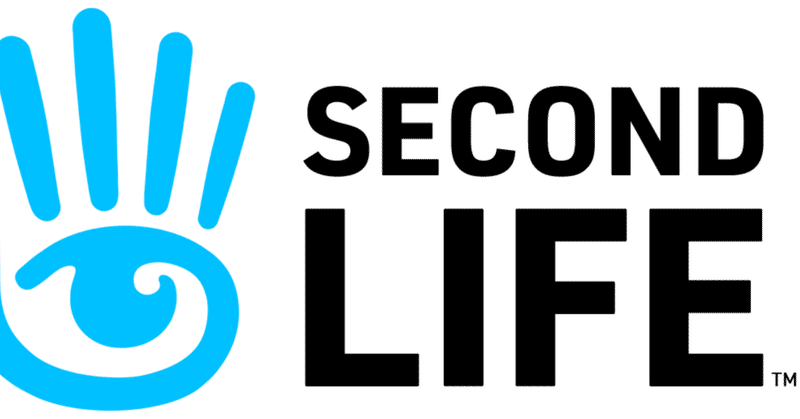
『ハイパーワールド 共感しあう自閉症アバターたち』を読んでみた
こんにちは。
ものくろです。
はじめに
今回は、池上英子(2017)『ハイパーワールド 共感しあう自閉症アバターたち』NTT出版を読んでみての感想となります(かなりのネタバレを含みます)。

本書について
本書では、ニューヨークを拠点に活動する社会学者の池上英子先生が「Second Life(セカンドライフ)」というメタバース(仮想世界)で、自閉症のある人(自閉症アバター)をエスノグラフィーという手法を用いて観察した本となります。エスノグラフィーとは、Wikipediaによると「フィールドワークに基づいて人間社会の現象の質的説明を表現する記述の一種。民族誌学とも。」とされるものです。
「Second Life」とは、2003年に公開されたPC専用の仮想空間アプリケーションになります。ここ数年で注目されてきているメタバース(仮想世界)ですが、20年も前から存在してものだとは驚きですね。
本書によれば、一般的に対人コミュニケーションが苦手と言われている自閉症のある人にも、Second Life上では「他者への共感性」が確かに見られたとされます。
「ハイパーワールド」とは
本書の題名にある「ハイパーワールド」とは一体何なのかといえば、自閉症の人によく見受けられる「感覚過敏/感覚鈍麻」によって、定型発達の人よりも自閉症のある人が世界の刺激(情報)を過敏、過多に受け過ぎていることを指した言葉になります。
他の例で例えるとすれば、私たち人間は視覚を通して世界を認識していますが、近視や遠視、乱視、緑内障や白内障、色覚異常(色覚多様性)などによって同じ世界を認識しているようで実は人によって見えている世界は異なっているように、同じ世界にいたとしても自閉症の人が感じている感覚世界は、定型発達の人が感じている感覚世界とは異なっているということになります。分かりやすく色覚多用性の写真を載せますが、私たちは同じものを見ているようで同じものを見ているわけではないのです。

参考URL: https://karapaia.com/archives/52232964.html
感覚過敏/感覚鈍麻について

参考URL: https://www.teensmoon.com/chart/%E3%80%90%E5%9B%B3%E8%A1%A8%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%80%91%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3-x-%E6%84%9F%E8%A6%9A%E9%81%8E%E6%95%8F%E3%83%BB%E9%88%8D%E9%BA%BB/
少し話は逸れてしまうのですが、一般的に感覚過敏/感覚鈍麻は上のイラストのように説明されます。今まで僕は、上のイラストのような極端な感覚過敏/感覚鈍麻には当てはまらないので自分に感覚過敏/感覚鈍麻はないのだと考えていました。しかし、外出するだけで疲れ果ててしまうことが多いことや他の発達障害のある人のお話を聞くことで自分にも当てはまっているのではないかと考えるようになりました。あまりスペクトラムという言葉を多用したくはないのですが、上記の感覚過敏/感覚鈍麻にもスペクラムがあり必ずしもその程度が極端である必要はないのではないかと考えるようになりました。
オフライン/オンラインでの情報量の違い
テレワーク化が進んで早数年が経過していますが、テレワークの環境が合っていると感じる人もいれば、合わないと感じる人もいるかと思います。テレワーク以外にも、オンライン授業などもだいぶ浸透しましたが、対面での臨場感や相手の表情、相互交流などでオンラインでは物足りないと感じている人がいるのはよく耳にしますよね。これは情報量という観点で非常に的を得た説明になります。オンライン上では、PCやスマートフォンというフィルターを介することで情報(刺激)量は格段に制限されてしまい、これがオンラインの物足りなさになっているのですが、一方で自閉症のある人にとってはむしろこれがメリットになっているのです。フィルターを通すことで、視覚情報、聴覚情報、触覚情報、嗅覚情報などはカットされますが、それによって自閉症のある人にとっての情報量は心地よい量になるのです。
自閉症のある人にとっては、通常の明るさでも世界が眩しく見えたり、大量の視覚情報によって酔ってしまうことや、服の生地の感触が気持ち悪く感じたり、香水や柔軟剤の匂いで気持ち悪くなってしまうなど、とにかく定型発達の人よりも多くの情報を吸収し過ぎてしまうのです。
そんな自閉症のある人にとっては、「Second Life」という原始的なメタバースは非常に居心地のよい場所になるのです(Second LIfeでは、VRゴーグルは必要なく、会話も音声通話ではなくキーボードでのチャットベースになっています)。
自閉症の程度によっては、情報量の多いリアルの世界では居心地が悪く自由に振る舞えないことがあるのですが、むしろ「Second Life」というメタバースでは現実世界よりも自由に振る舞うことができ、それが居場所になっている人も少なくないのだそうです。
目次紹介
本書の内容は、以下の通りです。
プロローグ
高機能自閉症の大人、ジョンとの出会い
アバターとしての出会った自閉症の人々
第1章 自閉症と出会う ─仮想する脳を旅して
自閉症は人間の脳の不思議への扉
自閉症の人の知覚の特徴
多数派の生活・文化で暮らすー異文化交流との相似
究極の鏡としての自閉症
仮想の世界で自分と出会う人々
セカンドライフという仮想空間
仮想世界のアバターたちー分身は成長する
文明を創ってきた仮想の力
アバターで哲学する方法
仮想世界の臨場性と「座の文芸」
デジタルエスノグラフィー、事始め
ヴァーチャル研究所「ラ・サクラ」の誕生
「仮想空間のマザー・テレサ」ジェントル・ヘロンとの出会い
仮想世界に集う自閉症当事者たち
大人になった自閉症の人たちは世界をどう認識しているか
自閉症研究の新しい課題
会話する自閉症アバターたちー仮想自助グループで安全につながる
「アバターはみんな自閉症的だ」
過剰な情報が引き算された世界
知覚過敏と情報の絞り込み
ニューロダイバーシティの時代
第2章 自閉症の社会史 ─カテゴリーは人をどう動かしてきたか
自閉症カテゴリーの発達
自閉症の歴史の重要性
カテゴリーの影響
米国における自閉症の歴史
自閉症の登場
「自閉症」の登場と冷蔵庫マザー
冷蔵庫マザー理論への疑問
自閉症はスペクトラム
「自閉症」のカミングアウト
一周遅れの自閉症マイノリティ運動ー米国での動き
テンプル・グランディンの登場
自閉症を個性として活かしたグランディン
進化を遂げたグランディン
自閉症当事者たちの自叙伝の出版
ハリウッドの貢献
映画「レインマン」の登場
ダスティン・ホフマンの役作り
レインマン現象
親たちを不安にさせた自閉症の原因説
自閉症流行病説のインパクト
予防接種原因説の恐怖
自閉症「大流行」を覆す社会学的研究
発言し、行動する親たちと市民団体
米国市民社会の伝統
自閉症研究に介入する親たちの団体ー「自閉症を今こそ治癒しよう財団」 など
全米規模の「自閉症は発言をする財団」ー発足と課題
ヘッジファンドの巨富を活かす「サイモンズ財団」ー遺伝子研究の発展と課題
コンピュータと脳神経科学の時代のニューロダイバーシティ
声をあげはじめた自閉症当事者たち
インターネットと脳神経科学の発展
ニューロダイバーシティの哲学と「ギーク」文化
第3章 過剰なる脳内世界 ─仮想空間の自閉症アバターたち
自閉症的経験を考える
自閉症アバターの多様性
欠如か過剰か
自閉症的経験とはなにか
身体的な心、心的な身体
概念の規定なしに直接体験される世界
「私の言葉で」ー自閉症の自然言語を求めて
身体化して発話することの困難
言葉と自閉症の不思議な関係
音楽こそが言葉ーデレク・パラヴァチーニ
自閉症当事者運動の難しさー聴覚障害者との違い
自閉症当事者運動の難しさー聴覚障害者との違い
自閉症当事者マーガレット
瞑想的な心と自閉症的な心
異星からの大使
自閉症自助グループに集うアバターたち
仲間内の気取らない会話
「不気味の谷」か「特別視」かー現実社会で苦しむ当事者たち
週一回の会合は二時間続く
橋を架ける人、司会のアニス
明晰な頭脳、重い身体のウッディ
トランスで仮想空間を生きる常連のカレン(サリー、ジョセフ)
高機能の生きづらさを強いられるラディアント
グループ参加のメリット
アバターが語る自閉症体験
共感しあうアバターたち
他者の心が読めないのは、お互い様
ルールをめぐる態度のすれ違い
社交辞令と正直ーNTとのすれ違い
感覚過敏は感覚情報の過剰負担
過剰負荷で自己をコントロールできなくなるメルトダウン
予測の困難からくる不安
無理はしないが一番か
自分を知り、違いを知る
共感覚の美しい世界
過剰なる脳の発達とその編集
ハイパーワールドを生きる強烈な人々
エピローグ
トビウオの飛翔を追ってー無縁的自由空間で輝く自閉症アバターたち
波間の船を上で揺れる観察者
米国での言語・文化マイノリティの体験から
ジョンとの再開
感想
本書は、以前紹介した以下の2つの記事と共通している部分があると思いました。一応リンクを貼りましたが、以下の感想文に直接は影響ありませんので、気になる方だけどうぞ。
第2、第3の居場所の存在
Second Lifeに暮らしている自閉症のある人(広く言えば、今生きている場所に居場所がないと感じている全ての人)にとって、自分と離れつつも近しい存在である第2、第3の自分となるようなアイデンティティや居場所を通じた他者との交流が重要なのだと感じました。
私たちは、必ずしも論理や理性だけで生きているのではなく、魂(心?)の宿った身体を通してこの世界を生きています。言い換えると、心と身体は不可分な一体になっていると考えます。
本書の後半で、猿の道具の使用について触れられていますが、私たち人間には道具を身体の一部として感じられる能力があるようです。その道具とは、必ずしも棒のような単純なものだけではなく、アバターや物語の登場人物、楽器、イラスト制作etcのように身体感覚を現実世界から、仮想世界へと延長させる役割をこなす全てのものが当てはまっていると考えています。
障害を抱える人や病気に苦しむ人たちのコミュニティがSNS上には多数存在していますが、それは普段日常生活ではなかなか繋がれない同士たちと繋がるための貴重な場所という役割が大きいと思います。
TwitterとSecond Lifeとの差異
それでは、Twitter等での繋がりと、Second Life等での交流にどんな違いがあるのでしょうか?
それは、大雑把に言えば、①リアルタイムな他者との交流②近すぎず遠すぎないアバターの存在、の2つに分けられると思っています。
①について、TwitterやFacebook、Instagramはお手軽なブログツールとしての側面が大きく、投げっぱなし、言いっぱなしが多いツールだと思います。また、リプライやDMなどの機能もありますが、これはチャットのようにいつ返事を返してもよいため、リアルタイム性に欠けていると言えます。その一方で、Second Lifeなどのメタバースではアバターを通して(チャットを通して)ではありますが、相手とのリアルタイムなコミュニケーションが可能になります(一方で、お互いに時間を共有する必要性があるという意味では非効率でもあります)。このリアルタイムな会話が他者との交流という側面を大きくしているのだろうと思います。そして、人によってタイピングの速度に個人差はありますが、タイピング中にはタイピング中である表示が出るため相手が考えていることが分かります。つまり、タイピングのラグは相手を待つ他者への思慮を生み出します。このラグが即時的なコミュニケーションが苦手な人にとってはむしろメリットになります。
ただ、最近はTwitterでもスペース機能が追加され、見知らぬ人との即時的なお喋りが可能になったため、Twitterでもまた新たな文化が生まれていくのだろうと思います(音声での会話が苦手な人には合わないかもしれないですが)。
②について、SNSの中でもFacebookは特にそうですが、あくまでもリアルな自分を発信するツールという側面が強く、ちょうどよい塩梅で自分との距離を置くのに不適であるように思います。その点、Second Lifeでは現実世界での自分を横において参加することが可能であり、この弱い匿名性がアバター同士の対等なコミュニケーションを可能にしているのであろうと思います。こちらについても、Twitterでは趣味アカウント、裏アカウントなど様々なアカウントを使い分けることができ、同じ目的を持つ者同士での交流はできているため、Second Lifeだけに当てはまるものではないのかなとは思います。
しかし繰り返しにはなりますが、SNSとメタバースの大きな違いは、やはりアバターの存在が大きいように思います。アバターという人形に自己を投影させて色々な場所を歩き回るわけですが、タイピスト(アバターの中の人)の中にはアバターを通した他者との交流を通じて、アバターの成長を感じることがあるそうです。これは、現実世界でのアイデンティティではなく、別のアイデンティだそうです。私たちには、日常のモード、仕事のモード、友達といる時のモードなど様々なペルソナ(人格)がありますが、表裏のない自閉症のある人にとって、新たなアイデンティティの発生は定型発達の人よりも余計に価値があるのではないかと思います。
古来より様々な種類の宗教の起源には、教祖に神様や仏様が降り立ったかのような伝説がありますが、それは才能のある人が熱心に修行に打ち込んだ結果なのかもしれません。しかし、これは誰にでもできることではありません。自分の中に自分ではない誰かが生まれることが鍵であるとして、それを一般向けに可能にするのがメタバースなのだと言います。一般的に、修行とは孤独(孤高?)を深めること、世間との関わりを断つような苦行を強いるものであり、その先に「救いの光」が現れるのだと思います。
発達障害のある人はセルフモニタリングが苦手だと言われており、自己分析を進める上でノートに日記を書いたり、それこそブログを書いてみることを勧めたりされています。これは、考えていること、感じていることを文字に起こすことで自分を客観視することになり、それによって客観的な分析が深まるという理屈だと思います。しかし、ある手段を用いた自己への没入とメタバースが大きく異なるのは、そこに他者の存在があることです。他者の存在による化学変化は予想できない変化を生み出すことになり、それによって新たなアイデンティティが育まれていき成長していくのだと思います。これは、自らが自らをくすぐることができないことと同じだと思います。もし世界に自分以外の人間がいないとすれば、その人は自分を認知することはできないだろう、という話は有名だと思います。これは、他者の存在は自己を映す鏡だということです。定型発達の人にとっては、生身のコミュニケーションがその機会にあたると思うのですが、ハイパーワールドを生きる自閉症のある人にとっては生身のコミュニケーションは情報量過多な嵐のような世界であり、そんな彼らにとってSecond Life等のメタバースは安全な場所に自己を置きながら他者と関わることのできる場所であるという点で非常に優れているのです。
気に入った文章を本文から一部抜粋
著者の池上先生が書かれていたことで、非常に印象に残った文章があり引用させていただきます(ここまで読んでいただいた文章は、実はほぼ全て間接引用で書かれていますので初めて引用するわけではないのですがm(_ _)m)。
私自身の立場もルーマンに近い。多数のアバターを操ったり、その人格に憑依したように見える人々を、精神を病んでいる、またはそうした傾向があるという立場から見るのは簡単だ。しかし私は端的に言って、そうした見方は当たらないと思っている。少なくとも物事の一面しかみていない。個々の人々をさらに詳細に評価すれば、それぞれの人々のなかに現実社会における悩みや不適応があり、それが仮想社会のなかで別の自己を試そうという動機になっている場合も十分ありうることだ。しかし昔から深き宗教者・修行者や哲学者がその道に入る動機には、なんらかの不適応、苦悩、違和感がつきものだった。その違和感こそが、固定観念からの自由を求める行動につなかったのだろう。
そして、障害者や自閉症の人たちは、健常者、定型発達者の単一定点視覚によるラベル貼りに、ほとほと迷惑しているが、この視点を変える装置としての仮想社会こそが、彼らを仮想社会に引きつける一因になっているようだった。少なくとも仮想社会に集まる人々のなかには、健常者か否かにかかわらず、社会の多数派が構成する固定観念とは違う世界があることを知っている人が多い、ということだろうか。
pp. 33-34
おわりに
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
もしこの記事が少しでもお役に立てましたら、♡(スキ)をしていただけると嬉しく、励みになります。そしてフォローしていただけましたら、頑張って書いた甲斐があるというものです。
ではまた〜👋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
