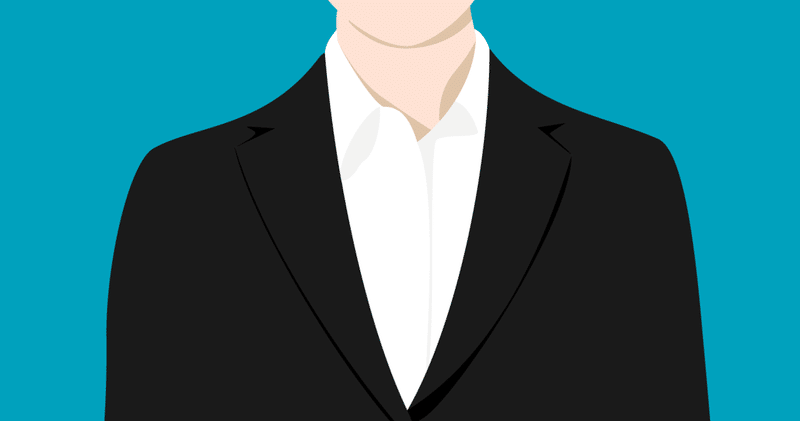
#2000字のドラマ_小説『スターティング・オーヴァー』
「選択肢を増やしたくて一応就活もしていて、内々定はもらったんですけど、やっぱり女優への道をどうしても諦められなくて。夏休みいっぱいは色々と考えてみようかと思っています」
そんな私の現状報告に、教授はこう即答した。
「就職しなさい。親御さんにも負担はかけられないだろうし、何より安定した仕事につくことが一番大事だろう?それがいい」
教授が軽く発した言葉に、失望した。
「はは。ま、そーですよねぇ〜。」
私は意見に同意するようなニュアンスの返事をして、軽く受け流そうとした。しかし、その一言は想像以上に私の心に決定的な打撃を与えた。
私がこれまでどれほどの情熱を傾け、どれだけの労力を費やして、自分の夢に向き合ってきたか。そのことをまるで分かっていない物言いだった。舞台で輝きたいと願った小学生の頃から、私の想いは何も変わっていない。今だって女優になるためにこの大学を選んで進学して、真摯に演技を学んできた。その積み重ねは何だったのか。
すっかり心が冷めてしまった私は、ゼミにも顔を出さずにそのまま家に帰ってきてしまった。ベッドの上に、スーツのまま突っ伏して、泣いた。悔しくてしょうがなかった。
こうしていると、ふと小学生の頃を思い出す。
小学校最後のミュージカルのオーディションで、あともう少しで主役の座を掴めるはずだったのに、幼馴染の咲良に主役が決まり、自分の力の及ばなさが悔しくて、布団にくるまって一晩泣き続けたことがあった。その時、一晩中ずっとそばにいてくれたのはおばあちゃんだった。
仕事で忙しい両親に代わって、いつも私の舞台を見に来てくれたおばあちゃん。録画された舞台のビデオには、いつも「美緒里ちゃんかわいいねぇ」っていう言葉がうっすら録音されていて、それがたまらなく恥ずかしかったけれど、とても嬉しかった。初めて両親が私の舞台を見た時も、「おばあちゃんがうるさくて!」なんて言いながら、みんなで感想を言い合ってくれた。
女優になることは、私だけの夢ではない。おばあちゃんの夢でもあり、お父さんとお母さんの夢でもあった。
私はスマホを開いて留守番電話のアプリを開く。鍵をかけて大事に保存された、一番古い音声を再生する。
「美緒里ちゃん。大学はどう?楽しい?美緒里ちゃんが早くテレビに出るように、おばあちゃんも頑張って長生きするから、勉強頑張ってちょうだいね。身体にも気をつけなさいね。たまには、おばあちゃんのところへ帰っておいでね。お父さんもお母さんも待ってるから」
年老いた祖母の声が、私の鼓膜に伝わる。
道に迷うとき、苦しくなるとき、帰ってくるのはいつもこの声がするところで、この声を聴くたびに私が女優であることを求められているような気がして、嬉しくなる。音声の再生を終えたスマホを、私はぎゅっと優しく握りしめた。
やり直しの効かない人生なのに、なんでやりたいことを否定されなければいけないのか。安定を得ることが親孝行なんだろうか。
違う。
それなら私は親不孝な人間でいたい。
私は、内々定先の会社の番号をダイヤルした。コールしてすぐに先方が電話口に出た。「申し訳ございませんが、内々定を辞退させていただきたく思います」と、言葉の隅にどこか罪悪感が滲む物言いで伝えた。伝えたあとでも迷いはあった。でも、退路を絶たなければ、次の未来へは進めない。電話を切り、少し武者震いした自分の体をさする。
「いいじゃん。」
「何が?っていうか帰ってたの?!」
同居人の咲良が、いつの間にか帰ってきていた。
「まあね〜。それより、電話の声。やっぱ腹から出てるだけあって綺麗だね。その芯の太い声が美緒里の魅力よねぇ」「なに?その褒め言葉」「私、嬉しいよ。美緒里が演技続けてくれるの」
咲良からの思いがけない言葉に私はなんだか照れくさくなってしまって、咲良の顔を直視できなくなった。ぷい、とそっぽを向く。
「本当はライバルが減ったほうがラッキーとか思ってるくせに」
「そう思ってたら美緒里とルームシェアして同じ大学に進学なんかしないし〜、ライバルがいなくなるのつまんないし〜。ね、どっちが先に映画の主演やるか、勝負ね」
咲良はいつものように、私の首に腕を絡めて抱きついてくる。ライバルのくせして、こうやって甘えてくるところが咲良のうっとおしいところだ。
「えー。私そんなガツガツした感じの女優嫌だ」
「いいじゃん、女優はガッツがあってなんぼじゃん?それよりなんかおやつ食べようよ。コンビニ行かない?」
「わかったわかった。暑苦しいから離れて」
私はベッドから起き上がって、咲良と一緒に部屋を出た。
咲良はスニーカーで、私はパンプスでコンビニへと歩く。うつ伏せで突っ伏していたせいか、すこし足がふらつく。
「美緒里、泣き疲れた〜?」
咲良が少し笑いながら、意地悪に質問してきた。
「そうね。ま、教授には何回も泣かされてきたから別になんともないけど」
「そんな強がっちゃってぇ。ま、あいつ確かにムカつくよね」
「ムカつくどころじゃないわよ、アイツ絶対見返してやる」
そう言って、私と咲良は笑った。午後の空に輝く少し傾き出した太陽が、これから先の海路を示す灯台のように、私と咲良を照らしていた。
[了]
ーこの小説は、タグ企画「 #2000字のドラマ 」応募作品です。ー
