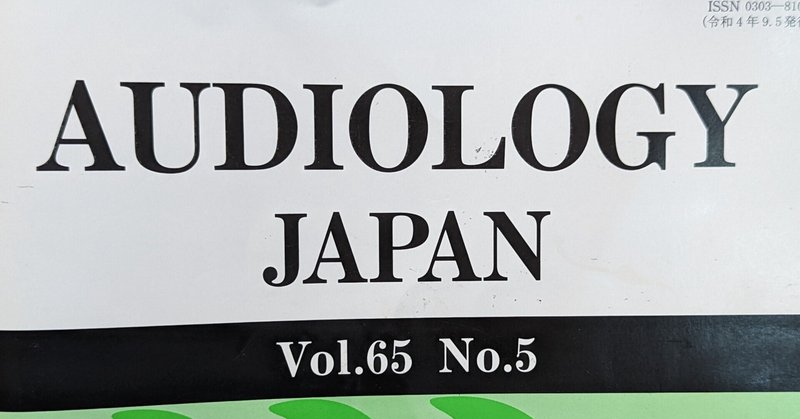記事一覧
補聴器ハンドブック勉強会in浜松2023の実耳測定実習レポート#062
あけましておめでとうございます。2023年も補聴器マガジンをよろしくお願いいたします。
さて1月8日9日の二日間は、毎年恒例となった中川さん主催の補聴器ハンドブック勉強会が開催されました。
この勉強会のスタートは、一人で読み解くのが難しい補聴器ハンドブックを、中川さんの解説の元、みんなで勉強するスタイルだったそうです。
しかし今年は補聴器未経験の言語聴覚士、中堅の認定補聴器技能者、そして補聴器
Part1 大塚が、はじめて聴覚医学会に行ったら大問題が議論されていました。#058
皆さん、日本聴覚医学会という団体をご存知でしょうか?
耳鼻咽喉科医や言語聴覚士の皆さんは知ってて当然ですが、補聴器技能者の多くは聴覚医学会についてあまり詳しく知らないと思います。
聴覚医学会の発足当初は耳鼻咽喉科医の皆さん、音響学の研究者の皆さん、そして補聴器技能者や補聴器メーカーの方、教育機関の方など、様々な方が所属して、聴覚についての研究発表が行われていたそうです。
しかし途中から「医師
安い、早い、上手い補聴器フィッティングにインサートイヤホン聴力測定が活躍する話【前編】#055
以前、『実耳測定装置が無いんだけど、うちのお店ではどうしたらいいの?』というご質問をいただいたことがあります。
たしかにこれまで、実耳測定、実耳フィッティングのことばかり書いてきた補聴器専門家の大塚ですが、実は実耳測定を行なわなくても、実耳で得られる目標利得・目標レスポンスに補聴器の音を近づける方法ないわけではないのです。
#052号のマガジンの中で 、インサートイヤホンとウレタンフォームを使っ
安い、早い、上手い補聴器フィッティングのためのインサートイヤホン聴力測定#052
前号(#051)では、僕の規定選択法に関する質問について、中川さんから回答をいただきました。クライアント情報に基づいた処方式の具体的な選び方は、補聴器店でも、そのまま使える内容でした。これから参考にさせていただきます。
処方式が決まったら、あとは”どんな補聴器を選んだとしても”目標利得に合わせるよう実耳でフィッティングしていけばよいわけです。
しかし僕の未熟が原因かも知れませんが、処方式を揃え
耳型練習の前に観察眼を鍛えよう!#047
今回は45号のつづき、耳型採取の新人向け練習法のご紹介です。
新人の方はご自身の練習に、ベテランの方は後輩指導のお役に立てていただければと思います。
さて耳型採取は手を動かす作業です。どうしても上手い下手があります。
そして新人のうちは自分が上手下手という話の前に、どんな耳型が上手く採取できたものか、どんな耳型が下手な耳型なのか。
最初は良し悪しがサッパリ分かりません。
たとえば補聴器メー
耳型とシェル、何から教えたらいいの!?#045
原稿執筆している4月現在、当社に初めて新卒の言語聴覚士が入社してくれました。(ありがとう、G藤さん、これから一緒にいい仕事をしましょう)
夢と希望と少しの不安を抱えて補聴器の業界に飛び込んでくれた若者たちを、心から祝福し、歓迎したいと思います。
希望を持った新人さんに、もしくは人手不足を嘆いていた職場の先輩にとって、現実的なお話しですが基本的に新卒の新人が即戦力になるとは限りません。
補聴器
補聴器のAIって何だ!?調整ソフト、使いこなしていますか?#043
最近はどこの補聴器メーカーも、AI、AI、AI、AI。AIが流行ってますね。
皆さんの考えるAIってなんでしょうか?
補聴器におけるAIってなんなんでしょう?
実は学生時代の大塚は情報系の勉強をしておりました。いわゆるプログラミングやコンピュータを専門にしていたので、最近の「AI、AI、AI!」そんな論調について、ちょっと違和感を感じている次第。
今回はAIと調整ソフトについて考えていきたいと
上司や社長、経営者に実耳測定を導入してもらうポイントはこれだ!#041
本誌039号では「シンプル、簡単、誰でもできる実耳フィッティングの実践手順!」と題して、実耳測定のメリットと実耳フィッティングの実践手順をご紹介させていただきました。
しかし現状では日本で実耳測定装置を持っている組織は、認定補聴器専門店や補聴器適合判定医が常勤する医療機関でも1%以下でしょう。知識を詰め込んでも、実耳測定の装置が無ければ実践する機会がありません。
今回は『どうしてもREMがやり
シンプル、簡単、誰でもできる実耳フィッティングの実践手順!(初心者用)#039
イチから始める補聴器フィッティングを毎月購読いただいている愛読者の皆様、ご感想やご質問のメッセージありがとうございます。
読者の中にはすでに実耳フィッティングを始めた方、これから始めようと思っている方が増えてきているようです。
これまでも補聴器の実耳フィッティングについてはご紹介してきましたが、事例や必要性などの話題が多く、具体的な手順のご紹介は十分ではありませんでした。
前回の中川さんの記
次回の補聴器マガジンは、補聴器ハンドブック勉強会で講演したREMフィッティングの「シンプル実践編」をご紹介
まだまだ寒い日が続きますが読者の皆様お元気ですか?補聴器専門家の大塚祥仁です。
次回のテーマは「REMフィッティングの実践編(初心者用のシンプル版!)」です。
補聴器フィッティングにREMを使うと、実は様々な活用方法があります。
次回は、その中でも特に初学者におすすめなカンタンかつシンプルなREMフィッティングの手順をご紹介させていただきます。
2月19日頃にお届けできるよう鋭意執筆中です
補聴器ハンドブック勉強会ダイジェスト版!♯037
イチから始める補聴器フィッティング読者の皆様、あけましておめでとうございます。
皆さんご存じかと思いますが、2022年1月9,10日に「補聴器ハンドブック勉強会2021年度in海浜幕張オンサイト」が開催されました。
全部で9つの講演と実習が行われ、最先端の検査技術、実耳フィッティングの実践事例や実習、シェル形状のクオリティ評価法、そしてNHKの「みんなの手話」でおなじみの森田明先生による日本手話