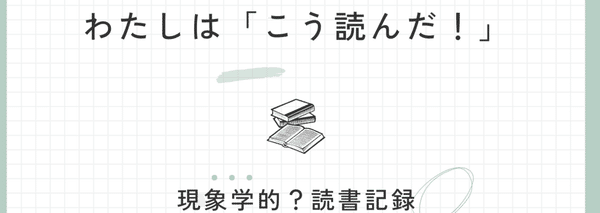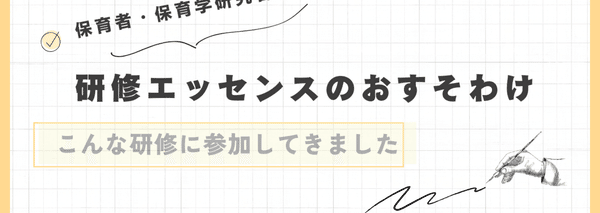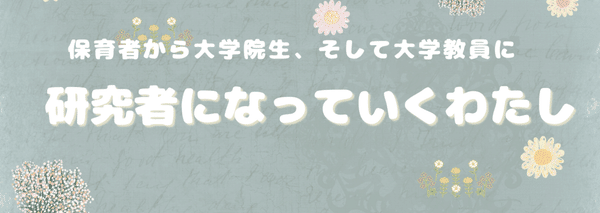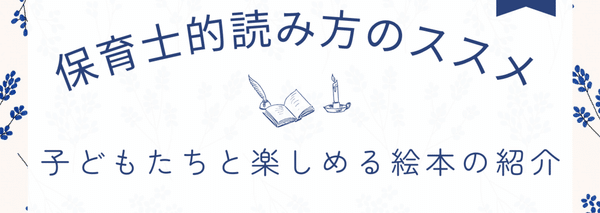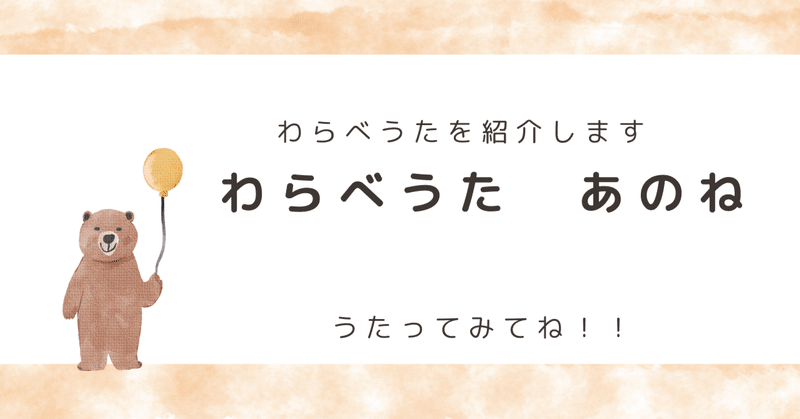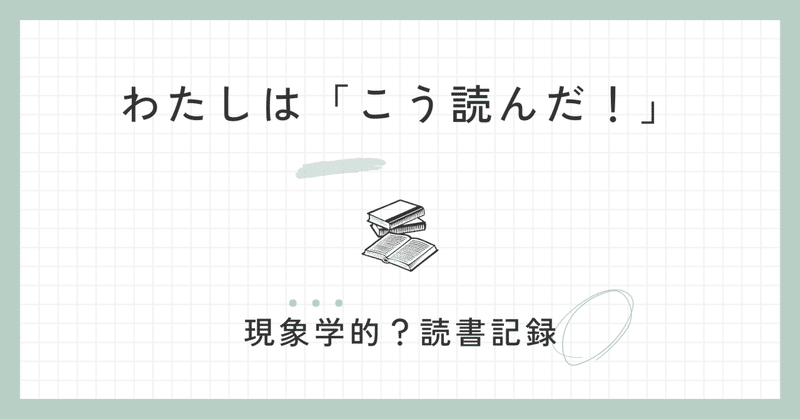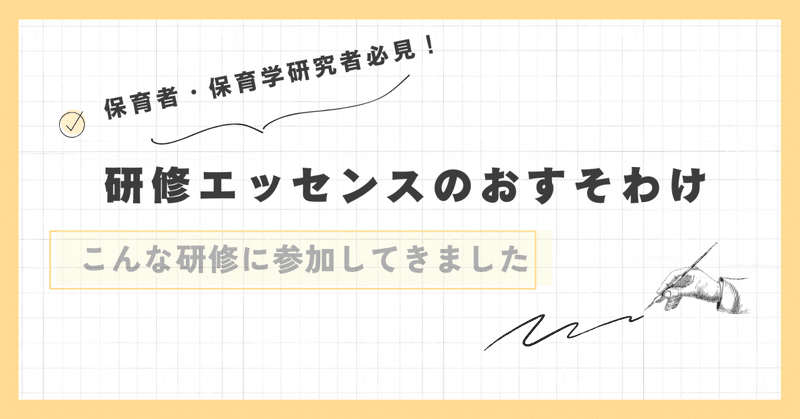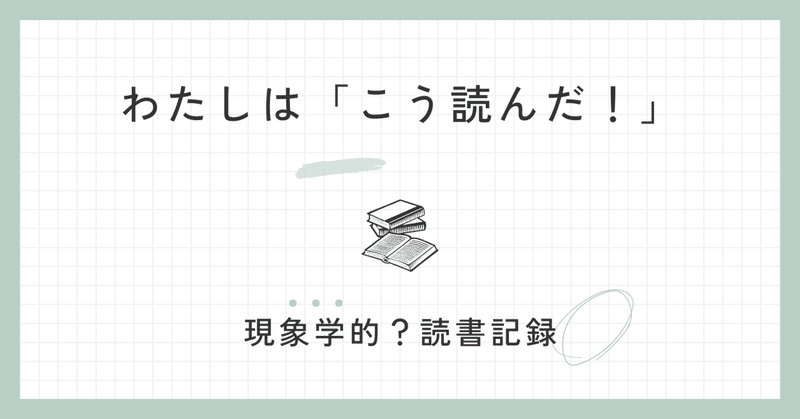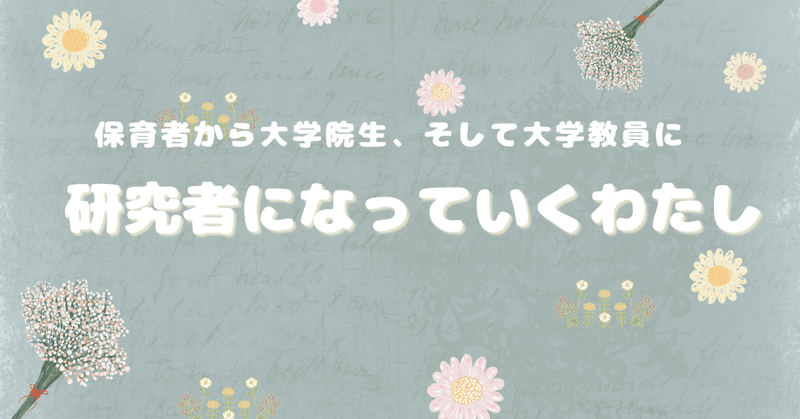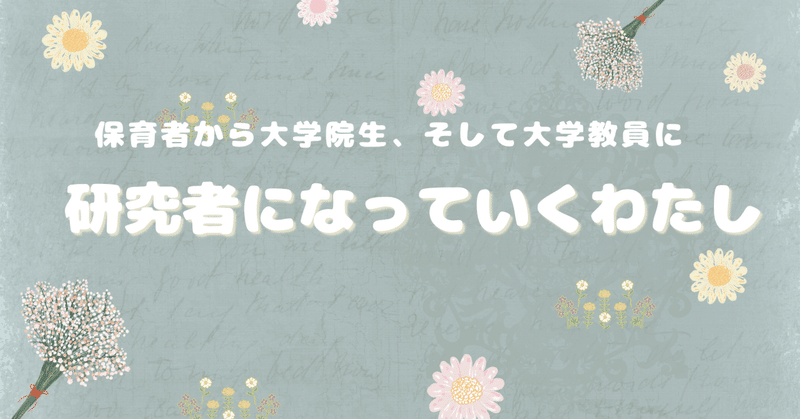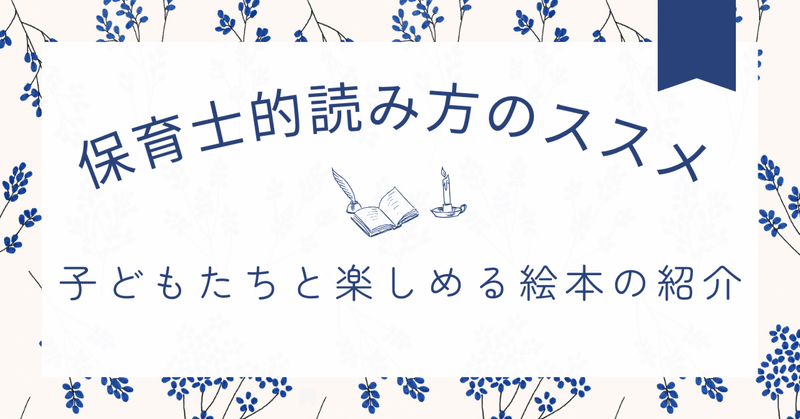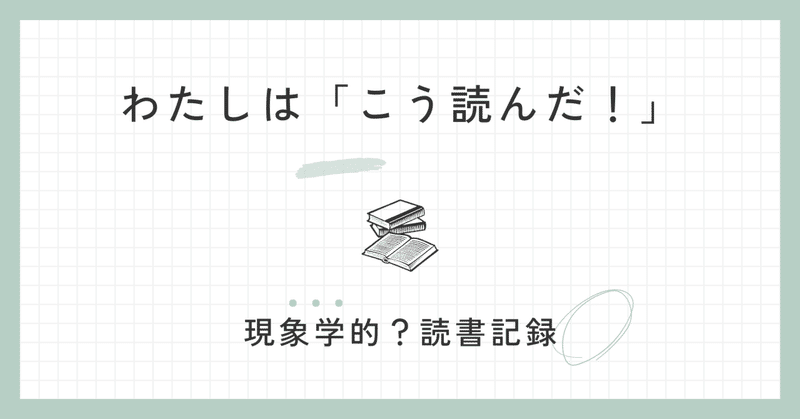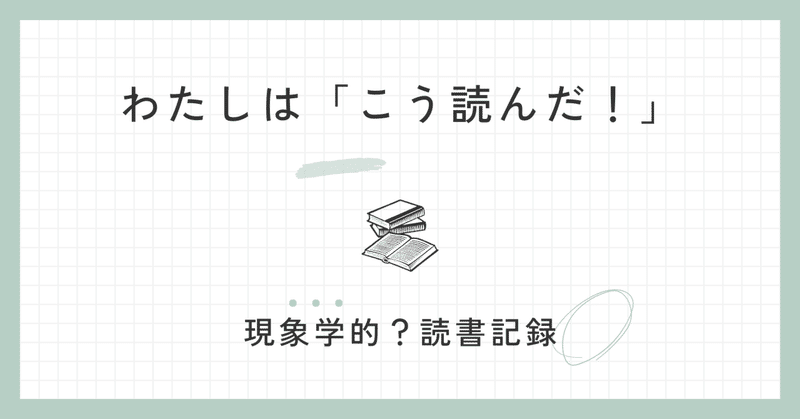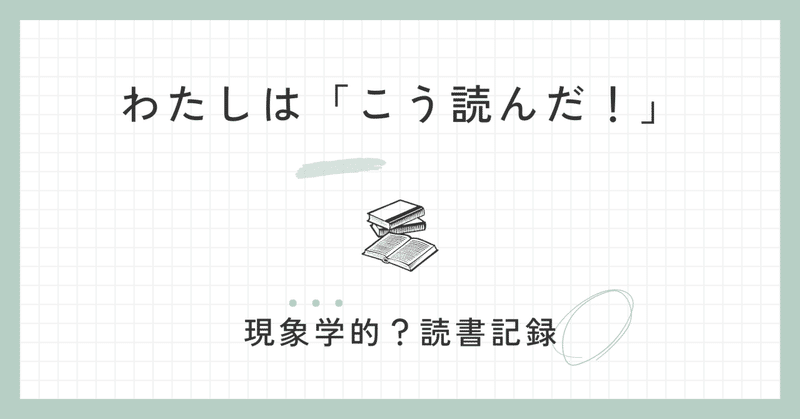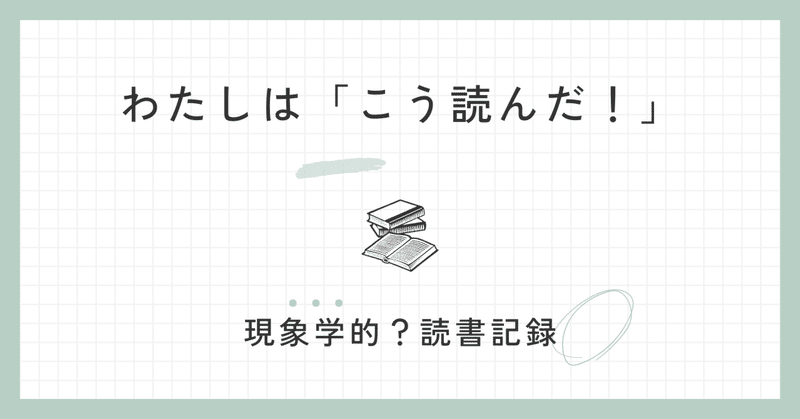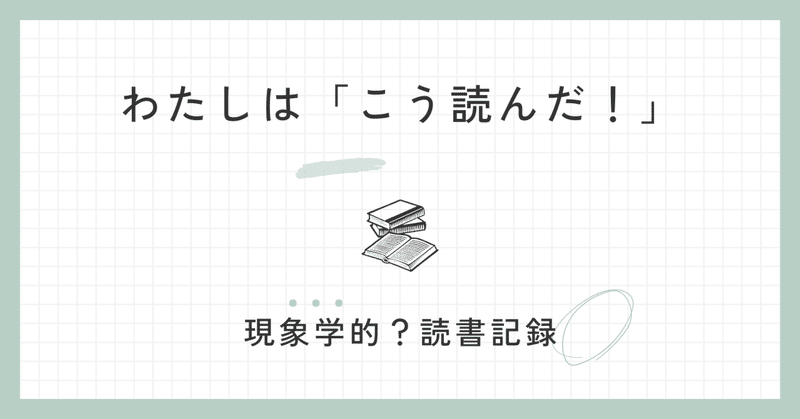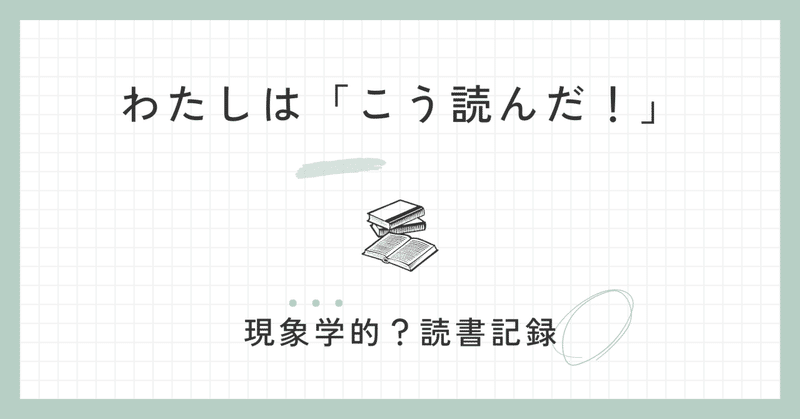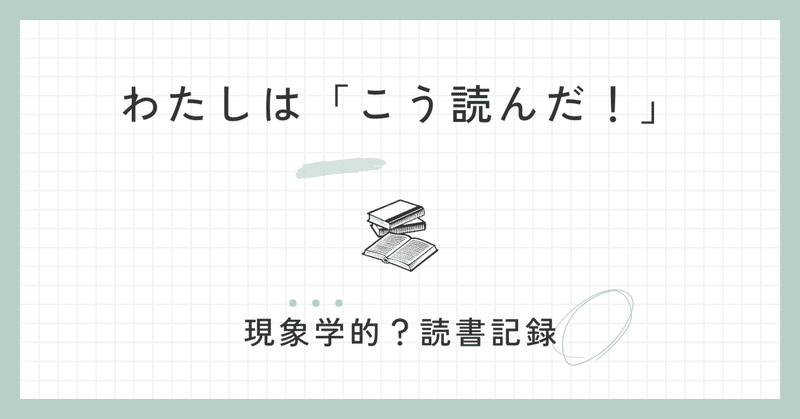最近の記事
マガジン
記事
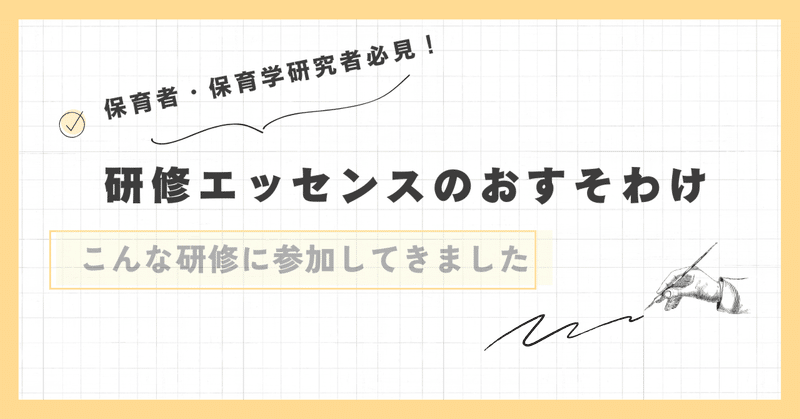
研修エッセンスのおすそわけ Vol.1 「親と子どもの主体性が出会う子育て」 根ヶ山光一先生 (公益財団法人 前川財団主催)
公益財団法人 前川財団主催のセミナー「親と子どもの主体性が出会う子育て」に参加しました。以前から、根ヶ山先生の考え方に惹かれ、著作も読んできました。直接お話が聞ける、それもzoomで無料、聞かない手はないと思って参加しましたが、あっという間の1時間半でした。 先生のこれまでの研究の成果から、ヒト以外の類人猿とヒトとの子育ての違いをわかりやすく説明していただきました。その決定的な違いは、ヒトの子育ては集団による子育て、アロマザリング(母親以外による養育行動)です。それはヒトの