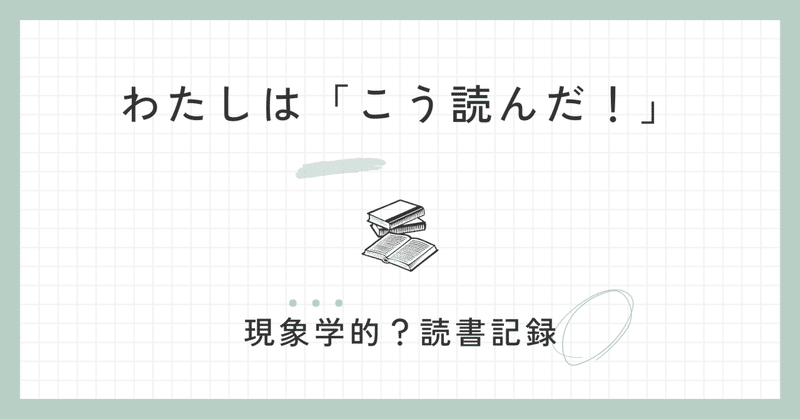
わたしは「こう読んだ!」Vol9. 『保育的発達論のはじまり』 川田学
保育学会文献賞を受賞された『保育的発達論のはじまり』です。2021年の6月にFBに書いた記事を、ほぼそのまま掲載します。川田先生には、某学会に来ていた書店でお声がけしたことがあり、(図々しくてすみません・・・)そのときはまだこの本が出ていなかったこともあり、別の本を勧めてくださいました。その本もとてもいい本です!
その後、保育学会のオンライン受賞式や、オンラインの研修会ーこのことは研修エッセンスのおすそわけに書いています、オンライン読書会でご一緒させていただきました。オンライン読書会は、このFBを書いた後にあったのですが、川田先生とこの本のことについて直接お話ができて、大変有意義なものでした。川田先生と調整くださった先生方に、感謝です。
前置きが長くなりましたが、以下、FBの記事です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この本は、発達心理学の知見はもちろんのこと、発達がどう捉えられてきたのかという歴史にまで踏み込んで書かれています。つながりのやせてしまった現代は、これまで練り上げられてきた発達観を親子が受け止めきれなくなっている状況であると...だからこそ、保育とは子育てとは、何をすればいい実践なのかを考える局面なのだと、川田先生はいいます。
象徴的だったのは、日本の古い子育て観を辿ることで、植物の育ちと子どもの育ちを重ねてきた歴史があるということを示されている点。子どもの自然な成長力を信じて、早くからいじりすぎないという子育て観です。また、沖縄の教訓化である「てぃんさぐぬ花」に見られる相互的循環的な子育て観。これも、現代の子育てや保育への、重要なヒントになると思いました。
主体性を「その子どもが周囲とのあいだに結んでいる関係の状態」と定義して、主体性の発達を4つの段階に分けて論じられていること、社会の仕組みを「弱く育ち合う個人」にシフトしていくべきと主張していること、2歳児をブラブラ期としていることなど、この本の面白さは、至る所にあります。川田先生の発達や保育、子育てに対するまなざしを、言葉にして惜しげもなく著されているのがこの本です。
最近、わたしが小さな植物を育てることに喜びを見出しているのも、育てる営みへの回帰なのかなぁ...なんて、思ってみたりもしました。本当に、本当に、おすすめの本です!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
