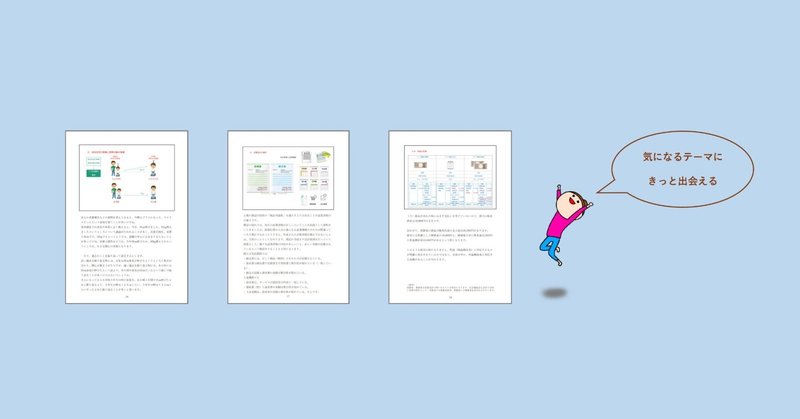
1から学べる社会福祉法人会計勉強会のストーリー⑨ 途中であきらめた・・・だと?
1から学べる社会福祉法人勉強会の資料や書籍は、本質を伝えることを目的にしています。本質を伝えるために資料や文章へのこだわりについてお伝えしていきます。今回は研修会で参加者さんが、途中であきらめたお話です。
勉強会とセミナー、研修会
コロナ禍以前の研修会の内容
現在、マツオカ会計事務所では、1から学べる社会福祉法人会計 勉強会を定期開催(月1回)と随時開催を行っています。定期開催は5年続けています。
コロナ禍の前は、研修関係では事務所主催のセミナーの開催と、公的な機関などからご依頼いただいた研修会で講師をさせてもらうことが多かったです。
公的な機関の研修の例は、
京都市主催 社会福祉法人の監事向け研修会(参加者500人程度)
京都府主催 府内市町村 指導監査担当者向け研修会
社会福祉法人関連団体での研修会
などで講師のご依頼をいただいていました。
全て会場形式の開催でした。まだ、オンライン形式の研修会などは経験がありませんでした。
社会福祉法人の内部研修会
公的な研修会や、事務所主催のセミナーの他にご依頼が多かったものが、法人の内部研修会の講師のご依頼でした。
主に顧問先の法人様です。会計担当者向けや管理職向けといった形での研修会です。
参加下さる人数は10人〜30人の、小さい研修会です。
普段から接している方も多く、お名前が分かり身近に感じられるところもこの研修会の良いところの1つでした。
研修会にスタッフが同席することによる1つ目の目的
私が講師をさせてもらう研修会では、必ずスタッフに同行してもらい、スタッフも参加者の立場で聞いてもらうようにしています。
目的は2つあります。
1つ目は、研修会での話し方や説明のフィードバックを行うためです。
自分が話をしているので、自分自身を客観視することが私には難しく感じます。
研修会後に、修正した方が良いこと、説明の内容や話し方、話のスピードなどについてフィードバックしています。
結構、直さないといけないことが出てきます。
次回に活かせるように、研修の見直しをしています。
このように、スタッフにフィードバックをしてもらうようになったきっかけは、次のようになります。
このきっかけは2つ目の目的にもつながります。
研修会であきらめた・・・だと?
5年ほど前、顧問先様から会計担当者さん向けの内部研修のご依頼をいただきました。
コロナ前でしたので、施設の会議室で行いました。
参加者は10名程度でした。
会計担当者さんとは面識があって、全員のお名前が分かりました。
テーマは、「会計担当者向けの実務上の注意点」でした。
2時間程の研修会が終わり、帰り道にスタッフと、研修のフィードバックを開始しました。
私:「どやった?」
スタッフ:「〇〇さんが、途中であきらめはりました」。
私:「ふ〜ん、あきらめはったん。えっ、あきらめた???」
スタッフの言葉が、スッと頭に入ってきません。
私:「ど、どういうこと?」
スタッフ:「話の中で、何々(会計用語)って言わはったじゃないですか。その言葉の意味がきっと分からなくて、その後は、話を聞くのをあきらめはったご様子です」。
(;゚Д゚)
すごい洞察力です。
私は衝撃を受けて言葉が出てきません。
今回の研修会は顧問先様です。
普段からよくお話する方々がお相手です。
親しみやすい研修会を心がけ、いい感じにできたかなと思っていたのに・・・
途中であきらめておられたとは・・・
スタッフ:「専門用語の意味や話の内容について、聞く方が途中でつまづくとそこから先は聞くのをあきらめます。所長にとって当たり前のことも、聞く方は当たり前ではないですから」。
これまでに講師をやってきた全ての回へ反省です。
1から学べる社会福祉法人会計勉強会が始まる
これまでの研修に対する反省と見直しを始めたその頃に、1から学べる社会福祉法人会計勉強会がスタートしました。
きっかけは、顧問先の理事長からのご依頼でした。
「うちの法人の将来を担う管理職向けの勉強会をして欲しい」とのお言葉をいただきました。
毎回のテーマ、内容についてはもちろん検討しています。
そしてもう一つ、勉強会の進め方について考え、スタッフに同席してもらうというのが2つ目の目的につながります。
研修会にスタッフが同席することによる2つ目の目的
コンセプトは、勉強会をあきらめてもらうことがないようにです。
スタッフが同席する2つ目の目的は、みなさんに質問をしてもらうためです。
質問は、勉強会の最後だけではありません。
私の説明の途中ででも、わからないことがあれば質問してもらいます。
あきらめられた研修では、話の中盤で言葉の意味がわからずにあきらめられた形です。
全ての説明が終わってからの最後の質問では、中盤のあきらめを止めることができません。
そこで、分かりにくい言葉があれば、その時に質問をしてもらおうと考えました。
勉強会の当初に、「話の途中でも、分かりにくいことがあれば遠慮なさらずに、その時に何でも聞いてください」とお伝えするようにしました。
しかし、どうでしょう。
自分が研修会に参加し、講師が話をしている途中に「ちょっと質問を」と手を挙げることなんてできるでしょうか。
私は恥ずかしくて、手を挙げれそうにありません。
しかし、勉強会ではあきらめて欲しくはありません。
そこでスタッフが同席して、私の説明に分かりにくい表現があった時や、参加者のみなさんが何かスッキリとされていない表情をされている時に、スタッフから私に質問をしてもらうようにしました。
私が説明している途中であっても、スタッフから「ちょっと良いですか?今のところをもう少し詳しく」や「ちょっと意味が分かりづらいです」などと発言してもらいます。
そして、いったん説明を中断して、納得してもらえるまで説明をやり直します。
参加者の方々も、スタッフと同じところで引っかかることがあるようで、質問をしてもらって説明をやり直すことがプラスに働くようになりました。
そしてもう一つ、大きなプラスとなったのは、私の話の途中で誰でも質問をしても良いという空気が生まれたことです。
スタッフが質問を繰り返すうちに、参加者の方々にも途中で質問をしても良いんだと感じてもらい、ドンドンと質問が出るようになりました。
質問の内容も、用語の意味だけでなく、「今の話なら、別の事例ではどうなるのか?」といった質問や「この点は意識しなくて良いんですか?」など、『良くぞ、聞いて下さった』や『良い点に気づいてくれました』というような、勉強会の内容より活性化する質問もドンドンと出るようになりました。
おかげで、勉強会は私からの一方通行の説明ではなく、双方向性のある勉強会となってきて、より一層、参加者の方が実際の実務に活かして下さっていることが実感できるようになりました。
これからもいろいろな方法を模索していき、より良い勉強会になっていくよう心掛けていきます。
最後までお読み下さり、ありがとうございました
ご参考
1から学べる社会福祉法人会計勉強会のエッセンスを、
「ふわふわ会計 note版」として会計に興味のある全ての方向けに記載しています。
勉強会の内容を書籍にして出版しています。
(第1巻〜第9巻 出版中)
1から学べる社会福祉法人会計勉強会の開催状況
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
