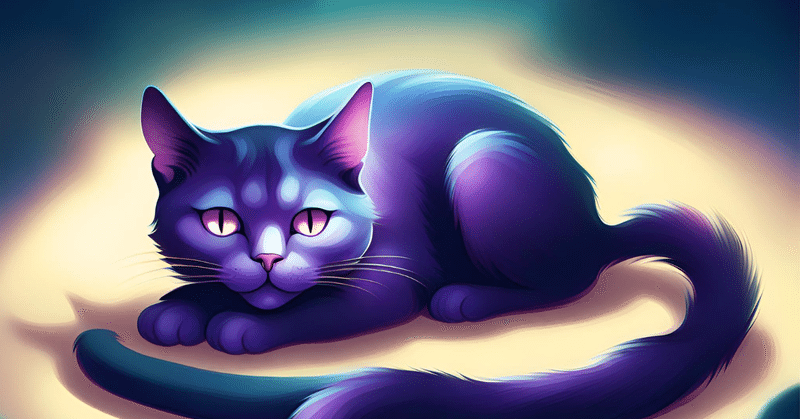
「ラバーソウル」5|SF短編小説に挑む#5
エピローグ↓(読んでいない方はこちらから)
愛が力学化された世界とシュレディンガーの猫①
「お前に何が分かるというんだ?」
赤のような青色をした猫は、二股のしっぽを持つちんちくりんな猫だった。
猫は大きなあくびをしながら高橋を見ている。
高橋はため息をついて猫に言葉を返した。
「僕にだってわかることはあるさ」
「いいや、お前は何も知らないよ。猫より何も知らない」
赤のような青色をした猫はにやにやしてそう言った。
「そりゃ君より知らないことは多いだろうけど、これでも博士号は持っているんだぜ?」
「それが何の役に立つと思うんだ? じゃあ、お前はあそこに見えるカップルが幸せかどうかわかるのか? その博士号の頭とやらで考えてみなよ」
猫は動くも様子もなく広場の端にある花壇に寝転んで、腕を組みながら呆れた様子で高橋を見ている。
猫の後ろにはきれいな白いコスモスが咲いていた。花壇のレンガは黒褐色をしていて、その二つはとても相性が良かった。
彼は振り向いて後ろのカップルを見た。一人はベージュのスーツを着ていて、もう片方は黒のスカートにグレーのカーディガンを羽織っていた。おそらく20代後半のカップルだと高橋は推測した。
彼らは笑顔で何かを話し合っていた。お互いの手を握りながら熱心に。まるでこの世界に二人以外存在しないみたいに。
「彼らは幸せだよ。あんなにも互いに愛し合っているじゃないか」
「やっぱりお前は何も分かっていない」
猫は鼻を鳴らして僕にきっぱりとそう言った。
「彼は彼女の手をまるで宝物みたいに優しく握っていて、そして彼女は彼のその握力と体温にとても安心している。それは愛が成せる技じゃないか?」
「まったくあほらしいね。”人間”ぶって一丁前に語るじゃないか、哀れな落ちこぼれめ!」
猫は思いっきり花壇のレンガをぱつんと叩いた。
高橋は俯いた。猫にすら落ちこぼれと言われたことが恥ずかしかった。
「じゃあ、あれが愛ではないというなら、何だっていうんだ?」
「そうだな。まず愛って言うのは純粋でなくちゃだめだ。分かるかい? 他に何も混じっちゃいけないんだよ。奴らには何が付いていると思う?」
高橋は顔を上げて振り返り、もう一度彼らを見てみた。
「彼らには”共振器”が、ある」
「Tio ĝustas!(その通り!)」
猫はまた花壇のレンガをぱつんと叩いて声を上げた。
「あれは力学化された愛さ。分かるかい?」
赤のような青色をした猫は興奮した様子で続けた。後ろにある白いコスモスは黄色へと変わっていた。
「奴らはあの装置を通して会話しているのさ。相手が聞いているのは自分の心から出た声では無く、あの装置から放出された信号さ。それは自然の理を逸脱していると思わないかい? 奴らは耳から入力された信号と共振器で受信した信号を重ね合わせて、それを”言葉”として受け取っている。それは二次変調された混じりけのある愛さ。分かるかい?」
”力学化された愛”
確かにその通りだと高橋は思った。この世界の愛は既に力学化されているのだ。数学的な統一を含んだ愛だ。
高橋はまた後ろにいるカップルの方を見た。男の言葉は空虚なものに聞こえ、女の笑顔は仮面のように思えた。高橋には人の心という概念が分からなくなっていた。全部猫の所為だ。
「でも、少なくとも彼らは嘘や方便を付いてはいない、そうだね?」
「それはそうだ。あの装置に嘘や方便は通用しないからね」
「それは純粋ではなくても、彼らの本心になるんじゃないかな?」
猫はやれやれと首を振り、呆れた顔で高橋を見た。だがそこに軽蔑は含まれていない。猫は彼のことが気に入っているのだ。
「日本語以外の言語を勉強したことはあるかい?」
猫は尋ねた。
「英語とフランス語なら一通りは」
「Bon!(よろしい!)」
猫は花壇を叩き、そして次のようなことを高橋に説明した。
第二言語の習得はその者の言語体系を大きく変えてしまう。その影響は感性のレベルまで波及する。例えば、英語を習得した日本人が以前より話し方が主張的になったり、フランス語を取得した者の説明がよりロジカルになったり、などなど。
また、グーグ・イミディル語には前後左右という概念がないことで、方角に対する感性がどの言語の話者より卓越している。その言語を身に付ければ空間把握能力が大きく向上するかもしれないとも語っていた。
”言葉”にはそれくらい大きな意味を持つ。
「今の”人間”はある意味で、装置によって自身の言語体系が変わってしまった状態と言えるのさ。そしてこれは人工的な変容であって、別言語の取得による体系の変化とは異なるのさ。 分かるかい?」
「人工的な変化による彼らの言語は、純粋では無いということだね」
「Bonega!(素晴らしい!)」
猫は花壇を何度も強くぱつんぱつんと叩いた。
やっと少しは分かってきたようだね、と猫は満足そうに二股のしっぽを器用に振っていた。
猫の言う通り、高橋は何も分かっていなかった。
「お前以上に、”人間”たちは何も分かっていないからね。おそらく理解すらできないだろうよ。自分がすがっているものすら理解できていない連中なんだよ」
赤のような青色をした猫の体は透けていき、にやにやした顔だけがはっきりとしていてより不気味さが際立っていた。
「猫にはそれが何故分かるんだ?」
「さっきから猫、猫と言っているが俺は猫ではない!」
顔だけになった猫は声を荒げた。
「では、猫ではなくなんと呼べばいいんです?」
「俺はシュレディンガーの猫と呼ばれるものだ。覚えておきな。また来るよ」
そう言って猫は完全に消えてしまった。
残ったのは猫が叩いていた花壇の爪傷と、そこに咲く青色のコスモスだけだった。
高橋は最後にもう一度あのカップルを見た。
赤のような青色をした猫の言葉が頭に浮かんだ。
「あれは力学化された愛さ。分かるかい?」
そうして彼は広場を後にした。
愛が力学化された世界シュレディンガーの猫①(完)
二◯二四二月
Mr.羊
続き↓
#SF小説
#宇宙SF
#連載小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
