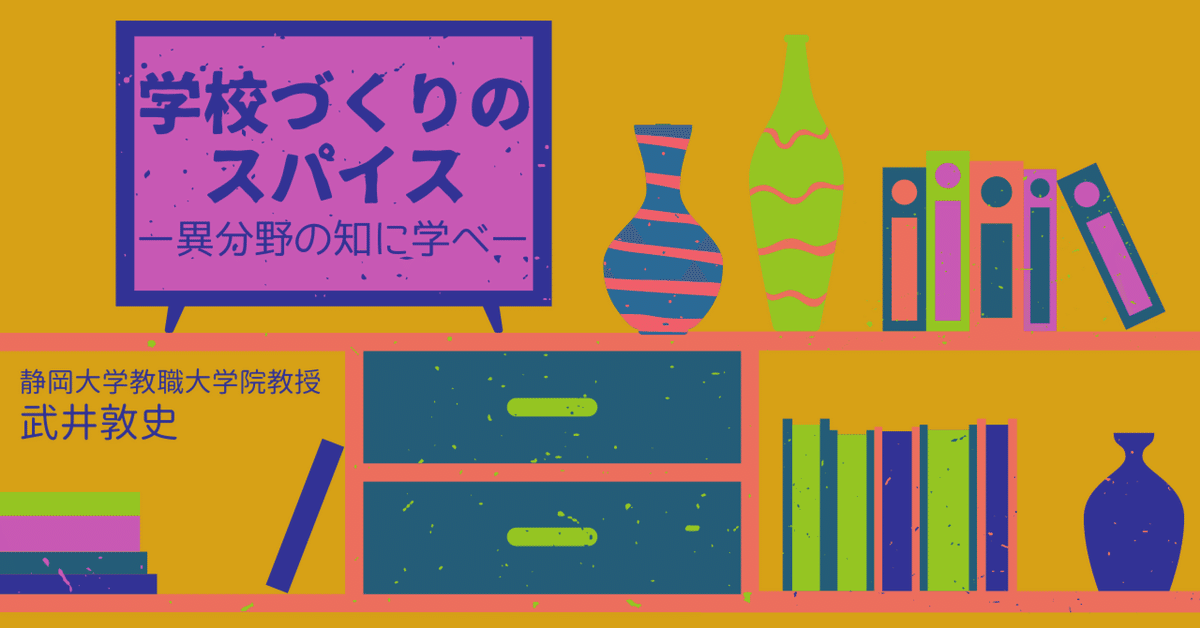
#40 議論されない教育問題~斎藤幸平『人新世の「資本論」』より~|学校づくりのスパイス
今回は斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』(集英社、2020年)を手がかりに、普段は「議論されない教育問題」について考えてみたいと思います。
本書はマルクスの「資本論」とその後の思想的転回を現代的視点から再評価したものですが、氏がこの本で展開しているのは、「マルクス主義にもいいところはあるので取り入れよう」といった中途半端な議論ではありません。
世界は資本主義を捨ててマルクス主義に全面移行すべきである、というラディカルな主張が本書のモチーフです。こうした、ある意味で過激な内容であるにもかかわらず、本書は2年ほど前に発刊されて以来、2022年7月までに、すでに45万部以上を売り上げているようです。
本気でマルクス主義
タイトルにある「人新世」とは、地球温暖化などの気候変動、生物多様性の喪失、化石燃料の燃焼による堆積物変化など、人類が地球に与えた影響により区分される地質時代のことです。本の表紙では「人類が地球を破壊しつくす時代」と説明されています。
ではなぜ人新世には資本主義を捨てなければならないのか? それは資本主義を捨てないと地球が持たなくなってしまう、という単純な理由によるものです。本書では、SDGsも危機から目を背けさせる「大衆のアヘン」(4頁)であると述べられています。
本書の前半では、「緑の経済成長」論をはじめ環境技術によって経済成長とCO2排出抑制を両立させようとするさまざまな議論を取り上げ、それが奏功する見込みの薄いことが論証されていきます。
たとえば、先進国だけ見れば確かにエネルギーの消費効率は改善しているかもしれないが、経済成長の中心が中国やブラジルなどに移り、エネルギー消費が拡大することによってCO2の排出量は増え続ける結果となっているそうです(69~72頁)。また、たとえある部門でのエネルギー効率が高まっても、そこで獲得される資本や収入が他の商品の生産や購買に使われ、節約分が帳消しになってしまうといいます(78頁)。
斎藤氏は資本主義の本質を次のように喝破します。「資本主義とは、価値増殖と資本蓄積のために、さらなる市場を絶えず開拓していくシステムである。そして、その過程では、環境への負荷を外部へ転嫁しながら、自然と人間からの収奪を行ってきた」(117頁)。
そしてそのための手立てとして氏が提案しているのは、①「使用価値経済への転換」、②「労働時間の短縮」、③「画一的な分業の廃止」、④「生産過程の民主化」、⑤「エッセンシャル・ワークの重視」の5点(299頁)です。世界の危機を直視して、対応するためには経済成長を捨てて社会共通の財産〈コモン〉を回復するしかない、というのが本書の結論です。
さて、本書では、展開されている論旨については一定の根拠のもとに丁寧に論じられてはいますが、必要なすべてが論じられているわけではありません。資本主義に変わる新しい社会構想を本一冊で論じ尽くすことなど、どだい無理な注文です。
だから、この本の主張は現実的ではないと見る人もいるはずです。
しかしそれでも世界経済のあり方という壮大な問いに対して堂々と代案を掲げて主張を展開するところに、筆者は斎藤氏の男気を感じます。氏は「マルクスで脱成長なんて正気か――。そういう批判の矢が四方八方から飛んでくることを覚悟のうえで、本書の執筆は始まった」(359頁)と述べています。

議論されない教育問題
本書の提起している種類の問題は、たとえ皆が薄々は感じてはいたとしても、正面から議論されることは稀です。私たち自身も資本主義の恩恵を受けて生活しており、「そういうおまえはどうなんだ」という切り返しが怖いからです。かく言う筆者も車を運転し、スマホを愉しみ途上国の安価な労働力によって生産された服を着て生活しています。
この議論されない問題の構造は、教育にもそのまま当てはまるのではないでしょうか。
現在の公教育システムに生活基盤を依存している教育関係者にとって、「学校という場所において、教員という専門職が、公教育サービスをなかば独占的に提供する」という公教育の構造自体に異論を唱えるのはむずかしいことです。この前提のもとでは、部分的な問題点の指摘や改善の提案に議論は終始しがちです。
しかしそうした議論は、もしかしたら本書の指摘するSDGsと同様に、私たちに気休めを提供しているだけなのかもしれません。
一方で小手先の対応ではどうにもならない教育課題も増えています。たとえば、終身雇用を前提としない新たな産業社会に対応した能力育成やマインドセットの確立、DX(デジタルトランスフォーメーション)によって教育サービスの格差がさらに拡大する可能性等の課題は、それらが資本主義に立脚し地球規模で生起しつつある問題であるがゆえに、学校現場や教員による個々の対応だけでは限界があることにもはや疑う余地はありません。
これらの課題に教育現場が直面していくためには、現在の公教育における相互依存関係をいったん括弧に入れたうえで、「これからの理想的な公教育のあり方とはどのようなものか」という問いを真剣に語り合い、そこから逆算して現在すべきことを考える発想が必要なのではないかと筆者は考えます。
こうした議論をすること自体がむずかしいことであるはずです。というのも、そのときにはもしかしたら、ハードウェアとしての「学校」や、教員という専門職の設置はもはや必然ではない、大学の教員養成課程も存続する必要性はない、という結論になるかもしれません。
しかしこれからの激しい変化の時代を生き抜く子どもを育てようとするなら、そうしたリスクを引き受ける勇気をわれわれも持つべきではないでしょうか。現状の安定を失うリスクを通り抜けてこそ、足腰の強い教育論は生まれるのではないかと筆者は考えています。
【Tips】
▼本当に脱資本主義は可能なのか? 以前にこの連載でも取り上げた井上智洋氏とスリリングな議論が展開されています。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
