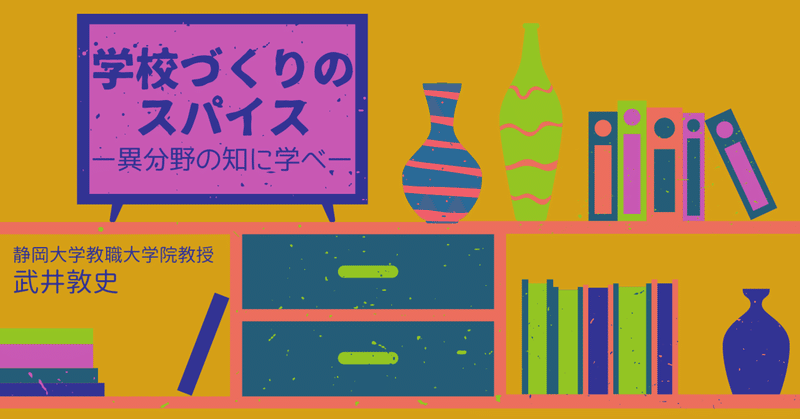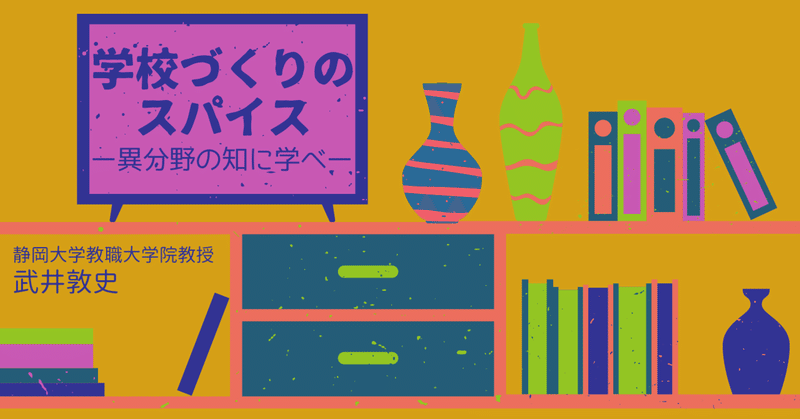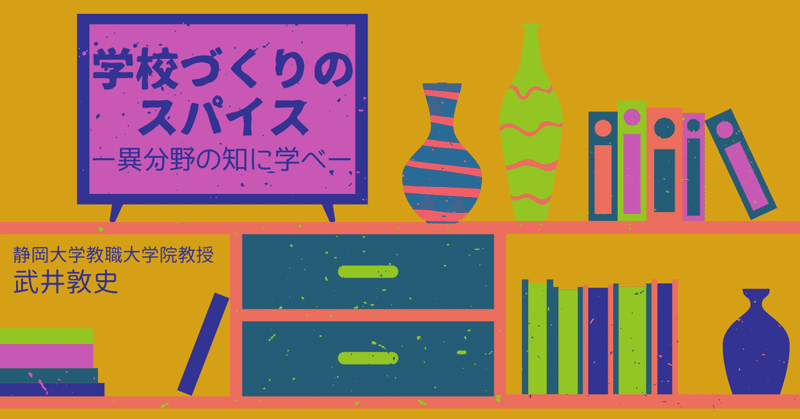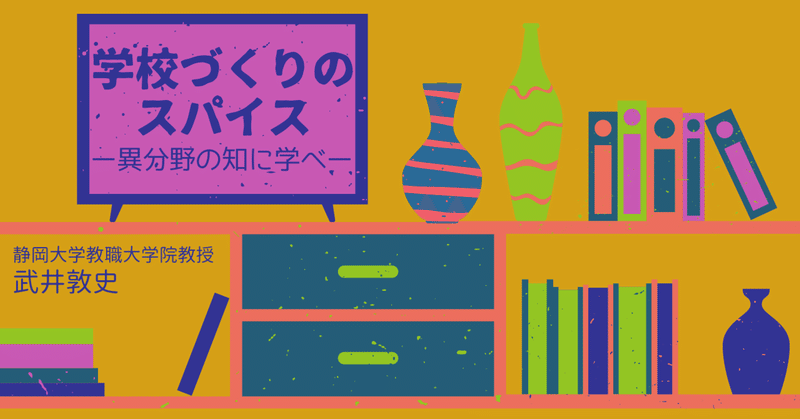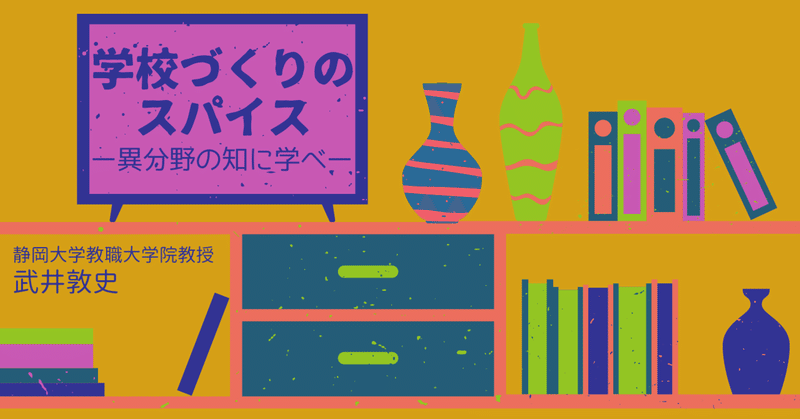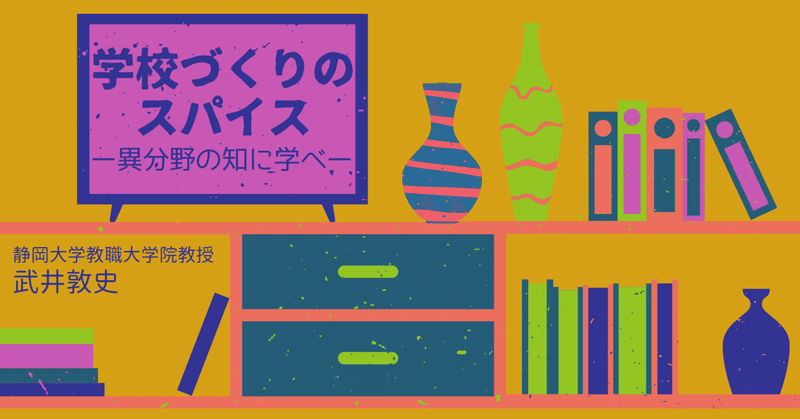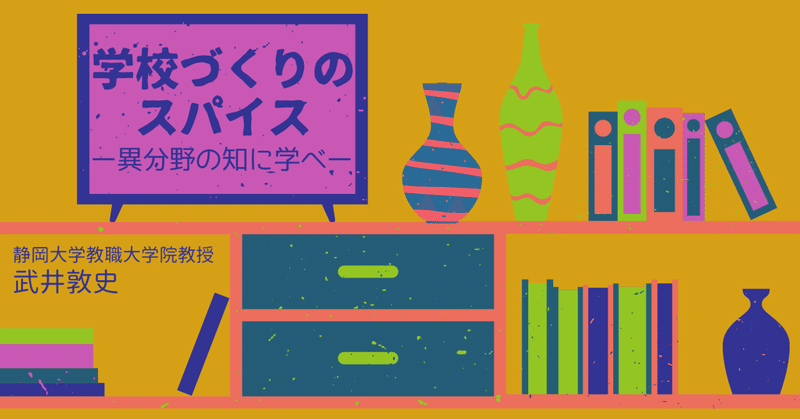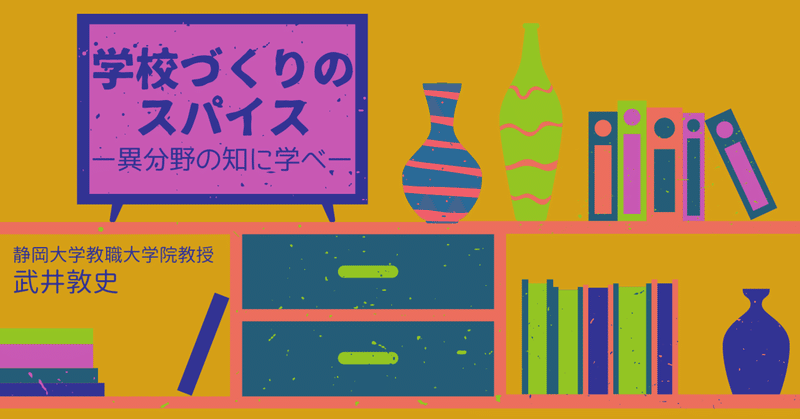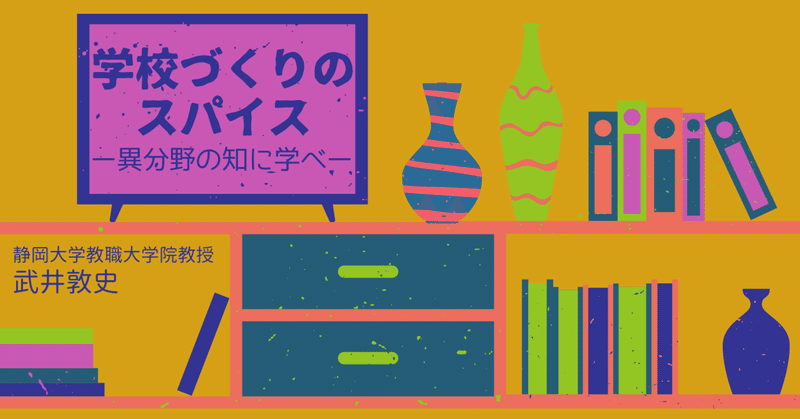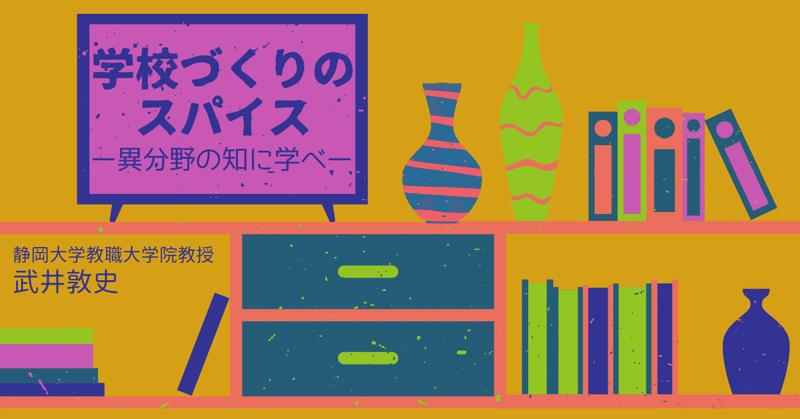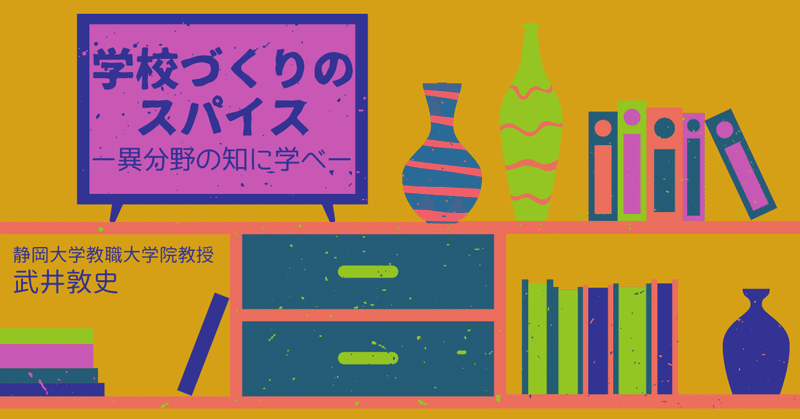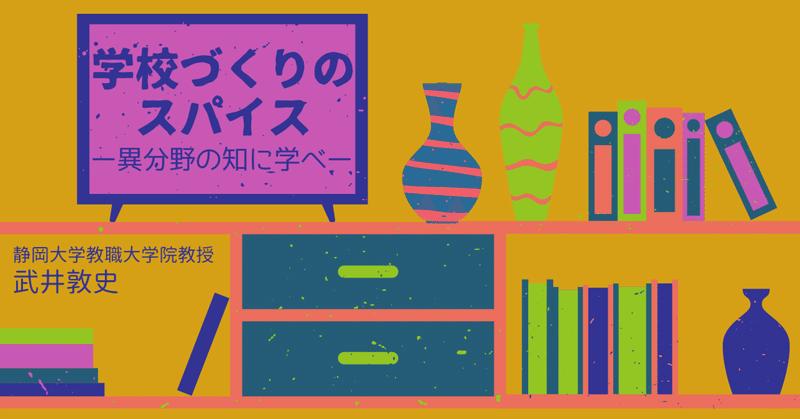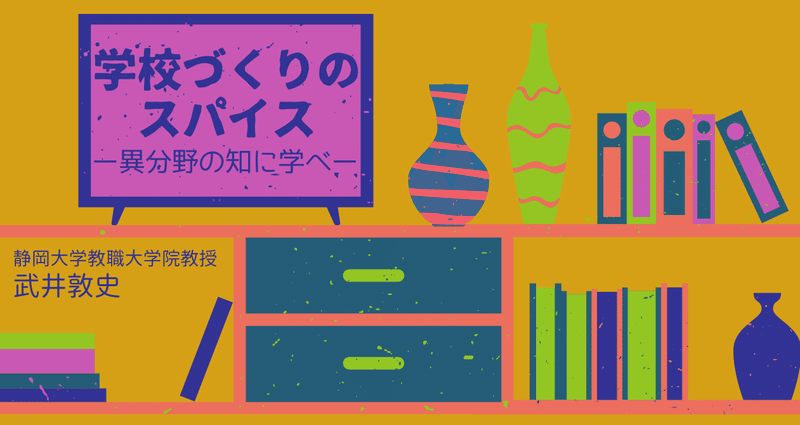
学校のリーダーシップ開発に20年以上携わってきた武井敦史氏が、学校の「当たり前」を疑ってみる手立てとなる本を毎回一冊取り上げ、そこに含まれる考え方から現代の学校づくりへのヒントを…
- 運営しているクリエイター
記事一覧
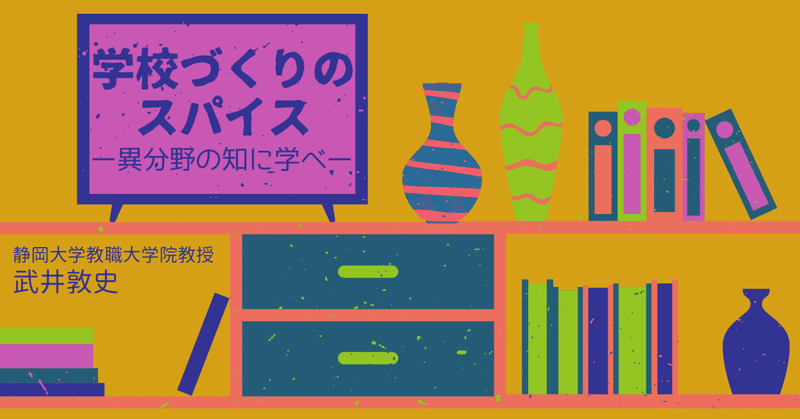
#63「成長の土壌」を忘れていないか?~ゲイブ・ブラウン『土を育てる 自然をよみがえらせる土壌革命』より~|学校づくりのスパイス
「子どもの成長にとって理想の環境とはどのようなものか」――古〈いにしえ〉より現代に至るまで、くり返し問われ続けてきました。さらに、子どもの成長環境は今日激変しつつあります。今回はリジェネラティブ(環境再生型)農業の第一人者ゲイブ・ブラウン氏の『土を育てる 自然をよみがえらせる土壌革命』(NHK出版、2022年)にヒントを得て、この問題に切り込んでみたいと思います。 「足し算」・「かけ算」の農業 リジェネラティブ(環境再生型)農業とは、農場や牧場を一つの生態系として管理する